 ■英語を話すハワイ生まれの日系二世を父と、日本語を話す近江八幡生まれの母とのあいだに生まれた少年が、2つの言語のあいだで揺れながら、どのように言語を、そしてそれにともなう思考の方法を獲得していったのかが、子どもの頃にペーパーバッグを集めていた話から大学時代に初めて翻訳の原稿を書いた話、そして小説を書き始めた頃などの経験をもとにつづられている。
■英語を話すハワイ生まれの日系二世を父と、日本語を話す近江八幡生まれの母とのあいだに生まれた少年が、2つの言語のあいだで揺れながら、どのように言語を、そしてそれにともなう思考の方法を獲得していったのかが、子どもの頃にペーパーバッグを集めていた話から大学時代に初めて翻訳の原稿を書いた話、そして小説を書き始めた頃などの経験をもとにつづられている。
わたしは片岡義男の本はエッセイしか読んでいないけれど、一見、論理的だけど、でも実際は論理的な文章というわけでもなく、かといって感情に訴えかけてくるわけでもないという不思議な語り口が好きで、今でも新刊をチェックしている数少ない作家でもある。日本語してはちょっと微妙だなぁと思うところもありつつ、なんか微妙なラインをすれすれに歩いているような感じなのは、2つの文化を行き来しているからなのだと思う。
■小説のほうは、ちょうど小学校高学年から中学の頃に、角川映画などで小説が次々と映画化されるブームがあって、そのときの印象からほとんど読んでいない。ほとんどと書いたのは、90年代初めの頃、村上春樹とか読むのだったら、片岡義男の本を読んだほうがいいんじゃないかという気分で、何冊か読んでみたことがあるのだけれど、続かなかったし、今では何を読んだのかも忘れてしまったから。
その後、90年半ばにちくま文庫から出た「ぼくはプレスリーが大好き」を読んだのがきっかけで、晶文社から出ている初期の本や太田出版からでたアンソロジーなどを読んではまってしまった。今小説のほうを読んだら印象が変わるのだろうか?と思いつつエッセイを読み続けているけれど、多分、これからも読まないような気がする。
■どこかのエッセイで、その頃の小説は漫画を小説化することをテーマにしていたといったことがかかれていた記憶があるけど、そういう意味ではライトノベルのはしりと言えるのかもしれない。ただライトノベルとしては、設定が非日常的なので、これから評価されるということはなさそう。
ついでにいうと堀江敏幸は「片岡義男の小説は小説についての評論であり、評論こそが小説である」と語っていたようだけど、小説の中にその評論の部分を感じられるようになるとまた印象が変わるのかもしれない。
■そういう意味では、今、70年代から80年代にかけての歌謡曲を聴くということは、歌謡曲の中に日本の音楽への評論が見え隠れする部分が感じられるからなのかも?なんてこじつけで思ったりもします。歌謡曲がJポップと呼ばれるようになってから評論というピースが抜け落ちてしまった気がするのね。 ■さて、連休もあっという間におしまい。どこに行く我が家はどこに行くというわけでもなく、はじめのほうにセプチマでやっていたCOINNのライブを見て、途中で、自転車で深大寺になる鬼太郎茶屋に行った程度でした。といってもTHE GOLDEN COINN SHOWでは、あいかわらず子どもたちは、ライブが始まって2曲目で「外で遊んでくる!」と飛び出し、ライブよりもセプチマの庭で遊ぶことに夢中でしたけど。
■さて、連休もあっという間におしまい。どこに行く我が家はどこに行くというわけでもなく、はじめのほうにセプチマでやっていたCOINNのライブを見て、途中で、自転車で深大寺になる鬼太郎茶屋に行った程度でした。といってもTHE GOLDEN COINN SHOWでは、あいかわらず子どもたちは、ライブが始まって2曲目で「外で遊んでくる!」と飛び出し、ライブよりもセプチマの庭で遊ぶことに夢中でしたけど。
よく考えたら漣くんなんてセプチマに初めて行ったのは1歳くらいの頃なわけで、年に数回しか遊びに行かないにしろ、勝手知った遊び場ですよね。当日はラマパコスやアグネスパーラーなど顔見知りのお店が出店してましたし。いつかセプチマでゆっくりとライブを見れる日が来るんでしょうかねぇ。
■秋は子どものイベントから自分が出るイベント(本屋さんのほうです)、遊びに行くイベントなど、毎週末なにかしらあってそれこそあっという間に寒くなってしまう感じですね。まぁ毎週、楽しみではあるのですが。

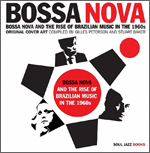 ■8月にミオ犬と子どもたちが長崎に帰ってときに、CDの整理をしたのですが、その際に収納用具を買うためにCDを売ったお金で買った本。なんかCD売ったお金でCDの収納用具だけを買うのは負けた気がしてので‥‥。何に負けるのかは不明ですが。
■8月にミオ犬と子どもたちが長崎に帰ってときに、CDの整理をしたのですが、その際に収納用具を買うためにCDを売ったお金で買った本。なんかCD売ったお金でCDの収納用具だけを買うのは負けた気がしてので‥‥。何に負けるのかは不明ですが。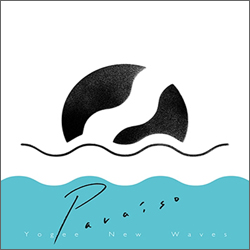 ■今年の夏はウワノソラ’67ばかり聴いていたけれど、その次に聴いていたのがYogee New Wavesの「PARAISO」。今年の初めくらいかな、新しいバンドの音楽を聴いてみようと思っていろいろ調べていた時に知ったバンド。シティポップとか言われているけれど、同じように言われているバンドと違って、影響された音楽がストレートに出てないところがいい。こういうの聴いてると、今のシティポップってなんだろうなと思う。
■今年の夏はウワノソラ’67ばかり聴いていたけれど、その次に聴いていたのがYogee New Wavesの「PARAISO」。今年の初めくらいかな、新しいバンドの音楽を聴いてみようと思っていろいろ調べていた時に知ったバンド。シティポップとか言われているけれど、同じように言われているバンドと違って、影響された音楽がストレートに出てないところがいい。こういうの聴いてると、今のシティポップってなんだろうなと思う。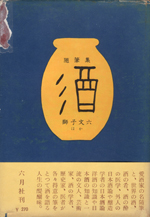 ■獅子文六や佐野繁次郎、小林勇、中里恒子、村井米子、大久保恒次などによる酒について文章を収録したアンソロジー。酒にまつわる個人的な随筆だけではなく、産地別のワインの紹介や世界の酒の紹介などお酒に関する解説なども載っていていいバランスになっている。
■獅子文六や佐野繁次郎、小林勇、中里恒子、村井米子、大久保恒次などによる酒について文章を収録したアンソロジー。酒にまつわる個人的な随筆だけではなく、産地別のワインの紹介や世界の酒の紹介などお酒に関する解説なども載っていていいバランスになっている。 ■9月5日はごちゃごちゃフェスティバル@セプチマへ。セプチマに行くのも久しぶりかもしれない。前回はなんのイベントに行ったんだっけね?
■9月5日はごちゃごちゃフェスティバル@セプチマへ。セプチマに行くのも久しぶりかもしれない。前回はなんのイベントに行ったんだっけね? ■開演時間が2時から6時ということもあり、子どもたちがたくさん来るのかなと思っていたのですが、それほどでもなく、なんかうちの子が飽きてちょっと騒ぎ出してくると、よしのももこさんが「それではここで『エノッキー&聖くんのギターに合わせて、リズムを鳴らそう!』をやりましょう」などと子ども参加型にしてくれたりして、我が家はかなり盛り上がりました。
■開演時間が2時から6時ということもあり、子どもたちがたくさん来るのかなと思っていたのですが、それほどでもなく、なんかうちの子が飽きてちょっと騒ぎ出してくると、よしのももこさんが「それではここで『エノッキー&聖くんのギターに合わせて、リズムを鳴らそう!』をやりましょう」などと子ども参加型にしてくれたりして、我が家はかなり盛り上がりました。 ■早稲田の教授で日本の近代文学の研究をしていた人。「角鹿の蟹」に続く随筆集として生前出す予定だったらしい。収録されている多くは、窪田空穂、森鴎外、夏目漱石、正宗白鳥といった作家について書かれたもので、同じく早稲田の教授といって思い出す岩本素白の随筆と違い文学に沿った随筆が中心になっている。しかも読んだことのない、もしくは初めて知る作家も多くて難しい‥‥素白先生も私が読んでないだけで学術的なものもありますけどね。
■早稲田の教授で日本の近代文学の研究をしていた人。「角鹿の蟹」に続く随筆集として生前出す予定だったらしい。収録されている多くは、窪田空穂、森鴎外、夏目漱石、正宗白鳥といった作家について書かれたもので、同じく早稲田の教授といって思い出す岩本素白の随筆と違い文学に沿った随筆が中心になっている。しかも読んだことのない、もしくは初めて知る作家も多くて難しい‥‥素白先生も私が読んでないだけで学術的なものもありますけどね。 基本的には知ってるエピソードが描かれているので、ある程度、ブライアン・ウィルソンを知っている人であれば違和感はないだろうけど、知らない人がどう感じるのかちょっと知りたい感じ。やっぱり60年代の描写が良くて、特にレコーディング風景は鳥肌が立つくらいでした。ブライアン・ウィルソンが一人一人演奏者に口で説明しているのが、いっせいに演奏された時に、一つのサウンドになる快感がすごい。一方で今のブライアン・ウィルソンの活動の充実ぶりを見ていると、「ペットサウンズ」~「スマイル」を振り返るのは、もうこれで終わりにしたいと思う。そして80年代は今のブライアン・ウィルソンに続くためのエピローグという気もしないでもないです。わたしとしては高校の時に1stソロを聴いて、それだけで感動した頃を思い出しました。
基本的には知ってるエピソードが描かれているので、ある程度、ブライアン・ウィルソンを知っている人であれば違和感はないだろうけど、知らない人がどう感じるのかちょっと知りたい感じ。やっぱり60年代の描写が良くて、特にレコーディング風景は鳥肌が立つくらいでした。ブライアン・ウィルソンが一人一人演奏者に口で説明しているのが、いっせいに演奏された時に、一つのサウンドになる快感がすごい。一方で今のブライアン・ウィルソンの活動の充実ぶりを見ていると、「ペットサウンズ」~「スマイル」を振り返るのは、もうこれで終わりにしたいと思う。そして80年代は今のブライアン・ウィルソンに続くためのエピローグという気もしないでもないです。わたしとしては高校の時に1stソロを聴いて、それだけで感動した頃を思い出しました。 ■8月の終わりは調布の京王多摩川アンジェにてイン・ザ・パシフィック恒例のバーベキュー。とわたしが思っているだけで、今年はインパシのメンバーはタクミくんだけでしたが。バーベキューと言うよりも野外の焼き肉パーティといった感じですが、普段、夜にしか会わない人たちでのバーベキューはこのくらいがちょうどいい。飲み放題だしだいたい飲んでばかりだしね。で、いつものようにバーベキューが終わったあと、4時くらいから調布で飲み始めて、解散したのは9時。子どもたちを連れての飲みで飲み過ぎました。帰ってからシャワー浴びさせて寝かしつけをしたのはなんとなく覚えているのですが、目が覚めたら明け方でした。
■8月の終わりは調布の京王多摩川アンジェにてイン・ザ・パシフィック恒例のバーベキュー。とわたしが思っているだけで、今年はインパシのメンバーはタクミくんだけでしたが。バーベキューと言うよりも野外の焼き肉パーティといった感じですが、普段、夜にしか会わない人たちでのバーベキューはこのくらいがちょうどいい。飲み放題だしだいたい飲んでばかりだしね。で、いつものようにバーベキューが終わったあと、4時くらいから調布で飲み始めて、解散したのは9時。子どもたちを連れての飲みで飲み過ぎました。帰ってからシャワー浴びさせて寝かしつけをしたのはなんとなく覚えているのですが、目が覚めたら明け方でした。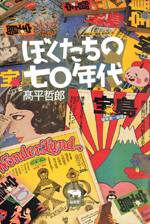 ■大学時代に企画したイベントのエピソードから晶文社の本に関わるようになったきっかけ、雑誌「ワンダーランド」の発刊から「宝島」になるまで、そして「宝島」の編集長を辞めたあとの、赤塚不二夫やタモリ、山下洋輔らとの仕事まで、高平哲郎の70年代を振り返った本。
■大学時代に企画したイベントのエピソードから晶文社の本に関わるようになったきっかけ、雑誌「ワンダーランド」の発刊から「宝島」になるまで、そして「宝島」の編集長を辞めたあとの、赤塚不二夫やタモリ、山下洋輔らとの仕事まで、高平哲郎の70年代を振り返った本。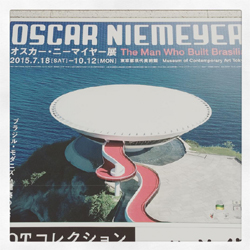 ■この本を読んでしばらく経った頃、「月刊宝島」と「キューティ」休刊のニュースが出ててちょっとびっくり。もちろん最近の「宝島」がどんな雑誌になっているのか、なんてまったく知らない。逆にまだ出ていたのか?と言う気もする。「宝島」ほど時代によって内容をがらりと変えることで生き続けてきた雑誌はないんじゃないかと思う。それほどまでに「宝島」という名前を残したいという執念はなんだったのだろう?高平哲郎の怨念か(笑)ぜったい無理だろうけど、「ワンダーランド」から休刊にいたるまでの「宝島」通史というのを読んでみたい気がする。
■この本を読んでしばらく経った頃、「月刊宝島」と「キューティ」休刊のニュースが出ててちょっとびっくり。もちろん最近の「宝島」がどんな雑誌になっているのか、なんてまったく知らない。逆にまだ出ていたのか?と言う気もする。「宝島」ほど時代によって内容をがらりと変えることで生き続けてきた雑誌はないんじゃないかと思う。それほどまでに「宝島」という名前を残したいという執念はなんだったのだろう?高平哲郎の怨念か(笑)ぜったい無理だろうけど、「ワンダーランド」から休刊にいたるまでの「宝島」通史というのを読んでみたい気がする。 ■暑い時は涼しい美術館だよな、なんて思って、現代美術館のオスカー・ニーマイヤーの展覧会「ブラジルの世界遺産をつくった男」を見た。しかし美術館は涼しいけど、現代美術館にしろ、8月のはじめに行った原美術館にしろ、逗子の近代美術館 葉山にしろ駅から遠いので、美術館に行くまでがつらいというね。
■暑い時は涼しい美術館だよな、なんて思って、現代美術館のオスカー・ニーマイヤーの展覧会「ブラジルの世界遺産をつくった男」を見た。しかし美術館は涼しいけど、現代美術館にしろ、8月のはじめに行った原美術館にしろ、逗子の近代美術館 葉山にしろ駅から遠いので、美術館に行くまでがつらいというね。 ■北は北海道から南は鹿児島までの旅の様子をつづった晩年の随筆集。昭和30年代後半から40年代初めに書かれたものを中心にまとめられている。晩年にこうした本が出たのは昭和37年に「大陸の細道」が芸術選奨文部大臣賞を受賞したあと、さまざまな雑誌や新聞からの原稿依頼が多くなり、その一つとして紀行文が書かれたようだ。
■北は北海道から南は鹿児島までの旅の様子をつづった晩年の随筆集。昭和30年代後半から40年代初めに書かれたものを中心にまとめられている。晩年にこうした本が出たのは昭和37年に「大陸の細道」が芸術選奨文部大臣賞を受賞したあと、さまざまな雑誌や新聞からの原稿依頼が多くなり、その一つとして紀行文が書かれたようだ。 ■週末(っていつの週末だ?)70年代バイブレーションを見に行こうと思って、横浜に向かっている電車の中で、ごはんを食べるところとか調べていたら、「上菅田町は横浜のチベット自治区」というタイトルで笹山団地を紹介しているブログを見つけ気になってしまい、そのまま笹山団地に行ってみた。
■週末(っていつの週末だ?)70年代バイブレーションを見に行こうと思って、横浜に向かっている電車の中で、ごはんを食べるところとか調べていたら、「上菅田町は横浜のチベット自治区」というタイトルで笹山団地を紹介しているブログを見つけ気になってしまい、そのまま笹山団地に行ってみた。 ■ついでに近くを散歩。記憶では小さな商店街というか、小さいお店が数軒集まっているところが2箇所あったと思うのですが、1箇所は普通のドラッグストアになってました。もうひとつは残っていたけれど、お店のほうは開いているのか、閉店しているのかよく分からない状態。週末だからといって賑わっている感じでもなし。団地にはまだ人が住んでいるのだから、もっと人が居てもいいのにと思う。
■ついでに近くを散歩。記憶では小さな商店街というか、小さいお店が数軒集まっているところが2箇所あったと思うのですが、1箇所は普通のドラッグストアになってました。もうひとつは残っていたけれど、お店のほうは開いているのか、閉店しているのかよく分からない状態。週末だからといって賑わっている感じでもなし。団地にはまだ人が住んでいるのだから、もっと人が居てもいいのにと思う。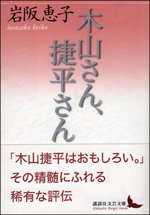 ■久しぶりの一人暮らしというわけで、週末になると、暑い中歩き回っている。
■久しぶりの一人暮らしというわけで、週末になると、暑い中歩き回っている。 ■2015年は電子音楽の夏、というわけではないけれど、先週の蓮沼執太のイベントに続き、宮内優里のライブを見てきました。ライブといっても会場は青山のFound MUJIで、それほど広くはない店内にたくさんの人が集まって、本人はほとんど見れず。今回のイベントでは、Found MUJIにある商品を使って即興でレコーディングしていくというものでした。事前に作ってきたリズムトラックに合わせて、缶や瓶、フライパンなどをたたく音をかぶせていき、最後にギターとキーボードでメロディ(?)を加えるという感じだったのですが、小気味のいいリズムとだんだんと曲が厚くなっていく様子に引き込まれていく感じでした。
■2015年は電子音楽の夏、というわけではないけれど、先週の蓮沼執太のイベントに続き、宮内優里のライブを見てきました。ライブといっても会場は青山のFound MUJIで、それほど広くはない店内にたくさんの人が集まって、本人はほとんど見れず。今回のイベントでは、Found MUJIにある商品を使って即興でレコーディングしていくというものでした。事前に作ってきたリズムトラックに合わせて、缶や瓶、フライパンなどをたたく音をかぶせていき、最後にギターとキーボードでメロディ(?)を加えるという感じだったのですが、小気味のいいリズムとだんだんと曲が厚くなっていく様子に引き込まれていく感じでした。 店内のライブにもかかわらず、アンコールにまで答えてくれて、最後は、お客さんのリクエストに答えて、まったく予定していなかった「読書」を弾き語りで歌ったりかなり得した気分。
店内のライブにもかかわらず、アンコールにまで答えてくれて、最後は、お客さんのリクエストに答えて、まったく予定していなかった「読書」を弾き語りで歌ったりかなり得した気分。 ■19歳の時に書いた「遠い園生」も収録されているが基本は70年代初めに書かれた短編をまとめたもの。悲劇の要素が強い「秋の朝 光のなかで」「サラマンカの手帖から」「風越峠にて」の3篇がよかった。久しぶりにフィクションを読んだ気がする。
■19歳の時に書いた「遠い園生」も収録されているが基本は70年代初めに書かれた短編をまとめたもの。悲劇の要素が強い「秋の朝 光のなかで」「サラマンカの手帖から」「風越峠にて」の3篇がよかった。久しぶりにフィクションを読んだ気がする。 アンビエントという言葉から静か目の音で音楽がなるがらんとした展示室を歩き回る感じをイメージしていましたが、かなり大きな音で音楽がなっており、BGMという感じはなく、5つのライブを同時に見ているようでした。それぞれの演奏(?)の手法も、テープを使うものやコントラバスを弾いたりするもの、Mac単体を操作しているものなど異なっていて興味深かったです。隣の展示室で奏でられている音に合わせて、演奏を変えたり、微妙に影響しあいつつ、それぞれの展示室だけでなく、美術館全体でも一つのライブを見ているみたいな雰囲気もありました。
アンビエントという言葉から静か目の音で音楽がなるがらんとした展示室を歩き回る感じをイメージしていましたが、かなり大きな音で音楽がなっており、BGMという感じはなく、5つのライブを同時に見ているようでした。それぞれの演奏(?)の手法も、テープを使うものやコントラバスを弾いたりするもの、Mac単体を操作しているものなど異なっていて興味深かったです。隣の展示室で奏でられている音に合わせて、演奏を変えたり、微妙に影響しあいつつ、それぞれの展示室だけでなく、美術館全体でも一つのライブを見ているみたいな雰囲気もありました。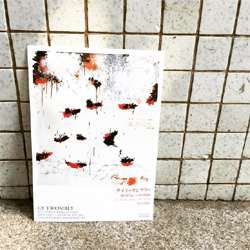 ■原美術館でやっていた「サイ トゥオンブリー:紙の作品、50年の軌跡」展は、前に日曜美術館で紹介されていたのを見て、機会があれば言ってみようと思った展覧会。サイ・トゥオンブリーを見たいというのが半分、カフェで中庭を眺めながらビールでも飲みたいというのが半分ってところか、と思っていたのだけれど、カフェのほうは満席でした。ザンネン。まぁこれだけ暑いとゆっくり休みたくなりますよね。
■原美術館でやっていた「サイ トゥオンブリー:紙の作品、50年の軌跡」展は、前に日曜美術館で紹介されていたのを見て、機会があれば言ってみようと思った展覧会。サイ・トゥオンブリーを見たいというのが半分、カフェで中庭を眺めながらビールでも飲みたいというのが半分ってところか、と思っていたのだけれど、カフェのほうは満席でした。ザンネン。まぁこれだけ暑いとゆっくり休みたくなりますよね。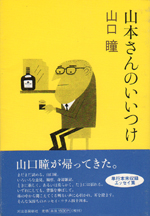 ■タイトルとなっている「山本さんのいいつけ」の山本さんとは一度だけ会って話をしたという山本周五郎のこと。その時に「出版社を限定して書け」「その出版社からジャンジャン前借りしろ」「メモをとれ日記をつけよ」と言われたけれど、ほとんど実行しなかったということがつづられている。ほかに江分利満について若いサラリーマンと伊豆にいった話、将棋について、向田邦子のことなど、1963年から1990年までに発表されたものが収録されているが、テーマや流れなどはない。作家の死後に編さんされたこういう本は、音楽で言ったらシングルのB面やデモを集めたものと思ってるので、その辺はもうあまり気にしていないし、内容も大きな発見などがあるわけではない。だったらなんで読むかというとただ時々山口瞳の文章を読みたくなるというだけ。そしてなんとなく気持ちだけでも背筋を伸ばしたいという気持ちがあるからなんだと思う。
■タイトルとなっている「山本さんのいいつけ」の山本さんとは一度だけ会って話をしたという山本周五郎のこと。その時に「出版社を限定して書け」「その出版社からジャンジャン前借りしろ」「メモをとれ日記をつけよ」と言われたけれど、ほとんど実行しなかったということがつづられている。ほかに江分利満について若いサラリーマンと伊豆にいった話、将棋について、向田邦子のことなど、1963年から1990年までに発表されたものが収録されているが、テーマや流れなどはない。作家の死後に編さんされたこういう本は、音楽で言ったらシングルのB面やデモを集めたものと思ってるので、その辺はもうあまり気にしていないし、内容も大きな発見などがあるわけではない。だったらなんで読むかというとただ時々山口瞳の文章を読みたくなるというだけ。そしてなんとなく気持ちだけでも背筋を伸ばしたいという気持ちがあるからなんだと思う。 ■「暮しの手帖」のパロディ「殺しの手帖」や、横山泰三、長新太、小島功風の画風で007を描いたり、「兎と亀」をヒッチコックやゴダール、ベイルマンなどの有名な監督が脚本を書いたらどうなるか、川端康成の「雪国」を書き出しを野坂昭如や植草甚一、星新一といった作家の作風で書いたものなど、「話の特集」に掲載されたものを中心に収録したヴァラエティブック。
■「暮しの手帖」のパロディ「殺しの手帖」や、横山泰三、長新太、小島功風の画風で007を描いたり、「兎と亀」をヒッチコックやゴダール、ベイルマンなどの有名な監督が脚本を書いたらどうなるか、川端康成の「雪国」を書き出しを野坂昭如や植草甚一、星新一といった作家の作風で書いたものなど、「話の特集」に掲載されたものを中心に収録したヴァラエティブック。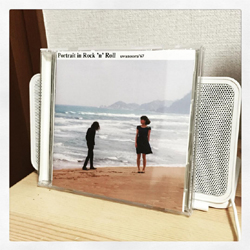 1曲目の「シェリーに首ったけ」などは、まさに「君は天然色」を2015年に再現したサウンドで、わくわくしてしまいます。YouTubeにあがっているPVを見るとドラムはツインだし、ほかの楽器もかなりオーバーダビングもしているしているようで、その凝り方が半端ない。歌詞の最後に月に吠えたりするところもGood!続く「年上ボーイフレンド」は「恋するカレン」や「Tシャツに口紅」を思い浮かべるし、「1969年のドラッグレース」的なセカンドラインのリズムと歌詞が楽しい「Hey×3・Blue×3」など、書き始めるときりがなくなってしまう。でもそれだけでなく、どこか「カップルズ」の頃のピチカートファイヴっぽい「傑作映画の後で」や、山下達郎の曲を思い起こさせる「レモンビーチへようこそ」、80年代のアイドルっぽい「Station No.2」など60年代のポップス全体、そして80年代の日本のポップス全体を視野に入れているところが、このアルバムが単なる真似に終わらず、普遍的なポップスの輝きを放っている所以なのではないだろうか。とかね。
1曲目の「シェリーに首ったけ」などは、まさに「君は天然色」を2015年に再現したサウンドで、わくわくしてしまいます。YouTubeにあがっているPVを見るとドラムはツインだし、ほかの楽器もかなりオーバーダビングもしているしているようで、その凝り方が半端ない。歌詞の最後に月に吠えたりするところもGood!続く「年上ボーイフレンド」は「恋するカレン」や「Tシャツに口紅」を思い浮かべるし、「1969年のドラッグレース」的なセカンドラインのリズムと歌詞が楽しい「Hey×3・Blue×3」など、書き始めるときりがなくなってしまう。でもそれだけでなく、どこか「カップルズ」の頃のピチカートファイヴっぽい「傑作映画の後で」や、山下達郎の曲を思い起こさせる「レモンビーチへようこそ」、80年代のアイドルっぽい「Station No.2」など60年代のポップス全体、そして80年代の日本のポップス全体を視野に入れているところが、このアルバムが単なる真似に終わらず、普遍的なポップスの輝きを放っている所以なのではないだろうか。とかね。 ■さて、話変わって連休の後半は、奥多摩にある百軒茶屋というキャンプ場に、漣くんの幼稚園の友だち3家族で行ってきました。キャンプ用品とか持ってないのでバンガローですけどね。百軒茶屋は大学の頃によく行ってバーベキューをしていたところ。最近はずっと行ってなくて15年ぶりくらいだったのですが、川の様子も変わってなくて、ちょっと懐かしかった。
■さて、話変わって連休の後半は、奥多摩にある百軒茶屋というキャンプ場に、漣くんの幼稚園の友だち3家族で行ってきました。キャンプ用品とか持ってないのでバンガローですけどね。百軒茶屋は大学の頃によく行ってバーベキューをしていたところ。最近はずっと行ってなくて15年ぶりくらいだったのですが、川の様子も変わってなくて、ちょっと懐かしかった。