 ◆連休中に行った展覧会をいくつか
◆連休中に行った展覧会をいくつか
前回に続いて小沼丹も出たらとりあえず買っておく系。今年に入ってもう一冊「更紗の絵」という本も出てるのでそちらも買っておかねば‥‥。講談社文芸文庫がそういう位置づけになりつつある今日この頃です。でも小沼丹は、老後の楽しみにしている全集はまだまだ読めないし、昔の単行本も高くて買えないので(昔よりも若干安くなってきてるような気も‥‥)、講談社文芸文庫から新しい本(?)が出るのはありがたい。意外と文芸文庫から小沼丹の本出てるんですよね。しかもあまり絶版になってない。(しかし7冊全部買うと9167円!)
■講談社文芸文庫から出ている小沼丹の本
「銀色の鈴」
「更紗の絵」
「村のエトランジェ」
「懐中時計」
「小さな手袋」
「埴輪の馬」
「椋鳥日記」
あと創元推理文庫から「黒いハンカチ」という探偵小説も出ています。
さて、この本は、戦中に疎開先での教員体験をユーモラスに描いた大寺さんものの「古い編上靴」、信州に別荘を持った友人を訪ねる「山のある風景」、戦前の良き時代の交友を語る「昔の仲間」、こどもの頃に定期的に訪ねた逗子の伯母の別荘でのできごとを語りつつ、伯母の家の凋落に時代の変遷を重ねる「小径」など7篇が収録されています。
どれも淡々とした文体でつづられた穏やかないい作品なのですが、なんといっても表題になっている「銀色の鈴」がいい。前妻の突然の死から再婚するまでを描いていて、自身の経験をもとにしているのにもかかわらず心情の告白するわけでもなく、娘たちとの葛藤があるわけでもなく、あくまでも普通の生活としての娘さんや飲み屋のおかみさん、作家仲間たちとのやりとりがあって、その間にあっさりとした表現で主人公の気持ちがつづられてます。そんな日々の表層の部分だけを切り取って巧みにっないでるだけなのに、行間から深い感情がじわあっと浮き上がってきます。この大寺さんという視点の人物を作ったことで、「いろんな感情が底に沈殿した後の上澄みのようなところが書」けたと小沼丹自身も言っていたようです。
ちなみに大寺さんものは以下の12篇。全部収録した文庫をどこかで出してくれないものかな。文芸文庫が難しいならちくま文庫でお願いします!(ちくま文庫のほうがあってる気がしますね)
■大寺さんもの
「黒と白の猫」
「タロオ」
「蝉の脱殻」
「揺り椅子」
「古い編上靴」
「銀色の鈴」
「藁屋根」
「眼鏡」
「沈丁花」
「鳥打帽」
「入院」
「ゴムの木」
さて、先週からミオ犬と子どもたちが長崎に帰っていたので、連休はなんとなく美術館巡り。去年もそうだったけれど、映画もぜんぜん見なくなってしまって久しいし、行きたくなるようなライブとかイベントがタイミングよく帰省中にあるということもそんなにないし、ついでに古本屋とかCDショップをまわりつつ行くとことと言えばまぁ美術館ぐらいしかないんですよね。
そんなわけで見に行った展覧会についてちょっとずつ。
■「操上和美写真展:時のポートレイト」
展覧会といえばまず東京都写真美術館を調べてしまう。でも操上和美についてはまったく知らなくて、説明によると「70年代から、日産『フェアレディZ』、サントリー『オールド』、ブリヂストン『レグノ』等のCMや、ロバート・フランク、笠智衆、キース・リチャーズ等のポートレイト」を手掛けているとのことで、最初はあんまり興味もなかったのですが、調べていくうちに初期の頃から「Switch」の表紙を手掛けていることを知り、興味がわいてきた次第。
実際にはコマーシャルフォトが展示されているわけではなく、おもちゃのカメラで撮影されたモノクロ写真や、故郷である北海道への旅をまとめたシリーズ、日常的に撮りためたスナップショットと、3つのシリーズの写真作品が展示されています。
特におもちゃカメラで撮られた「陽と骨」シリーズの作品は、元々が粗いにもかかわらず、それをさらに引き伸ばしていて、ざらざらとした質感や傷が生々しくてよかったですね。結局、モノクロでもカラーでも作品の中に詰め込まれた情報量が削られたものが好きなんだなあ~
■「大正・昭和のグラフィックデザイン小村雪岱展」
小村雪岱は原田治の「ぼくの美術帖」で知った画家。この展覧会では、泉鏡花などの本の装幀や舞台装置の原画などが展示されてます。描かれている内容は、女性の雰囲気も含めて江戸情緒にあふれているのですが、全体から受ける印象は洗練されていてその折衷がすばらしい。少女趣味っぽいところや色気にはしることもなく描いている対象を冷静に眺めてるところがいいな、と。実際は気に入った女子をモデルにして描いてるらしいので単にイメージなのかもしれないですけどね。
それにしても100年近く前に刊行された本も展示されているのですが、どれも状態がよくてびっくりです。個人蔵となっていたけれど、どんなコレクターが所有しているのだろうか。かなり気になります。あと今出ている本が100年後にこんな風に展示されるようなことがあるのかなぁ?ともちょっと思いましたね。電子書籍だから劣化せず100年後も今と同じ状態で見れるのか?しかし少なくとも紙の本は個人でもちゃんとすれば、100年保存できるかもしれないけど、100年後でもちゃんと起動するかたちでiPadを保存しておくのは無理だからねえ~
■「清方の美人画」
小村雪岱が鏡花の本の装幀を手掛ける前に、装幀を行っていたのが鏑木清方。芝木好子や戸板康二など最近読んだ本で続けてその名前が出てきていたりして気になってました。鎌倉に行ったときにちょっと時間が空いたので、いい機会と思い鏑木清方記念美術館に寄ってみることに。
ちょうど展示されていたのが、清方が鏡花をはじめとした挿絵画家として人気を得たあと、自由な画題で描きたいという思いから、日本画家に転身した後の時代の作品だったので、初心者としてはもう少しいろいろな面からこの画家の作品を見てみたいです。また機会があったらどこかの美術館に足を運んでみます。
■「芹沢銈介の作品と収集II 身にまとうよろこび」
去年から芹沢銈介の展覧会を見るのは3回目。今回は展覧会を見るというよりは、芹沢銈介美術館に行ってみたかっただけですね。実際、展示としては芹沢銈介の作品が半分、芹沢銈介が収集したアジアを中心とした着物や布が半分という感じでした。日本のものでは、影響を受けたと言われる沖縄のものがなかった気がしたけどなぜかな?
建物は建築家の白井晟一が設計したもので、建物の外の噴水と池、椿の緑、そしてそれを囲むような石の壁のコントラストとバランスがいい。そして建物の中は太い木の柱が多く使われていて、展示されている芹沢銈介の作品にマッチしていて、大胆に素材を使い分けている感じでした。
■「フィンランドのくらしとデザインームーミンが住む森の生活」展
こちらはついでに。見る前からわかっていましたが、ムーミンをはじめカイ・フランクの量産型食器、マリメッコのファブリック、アアルトの椅子や照明器具などについては、まとめた形で見るおもしろさはあったけれど、新鮮さはそれほどなかったです。それよりもフィンランドの自然を描いた絵画や彫刻、民族叙事詩「カレワラ」の挿絵原画など、前述のプロダクトデザインの土壌となった作品のほうがおもしろかったので、この辺の展示がもう少しあったらと思いました。(それだとキャッチーじゃなくなってしまい人が来なくなっちゃうのかもしれないけれど‥‥)

 ◆9月29日は暁くん1歳の誕生日でした
◆9月29日は暁くん1歳の誕生日でした

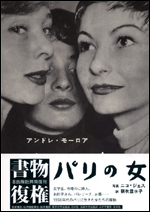 ◆明日は山下達郎の「サウンドクリエイターズファイル」の最終回
◆明日は山下達郎の「サウンドクリエイターズファイル」の最終回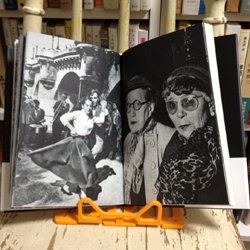 このアンドレ・モーロアとニコ・ジェスの「パリの女」は、シュガーベイブの「songs」に描かれたイラストの元ネタの写真が収録されていることで有名な(?)本。元ネタというかまあそのままです。いや、よく考えたらバンドのデビューアルバムのジャケットでなんでこの写真をイラストにして使おうと思ったのかがなぞ。音を何度も聴いてるとジャケットと合っていると思ってくるんだけど、デビューアルバムぽいフレッシュなインパクトはないですよねぇ~
このアンドレ・モーロアとニコ・ジェスの「パリの女」は、シュガーベイブの「songs」に描かれたイラストの元ネタの写真が収録されていることで有名な(?)本。元ネタというかまあそのままです。いや、よく考えたらバンドのデビューアルバムのジャケットでなんでこの写真をイラストにして使おうと思ったのかがなぞ。音を何度も聴いてるとジャケットと合っていると思ってくるんだけど、デビューアルバムぽいフレッシュなインパクトはないですよねぇ~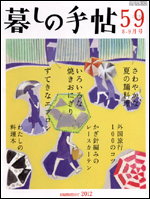 ◆月一ドライブ9月はこどもの国まで
◆月一ドライブ9月はこどもの国まで 今月は、こどもの国へ行ってきました。特に理由もないんですが、車を借りた時に行こうと思っていたところがダメになったので、適当にはなれた場所で漣くんが遊べそうなところという感じですね。
今月は、こどもの国へ行ってきました。特に理由もないんですが、車を借りた時に行こうと思っていたところがダメになったので、適当にはなれた場所で漣くんが遊べそうなところという感じですね。 でも動物園はそれほど広くはないのですが、実際に柵の中に入って触れるのがよかったです。こわがりな漣くんも動物に関してはあまりこわがらずに、うさぎや鹿の赤ちゃんとかを触ったりしてましたしね。
でも動物園はそれほど広くはないのですが、実際に柵の中に入って触れるのがよかったです。こわがりな漣くんも動物に関してはあまりこわがらずに、うさぎや鹿の赤ちゃんとかを触ったりしてましたしね。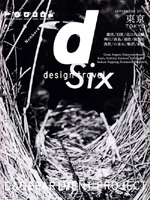 ◆ナガオカケンメイ×嶋浩一郎@B&B
◆ナガオカケンメイ×嶋浩一郎@B&B さて、対談のほうは最近刊行された「d design travel TOKYO」で紹介されているお店や人に関する取材時のエピソードや、これまでに出た「d design travel」を含めた雑誌の作り方、取材方法などについての話、そしてこれからの予定などをナガオカケンメイが話す横で、その話題に関する小ネタや豆知識を、嶋浩一郎がちょこちょこと披露するという内容でなかなか楽しかったです。
さて、対談のほうは最近刊行された「d design travel TOKYO」で紹介されているお店や人に関する取材時のエピソードや、これまでに出た「d design travel」を含めた雑誌の作り方、取材方法などについての話、そしてこれからの予定などをナガオカケンメイが話す横で、その話題に関する小ネタや豆知識を、嶋浩一郎がちょこちょこと披露するという内容でなかなか楽しかったです。 ◆三鷹 星と森と絵本の家
◆三鷹 星と森と絵本の家

 ◆約1か月ぶりの雑記だけど書いてる内容も1か月前の話。ボリショイサーカスに行ってきました
◆約1か月ぶりの雑記だけど書いてる内容も1か月前の話。ボリショイサーカスに行ってきました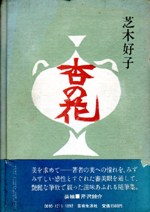 ◆宮内優里ライブ@江戸東京たてもの園下町夕涼み
◆宮内優里ライブ@江戸東京たてもの園下町夕涼み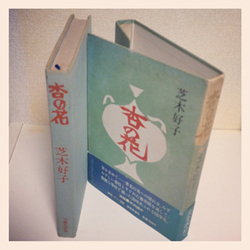 いろいろ技術が進歩したというけれど、本当の進歩というのは、「今までこういう本を作るのはものすごく手間がかかったけれど、手間が削減されてより簡単に同じものを作ることができるようになりました」ということなんじゃないかな。「こういう本を大量に作るのはやっぱり難しいから、より簡単に作れる本で大量生産を可能にしました。」ってのは進歩と言わないんじゃないだろうか、とか。あるいは「これからは○○だ」ではなく「今までは△△が主流だったけど、これからは△△とOOのそちらかが選べます」とか。こういう本に触れるといろいろ考えてしまう。多分、そうやってすべてにおいて昔に作られたきちんとしたいいものにちゃんと接するということが大事なんじゃないかな。そうしないと今ものとの違いや、これからのどういうものと自分がつきあっていくべきなのか、ということの判断ができなくなってしまうのではないかと思う。
いろいろ技術が進歩したというけれど、本当の進歩というのは、「今までこういう本を作るのはものすごく手間がかかったけれど、手間が削減されてより簡単に同じものを作ることができるようになりました」ということなんじゃないかな。「こういう本を大量に作るのはやっぱり難しいから、より簡単に作れる本で大量生産を可能にしました。」ってのは進歩と言わないんじゃないだろうか、とか。あるいは「これからは○○だ」ではなく「今までは△△が主流だったけど、これからは△△とOOのそちらかが選べます」とか。こういう本に触れるといろいろ考えてしまう。多分、そうやってすべてにおいて昔に作られたきちんとしたいいものにちゃんと接するということが大事なんじゃないかな。そうしないと今ものとの違いや、これからのどういうものと自分がつきあっていくべきなのか、ということの判断ができなくなってしまうのではないかと思う。
 ◆三連休はバーベキュー三昧(ってほどでもないか)
◆三連休はバーベキュー三昧(ってほどでもないか)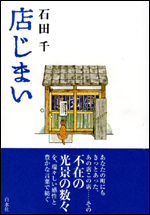 ◆今年、前半の後半によく聴いたCD
◆今年、前半の後半によく聴いたCD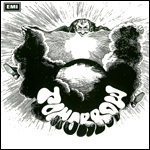 トゥモロウに限らず、ニック・ロウが在籍していたというキッピントン・ロッジや「ティーンエイジオペラ」「ラテン・ア・ゴー・ゴー」といったソロなどマーク・ワーツ関連のCDをけっこう聴いてましたね。マーク・ワーツはCD化されてないイージーリスニング~ラウンジ系のソロアルバムなどもたくさんあるみたいなのでそれらも機会があれば聴きたいところ(高そうだが)。で、このトゥモロウですが、テープの逆回転やインド風味なテイストなどをサイケデリックな要素をうまく取り入れつつも、プリティッシュビート~スウィンギソロンドン的なポッブなサウンドマナーをしっかり守っている感じが気に入ってます。
トゥモロウに限らず、ニック・ロウが在籍していたというキッピントン・ロッジや「ティーンエイジオペラ」「ラテン・ア・ゴー・ゴー」といったソロなどマーク・ワーツ関連のCDをけっこう聴いてましたね。マーク・ワーツはCD化されてないイージーリスニング~ラウンジ系のソロアルバムなどもたくさんあるみたいなのでそれらも機会があれば聴きたいところ(高そうだが)。で、このトゥモロウですが、テープの逆回転やインド風味なテイストなどをサイケデリックな要素をうまく取り入れつつも、プリティッシュビート~スウィンギソロンドン的なポッブなサウンドマナーをしっかり守っている感じが気に入ってます。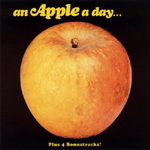 キンクスのプロデューサーとして知られるラリー・ペイジによるレーベル、ペイジ・ワンから1969年に発売された唯一のアルバム。オリジナル版はン十万円もするらしいです。グループ名とジャケットからなんとなくビートルズのアップル関連のグループなのではないかと思ったりしてましたが、どうやら違うらしいです。サウンド的にはビートルズの影響は大きいですけど。いや、ビートルズの影響を受けていないイギリスのポッブサイケのバンドなんてないんじゃないかと。メロディやサウンドもポッブで聴きやすいのですが、何回か聴いていると意外とハードなギターが鳴っているのに気がついたりして、それが聴き飽きないアクセントになっています。
キンクスのプロデューサーとして知られるラリー・ペイジによるレーベル、ペイジ・ワンから1969年に発売された唯一のアルバム。オリジナル版はン十万円もするらしいです。グループ名とジャケットからなんとなくビートルズのアップル関連のグループなのではないかと思ったりしてましたが、どうやら違うらしいです。サウンド的にはビートルズの影響は大きいですけど。いや、ビートルズの影響を受けていないイギリスのポッブサイケのバンドなんてないんじゃないかと。メロディやサウンドもポッブで聴きやすいのですが、何回か聴いていると意外とハードなギターが鳴っているのに気がついたりして、それが聴き飽きないアクセントになっています。 力レイドスコーブという名前のバンドは、アメリカにも日本にありますが、ジャケットもサウンドもアメリカからは出てこないバンド。サイケとフォーク(イギリスのね)とブログレ的な要素がまじりあって、なんとなくつかみどころがないサウンドになってる気がします。いや、端的にサウンドを説明すると直球のサイケなのですが‥‥。加えていい意味でも悪い意味でも強い個性を持ったメンバーがいないため、ポッブなんだけど地味な感じは否めないです。そういう部分も含めて、すべてがイギリスぼいスタイルで統一されているところがよかったりするんですけどね。あとマイナーなメロディがわりと多いんですが、メロディがマイナーになると一気に日本のGSぽい雰囲気になりますね。
力レイドスコーブという名前のバンドは、アメリカにも日本にありますが、ジャケットもサウンドもアメリカからは出てこないバンド。サイケとフォーク(イギリスのね)とブログレ的な要素がまじりあって、なんとなくつかみどころがないサウンドになってる気がします。いや、端的にサウンドを説明すると直球のサイケなのですが‥‥。加えていい意味でも悪い意味でも強い個性を持ったメンバーがいないため、ポッブなんだけど地味な感じは否めないです。そういう部分も含めて、すべてがイギリスぼいスタイルで統一されているところがよかったりするんですけどね。あとマイナーなメロディがわりと多いんですが、メロディがマイナーになると一気に日本のGSぽい雰囲気になりますね。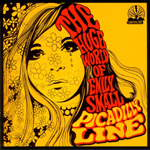 男性二人によるデュオによる1967年のアルバム。二声のコーラスで歌われる柔らかなメロディに、繊細なオーケストラが全体を覆う優しいサウンドで、トリップ感や妖しい感じはまったくなく、ポッブサイケというよりソフトロックに近いです。アメリカのバンドのような開放感はなく箱庭的なせいか、初期のドノヴァンとかアル・スチュアートなどの音を思い出したりします。あとニック・ドレイクとか。あそこまで繊細じゃないか。この後、二人はエドワーズ・八ンドと改名し、ジョージ・マーティンのプロデュースのもと、英国的な叙情性を持ち合わせたトラッドなアルバムを発表することを考えると、時代的な影響でこういうサウンドになったという感じなのかもしれません。
男性二人によるデュオによる1967年のアルバム。二声のコーラスで歌われる柔らかなメロディに、繊細なオーケストラが全体を覆う優しいサウンドで、トリップ感や妖しい感じはまったくなく、ポッブサイケというよりソフトロックに近いです。アメリカのバンドのような開放感はなく箱庭的なせいか、初期のドノヴァンとかアル・スチュアートなどの音を思い出したりします。あとニック・ドレイクとか。あそこまで繊細じゃないか。この後、二人はエドワーズ・八ンドと改名し、ジョージ・マーティンのプロデュースのもと、英国的な叙情性を持ち合わせたトラッドなアルバムを発表することを考えると、時代的な影響でこういうサウンドになったという感じなのかもしれません。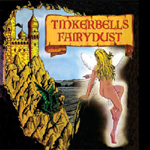 バッ八の「誓いのフーガ」が日本だけでヒットしたというグループ。クラッシックをもとにした曲って日本人好きですよね。これは当時録音はされたもののお蔵入りとなったアルバムにシングルトラックをカップリングしたもの。スパンキー&アワ・ギャングの「Lazy Day」やアソシエイションの「Never My Love」のカバーなどが収録されていたり、ビーチボーイズ風のコーラスが聴ける曲があったりとソフトロック度はかなり高め。でも油断して聴いているとヴァニラ・ファッジのバージョンをベースにした「(You Keep Me)Hangin’On」やヤードバーズのカバーなどハードな曲がはじまったりしてびっくりします。
バッ八の「誓いのフーガ」が日本だけでヒットしたというグループ。クラッシックをもとにした曲って日本人好きですよね。これは当時録音はされたもののお蔵入りとなったアルバムにシングルトラックをカップリングしたもの。スパンキー&アワ・ギャングの「Lazy Day」やアソシエイションの「Never My Love」のカバーなどが収録されていたり、ビーチボーイズ風のコーラスが聴ける曲があったりとソフトロック度はかなり高め。でも油断して聴いているとヴァニラ・ファッジのバージョンをベースにした「(You Keep Me)Hangin’On」やヤードバーズのカバーなどハードな曲がはじまったりしてびっくりします。