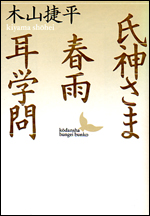 ◆冬から春にかけて聴いてたCDをいくつか
◆冬から春にかけて聴いてたCDをいくつか
講談社文芸文庫からでている木山捷平の本もようやくそろって、これでおしまい。木山捷平は作品数もそれほど多くないので、全作品をカバーしてくれれぱいいのに、なんて思ったりしますが難しいのかな。文芸文庫は短編集に関してはオリジナルに編纂したものも多いし(最近はそうでもない?)、網羅性という意味ではちょっと弱い。
あと、すぐに品切れになるものと増判されてわりといつまでも残っているものと分かれる気がするけれど、その区別はどこでつけてるんでしょうかね。単に売れてる売れてないだけではないような気がしますが。
さて最近よく聴いているCDをいくつか。(しかし前回もそうだったけど、このテーマで何か書こうとすると放置状態になって更新が遅れますね)
ざっくりと言って、今年に入ってからはイギリスのソフトロック~ハーモニーボップばかり聴いてます。去年の終わり頃に、来年は60年代の音楽をちゃんと聞きなおしてみようかな、なんてことをなんとなく思っていたら、年の初めのサンデーソングブックでバタースコッチの「そよ風の二人」がかかったので、一気にイギリスへ行ってしまった感じですね。「そよ風の二人」は1970年のヒット、というツッコミはなしで。あ、でも60年代って1961年から1970年までですってことで。
やっぱり、イギリスのポップスは、カラッと晴れわたってない分(偏見)、冬から春にかけての時期がよく似合う。まぁ今年は、3月になってもダッフルコートが手放せないくらい、いつまでも寒くてなかなか春になってくれませんでしたが。
 ■「Don’t You Know It’s Butterscotch」-Butterscotch-
■「Don’t You Know It’s Butterscotch」-Butterscotch-
工ジソンライトハウスをはじめ、バリー・マニロウやクリフ・リチヤードなどに曲を提供しているソングライターグループ、アーノルド、マーティン&モローのグループ。このCDのほかに最近、このチームがぽかの歌手に提供した曲を収録した作品集「Cant Smile Without You-1966_77」も出ています。イギリスだけではないけれど、60年代後半から70年代初めはこういう作家たちによるグループが多い。モンキーズの影響なんでしょうかねぇ。でもこの流れがキャロル・キングなどのSSWにつながっていくのかも、とか適当に言ってみたりして。で、このバタースコッチ、無理のない自然できれいなメロディとハーモニー、弾むような適度なピート感、そしてそれらを盛り上げるストリングスなど、バンク/ニューウェイヴ以降では考えられないストレートなサウンドのポップス。ヒットした「そよ風の二人」はもちろん、「Constant Reminder」「All On A Summers Day」や「Cows」などどれも名曲ばかり、なにげにインストの「Theme For A Theme」とかもちょっとヨーロッパの映画音楽風で気に人っていたりします。
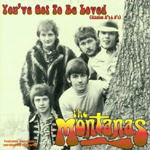 ■「You’ve Got To Be Loved」-The Montanas-
■「You’ve Got To Be Loved」-The Montanas-
1965年から1969年にかけてパイ・レーベルから出したシングル曲と未発表曲を網羅したペスト盤。このほかにMCAからシングルを1枚出しているだけでアルバムは残していないようです。拙い感じのR&B的な曲が数曲ありますが、トニー・ハッチがプロデュースを手掛けているだけあって、洗練したサウンドとコーラスがすばらしい。タイトルにもなっているトニー・ハッチ作の「You’ve Got To Be Loved」と董頭に、いま聴くと60年代にしか生まれようがなかった60年代的な名曲ではあるのだけれど、60年代後半のイギリスでこれが売れる感じはしないのはなぜだろう?もしかしたらロジャー・ニコルスで一番好きな曲かもしれない「Let’s Ride」のカバーも、原曲の雰囲気を残しつつ、自分たち(なのかな?)の個性もさりげなく主張(とまではいかないか)していてロジャー・ニコルズ&ア・スモール・サークル・オプ・フレンズよりもいいんじゃないかと思ったり、思わなかったり。しかしこのさりげなさがモンタナスのよさでもあり、弱みだったのかもしれない、とか思ったり、思わなかったり。
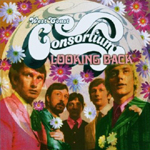 ■「Looking Back」-West Coast Consortium-
■「Looking Back」-West Coast Consortium-
トニー・マコウレイのことを調べてる時に知ったグループで、1967年から1970年にかけてPyeからリリースしたシングルのA面B面に未発表音源を加えたコンピ盤。「All The Love ln The World」という曲がイギリスでヒットしているのみでThe Montanasと同じでアルバムは出していないようです。この辺のイギリスのグループってシングル盤だけ出して解散しちゃったバンドが多いですね。というか、名義的にはWest Coast ConsortiumだったりConsortiumだったりROBBIEだったりしているとはいえ、 PYEだけで7枚のシングルを出してる段階で曲数的にはアルバム作れちゃうって気がしますが。まあアルバムよりもシングルが重視されていたってことなんでしょう。トニー・マコウレイ関連でたどり着きましたが、収録されてるのはメンバーによる曲が多く、これがソフトサイケだったり、フォークロックぽかったりGSぽかったりとさまざまですが、どれもポップでしてよいです。ちなみにこの後メンバーはAlRBUSというプロジェクトに発展するらしいのですが、こちらはまだ未聴。
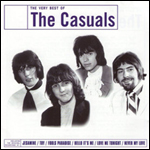 ■「The Very Best Of」-The Casuals-
■「The Very Best Of」-The Casuals-
1968年に全英で2位となった「Jesamine」や「Toy」(30位)を収録したベスト盤。ジャケットがかなり‥‥な感じなのですが、ロジャー・ニコルス/ポール・ウィリアムズ作の「Someday Man」やニルソン作の「Daddy’s Song」、アソシエーションの「Never My Love」といったカバーが収録されていて、いかにもこういった曲をカバーしそうなサウンドのバンド。一瞬「Hello lt’s Me」も?とか思ったけれどそんなわけはない、ですよね。「Jesamine」はバイスタンダーズの 「When Jesamine Goes」をタイトルを変えたカヴァー。また前述のアーノルド、マーティン&モローやロイ・ウッドによる曲などもあり、曲自体のある程度のクオリティを保ってます。でもこういうバンドを続けて聴いていると、バンドの個性ってなんなんだろう、という疑問が頭をかすめてしまうのも事実。その点、アメリカのコーラスグループだったりソフトロックと呼ばれるグループは、売れたかどうかは別としてそれぞれのバンドで個性と出すことに成功しているような気がします。この辺は層の厚さの違いなのだろうか。
 ■「Flying Machine」-Flying Machine-
■「Flying Machine」-Flying Machine-
ほんとはPickettywitchの「That Same Old Feeling」を聴きたいと思っているのだけれど、CDが見つからなくて代わりにこれが見つかったという。Flying Machineも長いこと行方不明だったのでうれしいけれど、「That Same Old Feeling」はPickettywitchのバージョンのほうが好きかな。とはいうもの「Smile A Little Smile For Me」「Send My Baby Home Again」「Marie Take A Chance」と冒頭で続くトニー・マコウレイの3曲でノックアウトなアルバムです。
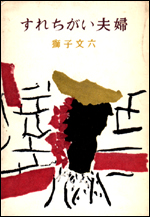 ◆病み上がりにカフェスローへ
◆病み上がりにカフェスローへ 木曜の夜から熱を出しまして、金曜、土曜と一日中寝込んでいたのですが、日曜になってようやく治ってきた感じだったので、気分転換も兼ねて国分寺に出てカフェスローに行ってきました。ちょうどカフェスローではゆっくり市が開催されていて、中庭(?)もにぎやか、お店のほうも満席に近い感じでした。ここはお店自体も広いし、机と机の間がゆったりしているので、満席に近くてもそれほど人がいる感じがしなくて、普通にベビーカーをお店に入れられるので家族で行くにはちょうどいいです。意外と漣くんも玄米のおにぎりやチリビーンズをのせたパンなどぱくぱく食べますしね。
木曜の夜から熱を出しまして、金曜、土曜と一日中寝込んでいたのですが、日曜になってようやく治ってきた感じだったので、気分転換も兼ねて国分寺に出てカフェスローに行ってきました。ちょうどカフェスローではゆっくり市が開催されていて、中庭(?)もにぎやか、お店のほうも満席に近い感じでした。ここはお店自体も広いし、机と机の間がゆったりしているので、満席に近くてもそれほど人がいる感じがしなくて、普通にベビーカーをお店に入れられるので家族で行くにはちょうどいいです。意外と漣くんも玄米のおにぎりやチリビーンズをのせたパンなどぱくぱく食べますしね。
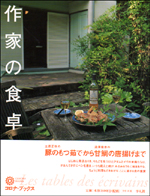 ◆作家の食卓がおいしそうなのは文章の力なのかもしれない
◆作家の食卓がおいしそうなのは文章の力なのかもしれない ◆電子音楽/ノイズ音楽の耐久レースライブイベント+ポーチでふるまいバーベキュー@セプチマ
◆電子音楽/ノイズ音楽の耐久レースライブイベント+ポーチでふるまいバーベキュー@セプチマ

 ◆カヌー犬ブックスも9周年を迎えました。ありがとうございました。
◆カヌー犬ブックスも9周年を迎えました。ありがとうございました。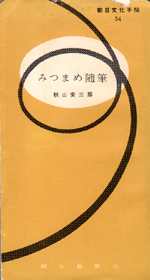 ◆ゴーグリーンマーケット@京王フローラルガーデシアンジェ
◆ゴーグリーンマーケット@京王フローラルガーデシアンジェ


 ◆東京蚤の市、ぶじ終了しました。皆さまありがとうございました!
◆東京蚤の市、ぶじ終了しました。皆さまありがとうございました!
 ◆いよいよ週末は東京蚤の市!
◆いよいよ週末は東京蚤の市!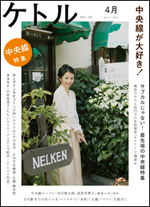 ◆5/26日、5/27に京王閣で行われる東京蚤の市に参加させていただきます。
◆5/26日、5/27に京王閣で行われる東京蚤の市に参加させていただきます。
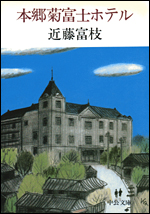 ◆奈良原一高と堀野正雄と口ベール・ドアノー
◆奈良原一高と堀野正雄と口ベール・ドアノー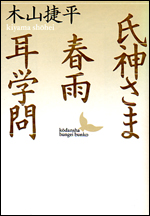 ◆冬から春にかけて聴いてたCDをいくつか
◆冬から春にかけて聴いてたCDをいくつか ■「Don’t You Know It’s Butterscotch」-Butterscotch-
■「Don’t You Know It’s Butterscotch」-Butterscotch-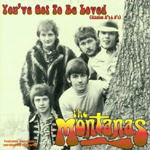 ■「You’ve Got To Be Loved」-The Montanas-
■「You’ve Got To Be Loved」-The Montanas-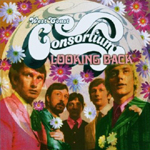 ■「Looking Back」-West Coast Consortium-
■「Looking Back」-West Coast Consortium-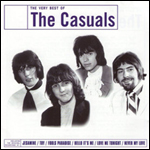 ■「The Very Best Of」-The Casuals-
■「The Very Best Of」-The Casuals- ■「Flying Machine」-Flying Machine-
■「Flying Machine」-Flying Machine-