 ◆3月30日にはけのおいしい朝市@江戸東京たてもの園に参加します~
◆3月30日にはけのおいしい朝市@江戸東京たてもの園に参加します~
■林芙美子というとやはり「放浪記」のイメージが強い。で、「放浪記」というと森光子のでんぐり返りが思い出されてしまっていまいち読もうとする気も起きないし、ましてやどこかで「自分の作品が世に出て認められるためには、ほかの作家を蹴落とすことでも目立つことでもなんでもする、手段を選ばない自己顕示欲のかたまりのような性格」などとという文章を読んでしまったらなおのこと。なんて思いつつも、「下駄で歩いた巴里」とかこの随筆集は読んでみたいと前々から思っていたのはなんでだったのだろうか?
この随筆集では友人との交流や住んでいる下落合周辺の様子など身辺雑記的な内容を中心に、旅に出たときの話や恋愛感などが加わるのだが、どれも楽しみながら書いている(いや、楽しみながら暮らしている)感じが伝わってきてよかった。中にはちょっとしたいざこざと書いたものとかありますけどね。恋愛感などはこの時代に女性がこういう考え方を書くということはどういうことだったんだろう、なんてちょっと思ったりしますが、実際にこの時代の人たちが、どういう考え方で恋愛をしていたか分からないのでなんともいえない。昔はこうだった、なんて紋切り型で示されることのほとんどは、人も思い込みの積み重ねでしかないからだ。
岩本素白の随筆を読んだ後だからかもしれないですが、(分量も含めて)もう少していねいな編集だったらよかったのにともちょっと思ってしまいますが‥‥
■3月に入ったので、もうダッフルコート、ニット帽、手袋で通勤するのはやめよう。少しくらい寒い日があっても我慢する、と思っていたのだけれど、2月の終わりに暖かい日があったと思ったら急に寒くなってしまい、まだニット帽、手袋が手放せない。自転車で駅までに行くときが寒いんですよね。
ニット帽は10年前くらいに買ったSILASのものをずっとかぶり続けてます。よく見ると外側が色あせてきているが、あまり気にしてない。代官山なんてもうずっと行ってないけど、どうなってるのだろう?今行ったら迷ってしまいそうだ。ボーネルンドもあるし暖かくなったら行ってみようかね。そういえば昔は、子どもが生まれたら子ども連れでOKURAに行きたいって思ってたな。
 ■3月30日に小金井公園の江戸東京たてもの園で行われるはけのおいしい朝市に、参加します。今回は開園20周年&30棟完成 江戸東京たてもの園フェスティバルの一環として、30のお店が、下町風情が漂う昔の商家・銭湯・居酒屋などが立ち並ぶ東ゾーンに並びます。カヌー犬ブックスは、去年、小金井神社で行われた50回記念のときと同じく、レコード屋のHigh Fidelityさんと一緒に出店します。
■3月30日に小金井公園の江戸東京たてもの園で行われるはけのおいしい朝市に、参加します。今回は開園20周年&30棟完成 江戸東京たてもの園フェスティバルの一環として、30のお店が、下町風情が漂う昔の商家・銭湯・居酒屋などが立ち並ぶ東ゾーンに並びます。カヌー犬ブックスは、去年、小金井神社で行われた50回記念のときと同じく、レコード屋のHigh Fidelityさんと一緒に出店します。
まだどんな本を持っていくか、ちゃんと決めてませんが、場所にあわせてちょっと古めの本を中心に持っていきたいと思っています。ほんとは外に出店するときにいつも使っているカラーボックスではなく、もう少し渋い雰囲気の本棚にもしたいところなんですけどね。ちなみに本屋さんとしては、ニチニチ日曜市おなじみの古本泡山さんとやぼろじでギャラリーも運営しているcircleさんも出店します。
小金井公園は、武蔵小金井からバス5分というちょっと行きにくい場所ですが、たぶん、咲き始めの桜も楽しめる時期なので、江戸東京たてもの園だけではなく小金井公園でものんびりと楽しめるのではないかと思ってます。

 ◆手紙社さんのアカテガミー賞の授賞式に行ってきました~
◆手紙社さんのアカテガミー賞の授賞式に行ってきました~

 ◆スプンフルさんとシャトー2Fさん
◆スプンフルさんとシャトー2Fさん スプンフルさんには、去年の2月くらいからイベントで使っている四角いボックスを3つ分ほど本を置いていて、ボックスごとにちょっとしたテーマを決めて本を持っていっています。気持ちとしては、毎週、1つのボックス分の本を毎週入れ替えていこうと思っているのですが、最近は2週間に一回ぐらいになってしまっている感じですね。
スプンフルさんには、去年の2月くらいからイベントで使っている四角いボックスを3つ分ほど本を置いていて、ボックスごとにちょっとしたテーマを決めて本を持っていっています。気持ちとしては、毎週、1つのボックス分の本を毎週入れ替えていこうと思っているのですが、最近は2週間に一回ぐらいになってしまっている感じですね。 ◆「無茶法師」と「笛吹銅次」
◆「無茶法師」と「笛吹銅次」 ◆2013年にイコンタで撮った子どもの写真
◆2013年にイコンタで撮った子どもの写真
 6×4.5cm判をスーパーセミイコンタ、6x6cm判をスーパーシックスそして6x9cm判をスーパーイコンタと呼んでいて、それぞれいくつもの機種があります。わたしが使っているイコンタは Super-Ikonta Six 3型で、1954年に登場したもの。6×6フィルムのカメラとしては小型で、蛇腹をしまった状態でなら持ち歩きもかなり楽。ちょうどモレスキンを携帯するためのポーターのモバイルバッグに入れるとぴったりだったので、どこかに出かけるときはたいてい肩からポーターのバッグをかけてます。
6×4.5cm判をスーパーセミイコンタ、6x6cm判をスーパーシックスそして6x9cm判をスーパーイコンタと呼んでいて、それぞれいくつもの機種があります。わたしが使っているイコンタは Super-Ikonta Six 3型で、1954年に登場したもの。6×6フィルムのカメラとしては小型で、蛇腹をしまった状態でなら持ち歩きもかなり楽。ちょうどモレスキンを携帯するためのポーターのモバイルバッグに入れるとぴったりだったので、どこかに出かけるときはたいてい肩からポーターのバッグをかけてます。 ◆今年は1963年のアメリカンポップスをテーマにしたい(のだが‥‥)
◆今年は1963年のアメリカンポップスをテーマにしたい(のだが‥‥)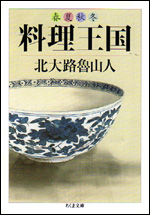 ◆1月に行った展覧会。ルネ・ブリ&ヴォルフガング・ティルマンス
◆1月に行った展覧会。ルネ・ブリ&ヴォルフガング・ティルマンス ルネ・ブリの写真展は、1950年代末~60年代半ばにかけて撮影された代表作品が14点と、それほど点数も多くなかったのですが、モノクロで撮られたポートレートやスナップは、どれもプリントがきれいで、ついなんども見てしまうほどでした。
ルネ・ブリの写真展は、1950年代末~60年代半ばにかけて撮影された代表作品が14点と、それほど点数も多くなかったのですが、モノクロで撮られたポートレートやスナップは、どれもプリントがきれいで、ついなんども見てしまうほどでした。 ヴォルフガング・ティルマンスのほうは、2004年にオペラシティーで行われた展覧会ぶり。10年前かと思うとなんだかびっくり。最近は世界各地を旅しながら撮影をおこなったり、印画紙を操作して抽象絵画のような作品を撮っているらしく、そういった作品を中心に展示されていました。世界各地といっても作品自体は、日常の延長というかミニマムな世界なんですけどね。
ヴォルフガング・ティルマンスのほうは、2004年にオペラシティーで行われた展覧会ぶり。10年前かと思うとなんだかびっくり。最近は世界各地を旅しながら撮影をおこなったり、印画紙を操作して抽象絵画のような作品を撮っているらしく、そういった作品を中心に展示されていました。世界各地といっても作品自体は、日常の延長というかミニマムな世界なんですけどね。 ◆「1を知るには10を知れ」
◆「1を知るには10を知れ」 ◆古本屋の思い出(と言うほどものでもない)
◆古本屋の思い出(と言うほどものでもない) ◆ゲイリー・ウィノグランド展@タカイシイギャラリーとジョナス・メカス展@ときの忘れもの
◆ゲイリー・ウィノグランド展@タカイシイギャラリーとジョナス・メカス展@ときの忘れもの ゲイリー・ウィノグランドは、もともとは広告の写真を撮っていたのですが、ロバート・フランクの影響を受けて1960年代前半からストリート・スナップを撮り始めた写真家。広角レンズを着けたカメラで、人物などを近い距離から撮影するという手法を用いています。そのため人物だけでなくその周りの風景や歩く人なども一緒に撮影されているのですが、広角レンズで撮っているため、被写体の比率が微妙に変わってしまったり、垂直に建っているはずの建物が斜めになってしまったりして、不安定な構図の写真になっています
ゲイリー・ウィノグランドは、もともとは広告の写真を撮っていたのですが、ロバート・フランクの影響を受けて1960年代前半からストリート・スナップを撮り始めた写真家。広角レンズを着けたカメラで、人物などを近い距離から撮影するという手法を用いています。そのため人物だけでなくその周りの風景や歩く人なども一緒に撮影されているのですが、広角レンズで撮っているため、被写体の比率が微妙に変わってしまったり、垂直に建っているはずの建物が斜めになってしまったりして、不安定な構図の写真になっています ジョナス・メカスのほうは「ジョナス・メカスとその時代展」というタイトルどおり、アンディ・ウォーホルやピーター・ビアード、ジョン・ケージといったアーティストの作品も展示されていて、ジョナス・メカスの作品は10点ほど。ただ日替わりでジョナス・メカス映像作品の上映も行われていました。わたしが行ったときも「Walden」という日常の風景を切り取った作品が上映されていましたが、時間がなくてちょこっと見て出てきてしまいました。映像もいいけれど、1時間以上見続けるのはちょっと辛いかも?それよりもやはりフィルムをつなぎ合わせてプリントした作品のほうが好きですね。ジョナス・メカスはきちんとまとめた形の展覧会をどこかでやって欲しいなぁ。
ジョナス・メカスのほうは「ジョナス・メカスとその時代展」というタイトルどおり、アンディ・ウォーホルやピーター・ビアード、ジョン・ケージといったアーティストの作品も展示されていて、ジョナス・メカスの作品は10点ほど。ただ日替わりでジョナス・メカス映像作品の上映も行われていました。わたしが行ったときも「Walden」という日常の風景を切り取った作品が上映されていましたが、時間がなくてちょこっと見て出てきてしまいました。映像もいいけれど、1時間以上見続けるのはちょっと辛いかも?それよりもやはりフィルムをつなぎ合わせてプリントした作品のほうが好きですね。ジョナス・メカスはきちんとまとめた形の展覧会をどこかでやって欲しいなぁ。