 「ku:nel」を眺めながらたまには料理でもしたいな、と思いつつ、夜中の3時半、会社帰り、旧山手通りを走るタクシーの中で、次の日曜日になにを作ろうか、なんて考えていたのは、もう2カ月前のこと。まだ冬の真っ盛りでものすごく寒かったけれど、2カ月経った今でもまだ寒くて、ピーコートが手放せない毎日。まだまだ春は遠いのか。井の頭公園の桜は少しくらい目が出てきたいしているのかな。
「ku:nel」を眺めながらたまには料理でもしたいな、と思いつつ、夜中の3時半、会社帰り、旧山手通りを走るタクシーの中で、次の日曜日になにを作ろうか、なんて考えていたのは、もう2カ月前のこと。まだ冬の真っ盛りでものすごく寒かったけれど、2カ月経った今でもまだ寒くて、ピーコートが手放せない毎日。まだまだ春は遠いのか。井の頭公園の桜は少しくらい目が出てきたいしているのかな。
料理だけに限らず、自分の手を動かして何かを作るというのは、楽しい。豆本の写真集や部屋に置く棚やテーブルを作ったり、フリーペーパーも、PCで作れる環境になっても最後まで、写真やイラストを切り貼りしてた。そして、単に紙を四つ折りするだけの作業でさえ、楽しかった、ような気がする。音楽をかけたり、スペースシャワーTVで週に何度も再放送される番組をつけっぱなしにしたりして、一人で、あるいは友達と「缶ジュースの缶で押すと疲れないんだよ」なんて、しゃべりながら、何年間、そして何枚の紙を四つ折りしたことか。
なんてことを思い出してしまうのは、最近、久しぶりにギターポップをよく聴いているからかな、というか、いつから聴かなくなったのか分からないくらい久しぶりなのです。というわけで、今どんなバンドがいるのか、ぜんぜん分からず、かろうじて記憶にある、キンダーコアとか、フィルターレコード、エレファント6、ミンティ・フレッシュ、パラソル、マーチ・レコーズ・・・・などのレーベル買い。“レーベル買い”という言葉も懐かしい。2000年過ぎてからのギターポップ事情は、ほんとまったくわかりません。ちなみに今、これを書きながら聴いているのは、オレンジ・ピールズのセカンド「So Far」。

 気分的にはその前に「饗宴」を読んだばかりだし、獅子文六の随筆もまとめて読んだばかりなので、しばらくいいや、って感じではある。獅子文六なら随筆ではなくて小説の方を読みたい。でもこういうときに限って100円コーナーの片隅にこういう本を見つけたり、気を抜いてほかに読む本がない、なんて状態になったりする。読み始めるとおもしろいんだけれど、もう少しお腹がすいた状態のときに・・・・という気分がつきまとってしまうのはしょうがない。
気分的にはその前に「饗宴」を読んだばかりだし、獅子文六の随筆もまとめて読んだばかりなので、しばらくいいや、って感じではある。獅子文六なら随筆ではなくて小説の方を読みたい。でもこういうときに限って100円コーナーの片隅にこういう本を見つけたり、気を抜いてほかに読む本がない、なんて状態になったりする。読み始めるとおもしろいんだけれど、もう少しお腹がすいた状態のときに・・・・という気分がつきまとってしまうのはしょうがない。 例えば今の若い人たちに、植草甚一という人はどのように受け入れられているのだろう。去年の9月からスクラップブックが再発されていて、時々本屋で平積みされているのを見かける。やはりある程度は売れているのだろうか、よく分からない。自分が興味をなくしてしまっただけなので、知らないところで意外と盛り上がっているのかもしれない。なんだか、私より少し下の世代で1990年代の半ばに植草甚一がブームだったときに、絶版で手に入れられなかった人たちが、まとめて買っているだけじゃないだろうか、という気もしないでもない。ほんとは持っていない分を再発で埋めてコンプリートにしたいところなのですが、実家に送ってしまってある──しかも冷蔵庫の裏に段ボールに入れたままで仕舞われているらしい──ので、自分がどの本を持っているのか正確に分からないという・・・・。
例えば今の若い人たちに、植草甚一という人はどのように受け入れられているのだろう。去年の9月からスクラップブックが再発されていて、時々本屋で平積みされているのを見かける。やはりある程度は売れているのだろうか、よく分からない。自分が興味をなくしてしまっただけなので、知らないところで意外と盛り上がっているのかもしれない。なんだか、私より少し下の世代で1990年代の半ばに植草甚一がブームだったときに、絶版で手に入れられなかった人たちが、まとめて買っているだけじゃないだろうか、という気もしないでもない。ほんとは持っていない分を再発で埋めてコンプリートにしたいところなのですが、実家に送ってしまってある──しかも冷蔵庫の裏に段ボールに入れたままで仕舞われているらしい──ので、自分がどの本を持っているのか正確に分からないという・・・・。 あとがきには
あとがきには 「旅のカケラ-パリ・コラージュ」もうそうですが、パリってフォトジェニックな街なのだなぁ、と思う。「旅のカケラ」では、看板や標識、マンホールなど、ミニマムな視点で撮り集めた写真がおもしろかったし、こちらは通りや建物を大きく捕らえたパノラマ写真が楽しい。このほかにもちょっと視点を変えれば、もっといろいろな写真を撮ることができるかもしれない。私は特にフランスかぶれというわけでもないし、パリに行ったこともないし、近いうちにパリに行くという予定もないので、観光案内というよりも写真集として楽しめるかどうかが、買うかどうかの基準となるのだけれど、そういう基準で選んでもパリのガイドブック(?)はおもしろいものが多いような気がします。意外と写真がおもしろいアメリカの本ってないような気がします。やはり街の写真といえば、ヨーロッパなのだろうか。よくわかりませんが。別に街にこだわっているわけでもないんですけど・・・・。
「旅のカケラ-パリ・コラージュ」もうそうですが、パリってフォトジェニックな街なのだなぁ、と思う。「旅のカケラ」では、看板や標識、マンホールなど、ミニマムな視点で撮り集めた写真がおもしろかったし、こちらは通りや建物を大きく捕らえたパノラマ写真が楽しい。このほかにもちょっと視点を変えれば、もっといろいろな写真を撮ることができるかもしれない。私は特にフランスかぶれというわけでもないし、パリに行ったこともないし、近いうちにパリに行くという予定もないので、観光案内というよりも写真集として楽しめるかどうかが、買うかどうかの基準となるのだけれど、そういう基準で選んでもパリのガイドブック(?)はおもしろいものが多いような気がします。意外と写真がおもしろいアメリカの本ってないような気がします。やはり街の写真といえば、ヨーロッパなのだろうか。よくわかりませんが。別に街にこだわっているわけでもないんですけど・・・・。 いつか大正・昭和初期の文壇における学閥(というのかな)について――具体的に書くとまずは早稲田、慶応から、――きちんと調べてみたいと思っている。思いつくままに簡単に書くと、早稲田は、横光利一、正宗白鳥、井伏鱒二、尾崎一雄、広津和郎、小沼丹・・・・あと個人的には、稲垣達郎とか岩本素白も入れたいところ。それから慶応では、小島政二郎、久保田万太郎、池田弥三郎、戸板康二、そしてこの水上瀧太郎などがあげられると思う。早稲田、慶応のほかに、東大仏文というのも気にはなっている。といっても、太宰治とか芥川龍之介、山田稔、澁澤龍彦、大江健三郎くらいしか思い浮かばないが。しかもあまり脈絡がない。
いつか大正・昭和初期の文壇における学閥(というのかな)について――具体的に書くとまずは早稲田、慶応から、――きちんと調べてみたいと思っている。思いつくままに簡単に書くと、早稲田は、横光利一、正宗白鳥、井伏鱒二、尾崎一雄、広津和郎、小沼丹・・・・あと個人的には、稲垣達郎とか岩本素白も入れたいところ。それから慶応では、小島政二郎、久保田万太郎、池田弥三郎、戸板康二、そしてこの水上瀧太郎などがあげられると思う。早稲田、慶応のほかに、東大仏文というのも気にはなっている。といっても、太宰治とか芥川龍之介、山田稔、澁澤龍彦、大江健三郎くらいしか思い浮かばないが。しかもあまり脈絡がない。 講談社文芸文庫のいいところは、巻末に年表と作品の一覧が載っていることで、この本でも、生涯に20以上の長編、300以上の短編、そして随筆や紀行文など、膨大な作品を残したという里見弴の作品がリストアップされていて、それを眺めるだけでもなんとなく楽しい。といっても手に入れられるのはその中のほんの少しだけですけど。ついでにアマゾンで里見弴の作品を検索してみたら「極楽とんぼ」「道元禅師の話」「多情仏心」「善心悪心―他三編」「文章の話」「安城家の兄弟」「今年竹」「里見弴随筆集」「桐畑」「雑記帖」「秋日和・彼岸花」と、この「初舞台・彼岸花」が表示されました。12冊、これを多い見るか、少ないと見るか。
講談社文芸文庫のいいところは、巻末に年表と作品の一覧が載っていることで、この本でも、生涯に20以上の長編、300以上の短編、そして随筆や紀行文など、膨大な作品を残したという里見弴の作品がリストアップされていて、それを眺めるだけでもなんとなく楽しい。といっても手に入れられるのはその中のほんの少しだけですけど。ついでにアマゾンで里見弴の作品を検索してみたら「極楽とんぼ」「道元禅師の話」「多情仏心」「善心悪心―他三編」「文章の話」「安城家の兄弟」「今年竹」「里見弴随筆集」「桐畑」「雑記帖」「秋日和・彼岸花」と、この「初舞台・彼岸花」が表示されました。12冊、これを多い見るか、少ないと見るか。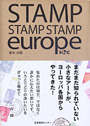 切手収集というのは、子どもの頃誰もが一度は夢中になるものなのでしょうか。私は集めたことのがないので分かりません。子どもの頃、集めていたものといえば、キーホルダーと切符くらいかな。キーホルダーは遠足や旅行に行ったときに必ず買ってましたね。特になにかに付ける、といったことをしていなかったので、ただ厚紙の箱に入れっぱなしで、たまってくると金属なのでその箱が重くなってしまって、持ち上げたら底が抜けたのを覚えてます。
切手収集というのは、子どもの頃誰もが一度は夢中になるものなのでしょうか。私は集めたことのがないので分かりません。子どもの頃、集めていたものといえば、キーホルダーと切符くらいかな。キーホルダーは遠足や旅行に行ったときに必ず買ってましたね。特になにかに付ける、といったことをしていなかったので、ただ厚紙の箱に入れっぱなしで、たまってくると金属なのでその箱が重くなってしまって、持ち上げたら底が抜けたのを覚えてます。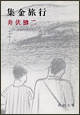 荻窪にあるあるアパートの主人が死んで、小学生の男の子がひとり取り残された。主人と親しかった主人公は。部屋代を踏み倒して逃げた人たちから勘定を取り立てるため、昔の恋人に慰謝料を請求する年増美人と一緒に、岩国、下関、福岡、尾道、福山と集金旅行に出る・・・・という話。
荻窪にあるあるアパートの主人が死んで、小学生の男の子がひとり取り残された。主人と親しかった主人公は。部屋代を踏み倒して逃げた人たちから勘定を取り立てるため、昔の恋人に慰謝料を請求する年増美人と一緒に、岩国、下関、福岡、尾道、福山と集金旅行に出る・・・・という話。 雑誌「あまカラ」のせいで、なんとなく小島政二郎というと食べ物に詳しい、食通というイメージがあるけれど、久米正雄に「小島なんか、鼻ッつまりじゃないか。鼻ッつまりに、物のうまいまずいが分かってたまるものか」なんて言われていたとは。とはいうものの、日本のあちらこちら出かけていっておいしいものを求めるさまを読んでいると、ほんとうにたべることがすきなのだなぁ、と思う。もちろん“好き”なだけではないのだろうけれど・・・・。今の世の中なんて小島政二郎に言わせれば、まずい食材に過度に人工的な手を加えたどうしようもないものばかり、ということになるのだろうか。いや、食べ物だけでなく、空気までまずいと言われそう。
雑誌「あまカラ」のせいで、なんとなく小島政二郎というと食べ物に詳しい、食通というイメージがあるけれど、久米正雄に「小島なんか、鼻ッつまりじゃないか。鼻ッつまりに、物のうまいまずいが分かってたまるものか」なんて言われていたとは。とはいうものの、日本のあちらこちら出かけていっておいしいものを求めるさまを読んでいると、ほんとうにたべることがすきなのだなぁ、と思う。もちろん“好き”なだけではないのだろうけれど・・・・。今の世の中なんて小島政二郎に言わせれば、まずい食材に過度に人工的な手を加えたどうしようもないものばかり、ということになるのだろうか。いや、食べ物だけでなく、空気までまずいと言われそう。