 木山捷平の本は、表紙の絵なども含めてよい雰囲気を出しているもが多く、できれば単行本でそろえたいのだけれど、彼のゆるやかなユーモア漂う作品には根強いファンがいるようで、古本屋さんで見かける木山捷平の本は割と高い値段が付けられていて、私にはちょっと手が出ない。だから少なくとも講談社文芸文庫から出ている9冊はそろえたいつもりで、本屋さんで見かけた時には必ず買うようにしている。ブックファーストやパルコブックセンターなどで探しても意外とないのです。
木山捷平の本は、表紙の絵なども含めてよい雰囲気を出しているもが多く、できれば単行本でそろえたいのだけれど、彼のゆるやかなユーモア漂う作品には根強いファンがいるようで、古本屋さんで見かける木山捷平の本は割と高い値段が付けられていて、私にはちょっと手が出ない。だから少なくとも講談社文芸文庫から出ている9冊はそろえたいつもりで、本屋さんで見かけた時には必ず買うようにしている。ブックファーストやパルコブックセンターなどで探しても意外とないのです。
そんな風に思っている割には、たまたま時間があったので、一日で読み終えてしまった。ほんとうは、2冊くらい持ち歩いてゆっくりと読むか、もしくは旅行にまとめて持っていってじっくりと読みたい、と思う。そういう意味で、小沼丹の文庫を、ランカウイ島の、町に出るにはタクシーで1時間以上かかる森の中のホテルで、プールサイドや部屋のベッドサイド、海を見渡せるテラス席でまとめて読んだのは贅沢だったなぁ、と思う。いつかそういう時には、木山捷平の文庫本を持っていって再読することにしよう。
今年の夏は久しぶりにブラジルものとジャマイカもののレコードを聴いてみようと思って、寝室にあるレコードからブラジルものを引っ張り出して、テレビの下のラックに移動させてみました。ブラジルものは年々かおきに自分の中でブームが起きているわりには、思っていたよりも少なくて、20cmくらいしかなかった。これから9月くらいまでは、ブラジルものもジャマイカものも再発盤がものすごい勢いで出ているので、その辺を適当に選んで、レコードを買っていくつもり。と言ってもソウルセットやハーブビーなどの新譜が出たら当然買うので、そればかり、というわけではないですけどね。

 日本のよさとかわるいところとか考えていると、いやな気分や憂鬱な気分になりがちなので、あまり考えたくないというのが本音。加えて私の少ない知識で、歴史等について中途半端なことを書くのもどうかと思うし、カヌー犬ブックスの雑記としてもどうかと思うので書かない。いや書けない。けれど、ときどき疑問に思うのは、あれほど戦争は悪いということを主張しつつ、いまだに歴史の教科書で戦国武将を英雄扱いするのはどうゆうことなのだろうか、ということだったりする。国内だったら戦争をしてもかまわないということなのだろうか。まっどうでもいいんですけど。
日本のよさとかわるいところとか考えていると、いやな気分や憂鬱な気分になりがちなので、あまり考えたくないというのが本音。加えて私の少ない知識で、歴史等について中途半端なことを書くのもどうかと思うし、カヌー犬ブックスの雑記としてもどうかと思うので書かない。いや書けない。けれど、ときどき疑問に思うのは、あれほど戦争は悪いということを主張しつつ、いまだに歴史の教科書で戦国武将を英雄扱いするのはどうゆうことなのだろうか、ということだったりする。国内だったら戦争をしてもかまわないということなのだろうか。まっどうでもいいんですけど。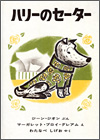 「どろんこハリー」「うみべのハリー」に続いてハリーシリーズも3冊目。これでそろったと思ったら「ハリーのだいかつやく」という本もあるらしい。定価で1000円くらいなのだからわざわざ古本屋に並ぶのを待たないで、新品で買えばいいのでは?と、自分でも思う。実際、パルコブックセンターの絵本売場に行けば、「ハリーのだいかつやく」も見つかると思うけれど、新品で買うことがほとんどないのは、「明日の電車の中で読む本がない」というようなせっぱ詰まった状況にならないから、ということと、実際には頻繁にそれらの本を読み返すこともないから。子供がいたらちょっと違うのかもしれないけどね・・・・。
「どろんこハリー」「うみべのハリー」に続いてハリーシリーズも3冊目。これでそろったと思ったら「ハリーのだいかつやく」という本もあるらしい。定価で1000円くらいなのだからわざわざ古本屋に並ぶのを待たないで、新品で買えばいいのでは?と、自分でも思う。実際、パルコブックセンターの絵本売場に行けば、「ハリーのだいかつやく」も見つかると思うけれど、新品で買うことがほとんどないのは、「明日の電車の中で読む本がない」というようなせっぱ詰まった状況にならないから、ということと、実際には頻繁にそれらの本を読み返すこともないから。子供がいたらちょっと違うのかもしれないけどね・・・・。 「現代詩手帖」や「ユリイカ」に連載されたコラムを中心に、セリーヌと1980年代のロマン・ノワールの関係を探った文章などを加えてまとめられた本。文字数の決まった短めのものと論文ともいえる内容のものなどがバランスよく並べられていて、それがいいテンポになっている。
「現代詩手帖」や「ユリイカ」に連載されたコラムを中心に、セリーヌと1980年代のロマン・ノワールの関係を探った文章などを加えてまとめられた本。文字数の決まった短めのものと論文ともいえる内容のものなどがバランスよく並べられていて、それがいいテンポになっている。 定期入れをなくした。月曜日に駅でいらなくなったパスネットを捨てて、荷物が多かったのでリュックのポケットにパスケースを入れられず、違うところに入れたところまで憶えているのだが、部屋中探してみても、ない。ジーンズのポケット、テーブルの下に重ねてある本の間、CDラックの隙間、部屋の鍵置き場、靴箱・・・・思いつくところを探してみても、ない。定期が入っていたわけではなくて、SUICA(残り2000円くらい)とパスネット(残り900円くらい)を入れていたので、合計でも損害額としては3000円くらいなんですけど、パスケースをなくす、なんてことは、高校に入った時に初めて定期を持って以来、初めてのことなので、すこしショックでもある。
定期入れをなくした。月曜日に駅でいらなくなったパスネットを捨てて、荷物が多かったのでリュックのポケットにパスケースを入れられず、違うところに入れたところまで憶えているのだが、部屋中探してみても、ない。ジーンズのポケット、テーブルの下に重ねてある本の間、CDラックの隙間、部屋の鍵置き場、靴箱・・・・思いつくところを探してみても、ない。定期が入っていたわけではなくて、SUICA(残り2000円くらい)とパスネット(残り900円くらい)を入れていたので、合計でも損害額としては3000円くらいなんですけど、パスケースをなくす、なんてことは、高校に入った時に初めて定期を持って以来、初めてのことなので、すこしショックでもある。 古本屋イベントも無事終了し、気分的にも、体調的にも、部屋の中の様子も、ようやく今日から“通常通り”という感じです。はじめてのことだったので、本当に高校の文化祭というか、お店屋さんごっこ、という感じがぬぐえませんでしたが、たくさんの人に来ていただきほんとうにありがとうございました。
古本屋イベントも無事終了し、気分的にも、体調的にも、部屋の中の様子も、ようやく今日から“通常通り”という感じです。はじめてのことだったので、本当に高校の文化祭というか、お店屋さんごっこ、という感じがぬぐえませんでしたが、たくさんの人に来ていただきほんとうにありがとうございました。 いつかブラウニーのフィルムで写真を撮ってみたいなぁ、なんて思いつつ、なんの知識もなく、そのいつかのためにブックオフにて100円で買ったのだけれど、家に帰って中古カメラ屋のサイトやヤフオクで調べてみたら、きれいなものは50万近い価格がついているようなカメラということが判明、即あきらめました。本の中でも「中判カメラの最高峰」「ハッセルを購入することは人生の一大事」「3年くらいのろーんを組み」といった言葉が踊っておりました。やれやれ。もっとも最近は安くなっきているとのことですが・・・・。
いつかブラウニーのフィルムで写真を撮ってみたいなぁ、なんて思いつつ、なんの知識もなく、そのいつかのためにブックオフにて100円で買ったのだけれど、家に帰って中古カメラ屋のサイトやヤフオクで調べてみたら、きれいなものは50万近い価格がついているようなカメラということが判明、即あきらめました。本の中でも「中判カメラの最高峰」「ハッセルを購入することは人生の一大事」「3年くらいのろーんを組み」といった言葉が踊っておりました。やれやれ。もっとも最近は安くなっきているとのことですが・・・・。 「まだまだ先だから・・・・」なんて思っているうちに、気がつけば、fooでの3日間カヌー犬ブックス開店も今週末に。本を並べる簡単な棚や看板を作ったり、写真を大きく引き伸ばしたり、久しぶりにMOサイズの写真集を作ったり、必要なものを買いそろえたり・・・・いよいよ準備も佳境です。
「まだまだ先だから・・・・」なんて思っているうちに、気がつけば、fooでの3日間カヌー犬ブックス開店も今週末に。本を並べる簡単な棚や看板を作ったり、写真を大きく引き伸ばしたり、久しぶりにMOサイズの写真集を作ったり、必要なものを買いそろえたり・・・・いよいよ準備も佳境です。 私小説とも少し違うような、身辺小説、もしくはエッセイとも言えるような作品と、フィクションと思われる作品が、半分ずつ収録された本。例によってかなり自虐的なのだが、これだけ山口瞳の本を読み続けていると、それほどつらい感じを受けなくなってしまう。ちょっと慣れてしまってると言えるかもしれない。
私小説とも少し違うような、身辺小説、もしくはエッセイとも言えるような作品と、フィクションと思われる作品が、半分ずつ収録された本。例によってかなり自虐的なのだが、これだけ山口瞳の本を読み続けていると、それほどつらい感じを受けなくなってしまう。ちょっと慣れてしまってると言えるかもしれない。 エレベーターを出ると、さっきまでの雨はすっかりやんでいて、ガラスのドアの向こうはまだ明るい。会議室をでたときに、視界の片隅に入った廊下の奥のガラス窓を見た時には、外が暗く見えたので、少しびっくりした。ガラス自体に暗い色が入っていたのだろうか。
エレベーターを出ると、さっきまでの雨はすっかりやんでいて、ガラスのドアの向こうはまだ明るい。会議室をでたときに、視界の片隅に入った廊下の奥のガラス窓を見た時には、外が暗く見えたので、少しびっくりした。ガラス自体に暗い色が入っていたのだろうか。