 今年はあまり雨も降り続かず、梅雨らしくない。明日は夏至なので一年で一番昼間が長いときなので、こういうときに定時で会社を出たりすると、外が明るくてうれしくなってしまう。といってもそうそう定時であがれるものではないが。
今年はあまり雨も降り続かず、梅雨らしくない。明日は夏至なので一年で一番昼間が長いときなので、こういうときに定時で会社を出たりすると、外が明るくてうれしくなってしまう。といってもそうそう定時であがれるものではないが。
デンマーク、スウェーデン、フィンランドと北欧の国を回ったのは一昨年の今頃の時期だったのだけれど、そのときは11時近くまで明るくて、6時前からカフェやバーで飲んでいた人たちが(デンマークなどは、5時過ぎにはお店がほとんど閉まってしまう)、まだ夕暮れといった雰囲気ですらない明るさの8時くらいから公園や遊園地に人が集まってくる、なんて風景を、ものすごくうらやましい気持ちで眺めていたのを思い出す。このまま晴れの日が続くようだったら、会社が終わった後、近くの東京タワーに行ったりバッティングセンターに行ったりするのもいいかもしれない。
日曜日は、東麻布のfooで行われた、うれし屋さんのフリマに段ボール1箱分の本を持って参加。屋内とはいえ、この時期のフリマでこんなにいい天気だなんて、うれし屋さんはなんて日ごろの行いがいいんでしょうか。
というわけで、吹き抜けのテラスは気持ちいい空間になっているし、訪れる人のほとんどが、うれし屋さんの着物や布、毛糸が目当ての女の子ばかりだったので、私は片隅に本を置きっぱなしにしたまま、オープンテラスでコーヒーを飲んだりクッキーを食べたり、タバコを吸ったりしつつ、小学生の男の子と遊んだりと、のんびりと休日の一日を過ごしてしまいました。5月の自分のイベントのときはあまり天気も良くなかったし、自分が主催なのでそうそうだらだらともしてやれなかったので、こういう風にちょこっとだけ参加するというのは楽しい。もう何年もカバーから出していないのに「ウクレレ持ってくれば良かった」とか、子供がずっといるんなら「ビューマスターを持って来ればよかった」なんて思っていたり・・・・。店主がそんな感じなので、当然、本のほうはほとんど売れず、持って行った本をそのまま持って帰るという羽目になってしまいましたが・・・・。
それにしても、来る人、来る人、誰もが置いてマネキンに着せてある着物や布を見て、「かわいい」という言葉を連発しているのにはびっくり、いやぁ、36年間でこれほど「かわいい」という言葉を聞いた一日はないです。女の子にとっての「かわいい」という価値、あるいは言葉というのは不思議だなぁと、しみじみ思う。

 別になにが忙しいというわけではないのだけれど、家に帰ってうだうだしているうちに、すぐに寝る時間になってしまい、雑誌などを読んでいる余裕がない。だからこの「ku:nel」も5月の終わりに、ポイント欲しさにわざわざタワーレコードまで行って買ったのに、ほとんど読んでないままテーブルの下に置きっぱなしのままです。それは多分、時間の問題というよりも気持ちの問題なのかもしれないけれど・・・・。
別になにが忙しいというわけではないのだけれど、家に帰ってうだうだしているうちに、すぐに寝る時間になってしまい、雑誌などを読んでいる余裕がない。だからこの「ku:nel」も5月の終わりに、ポイント欲しさにわざわざタワーレコードまで行って買ったのに、ほとんど読んでないままテーブルの下に置きっぱなしのままです。それは多分、時間の問題というよりも気持ちの問題なのかもしれないけれど・・・・。 山口瞳は私小説の作家といえるのだろうか。「江分利満氏の優雅な生活」をスタートとして「血族」「家族」をその到達点とし、それを補う形で「男性自身」が存在すると考えるならば、山口瞳の小説は、(過去やルーツを含めて)自身の身辺を語ったものと言えるかもしれない。後年の「迷惑旅行」「湖沼学入門」などの取材旅行ものも、どこか木山捷平や井伏鱒二を思い出させる。とはいうものの、あきらかに自身をモデルとした「江分利満氏の優雅な生活」を読んでいると、江分利氏の主張は、山口瞳の主張であり、江分利氏のつぶやきは、山口瞳のつぶやきであるのにもかかわらず、どこかフィクションっぽさを感じでしまうのはなぜだろう。
山口瞳は私小説の作家といえるのだろうか。「江分利満氏の優雅な生活」をスタートとして「血族」「家族」をその到達点とし、それを補う形で「男性自身」が存在すると考えるならば、山口瞳の小説は、(過去やルーツを含めて)自身の身辺を語ったものと言えるかもしれない。後年の「迷惑旅行」「湖沼学入門」などの取材旅行ものも、どこか木山捷平や井伏鱒二を思い出させる。とはいうものの、あきらかに自身をモデルとした「江分利満氏の優雅な生活」を読んでいると、江分利氏の主張は、山口瞳の主張であり、江分利氏のつぶやきは、山口瞳のつぶやきであるのにもかかわらず、どこかフィクションっぽさを感じでしまうのはなぜだろう。 「カレンダーの余白」に続いて昭和43年に発表された2冊目の随筆集。タイトルにあるように新聞や雑誌などで気になった記事を紹介する形のものや酒に関する交遊録「酒徒交傳」、中原中也、直木三十五、古川録波、菊池寛など、同僚や友人たちの思い出やエピソードを語ったものなどで構成されています。個人的にはやはりさまざまな作家たちが次々と登場する「酒徒交傳」が興味深い。もちろん変わっていく鎌倉の様子が描かれる身辺雑記もおもしろいけれど・・・・。先日、講談社文芸文庫の巻末に掲載されている作品リストをチェックしたら、このような随筆集もほぼ読みつくしている感じになってきていたるので、これからは一冊一冊大切に読んでいくことにしたい。
「カレンダーの余白」に続いて昭和43年に発表された2冊目の随筆集。タイトルにあるように新聞や雑誌などで気になった記事を紹介する形のものや酒に関する交遊録「酒徒交傳」、中原中也、直木三十五、古川録波、菊池寛など、同僚や友人たちの思い出やエピソードを語ったものなどで構成されています。個人的にはやはりさまざまな作家たちが次々と登場する「酒徒交傳」が興味深い。もちろん変わっていく鎌倉の様子が描かれる身辺雑記もおもしろいけれど・・・・。先日、講談社文芸文庫の巻末に掲載されている作品リストをチェックしたら、このような随筆集もほぼ読みつくしている感じになってきていたるので、これからは一冊一冊大切に読んでいくことにしたい。 少し早めに仕事を切り上げてブックオフに寄って帰る。定期券内にブックオフがあるとつい寄ってしまうのは私だけか。平日の夜は、漫画の立ち読みする子供たちもそんなにいないし・・・・。とりあえず100円コーナーから眺めていくのだけれど、下の棚に何冊か本が積んであって、よく見ると一番上においてあるのは、「父の乳」。しかも100円。思わず運命か、と思って、近寄ってみると、ちょっと離れた場所で本を探していたおじいさんが近寄ってきて、その「父の乳」の上に手に持っていた本を重ねて移動させてしまった。どうやらその人がすでに確保した本だったらしい。
少し早めに仕事を切り上げてブックオフに寄って帰る。定期券内にブックオフがあるとつい寄ってしまうのは私だけか。平日の夜は、漫画の立ち読みする子供たちもそんなにいないし・・・・。とりあえず100円コーナーから眺めていくのだけれど、下の棚に何冊か本が積んであって、よく見ると一番上においてあるのは、「父の乳」。しかも100円。思わず運命か、と思って、近寄ってみると、ちょっと離れた場所で本を探していたおじいさんが近寄ってきて、その「父の乳」の上に手に持っていた本を重ねて移動させてしまった。どうやらその人がすでに確保した本だったらしい。 サセックの旅行絵本は、復刊されるたびに買っている。
サセックの旅行絵本は、復刊されるたびに買っている。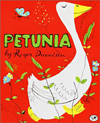 久しぶりにアマゾンで買った本のうちの一冊。前回(といってもそれがいつだったか?)注文したときは、品切れか何かで手に入らなかったのだけれど、今回は意外と早く届いたのでうれしい。翻訳もされていて、日本語のタイトルは「がちょうのペチューニア」となってます。Roger Duvoisinの本は「White Snow Bright Snow」に続いて2冊目。ちょっと絵のタッチが違いますね。絵本は買いだすとどんどん欲しくなるんですよねぇ。
久しぶりにアマゾンで買った本のうちの一冊。前回(といってもそれがいつだったか?)注文したときは、品切れか何かで手に入らなかったのだけれど、今回は意外と早く届いたのでうれしい。翻訳もされていて、日本語のタイトルは「がちょうのペチューニア」となってます。Roger Duvoisinの本は「White Snow Bright Snow」に続いて2冊目。ちょっと絵のタッチが違いますね。絵本は買いだすとどんどん欲しくなるんですよねぇ。 これは一つの考え方なのですべての場合に当てはまるというわけではないけれど、物事を好きになるということの基準のひとつに「ひとりでする」かどうかということが挙げられると思う。例えば、映画。子供の頃はたいてい親や兄弟たち、友達と見に行っているけれど、映画が好きになると次第にひとりで映画館に入り浸るようになる。ライブやクラブ、あるいは旅行などもにいくのもそう。初めは誰かと一緒に行くけれど、だんだんとひとりで行くようになる。ずっと友達と一緒かもしれない。だからといって映画などが好きではないということにはならないけれど・・・・。でも“何かをひとりでする”ということは、やはりほんとうに好きだからだと思う。
これは一つの考え方なのですべての場合に当てはまるというわけではないけれど、物事を好きになるということの基準のひとつに「ひとりでする」かどうかということが挙げられると思う。例えば、映画。子供の頃はたいてい親や兄弟たち、友達と見に行っているけれど、映画が好きになると次第にひとりで映画館に入り浸るようになる。ライブやクラブ、あるいは旅行などもにいくのもそう。初めは誰かと一緒に行くけれど、だんだんとひとりで行くようになる。ずっと友達と一緒かもしれない。だからといって映画などが好きではないということにはならないけれど・・・・。でも“何かをひとりでする”ということは、やはりほんとうに好きだからだと思う。 突然ですが「物事を深く狭く掘り下げるタイプ」か「広く浅く掘るタイプ」のどちらかと言えば、私はそのどちらでもなくて、昔、友達に指摘された言葉を使うなら、「あるきっかけがあって地面に穴を掘ったら、そこからもぐらのように地下2mくらいの場所を掘り続けている」という感じ。しかも本当に適当に偶然に頼って掘っているので、まったく体系的な把握ができないし、ときどき自分が掘った穴に戻ってしまったりする。
突然ですが「物事を深く狭く掘り下げるタイプ」か「広く浅く掘るタイプ」のどちらかと言えば、私はそのどちらでもなくて、昔、友達に指摘された言葉を使うなら、「あるきっかけがあって地面に穴を掘ったら、そこからもぐらのように地下2mくらいの場所を掘り続けている」という感じ。しかも本当に適当に偶然に頼って掘っているので、まったく体系的な把握ができないし、ときどき自分が掘った穴に戻ってしまったりする。 上林暁、29作目、最後の作品。昔の作品も読んでみたいけれど、簡単に手に入りそうもないし、新たに出そうもないのが残念。とりあえず今日、坪内祐三が編集した「禁酒宣言」を今日はネットで注文したので届くのが楽しみ。
上林暁、29作目、最後の作品。昔の作品も読んでみたいけれど、簡単に手に入りそうもないし、新たに出そうもないのが残念。とりあえず今日、坪内祐三が編集した「禁酒宣言」を今日はネットで注文したので届くのが楽しみ。