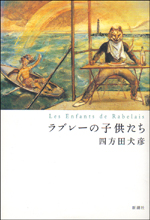 ■澁澤龍彦の反対日の丸パンから、ロマン・バルトのてんぷら、谷崎潤一郎の柿の葉寿司、ポール・ボウルスのモロッコ料理そして明治天皇の大昼食まで、古今東西の芸術家が好み、レシピを残した料理を実際に作って食べて語った本。こういう本ってわりと写真が中心になってしまい、文章はそれを簡単に説明するだけ、みたいな形になりがちなんだけど、それらの料理と芸術家たちのエピソードはもちろん、それぞれの国や地域、そして時代に根ざした文化的な背景が詳しく記されてるところがいい。
■澁澤龍彦の反対日の丸パンから、ロマン・バルトのてんぷら、谷崎潤一郎の柿の葉寿司、ポール・ボウルスのモロッコ料理そして明治天皇の大昼食まで、古今東西の芸術家が好み、レシピを残した料理を実際に作って食べて語った本。こういう本ってわりと写真が中心になってしまい、文章はそれを簡単に説明するだけ、みたいな形になりがちなんだけど、それらの料理と芸術家たちのエピソードはもちろん、それぞれの国や地域、そして時代に根ざした文化的な背景が詳しく記されてるところがいい。
掲載されている料理の写真も、きちんとコーディネートがされているのだけれど(料理自体も専門のレストランや料理学校の人が作っているとのこと)、過度な演出があるわけではなく、シンプルに料理そのものを紹介していて、本の内容と合っていると思う。
続編を読んでみたいけど、この本が出てからもう10年以上経っているのでもう出ないんでしょうねぇ~
■慌ただしく年末年始も過ぎて、2017年。2016年は26冊しか雑記を更新できませんでした。読んでる本はもう少し多いので30冊ちょっとというところですかね。しかも身辺雑記的な随筆や食べものについて本ばかりで、小説とかまったくなし。もうラテン文学とかメタフィクションとか読めないなぁと思うけど、気軽に読めるし今の自分には合ってる。
今さらですが、カヌー犬ブックスは、料理系の本を中心にしてて、初めて会った人とかに「どんな本を扱ってるんですか?」と聞かれて「料理や食べもの系が多いです」って答えると、わりと、特に男の人には、「ふーん(自分には関係ないかな?)」という感じになりがちなんですよね。でも、レシピとかは料理に好きかとか読み手を限定してしまいますが、食べもの関連の随筆は、別に食べものに関して詳しく解説しているわけでもないし、書いている作家もどちらかというと力を抜いて書いていて読むほうも構える必要はないし、わりとみんなに薦められると思ってるんですよ。そもそも普段料理をしなくて、別に料理が好きじゃない人も、食べものを食べない人はいないですしね。
というわけで、今年はもう少し、食べもの関連の随筆のおもしろさを伝えていけたらと思ってます。どういう風にしようかはあんまり具体的に考えてませんが‥‥
お酒についての随筆もたくさんあるので、泥酔ファンクラブの人たちも読んでほしいなぁと思っています!
そんなわけで、今年もよろしくお願いしますー!

 ■後藤繁雄の本は1冊だけポラロイドカメラで撮った写真集「Wasteland guide」を持っているんですが、ちゃんとした文章を読むの初めて。旅先での風景がポラロイド独特の淡い色合いで切り取られている15cm四方の小さな本で、中の文章もふくめてけっこう好きで、ときどき見返したりしているんだけど、なんとなくほかの本に手をのばすきっかけがなかったんですよね。
■後藤繁雄の本は1冊だけポラロイドカメラで撮った写真集「Wasteland guide」を持っているんですが、ちゃんとした文章を読むの初めて。旅先での風景がポラロイド独特の淡い色合いで切り取られている15cm四方の小さな本で、中の文章もふくめてけっこう好きで、ときどき見返したりしているんだけど、なんとなくほかの本に手をのばすきっかけがなかったんですよね。
 ■「食」をテーマに編んだアンソロジーシリーズの、カレーライス、お弁当、おやつに続く第4弾。ちょうど夏くらいに出たこともあり、夏の間に読もうと思っていたら夏が終わり、次の夏が来て今年こそはと思いつつも秋になり、3年目にしてようやく読めた感じです。
■「食」をテーマに編んだアンソロジーシリーズの、カレーライス、お弁当、おやつに続く第4弾。ちょうど夏くらいに出たこともあり、夏の間に読もうと思っていたら夏が終わり、次の夏が来て今年こそはと思いつつも秋になり、3年目にしてようやく読めた感じです。
 ■西荻の南口を出て左に入ったところすぐにあるヒュッテは、オーナーが山好きということでアウトドアでもよく使うスキレットをいたメニューやスキットルによるウィスキーのマイボトルキープ、山のかたちの箸置など山をテーマにした山小屋バル。1階は立ち飲みスペース、1階は座って飲むスペースになっています。
■西荻の南口を出て左に入ったところすぐにあるヒュッテは、オーナーが山好きということでアウトドアでもよく使うスキレットをいたメニューやスキットルによるウィスキーのマイボトルキープ、山のかたちの箸置など山をテーマにした山小屋バル。1階は立ち飲みスペース、1階は座って飲むスペースになっています。 ■今年の夏はレゲエのシングル盤をちょこちょこ買っていたので、それに合わせて改訂された方を読んでみた。情報もかなり増えて厚さも倍くらいになってます。よくあるディスクガイドとは違うワクワクする感じがこの本にはあると思う。まぁ半分以上はわかってないんですけどね。逆に前に読んだ改定前の本で、わかってなくて読み飛ばしていた内容が20年近く経っておもしろく読めたりするのも楽しい。レゲエのシングル盤ブームはいつものわたしのブームのように夏が終わる前に不完全燃焼のまま収束してしまったけど、これがきっかけてこれからも気が向いたときにレコードをチェックする感じになりそうなので、また5年後、10年後に繰り返して読み返すのだろう。
■今年の夏はレゲエのシングル盤をちょこちょこ買っていたので、それに合わせて改訂された方を読んでみた。情報もかなり増えて厚さも倍くらいになってます。よくあるディスクガイドとは違うワクワクする感じがこの本にはあると思う。まぁ半分以上はわかってないんですけどね。逆に前に読んだ改定前の本で、わかってなくて読み飛ばしていた内容が20年近く経っておもしろく読めたりするのも楽しい。レゲエのシングル盤ブームはいつものわたしのブームのように夏が終わる前に不完全燃焼のまま収束してしまったけど、これがきっかけてこれからも気が向いたときにレコードをチェックする感じになりそうなので、また5年後、10年後に繰り返して読み返すのだろう。
 ■で、今週末は東京蚤の市です!なんと10回目!今回は北欧市だけでなく豆皿市も同時開催されるし、八角テントのライブもカジくんや畠山美由紀といった前回までの人に加え、なつやすみバンドや栗コーダーカルテット、ボノボの蔡忠浩、ビューティフルハミングバードと盛りだくさんでますます盛り上がりそうです。お店のほうも200店舗以上が出店、たしか1回目は120か130店だった記憶があるので10回を経てかなり増えましたね。
■で、今週末は東京蚤の市です!なんと10回目!今回は北欧市だけでなく豆皿市も同時開催されるし、八角テントのライブもカジくんや畠山美由紀といった前回までの人に加え、なつやすみバンドや栗コーダーカルテット、ボノボの蔡忠浩、ビューティフルハミングバードと盛りだくさんでますます盛り上がりそうです。お店のほうも200店舗以上が出店、たしか1回目は120か130店だった記憶があるので10回を経てかなり増えましたね。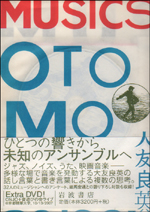 ■ジャズ、ノイズ、うた、映画音楽‥‥などについて、音楽を聴き始めたころのことからこの本が出た時点での音楽活動にいたるまで、自身の音楽経験や活動をつづった本。何をもって人はノイズと認識するのかといったことや耳のカクテル効果、ミュージシャンがライブの時にステージで何を聴いているかのアンケートなど興味深い話が多く一気に読んでしいました。()
■ジャズ、ノイズ、うた、映画音楽‥‥などについて、音楽を聴き始めたころのことからこの本が出た時点での音楽活動にいたるまで、自身の音楽経験や活動をつづった本。何をもって人はノイズと認識するのかといったことや耳のカクテル効果、ミュージシャンがライブの時にステージで何を聴いているかのアンケートなど興味深い話が多く一気に読んでしいました。()

 ■少女小説を書いていたり編集者として働いていた頃から、老人ホームに入ってからの頃までに出会った人々についてつづったエッセイ集。井伏鱒二や里見トン、瀬戸内寂聴、宇野千代と言った作家から竹下夢二、森繁久弥、市井の人々まで、さまざまな人が登場して、こういうつながりがあったのか、などいろいろ発見も多い。この人の若い頃に出した本を読みたいと思うけれど、さすがに少女小説は40代後半のおじさんにはつらいので、随筆集とか出ていないのだろうか?
■少女小説を書いていたり編集者として働いていた頃から、老人ホームに入ってからの頃までに出会った人々についてつづったエッセイ集。井伏鱒二や里見トン、瀬戸内寂聴、宇野千代と言った作家から竹下夢二、森繁久弥、市井の人々まで、さまざまな人が登場して、こういうつながりがあったのか、などいろいろ発見も多い。この人の若い頃に出した本を読みたいと思うけれど、さすがに少女小説は40代後半のおじさんにはつらいので、随筆集とか出ていないのだろうか?
 ■次回の出店は、11月3日に東小金井駅の高架下で行われる家族の文化祭になります。今回のテーマは「家族の食卓」ということなので、いつもサイトで販売している食の本で家族で楽しめるものや家族で楽しめるレシピなどが掲載されている本などを多めにピックアップして持って行きたいと思います。もちろん絵本や児童書なども持って行きますよー
■次回の出店は、11月3日に東小金井駅の高架下で行われる家族の文化祭になります。今回のテーマは「家族の食卓」ということなので、いつもサイトで販売している食の本で家族で楽しめるものや家族で楽しめるレシピなどが掲載されている本などを多めにピックアップして持って行きたいと思います。もちろん絵本や児童書なども持って行きますよー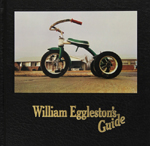 ■1976年にMoMAにて開催された初の“カラー”の展覧会の際に出版された図録的な写真集。これは2003年に復刻されたもので、いまではわりと手軽に手に入るエグルストンの入門編といった感じですね。
■1976年にMoMAにて開催された初の“カラー”の展覧会の際に出版された図録的な写真集。これは2003年に復刻されたもので、いまではわりと手軽に手に入るエグルストンの入門編といった感じですね。 ■10月2日に小金井神社で開催されるはけのおいしい朝市に出店します。はけのおいしい朝市に出店するのは1年ぶり、小金井神社での出店は2年ぶり、かな。小金井神社のはけのおいしい朝市は、うちの子どもたちも含め、神社の境内を子どもたちが走り回り、にぎやかな雰囲気で楽しいので、今から楽しみにしています。といっても、来週末なんで、もう準備をし始めなくちゃいけないんですけどね。
■10月2日に小金井神社で開催されるはけのおいしい朝市に出店します。はけのおいしい朝市に出店するのは1年ぶり、小金井神社での出店は2年ぶり、かな。小金井神社のはけのおいしい朝市は、うちの子どもたちも含め、神社の境内を子どもたちが走り回り、にぎやかな雰囲気で楽しいので、今から楽しみにしています。といっても、来週末なんで、もう準備をし始めなくちゃいけないんですけどね。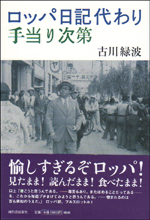 ■「週刊娯楽よみうり」に1958年から1959年にかけて連載したコラムをまとめた本。食べ物や映画や舞台、読んだ本‥‥などについて、日記代わりのようにつづられている。ほめたりときに毒舌をはきつつ短めの文章でテンポよく読めます。
■「週刊娯楽よみうり」に1958年から1959年にかけて連載したコラムをまとめた本。食べ物や映画や舞台、読んだ本‥‥などについて、日記代わりのようにつづられている。ほめたりときに毒舌をはきつつ短めの文章でテンポよく読めます。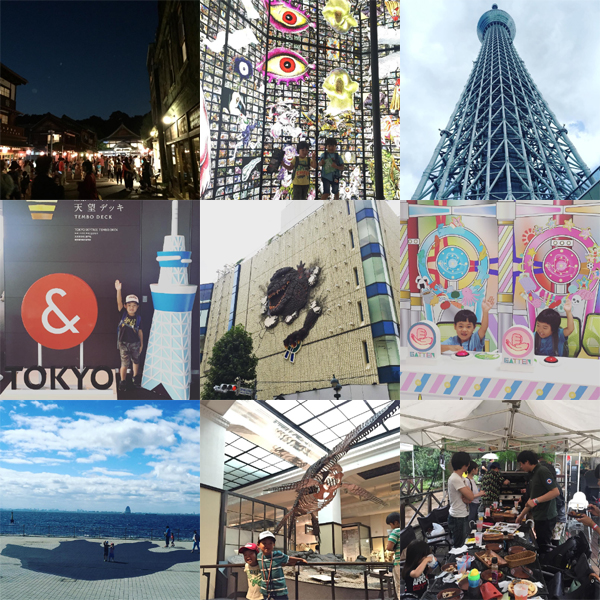
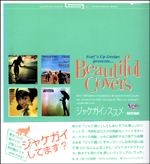 ■レコードジャケットがたくさん載っている本を読んでいるのは楽しい。レコードジャケットに添えられている文章が著者の思い入れたっぷりだったりするとさらに楽しい。思わず「ジャケガイ」してしまいそうな美しいジャケットのレコードをオールカラーで掲載したこの本もそんな本。まぁだいたいきれいな女性が写っているジャケットが多く、イージリスニングからオールディーズ、ジャズ、ボサノバなど1970年くらいまでのレコードが紹介されている。サバービアスイートの一面を拡大させた感じと言えるかな。
■レコードジャケットがたくさん載っている本を読んでいるのは楽しい。レコードジャケットに添えられている文章が著者の思い入れたっぷりだったりするとさらに楽しい。思わず「ジャケガイ」してしまいそうな美しいジャケットのレコードをオールカラーで掲載したこの本もそんな本。まぁだいたいきれいな女性が写っているジャケットが多く、イージリスニングからオールディーズ、ジャズ、ボサノバなど1970年くらいまでのレコードが紹介されている。サバービアスイートの一面を拡大させた感じと言えるかな。 ■立川の砂川七番にあったギャラリーセプチマが7月いっぱいでクローズしてしまいました。7月の最後は、タイミングが合ったこともあって、3週続けてセプチマに行って、いろいろな人のライブを見たり、それまで話していなかった人と話したりしました。ほんとの最後の最後までいられなかったけれど、最後の日にセプチマに行けてよかった。
■立川の砂川七番にあったギャラリーセプチマが7月いっぱいでクローズしてしまいました。7月の最後は、タイミングが合ったこともあって、3週続けてセプチマに行って、いろいろな人のライブを見たり、それまで話していなかった人と話したりしました。ほんとの最後の最後までいられなかったけれど、最後の日にセプチマに行けてよかった。
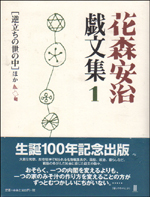 ■昭和29年に刊行された「逆立ちの世の中」と、「暮しの手帖」以外の雑誌・新聞に寄稿した文章を掲載したもの。ファッションやゲージュツ、戦後の世相などについて独特の口調で語っている。最初に花森安治の本を読んだのはいつだったか忘れてしまったけれど、それほど熱心に「暮らしの手帖」を読んでいたわけではなかったので、この絵を描く人がこんな文章を書くんだという感じでちょっと違和感があったけど、最近は慣れてきました。むしろ内容的には辛辣なことを言っているので、この口調によってきつさを緩和しつつ、読む人にストレートに訴えかけてきているような気がします。
■昭和29年に刊行された「逆立ちの世の中」と、「暮しの手帖」以外の雑誌・新聞に寄稿した文章を掲載したもの。ファッションやゲージュツ、戦後の世相などについて独特の口調で語っている。最初に花森安治の本を読んだのはいつだったか忘れてしまったけれど、それほど熱心に「暮らしの手帖」を読んでいたわけではなかったので、この絵を描く人がこんな文章を書くんだという感じでちょっと違和感があったけど、最近は慣れてきました。むしろ内容的には辛辣なことを言っているので、この口調によってきつさを緩和しつつ、読む人にストレートに訴えかけてきているような気がします。