 大佛次郎の随筆を読みたいな、とずっと思いつつも、機会がなく時間が過ぎてしまった。「猫のいる日々」について書いたのが去年の3月、ようやく2冊目です。
大佛次郎の随筆を読みたいな、とずっと思いつつも、機会がなく時間が過ぎてしまった。「猫のいる日々」について書いたのが去年の3月、ようやく2冊目です。
日々の移り変わりや出来事をとおして想う事柄が、適度な力加減でつづられていていい随筆だなぁと思う。10年後ぐらいにまた読み返したい。実際のところ、読み終わった直後にまた読み返したい、と思わせる随筆やエッセイはそれほどないものなのだ。ちなみにあとがきは永井龍男。これから10年、20年経って新しい作家との出会いがあったとしても、この大佛次郎や永井龍男、吉田健一、小沼丹、井伏鱒二、木山捷平といった作家は、ときおり読み返すことになるのだろう。
そんなことを考えたのは、夏の初めくらいに、今買っているこのCDを自分はいつまで聴き続けるのだろうか、自分にとって一生つきあっていけるアーティストやジャンルはなんなんだろうか、ということを、ふと思ってしまったから。少なくとも60や70歳になったとき、ハーフビーやジャスティスは聴いていないのではないだろうか。ソフトロックやギターポップはどうなんだろう?ボサ・ノヴァ?ジャズ?なんて考えたり‥‥。でもこれから20年、30年後と思うと、1960年代の音楽なんて60年、70年前の音楽になってしまうのか、なんて計算をすると愕然としてしまいます。まぁどうでもいいことだけれど、どうなっちゃうんでしょうねー。そもそも今持っているCDを20年、30年後に聴くことができるのか?という疑問もありますしね。そういえば昔、CDが出始めた頃、CDのデータは10年くらいで全部消去されてしまう、なんて噂もあったな~
で、おじいさんになっても演奏したり歌ったりしている音楽ならば、歳をとっても聴き続けられるのではないか、という安易な考えのもと、今年の夏は、おじいさんのCDばかり聴いてました。
まず頭に浮かんだのが顔が、イブライム・フェレールとカルトーラ、それからリコ・ロドリゲス、アンリ・サルバドール。とりあえず、ブームから10年遅れの「ブエナビスタ・ソシアル・クラブ」から聴いてみたら、あのときは嫌な経験もあってキューバ音楽を聴く気になれなかったのだけれど、今聴いてみるとよさがわかるというか、あのとき聴かずに今になってはじめて聴いてよかった、なんて思う。映画公開後に、ルベーン・ゴンサレスやコンパイ・セグンド、エリアデス・オチョアといった人の単独のCDが意外とたくさん出ていたのにびっくりしつつ、このまま古いソンまで聴いてみるかどうかちょっと思案中。やっぱり個人的には、ファニアみたいな盛り上がりまくりのサルサよりも、ゆったりとしたメロディが心地よいソンの方が好きだ。
サンバのほうは、もともと好きだったカルトーラをはじめ、ネルソン・サルジェントやギリェルミ・ジ・ブリート、オス・イパネマズ、ウィルソン・モレイラといったCDをよく聴いてました。
そんなわけで、コンポの横に積み上げられたCDのジャケットは、どれもおじいさんの顔ばかりで、平均年齢も80歳を越えているのではないかと思う。なんたって「愛するマンゲイラ」を発表した時のカルトーラの歳が69歳で最年少なのでは?という状態ですから。でも、どの人もいい顔をしていて、いつかこんなおじいさんになりたいなぁ、とコンポに入っているCDを変えるたびにちょっと思ったりもします。

 渋谷のHMVの6階にある青山ブックセンターが9月で閉店してしまうそうです。オープンしたのが昨年の11月なので1年持たなかったのか~と思うとちょっと寂しい。たまに写真展を見に行ったりしただけだったけれど、いつもがらんとしてたからなー。近くにあるリブロのほうが行きやすい場所にあるし、タワーブックスみたいにHMVのポイントがつくわけでもないので、わざわざ6階まであがって行く気にあまりなれなかったのも事実。個人的にはABCは、レコード屋で例えると一時期のWAVEみたいな位置づけですね。いくらHMVが渋谷系をあおろうが、タワーレコードがビルになろうが、WAVEは別格、みたいな感じ。両方とも会社としてダメになっちゃったところも似てるのが哀しいけれど‥‥。まぁABCは、本店や六本木店などもまだまだ健在なので頑張って欲しいです(と、なぜか上から)。
渋谷のHMVの6階にある青山ブックセンターが9月で閉店してしまうそうです。オープンしたのが昨年の11月なので1年持たなかったのか~と思うとちょっと寂しい。たまに写真展を見に行ったりしただけだったけれど、いつもがらんとしてたからなー。近くにあるリブロのほうが行きやすい場所にあるし、タワーブックスみたいにHMVのポイントがつくわけでもないので、わざわざ6階まであがって行く気にあまりなれなかったのも事実。個人的にはABCは、レコード屋で例えると一時期のWAVEみたいな位置づけですね。いくらHMVが渋谷系をあおろうが、タワーレコードがビルになろうが、WAVEは別格、みたいな感じ。両方とも会社としてダメになっちゃったところも似てるのが哀しいけれど‥‥。まぁABCは、本店や六本木店などもまだまだ健在なので頑張って欲しいです(と、なぜか上から)。 駒場東大前にあるNO.12 GALLERYでやっていた「コウガグロテスク」平野甲賀展を、お盆休み中12日に見てきました。11日には平野甲賀とSarudog(Mu-Stars)のトーク・イベントもあったのですが、これは行けず。というか、なんでMu-Starsなのか。展示の内容も、平野甲賀の作品に加えて、イルリメや阿部海太郎、かくたみほといった人たちによる『コウガグロテスク06』を使った作品も展示されていて、どういう人選なのかどうもわかりません。ギャラリー自体が広くないので、平野甲賀本人の作品をもっと展示してくれればいいのに、と思う。でも展示は多くなかったけれど、手書きの元原稿や切り抜き、ちらしなどがたくさん置いてあって見応えはありましたね。
駒場東大前にあるNO.12 GALLERYでやっていた「コウガグロテスク」平野甲賀展を、お盆休み中12日に見てきました。11日には平野甲賀とSarudog(Mu-Stars)のトーク・イベントもあったのですが、これは行けず。というか、なんでMu-Starsなのか。展示の内容も、平野甲賀の作品に加えて、イルリメや阿部海太郎、かくたみほといった人たちによる『コウガグロテスク06』を使った作品も展示されていて、どういう人選なのかどうもわかりません。ギャラリー自体が広くないので、平野甲賀本人の作品をもっと展示してくれればいいのに、と思う。でも展示は多くなかったけれど、手書きの元原稿や切り抜き、ちらしなどがたくさん置いてあって見応えはありましたね。 私が勤めている会社は、お盆の期間に2日、共通のお休みがあって、7、8、9月のあいだにあと2日自由にお休みをとることができます。今年は13、14日が共通のお休み、残りをいつとるかはまだ決めてません。どうしようかな~。夏休みというイメージで考えると、お盆の頃になるともう後半という感じで、海にも行けなくなるし、もうそろそろ終わりだな~、読書感想文やポスターとか残りの宿題もしなくちゃね、気がつくとだんだん日も短くなってきたりしてるし‥‥という気分。そんな時期なのに我が家の朝顔は、まだ二葉のあいだから本葉が出始めたばかり。去年の様子から秋口まで花が咲いたりするのを知っているので、そんな状態でも毎朝水をあげているけれど、もしわたしが小学校一年生だったら、かなりがっかりしてしまうだろうと思う。梅雨が明けるのが遅かったとはいえ、8月に入ってこんなに暑い日が続いているのにね。で、それにしても暑い。何もする気も起きない~なんて思いつつ「百鬼園先生言行録」を読んでいたら、百鬼園先生の家は37度もあるそうで、それに比べればましなのか。どうなのか?
私が勤めている会社は、お盆の期間に2日、共通のお休みがあって、7、8、9月のあいだにあと2日自由にお休みをとることができます。今年は13、14日が共通のお休み、残りをいつとるかはまだ決めてません。どうしようかな~。夏休みというイメージで考えると、お盆の頃になるともう後半という感じで、海にも行けなくなるし、もうそろそろ終わりだな~、読書感想文やポスターとか残りの宿題もしなくちゃね、気がつくとだんだん日も短くなってきたりしてるし‥‥という気分。そんな時期なのに我が家の朝顔は、まだ二葉のあいだから本葉が出始めたばかり。去年の様子から秋口まで花が咲いたりするのを知っているので、そんな状態でも毎朝水をあげているけれど、もしわたしが小学校一年生だったら、かなりがっかりしてしまうだろうと思う。梅雨が明けるのが遅かったとはいえ、8月に入ってこんなに暑い日が続いているのにね。で、それにしても暑い。何もする気も起きない~なんて思いつつ「百鬼園先生言行録」を読んでいたら、百鬼園先生の家は37度もあるそうで、それに比べればましなのか。どうなのか? 「屋上がえり」も含めて、「月と菓子パン」「踏切趣味」「ぽっぺん」「部屋にて」など、石田千の本はひかれるタイトルばかりなので、本屋さんで見つけるとつい手に取ってしまう。石田千も“同時代に生きている作家の新作を心待ちにしている”作家の一人といえるかも。歳も近いしね‥‥(あまり意味はなし)。
「屋上がえり」も含めて、「月と菓子パン」「踏切趣味」「ぽっぺん」「部屋にて」など、石田千の本はひかれるタイトルばかりなので、本屋さんで見つけるとつい手に取ってしまう。石田千も“同時代に生きている作家の新作を心待ちにしている”作家の一人といえるかも。歳も近いしね‥‥(あまり意味はなし)。 週末の富士見ヶ丘は、七夕祭りと題してなぜかサンバとよさこいソーランを踊る人たちが商店街を行進。通り沿いのお店が店の前に模擬店などが出してかなり盛り上がっていたけれど、なんだかなーという感じは否めません。先日、お店を閉めてしまったくだものやさんのおじさんが、模擬店の前で張り切っているのを見てちょっとほっとしてしまったりしたけどね。あと、「サンバカーニバルははなの舞までで終了です」というアナウンスが笑えました。普通の盆踊りは開催されるのだろうか。
週末の富士見ヶ丘は、七夕祭りと題してなぜかサンバとよさこいソーランを踊る人たちが商店街を行進。通り沿いのお店が店の前に模擬店などが出してかなり盛り上がっていたけれど、なんだかなーという感じは否めません。先日、お店を閉めてしまったくだものやさんのおじさんが、模擬店の前で張り切っているのを見てちょっとほっとしてしまったりしたけどね。あと、「サンバカーニバルははなの舞までで終了です」というアナウンスが笑えました。普通の盆踊りは開催されるのだろうか。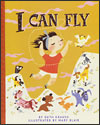 この本は、先月渋谷のロゴスでやっていた洋書バーゲンに行ったときに買った。といってもバーゲン会場で買ったわけではなくて、普通の売り場の絵本コーナーに置いてあったもので、値札に「セール」と書いてあったことを考えると、洋書バーゲンにあわせて値段を下げたのかもしれない。実際アマゾンよりで売られている価格よりも安かったし。
この本は、先月渋谷のロゴスでやっていた洋書バーゲンに行ったときに買った。といってもバーゲン会場で買ったわけではなくて、普通の売り場の絵本コーナーに置いてあったもので、値札に「セール」と書いてあったことを考えると、洋書バーゲンにあわせて値段を下げたのかもしれない。実際アマゾンよりで売られている価格よりも安かったし。 内容的には「最近の日本どうなってんの」的なコラムが多いので、これに「愚者の楽園」というタイトルをつけるなんて獅子文六にしてはストレートだなぁ、と思いながら読んでいたのだけれど、(といってもそんなに凝ったタイトルをつけることもあまりありませんが‥‥)あとがきによるとこのタイトルは、この連載の前の執筆者が名づけたものということです。獅子文六をストレートかひねくれているかという分類で分けると前者になると思うけど、なんとなく違和感があったので少し納得。
内容的には「最近の日本どうなってんの」的なコラムが多いので、これに「愚者の楽園」というタイトルをつけるなんて獅子文六にしてはストレートだなぁ、と思いながら読んでいたのだけれど、(といってもそんなに凝ったタイトルをつけることもあまりありませんが‥‥)あとがきによるとこのタイトルは、この連載の前の執筆者が名づけたものということです。獅子文六をストレートかひねくれているかという分類で分けると前者になると思うけど、なんとなく違和感があったので少し納得。 なんだか貧乏話を続けて読んでしまった。普通なら「もういいや」という気分になってしまいそうなのだけれど、どちらも違う意味でどこかのんびりした雰囲気なので、気が滅入ることはなかったです。いや、吉田健一はほんとうに貧乏なのかわからない。乞食の格好をして文芸春秋社の前に座ったとか、戦後、米を転売しようとして東北まで行って、警察に捕まった話など、前に読んだことのある話でも、必要に迫られてというよりも、酔狂で、あるいはおもしろそうだから、みたいなところがある。あの吉田茂の息子で貧乏なわけないだろう、という気もするし、吉田茂はまったく息子に援助をしなかったらしいということなので、ほんとうに貧乏だったのかも、という気もするし、実際はどうだったのか。そんなことはどうでもよろしいって言われそうだが‥‥。
なんだか貧乏話を続けて読んでしまった。普通なら「もういいや」という気分になってしまいそうなのだけれど、どちらも違う意味でどこかのんびりした雰囲気なので、気が滅入ることはなかったです。いや、吉田健一はほんとうに貧乏なのかわからない。乞食の格好をして文芸春秋社の前に座ったとか、戦後、米を転売しようとして東北まで行って、警察に捕まった話など、前に読んだことのある話でも、必要に迫られてというよりも、酔狂で、あるいはおもしろそうだから、みたいなところがある。あの吉田茂の息子で貧乏なわけないだろう、という気もするし、吉田茂はまったく息子に援助をしなかったらしいということなので、ほんとうに貧乏だったのかも、という気もするし、実際はどうだったのか。そんなことはどうでもよろしいって言われそうだが‥‥。 カヌー犬ブックスも少し本の量が増えてきたし、これ以上分類分けをしてもわかりにくくなるだけになりそうなので、思い切って検索を作ってみました。といっても、全文検索は難しそうなので書名と著者名で引っかかるものだけ、複数語の単語は入れられないという簡単なものです。検索を考えたときからどうしようと思っていた著者名のゆれも考慮していません。海外文学は、翻訳者や出版された時期によって著者名の表記が変わってしまうのが困ったところ。ほかの検索サイトはどうしているのだろう。ちゃんとデータベース作ってるのだろうか。なので、例えば「ジョン・アップダイク」と入力しても「ジョン・アプダイク」は検索されないため、「ダイク」とか適当に入れてもらえるとうれしいです。もしくは少し増えてきたと言ってもそれほど多くの在庫があるわけではないので、「ジョン」でもいいと思います。
カヌー犬ブックスも少し本の量が増えてきたし、これ以上分類分けをしてもわかりにくくなるだけになりそうなので、思い切って検索を作ってみました。といっても、全文検索は難しそうなので書名と著者名で引っかかるものだけ、複数語の単語は入れられないという簡単なものです。検索を考えたときからどうしようと思っていた著者名のゆれも考慮していません。海外文学は、翻訳者や出版された時期によって著者名の表記が変わってしまうのが困ったところ。ほかの検索サイトはどうしているのだろう。ちゃんとデータベース作ってるのだろうか。なので、例えば「ジョン・アップダイク」と入力しても「ジョン・アプダイク」は検索されないため、「ダイク」とか適当に入れてもらえるとうれしいです。もしくは少し増えてきたと言ってもそれほど多くの在庫があるわけではないので、「ジョン」でもいいと思います。