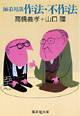 ここで告知するのもどうかと思うのだけれど、友だちが主催する写真展に参加することになりました。30代半ばの7人によるモノクロ写真を展示するグループ展で、クリップインターメディアという恵比寿にある会社を会場にして、2007年 2月5日(月)から11日(日)のあいだ、平日は夕方から、土日は昼間、10日は19時からレセプション・パーティーも開く予定です。詳しくはこちらをご覧いただければと思います。
ここで告知するのもどうかと思うのだけれど、友だちが主催する写真展に参加することになりました。30代半ばの7人によるモノクロ写真を展示するグループ展で、クリップインターメディアという恵比寿にある会社を会場にして、2007年 2月5日(月)から11日(日)のあいだ、平日は夕方から、土日は昼間、10日は19時からレセプション・パーティーも開く予定です。詳しくはこちらをご覧いただければと思います。
「時代の狭間で若い感性を失いつつ、確固たる価値の完成系にも辿り着いていない30代半ばの迷える男性達が見ている『心の風景』」なんてという、なんだかすんごいテーマが掲げられていますが、わたしは1月の初めに急に誘われたので、去年、高浪さんのお店で焼いた写真や、何年か前に写真美術館のワークショップで引き伸ばした写真から何枚か選んで出展しようと思っています。この写真展には間に合わうかどうか分からないけれど、3月に写真美術館で行われる写真暗室入門ワークショップを申し込んだこともあって、年が明けてから、モノクロフィルムを入れたカメラを割と持ち歩いていたので、1月に何本か撮ったモノクロ写真から何枚か出せたらなぁ、という感じ。
前にワークショップに参加したときは、全然用意ができていなくて、昔に撮った写真をかき集めて持っていって、なにも知らないまま、教えてもらうままに作業をしただけだったのですが、今度は事前に写真を撮っておいて引き伸ばしたいものをきちんと選んだり、作業の手順などを再度予習しておきたいです。で、その後は、年に一度か二度でいいから、自分一人で暗室を借りて引き伸ばしができるようになりたいですね。そんなことしなくても、デジカメ買ってフォトショップでやればいいじゃん、という意見もありますが‥‥。
「北欧デザイン1 家具と建築」-渡部千春-
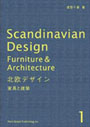 これもプチグラの新春セールで購入。ときどきパラパラと見ているだけなのだけれど、こういう本を見ていると、北欧に行きたくなりますね。いや、北欧じゃなくてもいいかな。
これもプチグラの新春セールで購入。ときどきパラパラと見ているだけなのだけれど、こういう本を見ていると、北欧に行きたくなりますね。いや、北欧じゃなくてもいいかな。
普段、スペースシャワーTVとかミュージックオンTV、MTVばかり見ていると、微妙な範囲で音楽に詳しくなってきます。ものすごく売れているヒット曲はそれほど流れないし、ビデオを作っていない小さなインディーズから出ている人の曲は、もちろん放送されないので、メジャーから出たばかりの人とかが多いんですけどね。それに注意して見ているわけではないし、記憶力もないので、バンド名とか曲名はぜんぜん覚えられません。だた別のどこかで聞いたり、HMVなどでジャケットを見かけたりすると、「あぁよく流れてる曲だなぁ」とか「あの曲歌ってる人かぁ」なんて思う。それにしても、ライブの映像などを見ていると、どんな音楽にそれなりのファンというものがいるものなのだなぁ、と。まぁ人のことを言える趣味でもないけれど‥‥。
それからテレビを見ていると、自分がもし今中学生だったらどんな音楽を聴いているんだろう、なんて考えたりもします。中学生というところがポイントです。高校になると、わりと自分の趣味がはっきりしてくるし、情報量も増えるけれど、中学の頃は、普通のヒット曲と自分の好みが混じり合っている時期なので、後になって、その時どんな音楽を聴いていたか考えるとちょっと恥ずかしい。
現実にわたしが中学生だった頃は、1982年から1984年になるわけですが、その頃、流行っていたニューミュージック系の音楽を聴きつつ、山下達郎や伊藤銀次、佐野元春、杉真理、村松邦男、大貫妙子‥‥など、大滝詠一が関わった人を追っかけてましたね。あとはっぴいえんどにさかのぼって細野晴臣を聴いて、YMOをちゃんと聞き直したり、ティン・パン・アレイを知ったり(でもこの辺は、ラジオとかで聴くだけでさすがにレコードは買わなかったです。)。そんな20年前のそのあたりの人たちに、今当たるのはどんな人だちなんだろうか。う~ん、わからん。
そういうことをあまり考えないで、多分ハードコア系は聴いてないと思うし、HipHop系も微妙、かといって、セカンドロイヤルやエスカレーターにはとどいてないだろうし‥‥なんて切り分けていくと、結局、普通にバンプ・オブ・チキン、アジカンとか聴いてそう。そのあと、ちょっといろいろ聴き始めてゴーイング・アンダー・グランド、スネオヘアー、くるりとか‥‥。で、やっぱりフリッパーズギターの再発なんか買ったりして、今さらコーネリアスの最初の方とか(「SENSUOUS」は、中学生には難しいだろう)、オリジナル・ラブ、ピチカート・ファイブとか聴いちゃったりしてるのか。その流れも中学生としては微妙だな。あと木村カエラは絶対聴いてると思うんですよ。(洋楽編に続くかも‥‥)
「ふるさと隅田川」-幸田文-
 「悪夢探偵」を観に行く。塚本晋也監督、出演しているのは、松田龍平、hitomi、安藤政信、大杉漣、原田芳雄‥‥。おおざっぱに言うと、密室で自分の体を切りつけて失血死するという殺人事件が続けて発生する。被害者はいずれも、死ぬ最後に「0」という番号に携帯電話から電話をかけていたため、事件を担当する女刑事、霧島慶子は、電話を通じて自殺者に何らかの暗示を掛けているのでは?と推測し、捜査を進める。そして、他人の夢の中に入れる能力を持つ影沼京一という男の存在を知り、彼に捜査への協力を申し入れるのだが‥‥というストーリー。
「悪夢探偵」を観に行く。塚本晋也監督、出演しているのは、松田龍平、hitomi、安藤政信、大杉漣、原田芳雄‥‥。おおざっぱに言うと、密室で自分の体を切りつけて失血死するという殺人事件が続けて発生する。被害者はいずれも、死ぬ最後に「0」という番号に携帯電話から電話をかけていたため、事件を担当する女刑事、霧島慶子は、電話を通じて自殺者に何らかの暗示を掛けているのでは?と推測し、捜査を進める。そして、他人の夢の中に入れる能力を持つ影沼京一という男の存在を知り、彼に捜査への協力を申し入れるのだが‥‥というストーリー。
でも実際は、松田龍平演じる影沼京一が、自ら探偵と名乗っているわけではないし、そもそも探偵という言葉は出てこなかったような気がします(出てきたとすればあのシーンだな)。全体としてかなり暗いのだけれど、音の使い方とか動きとかが、なんとなく「鉄男」っぽいところがあってよかったです。
どこかにシリーズ化する予定と書いてあったけれど、これをシリーズ化できるのかな、という気はします。でも第二弾を観てみたいですね。ただエリート刑事を演じるのがhitomiというのがねぇ。なんとなく塚本映画にあっていないような‥‥。
で、週末、この映画を観たせいで、今週、わたしの中では、「ああ、いやだ、ああああ、いやだ。ああ、いやだ」という言葉が、ちょっとした流行りになってます。仕事でちょっと面倒なことがあったり、どうしようもないやりとりしていたりすると、頭の中で、「ああ、いやだ、ああああ、いやだ。ああ、いやだ」という言葉が浮かんできます。もちろん口に出して言ったりしてませんけどね。たいていの場合、たいしたことでもないので、おおげさないいまわしと反して、そのあとでなんとなくおかしな気分になるのがいい、かも。
「昼月の幸福―エッセイ41篇に写真を添えて」-片岡義男-
 去年は片岡義男の本もまったく読んでいませんでした。エッセイしか読まないとしても、片岡義男に関しては、山口瞳や永井龍男と違ってまだ読んでない本がたくさんあるし、現役の作家なのでもっと簡単に手に入りそうなのに、意外と古本屋で見かけような気がします。単にちゃんとチェックしていないだけかもしれませんが‥‥。
去年は片岡義男の本もまったく読んでいませんでした。エッセイしか読まないとしても、片岡義男に関しては、山口瞳や永井龍男と違ってまだ読んでない本がたくさんあるし、現役の作家なのでもっと簡単に手に入りそうなのに、意外と古本屋で見かけような気がします。単にちゃんとチェックしていないだけかもしれませんが‥‥。
この本は、タイトルの昼月をはじめ、三日月や空、雲、風、海‥‥など、都会での生活の中でどうやって自然を感じるかということが、1990年代以降、片岡義男のスタイルとなっている写真と併せて書かれてます。個人的なイメージに過ぎないけれど、カフェとかに置いてあって、行くたびにちょっとずつ読みたい、と思う。薄暗い喫茶店でなくて、明るめのカフェのほうがいいなぁ。
月曜日は、有給休暇をとって南船橋のイケアへ。新横に行ったのは11月なので、また?という感じではありますが、ちょっと欲しいものがあったりしたし、混んでいる休日ではなくて平日に行ってみたかったのだ。それに今年(2006年4月~2007年3月)は旅行にも行っていないので、有休も2日しか使ってなかったし‥‥。
さて、昼前くらいにうちを出て、新宿から総武線で西船橋、武蔵野線で南船橋と移動。平日なので電車の中は空いているし、外はいい天気だし、ちょっとした小旅行だなぁ、なんて思いながら、窓ガラスを通して背中に日差しを感じながら電車に揺られていると、ミオ犬のケータイに「今、イケアに向かっているのだけれど、なにか欲しいものある?」といった内容のメールが、先日、代々木のDADA CAFEで会った友だちから届いた。向こうも同じように有休を取ったとのこと。う~ん、行動パターンが似すぎ!
南船橋は遠かったけれど、やはり平日に来てよかった。人があまりいないのでゆっくりと、時には逆走したりして店内を見れるし、カートを移動させるのにもぶつかったりしないし、カフェに列もできてないし、とりあえず、入ってすぐに出口近くにあるカフェ(?)でホットドッグ食べて、途中、友だちと合流したあとお茶して、帰り間際には平日限定のディナーセットまで食べるというイケアづくしの一日を堪能してきました。
「せかいでいちばん おかねもちのすずめ」-エドアルド・ペチシカ、ズデネック・ミレル-
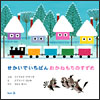 正直な話、プチグラがクルテクを紹介し始めた頃は、チェブラーシカのすぐ後ということもあって、もういいかなぁ、という気分だったのですが、家でカートゥーンネットワークが見られるようになって、毎週、なんとなくアニメを見てしまうと、グッズとか絵本とか欲しくなったりして。どちらかというと、プチグラ関係では、マウスの方がキャラ的には中途半端な感じがして好きなんだけれど、あまりいいグッズが出てないんですよね。
正直な話、プチグラがクルテクを紹介し始めた頃は、チェブラーシカのすぐ後ということもあって、もういいかなぁ、という気分だったのですが、家でカートゥーンネットワークが見られるようになって、毎週、なんとなくアニメを見てしまうと、グッズとか絵本とか欲しくなったりして。どちらかというと、プチグラ関係では、マウスの方がキャラ的には中途半端な感じがして好きなんだけれど、あまりいいグッズが出てないんですよね。
さて週末は、代々木にあるプチグラのショールームで行われていた、プチグラ新春セールに行ってきました。代々木なんて普段は行く機会もなくて、ただ通り過ぎるだけなのですが、駅を降りてみると、すぐ近くに高島屋やが見えたりしてもうすぐそこは新宿で、駅前にはNTTドコモタワーがあったりするのに、ちょっと路地を入ると、ものすごい古い家やマンションが残っていたり、見た目には普通の小さなビルなのに実は専門学校、みたいな建物があったりして、おもしろい。プチグラのオフィスも住宅街の真ん中にあって、古めのビルを改装したものらしく、塗り直した白い壁と建物の形の感じがよかったり、ガラスに入っている模様、セールだからか分かりませんが、入り口にムーミンパパの看板(?)が置いてあったりして、こんなところで働きたいなぁ、と思うようなオフィスでした。実際に働いたら建物のことなんて考えている場合でもないのだろうけどね‥‥。座ったりするところはないけれど、「Hot Drinks around the World 世界のホットドリンク」に載っているホットドリンクとクッキープレゼントもあるので、ちょっとひと休みという感じで落ち着けます。セールの方は21日までです。
プチグラのオフィスを出た後は、DADA CAFEでランチ。ここはマンションやNTTドコモタワーに囲まれた路地裏にあって、昭和15年に建てられた2階建て一軒家を改装したというCafe。改装はされているものの、ここには廊下だったんだろうなぁとか、ここに押入があったんだろうなぁとか、エアコンが置いてあるところは元は床の間だったんだろうなぁ、なんてことを思ったりしていると、子どもの頃に遊びに行ったおばあさんの家を思い出します。見た目は普通の家なので、入るときに靴を脱ぎたくなってしまいますね。ご飯も五穀米で、ちょっと定食っぽくある程度量もあっておいしかったし、写真を見るかぎりではデザートもおいしそうでした。そういえば、先週、ロバロバに行く前に、下北沢にあるmois cafeでランチを食べたし、なんとなく、古い一軒家を改装したカフェが、わたしのなかでは流行りつつあるような、ないような。神楽坂のカドにもまた行きたい。
ところで、DADA CAFEでご飯を食べていると、友だちが入ってきてので、びっくり!下北や吉祥寺であれば、偶然に友だちに会うこともあるけれど、代々木で、しかもイベントとかでなく、お店でばったり誰かに会うことがあるなんて思ってもいませんでした。ところがこの偶然はまだ続くのでした。
「ぼくの父はこうして死んだ-男性自身 外伝-」-山口正介-
 「礼儀作法入門」を読んだついでに読み始めてしまったのだけれど、ちょっと失敗でした。少なくとも「江分利満氏の優雅なサヨナラ」を読んだ後に読めばよかった。タイトルのとおり山口瞳の闘病生活~死にいたるまでを息子の山口正介がつづった本なのですが、やはり“外伝”は“外伝”であって、まずは本人の視点からのものを読むべきだったかな、と。
「礼儀作法入門」を読んだついでに読み始めてしまったのだけれど、ちょっと失敗でした。少なくとも「江分利満氏の優雅なサヨナラ」を読んだ後に読めばよかった。タイトルのとおり山口瞳の闘病生活~死にいたるまでを息子の山口正介がつづった本なのですが、やはり“外伝”は“外伝”であって、まずは本人の視点からのものを読むべきだったかな、と。
確かに内容的には興味深いしおもしろい。でもそれはまず本人の視点からの描写があり、それに対する枝としてのおもしろさでもあるように思う。多分、山口正介自身も、それを意識してこの本を書いているような気がします。だからかわかりませんが、なんとなく父親に対する遠慮みたいなものが、全体的に漂っていてどうもすっきりしない
。同じように父親の死を描いた幸田文の「父・こんなこと」には、露伴に対する愛憎や著者の葛藤が遠慮なく、しかも感情的な視点と客観的な視点とをうまく交えながら描かれてたのを考えると、どうも物足りなさが残ってしまいます。
ロバロバカフェの年始めは、「マスキングテ-プを使った作品展」。ということで、久しぶりに下北から小田急に乗って経堂へ。ロバロバカフェに行くのは去年のゴールデンウィークの「“本”というこだわり、“紙”でできることvol.3」以来なので、半年以上ぶり。前回行ったときは、「この前来たときは寒くて大変だったのにすっかり暖かくなって‥‥」なんて話をしていたのに、今度はすっかり逆に季節になってしまってます。行ってみると近いな~と思うんですけどね~。
マスキングテ-プについて言えば、古本市の時も、小冊子のときもその話をしたりしていたので、ついにここまで、という感じです。実際に倉敷にあるカモ井加工紙株式会社まで工場見学に行って来たみたいで、その見学記が書かれた小冊子が置いてあったりしていました。展示の方は、コラージュ風なものから、マスキングテープで描かれた絵、ちょっとした遊び感覚のもの、そして帽子という立体物まで、アイデアに溢れたさまざまな作品があり、楽しい。というか、ロバロバのカウンターで、置いてある本や小冊子を眺めたり、店長さんと話したりしながら、カウンターでコーヒー飲んでると落ち着くのはなんでかね~。
「続 礼儀作法入門」-山口瞳-
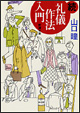 昨日の続き‥‥。
昨日の続き‥‥。
土曜に青山ブックセンターに行きたかったのは、渋谷からブックセンターまでのあいだにある古本屋さんが日曜お休みだったということと、ひさしぶりに日月堂に行きたかったから。日月堂は、実は一度しか行ったことがないのですが、何も買わなかったのに、昔の缶詰のラベルや袋、新聞の切り抜きなど、いろいろ見せてもらったり、教えてもらったりしたので、機会があればまた行きたいなぁとずっと思っている古本屋さん。そのわりには前に行ったときからかなり時間が経ってしまってますが。自分では集めたりする気はないけれど(集められない)、“紙もの”は常に気になっちゃいますね。
“紙もの”といえば、表参道駅の近くにあるpress sixもお気に入りのお店の一つ。こちらはフランス(ヨーロッパ?)のパンを入れる袋や封筒などがあって、どれもいいデザインなので、みているだけでも楽しい。見ているとお店に来るたびに一つずつ買って、集めて行くのもいいかもね、なんて思ったりもするけれど、いいなぁと思うのは意外と高かったりするので、なんとなく踏み切れないまま何年か経ってしまってるという感じ。
去年、パリの蚤の市に行ったときに、こういう袋を売っているお店(?)が何軒かあって、そこでも割と高い値段が付けられていたことを考えると、このくらいの値段でもしょうがないんだろうなぁ、とも思います。いい年した男が紙の袋の値段でなに言ってんだかっ、という気もしないでもないですが。
「礼儀作法入門」-山口瞳-
 ガラにもない少女小説を読んだのもつかの間、いつものおやじエッセイに戻ります。
ガラにもない少女小説を読んだのもつかの間、いつものおやじエッセイに戻ります。
昨年、山口瞳の本を3冊しか読んでいないことが判明したので、今年は、将棋や競馬ものを含めて、文庫本を制覇するというのがいちおうの目標。何事もはじめが肝心というわけで、今年の読書は、本棚に置きっぱなしになっていた「礼儀作法入門」から始めてみたのですが(「戦場のガールズライフ」は、年末ぎりぎりに読んだので‥‥)、なんとなく、年の初めに読む本、としては、なかなかぴったりなタイトルかもしれない、なんてことも思ったりしてます。
さて、この本はマナーの解説本ではなく、その解説書の副読本として読んで欲しい、と山口瞳本人は書いているけれど、わたしとしては、あとがきに書かれているように、山口瞳本の副読本としたほうがぴったりくるような気がします。というのは、やはり、山口瞳は偏見の人なのですよ。確かにマナーとして見習わなくてはいけないこともたくさんあるけれど、逆に「それはどうかなぁ」ということもたくさんあるし、自分の経験や意見を書いておきながら、最後に「~ということもあるので、、最近、わたしはその考えを改めている」みたいなことが書いてあったりします。しかも、何冊か山口瞳の本を読んできた人にとっては、どこかで書かれているような主張が目につくだろうし、多分それは、ここで書かれているよりも詳しく、具体例が分かりやすく、そして主張も激しいものに違いなく、明らかにそちらを読んだ方が、エッセイとしてはおもしろいだろうと思う。でもこうやって簡潔な例に対する答えという形で書かれると、全体として山口瞳の主張集みたいな趣が出てきて、「男性自身」などいつものエッセイとは違ったわかりやすさやおもしろさがあります。ファンとしては、ムキになったところがないので、少し肩すかしに感じてしまう部分もあるけれど、逆に気楽な感じが「礼儀作法入門」という堅いタイトルに反しているようでいい。その辺は、「GORO」という「男性自身」とは違う読者層向けの雑誌に連載されたということがよい影響を与えているのかもしれません。
昨日は、夕方まで雨が降っていてしかも寒かったので、ほとんど家の中にいました。普通の週末だったら、無理にでもちょっと出かけてしまうところだけれど、年末年始ずっと天気良かったし、なんて思ってしまうのは、ずっと休みだったし3連休だから。こういう余裕がいつもあるといいのに。そんなわけで、今日は昨日行く予定だった青山ブックセンターでやっている「洋書ビッグバーゲン2007」へ。最終日ということもあって、やはり欲しい本もあまりなく、あってもページやカバーが破れていたりして、がっかり。その後、ナディッフとロゴスギャラリーでの洋書バーゲンも見て回ったのだけれど、結局、何も買わずに帰ってきました。「どうしようかなぁ」と考えてしまう本を買うんだったら、ちょっと高くてもほんとに欲しい本をアマゾンで買ったほうがいい、と思ってしまう。アマゾン安いしね。
「あまカラ(抄)3」-高田宏編-
 今年最後の雑記です。数えてみたら今年は84でした。去年は124、一昨年は159だったので、あんまり書いてない。一応買った本、読んだ本については、残らず書いているので、単に読んだ本の量が少なくなったということか。本を読む時間がなくなっていることは、自分でも分かっていたけれど、一昨年の約1/2になっているとは思ってませんでした。まぁ171冊の中には雑誌とか写真集とかも含まれてるしね‥‥。でも来年は100冊くらいは、本を読みたい(買いたい)、かな。
今年最後の雑記です。数えてみたら今年は84でした。去年は124、一昨年は159だったので、あんまり書いてない。一応買った本、読んだ本については、残らず書いているので、単に読んだ本の量が少なくなったということか。本を読む時間がなくなっていることは、自分でも分かっていたけれど、一昨年の約1/2になっているとは思ってませんでした。まぁ171冊の中には雑誌とか写真集とかも含まれてるしね‥‥。でも来年は100冊くらいは、本を読みたい(買いたい)、かな。
さて、今年読んだ主な作家としては、獅子文六が8冊、安藤鶴夫と小島政二郎、庄野潤三が5冊といったところで、一時期かなり読んでいた山口瞳は3冊しか読んでないし、永井龍男にいたっては1冊も読んでないという有様。両者とも手に入りやすい本がなくなってきたとはいえ、永井龍男の本を一年以上読んでないなんて、ちょっとショックだ。来年は、古本屋を回るときにもう少し気をつけて、ちょっと値段が高くても手に入れておくようにしたい。
本屋のほうは、年の初めにロバロバカフェの古本市に参加したことと、11月にようやくトランクルームを借りたことくらいしかトピックはないですね。相変わらずです(売上げを含めて)。古本市は、多分、ロバロバの店主を始めいろいろな人に甘えてしまって、店番するわけでもないのに、週末になると一日、うろうろして来てくれた人としゃべったりしてただ楽しんでしまった、という感じでした。でも時期が時期だったせいもあり、雪や雨が降ったりしてかなり寒かった‥‥。来年の予定はぜんぜん決まってないけれど、トランクルームも借りたし、もう少し在庫を増やして、見に来てくれた人が欲しいと思うような本がそろっているような本屋にしていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。
「まぼろしの記」-尾崎一雄-
 去年の年末は、ロバロバカフェの古本市準備でてんやわんやだったのですが、今年はわりとのんびり。昨日は寒い中、高円寺や阿佐ヶ谷を散歩して、夜はテレビを見ながら年賀状を書いて、今日はちょっと部屋の掃除をしたりしたあと、吉祥寺に行って‥‥という。掃除も床とかはミオ犬がやってくれてたし、クローゼットの中などは、1カ月前くらいに片づけておいたので、やることといえば、窓と飾ってあるおもちゃやスノードームを拭くくらいなのだ。昼間は、風は強いけれど日差しはあったので、ベランダに出て窓を拭いていると、背中が暑くなってきたりして、あらためて今年の冬は暖かいと思う。それにしても拭くたびにスノードームの中の水が減っていってしまっているのが悲しい。苦労して手に入れたペプシのおまけのスヌーピーのスノードームなんて、もう水の上に頭の先が出ちゃってます。やはり年中エアコンのきかせた、乾燥した部屋の中に置いたらいけないのだろうか。
去年の年末は、ロバロバカフェの古本市準備でてんやわんやだったのですが、今年はわりとのんびり。昨日は寒い中、高円寺や阿佐ヶ谷を散歩して、夜はテレビを見ながら年賀状を書いて、今日はちょっと部屋の掃除をしたりしたあと、吉祥寺に行って‥‥という。掃除も床とかはミオ犬がやってくれてたし、クローゼットの中などは、1カ月前くらいに片づけておいたので、やることといえば、窓と飾ってあるおもちゃやスノードームを拭くくらいなのだ。昼間は、風は強いけれど日差しはあったので、ベランダに出て窓を拭いていると、背中が暑くなってきたりして、あらためて今年の冬は暖かいと思う。それにしても拭くたびにスノードームの中の水が減っていってしまっているのが悲しい。苦労して手に入れたペプシのおまけのスヌーピーのスノードームなんて、もう水の上に頭の先が出ちゃってます。やはり年中エアコンのきかせた、乾燥した部屋の中に置いたらいけないのだろうか。
スノードームついでに書くと、木村カエラの新曲は「Snowdome」というタイトルですね。作曲はビークルだしちょっと気になります。年明けくらいにサクサクに出ないかな。あと、先週、NHKの「ゆるナビ」という番組のいちコーナーで、スノードームコレクターの知人がスノードームを紹介していたり、冬ということもあって、自分の中では、ミニスノードームブームが再来の予感。
