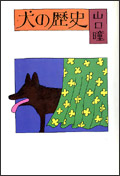 ◆「おじさん、“わぎだ”ってなんですか?」横須賀、遊郭跡散歩
◆「おじさん、“わぎだ”ってなんですか?」横須賀、遊郭跡散歩
8月30日が山口瞳の命日ということもあって、文庫本でタイトルを見たことがなかった単行本を読んでみたのだが、数ページ読んだだけで、どこかで読んだことがあることに気がついた。。全部読んだことがあるかというと、そこまでの記憶はない。
「男性自身」の単行本と文庫本の収録内容が異なっていることは有名ですが、これも文庫化するにあたって、タイトルを変えたり、収録内容を再構成したりしたのだろう。一番最後に収録されている「谷間の華」をタイトルにした文庫本があるので、それとどのくらいかぶるのか確認したいのだけれど、どうも「谷間の花」が本棚に見あたらくて、ちょっと気持ち悪い状態。作品の「谷間の花」を読んだ記憶があるのだから、「谷間の花」の文庫も読んだはずなんだけれど、どこにいっちゃったのかな?
わざわざ一人で「ブルーノ・ナムーリ展」を見に横須賀まで行こうと思ったのは、横須賀に行ったら、行ってみたい場所があったから。それは、山口瞳の「血族」のテーマでもあった「和木田」。すなわち「柏木田」遊郭跡。もちろん今ではその面影はまったく残ってないらしいけれど、命日も近いし、行くなら今しかないような気がしたわけです。まぁさすがに子どもを連れて家族で行くような場所ではないですし‥‥。
小説では「和木田」と書かれていた「柏木田」は、もう地名さえも残ってなくて、現在では横須賀市上町3丁目あたりになります。最寄り駅は京急の県立大学駅で、そこからちょっと歩く感じ。
実際に歩いてみると、海側ではないので、海風があたるわけでもなく、猛暑日の午後3時に歩きまわるにはかなり暑かった。ただ上町3丁目あたりというだけで、詳しい住所などを調べておかなかったにもかかわらず、てきとうに大通りから入ったら、不自然に広い道路に出て、「おっ、この辺か!?」などと思っているうちに、目印の一つだった、昔は福助楼という名前だったらしい福助ホテルが見えて、思わずその広い道の真ん中に立って通りを見渡してしまいました。
福助ホテルの入り口には、「本日より営業を停止させていただきます」といった張り紙がしてあって、もう閉店しているみたいだったけれど、いつから営業をやめたのだろうか?それにしても「本日から」って言われてもねぇ。

しばらく周辺を歩きまわって、写真を撮ったりしたが、さすがに暑いし、カメラを持ってこの辺を歩きまわるのがどうも居心地が悪くて(小心者なんです)。すごすごと駅まで引き返しました。ざっと見ただけなんで、確かなことは分からないけれど、ここ以外では、柏木田遊郭の跡がはっきり分かるような場所ももう残ってないのではないか、と。気分的には柏木田遊郭の唯一の名残りかもしれない福助ホテルが取り壊される前に柏木田に行けてよかったと思う。
ちなみに県立大学の駅の逆側は、横須賀三遊郭のひとつ「安浦」があって、駅名もつい最近までは、県立大学ではなく安浦だったようだ。
ついでにその辺も歩いてみようかと思ったけれど、時間もあまりなく、炎天下のなか歩き疲れたこともあって、そのまま県立大学をあとにしました。

 ◆クレイジーケンバンドを聴きながら京浜急行に乗って横須賀まで
◆クレイジーケンバンドを聴きながら京浜急行に乗って横須賀まで
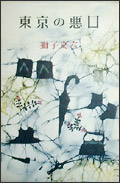 ◆銀座から渋谷へギャラリー巡り。「マイケル・ケンナ展」など
◆銀座から渋谷へギャラリー巡り。「マイケル・ケンナ展」など
 ◆早稲田出身の作家と慶応出身の作家について
◆早稲田出身の作家と慶応出身の作家について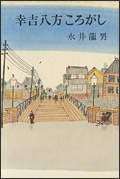 ◆横田基地友好際に行くともう夏の終わりという気がしますね。
◆横田基地友好際に行くともう夏の終わりという気がしますね。

 ◆森茉莉と吉田健一
◆森茉莉と吉田健一 ◆ひまわりの迷路?
◆ひまわりの迷路?
 ◆笹山団地
◆笹山団地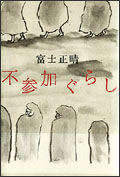 ◆一泊二日で二宮へ
◆一泊二日で二宮へ ◆2010年、山下達郎イヤー
◆2010年、山下達郎イヤー