 最近は朝が早いせいで電車の中ですぐに寝てしまうので、本を読む時間が細切れになってしまう。吉田健一の本は、どこでやめても、どこから読んでも楽しめると思っていたけれど、それは、ある程度ゆっくりと読み進められるというときのことで、あまりにも細切れだと、さすがに読み進めるのが難しかったです。というわけで、途中(といってもかなり最初のほう)で読むのを断念、いつかもう少し時間(と気持ち?)に余裕があるときに、読むことにしよう。
最近は朝が早いせいで電車の中ですぐに寝てしまうので、本を読む時間が細切れになってしまう。吉田健一の本は、どこでやめても、どこから読んでも楽しめると思っていたけれど、それは、ある程度ゆっくりと読み進められるというときのことで、あまりにも細切れだと、さすがに読み進めるのが難しかったです。というわけで、途中(といってもかなり最初のほう)で読むのを断念、いつかもう少し時間(と気持ち?)に余裕があるときに、読むことにしよう。
それにしても麻生太郎が総理の時に、吉田健一ブームは起きなかったな、と思う。吉田茂経由で白洲次郎は、その生涯を描いたテレビドラマが放送されたり、本屋でも関連書籍が平積みになっていたりしたのにね。もう一押しが足りなかったか。
といっても、いま、カヌー犬ブックスに吉田健一の在庫はほとんどないので、ブームにのって売上げが上がるというわけではありませんが‥‥。いや、個人的には、吉田健一の作品のドラマ化とかチャレンジャブルなことをして欲しい。そして潔く失敗して欲しい。映画の宣伝文句でよく使われるのとは違う意味で映像化不可能なのだから‥‥。
明日はちょっと用事があったのでお休みを取ったのですが、ついでに金曜もお休みにしてしまったため、明日から4連休です。たまたまなんですが、会社の人、みんなに「お盆で実家とかに帰るの?」と聞かれてしまう。特に何をする予定があるわけでもないんですけどね。
それから、私はお盆とかお正月に実家に帰るという習慣がまったくないので、ニュースで、混み合った新幹線に乗り込んでいる映像や、渋滞した高速の映像を見ていると「なんでそこまでして帰るのか?なにがみんなをそうさせているのか?」という気持ちになってしまいます。多分、ほかの人にはそうでもないんでしょうけど、私にとっては不思議な光景です。あの気持ちは永遠に分からないような気がしますね。

 さて、前回のつづき‥‥と書き始めたいところですが、ミオ犬がLISMO Video DVDレンタルで、「グーグーだって猫である」とか「転々」とか「たみおのしあわせ」とか「百万円と苦虫女」とか‥‥去年見れなかった日本映画を予約したりしているらしいので、音楽もので夏っぽい映画というのはおあずけか?別に「真夏の夜のジャズ」以外に見たいものが思い浮かんでるってわけでもないんですけど‥‥。
さて、前回のつづき‥‥と書き始めたいところですが、ミオ犬がLISMO Video DVDレンタルで、「グーグーだって猫である」とか「転々」とか「たみおのしあわせ」とか「百万円と苦虫女」とか‥‥去年見れなかった日本映画を予約したりしているらしいので、音楽もので夏っぽい映画というのはおあずけか?別に「真夏の夜のジャズ」以外に見たいものが思い浮かんでるってわけでもないんですけど‥‥。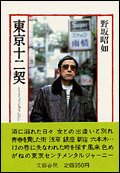 野坂昭如の本を読むのは初めてですね。なんか東京のどの土地に行っても女を買った話ばかりで、先日読んだ「東京余情」に収録されていた舟橋聖一の「赤線風流抄」みたいな気がしないでもない。まぁ実際、赤線に近いところや飲み屋の集まったところが、その時代時代を直接うつしだしているような気がしたりするのだけれど、どうなんでしょう。
野坂昭如の本を読むのは初めてですね。なんか東京のどの土地に行っても女を買った話ばかりで、先日読んだ「東京余情」に収録されていた舟橋聖一の「赤線風流抄」みたいな気がしないでもない。まぁ実際、赤線に近いところや飲み屋の集まったところが、その時代時代を直接うつしだしているような気がしたりするのだけれど、どうなんでしょう。 気が向いたときに読むという感じの“パリ滞在記”。辻邦生の「パリの手記」シリーズは全部で5巻あるのですが、持ち歩きしやすいように文庫で買ってしまったので、全部読めるのはいつになるのかちょっと不安。これを買った後、古本屋や古書展で5巻ぞろいで売られているのを見つけてがっかりしてます(かなり痛みがあったけれどけっこう安かった‥‥)。
気が向いたときに読むという感じの“パリ滞在記”。辻邦生の「パリの手記」シリーズは全部で5巻あるのですが、持ち歩きしやすいように文庫で買ってしまったので、全部読めるのはいつになるのかちょっと不安。これを買った後、古本屋や古書展で5巻ぞろいで売られているのを見つけてがっかりしてます(かなり痛みがあったけれどけっこう安かった‥‥)。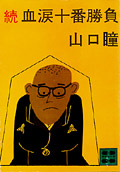 前回の飛車落ちからさらに進んで角落ちでのぞんだ「続・血涙十番勝負」。結果は飛車落ちで3勝6敗1引き分け、角落ちで1勝9敗。本の中でも、角落ちの難しさや角落ちに対するプロの意気込み(プロは角落ちで素人に負けることを恥とする)が何度も書かれているが、まさにそのとおりの結果に。いや、最後の1勝のために、9連敗があったのだ、とも言えます。適当ですが。
前回の飛車落ちからさらに進んで角落ちでのぞんだ「続・血涙十番勝負」。結果は飛車落ちで3勝6敗1引き分け、角落ちで1勝9敗。本の中でも、角落ちの難しさや角落ちに対するプロの意気込み(プロは角落ちで素人に負けることを恥とする)が何度も書かれているが、まさにそのとおりの結果に。いや、最後の1勝のために、9連敗があったのだ、とも言えます。適当ですが。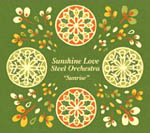 井の頭公園では、佐々木謙太朗という人が、スティールパンを演奏していて、ちょっと聴きいってしまいました。ソロで演奏していたのですが、スティールパン一台でこんなに音がきれいに響くんだ、と思うくらい、いい感じに公園内に響いていて良かったです。
井の頭公園では、佐々木謙太朗という人が、スティールパンを演奏していて、ちょっと聴きいってしまいました。ソロで演奏していたのですが、スティールパン一台でこんなに音がきれいに響くんだ、と思うくらい、いい感じに公園内に響いていて良かったです。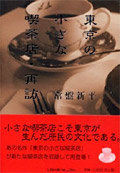 「東京の小さな喫茶店」を読んだのは、発売されてからかなり経った頃だったと思うのだけれど、休日、古本屋さんやレコード屋さんを回るときに持っていって、喫茶店でコーヒーを飲みながら、何回か読んだ記憶があります。多分、まだうちにあるのではないかと思う。でもどこにあるのかはわかりません(まぁクローゼットの奥かベッドの下の段ボールの中ですが‥‥。そこになければ実家か?すぐに取り出せないのならないと同じ?)。
「東京の小さな喫茶店」を読んだのは、発売されてからかなり経った頃だったと思うのだけれど、休日、古本屋さんやレコード屋さんを回るときに持っていって、喫茶店でコーヒーを飲みながら、何回か読んだ記憶があります。多分、まだうちにあるのではないかと思う。でもどこにあるのかはわかりません(まぁクローゼットの奥かベッドの下の段ボールの中ですが‥‥。そこになければ実家か?すぐに取り出せないのならないと同じ?)。 「世相講談」がおもしろかったので下巻を読むのはもったいなくなってしまい、後まわしにしていた将棋と競馬ものの本を読んでしまおうと、読み始めてみたのですが、いやこれもおもしろい。将棋については、普通に小学校の時とかに遊んだだけなので、定石とかまったく分からないし、採譜もまったく読めない、かつ棋士についても名前を聞いたことがある程度しか知らない。でもおもしろい。何がおもしろいのかといえば、勝負が始まる前の棋士の紹介、勝負中の心理描写、勝負が終わったあとのいいわけ?、つまり採譜以外すべておもしろいんですよ(といったら言い過ぎか)。
「世相講談」がおもしろかったので下巻を読むのはもったいなくなってしまい、後まわしにしていた将棋と競馬ものの本を読んでしまおうと、読み始めてみたのですが、いやこれもおもしろい。将棋については、普通に小学校の時とかに遊んだだけなので、定石とかまったく分からないし、採譜もまったく読めない、かつ棋士についても名前を聞いたことがある程度しか知らない。でもおもしろい。何がおもしろいのかといえば、勝負が始まる前の棋士の紹介、勝負中の心理描写、勝負が終わったあとのいいわけ?、つまり採譜以外すべておもしろいんですよ(といったら言い過ぎか)。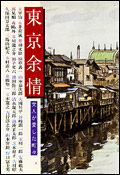 永井荷風から太宰治、芥川龍之介、久保田万太郎、野口富士男、そして安藤鶴夫や五木寛之、植草甚一まで、明治・大正・昭和を通して東京について書かかれた3編の小説、21編の随筆、1編の対談を収録したもの。東京について書かれた文章を集めたアンソロジーといえば、「東京百話」とか「大東京繁昌記」が有名ですが、これも1冊だけれど幅広く選ばれていてよくまとまっているのではないかと思います。いくつかは、個々の作家の作品の中で読んだことがあるものがあったりしましたけどね‥‥。それから、高見順の「如何なる星の下に」について言及している作品が何編かあって、当時、この作品がたらしたインパクトの大きさを改めて実感しました。
永井荷風から太宰治、芥川龍之介、久保田万太郎、野口富士男、そして安藤鶴夫や五木寛之、植草甚一まで、明治・大正・昭和を通して東京について書かかれた3編の小説、21編の随筆、1編の対談を収録したもの。東京について書かれた文章を集めたアンソロジーといえば、「東京百話」とか「大東京繁昌記」が有名ですが、これも1冊だけれど幅広く選ばれていてよくまとまっているのではないかと思います。いくつかは、個々の作家の作品の中で読んだことがあるものがあったりしましたけどね‥‥。それから、高見順の「如何なる星の下に」について言及している作品が何編かあって、当時、この作品がたらしたインパクトの大きさを改めて実感しました。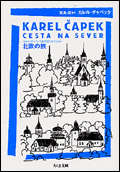 今日のおやつは、高崎に住むミオ犬の友だちからいただいた出産祝いに添えられていたガトーフェスタ・ハラダの「グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート」。片面にホワイトチョコレートがコーティングされているラスク。しっかりとコーティングされているのでかなり甘いのだけど、ちょっと濃いめにいれたコーヒーによく合います。
今日のおやつは、高崎に住むミオ犬の友だちからいただいた出産祝いに添えられていたガトーフェスタ・ハラダの「グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート」。片面にホワイトチョコレートがコーティングされているラスク。しっかりとコーティングされているのでかなり甘いのだけど、ちょっと濃いめにいれたコーヒーによく合います。 40年代から60年代にかけて出版されたアメリカの料理本やレシピ本を紹介した本。もちろんこんなコテコテの料理を自分で作って食べようとは思わないけれど、昔の荒い写真の雰囲気やイラストがかわいいのでときどき開いてはページをめくってみたりしてます。
40年代から60年代にかけて出版されたアメリカの料理本やレシピ本を紹介した本。もちろんこんなコテコテの料理を自分で作って食べようとは思わないけれど、昔の荒い写真の雰囲気やイラストがかわいいのでときどき開いてはページをめくってみたりしてます。