 ■経済界という会社から出ている「蘇る!」という雑誌に1995年から1998年にかけて連載されたもの。1回だけ経済界大賞の授賞式に行ったときの様子をとりあげてるけど、ほかは町田に引っ越す前によく行っていた平井や神保町、銀座、浅草などに行き、行きつけのお店でごはんを食べたり、喫茶店でコーヒーを飲んだりする様子がつづられています。なんで、経済の雑誌に3年にもわたって連載されたのか不思議。どんな人が読む雑誌なのでしょうか?雑誌を読む人たちにどのように受け入れられたんでしょうか?
■経済界という会社から出ている「蘇る!」という雑誌に1995年から1998年にかけて連載されたもの。1回だけ経済界大賞の授賞式に行ったときの様子をとりあげてるけど、ほかは町田に引っ越す前によく行っていた平井や神保町、銀座、浅草などに行き、行きつけのお店でごはんを食べたり、喫茶店でコーヒーを飲んだりする様子がつづられています。なんで、経済の雑誌に3年にもわたって連載されたのか不思議。どんな人が読む雑誌なのでしょうか?雑誌を読む人たちにどのように受け入れられたんでしょうか?
行く場所はたいてい同じで、連載中に同じお店が何回も出てきたりします。お店の紹介にフォーカスしたものではないけれど、同時期に出た「東京の小さな喫茶店」の食べもの屋さん編とも言えるかもしれません。
先日読んだ「私的読食録」で、角田光代が、「昔の男の人って『食べものについてまずい、旨いをいうな』と言われて育ったせいか、男性作家は何がおいしいとかあまり書いていない気がする」と言っていたけど、この本でも、お店で食べるものそのものよりも、お店の人との関係や、お店の成り立ち、一緒に食べている人との話などに重点が置かれている感じですね。
2000年以後の常盤新平の本は、過去のことの悔恨や歳を取ったことの嘆きなどが強く出ていて、10代の頃から読んでいるわたしとしては、複雑な気持ちになってしまうんですが、(それがまたよかったりする)ここでも歳を取った嘆きが随所でつづられているけど、来年見る桜に思いをはせたりして、ところどころに明るい部分があって救われるところがあって、ほっとします。この頃(1990年代半ば)の本を最近読んでないけど、2000年代の本を読んだ上で読み直したら、初めて読んだときと違った印象を受けるような気がします。
 ■土曜は、ギンザグラフィックギャラリーで開催されている「平野甲賀と晶文社展」へ。
■土曜は、ギンザグラフィックギャラリーで開催されている「平野甲賀と晶文社展」へ。
1階では自身の装丁と舞台やコンサートのチラシやポスターを手直しし、大きめの紙に刷り出した作品が、B1では、晶文社の装丁本が展示されているという構成でした。
普段、本などで見るものよりも大きいサイズで、4つの壁に90点もの作品が展示されているのを見ると、改めて平野甲賀の描く文字の力強さを感じてしまいます。文字の形や文字と文字とのレイアウトの構成など、普段、なんとなく平野甲賀の文字だなと、思いながら見ているだけでは気がつかない発見もあったりしました。もしもカヌー犬ブックスが店舗を持つことがあったら、お店のどこかに飾りたいと思う。(絶対にないと思うけど)
B1の書籍の展示のほうも、展示数が多く、また見たことのない本もあったり、シリーズでまとめられて展示されていたりして、楽しかった。読んでみたい本、手に入れたい本がたくさんあって、欲しくなってしまったり、また昔、持っていたけどもう手放してしまった本があると、懐かしい気分&やっぱり手放さなければよかったなどと思ったりしました。
せっかく銀座に出たのだから、事前にもう少しちゃんと調べて、ギャラリーめぐりをすればよかったと後悔してますが、当日は、高円寺の古書展から御茶ノ水→神保町で、本やレコードをたくさん買ってしまい、荷物が重くて仕方なかったので、じっくり散歩するという感じではなくなってしまったんですよね。
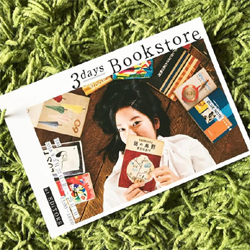 ■さて、3月23日から25日の3日間、手紙社の西調布にあるEDiTORSで開催される3days Bookstoreに参加します。参加する古本屋さんはMAIN TENTさん、古書まどそら堂さん、古書モダン・クラシックさん、古書玉椿さん、クラリスブックスさん、古書むしくい堂さんとカヌー犬ブックスの7店。よくある古本市のように7つの古書店がそれぞれ出店する、ということではなく、7つのお店が集まって、3日間限定の古書店をひらくというコンセプトで、キッチンや休憩広場(?)などもともとあるEDiTORSの設備を活かしながら、ちょっと変わった雰囲気の、でも本好きの人に楽しんでもらえるような古本屋にしたいと思っています。皆さま、ぜひ遊びに来てくださいね。
■さて、3月23日から25日の3日間、手紙社の西調布にあるEDiTORSで開催される3days Bookstoreに参加します。参加する古本屋さんはMAIN TENTさん、古書まどそら堂さん、古書モダン・クラシックさん、古書玉椿さん、クラリスブックスさん、古書むしくい堂さんとカヌー犬ブックスの7店。よくある古本市のように7つの古書店がそれぞれ出店する、ということではなく、7つのお店が集まって、3日間限定の古書店をひらくというコンセプトで、キッチンや休憩広場(?)などもともとあるEDiTORSの設備を活かしながら、ちょっと変わった雰囲気の、でも本好きの人に楽しんでもらえるような古本屋にしたいと思っています。皆さま、ぜひ遊びに来てくださいね。
【開催概要】
日程:2018年3月23日(金)~3月25日(日)
時間:11:00~18:00
入場料:無料
会場:EDiTORS(東京都調布市下石原 2-6-14 ラ・メゾン 2階)

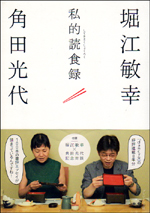 ■小説、絵本、詩集、料理本など、さまざまな本で登場する「食」について、角田光代と堀江敏幸が交互につづったエッセイ集。雑誌「dancyu」での連載をまとめたものになります。単行本にするにあたっての二人の対談も収録されてます。基本的に今手に入る本を紹介しているので、読みたい本をリストにして本屋さんで探してみるのにちょうどいいと思います。
■小説、絵本、詩集、料理本など、さまざまな本で登場する「食」について、角田光代と堀江敏幸が交互につづったエッセイ集。雑誌「dancyu」での連載をまとめたものになります。単行本にするにあたっての二人の対談も収録されてます。基本的に今手に入る本を紹介しているので、読みたい本をリストにして本屋さんで探してみるのにちょうどいいと思います。
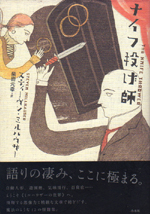 ■すこしずつ海外文学の本を読むのを増やしていこうと思っているけど、なかなか読めません。昔名に読んでたんだろ?で、ミルハウザー。ミルハウザーの本を読むのはほんとひさしぶり。「イン・ザ・ペニー・アーケード」や「バーナム博物館」など、この作家の作り出す世界が大好きでした。
■すこしずつ海外文学の本を読むのを増やしていこうと思っているけど、なかなか読めません。昔名に読んでたんだろ?で、ミルハウザー。ミルハウザーの本を読むのはほんとひさしぶり。「イン・ザ・ペニー・アーケード」や「バーナム博物館」など、この作家の作り出す世界が大好きでした。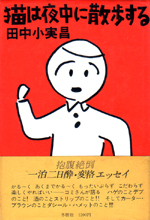 ■前回もちょっと書いたけれど、前半は、戦中に徴兵されたときのことから、戦後まだストリップという名称もない時代にストリップを始めたこと、その後、バーテンやテキヤなど職を変えたころのできごとなどがつづられており、後半は自身が翻訳した小説の解説を収録している。自身の体験については、ほかの本で読んだことのある内容が多いし、解説のほうは推理小説が多いので、小説自体は読んでないものばかりなのですが、語り口がいいのでついつい引き込まれてしまう。まぁ飲み屋で奥に座っている常連さんの話を聞いてるという感じでしょうか(単なるイメージです)。
■前回もちょっと書いたけれど、前半は、戦中に徴兵されたときのことから、戦後まだストリップという名称もない時代にストリップを始めたこと、その後、バーテンやテキヤなど職を変えたころのできごとなどがつづられており、後半は自身が翻訳した小説の解説を収録している。自身の体験については、ほかの本で読んだことのある内容が多いし、解説のほうは推理小説が多いので、小説自体は読んでないものばかりなのですが、語り口がいいのでついつい引き込まれてしまう。まぁ飲み屋で奥に座っている常連さんの話を聞いてるという感じでしょうか(単なるイメージです)。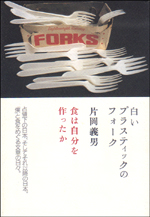 ■戦後の幼年期に、ハワイに住む祖父から送られてきた缶詰やお菓子の話から大学時代、そして現在までの食体験をつづったエッセイ集。キャンベルのスープ缶、びん入りのマヨネーズ、ハーシーズのチョコレート、スニッカーズ、ジェロ‥‥など、戦後の日本の状況やアメリカとの関係などと絡めた幼年期のエピソード中心になっている。片岡義男の場合、日本とアメリカが自分のルーツとして並列で存在していて、どちらがどうということがなく、両方をわりと客観的にとらえているところが読んでいておもしろい。
■戦後の幼年期に、ハワイに住む祖父から送られてきた缶詰やお菓子の話から大学時代、そして現在までの食体験をつづったエッセイ集。キャンベルのスープ缶、びん入りのマヨネーズ、ハーシーズのチョコレート、スニッカーズ、ジェロ‥‥など、戦後の日本の状況やアメリカとの関係などと絡めた幼年期のエピソード中心になっている。片岡義男の場合、日本とアメリカが自分のルーツとして並列で存在していて、どちらがどうということがなく、両方をわりと客観的にとらえているところが読んでいておもしろい。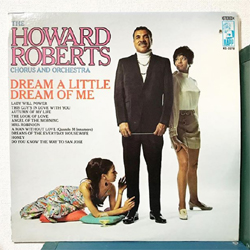 ■年末からコーラスものを中心にイージリスニングばかり聴いている。ジョニー・マン・シンガーズ、レイ・チャールズ・シンガーズ、アニタ・カー・シンガーズ、フラバルー・シンガーズといった○○シンガーズというグループだったり、○○シスターズ、○○ファミリーだったり、インスト中心のレコードでも、クレジットにコーラスが入っているものをチェックしてしまう。クリスマスの時期など、冬の夜に小さめの音で流しているといい感じなのですが、各グループで大きな個性があるわけではないので、聴き続けているとちょっと飽きてきて、ハイローズやシンガーズ・アンリミテッドなど、もっとうまいコーラスや、アーバーズのようなソフトロックに近いテイストのものに変えてみたりしている。
■年末からコーラスものを中心にイージリスニングばかり聴いている。ジョニー・マン・シンガーズ、レイ・チャールズ・シンガーズ、アニタ・カー・シンガーズ、フラバルー・シンガーズといった○○シンガーズというグループだったり、○○シスターズ、○○ファミリーだったり、インスト中心のレコードでも、クレジットにコーラスが入っているものをチェックしてしまう。クリスマスの時期など、冬の夜に小さめの音で流しているといい感じなのですが、各グループで大きな個性があるわけではないので、聴き続けているとちょっと飽きてきて、ハイローズやシンガーズ・アンリミテッドなど、もっとうまいコーラスや、アーバーズのようなソフトロックに近いテイストのものに変えてみたりしている。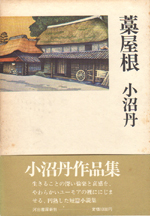 ■電車の中や一人でごはんを食べる時はできるだけ本を読むようにしている。特に電車の中はちょっと混んでるとついスマホを見てしまいがちなので、そこは流されないようにしつつ、隣の人を少し押してでもカバンから本を出す。
■電車の中や一人でごはんを食べる時はできるだけ本を読むようにしている。特に電車の中はちょっと混んでるとついスマホを見てしまいがちなので、そこは流されないようにしつつ、隣の人を少し押してでもカバンから本を出す。