 昨年、最後に読んだ本。年末ののんびりした時期に、東京の奥さんを置いて脚本を書くため国府津に滞在する売れない作家とそれほど美人というわけでもない芸者の駆け引きの話なんて読まなくても‥‥なんて思ったことを覚えてます。
昨年、最後に読んだ本。年末ののんびりした時期に、東京の奥さんを置いて脚本を書くため国府津に滞在する売れない作家とそれほど美人というわけでもない芸者の駆け引きの話なんて読まなくても‥‥なんて思ったことを覚えてます。
この作品は、三人称で書かれていますが、自身をモデルとした私小説に近い作品で、いわゆる5部作と呼ばれている「発展」「毒薬を飲む女」「放浪」「段橋」「憑き物」という連作の2作目となります。この後、岩野泡鳴は、文学を放棄し北海道に渡って蟹の缶詰工場を作るという事業を始めるのですが、事業が軌道に乗ることもなく、北海道でも色町には遊びに入り浸って、そこで芸者といい関係になったりしてと、どうしようもない話が続くんですけど、もし手にはいるようだったらほかの作品も読んでみたい。それにしても昔の作家は、ほんといろんな意味で“ろくでなし(ほめ言葉)”ばかりだったのだなぁと。
土曜日は、「マザーディクショナリー春の会」へ。今回の会場は、新宿御苑に隣接した「ラミュゼ de ケヤキ」という一軒家。もともとはピエール・バルーご夫妻の住居だったのを、現在は夫妻が中心となってレンタルスペースとして貸し出したり、コンサートを行ったりしているらしいです。マザーディクショナリーのイベントは前回の森のテラス(仙川)といい、会場のチョイスがとてもよくて、ワークショップに参加したり、コンサートを聴いたりしなくても、その場所に行って、アートマーケットを眺めたり、ご飯を食べたりするだけで楽しい。
マザーディクショナリーのイベントだけあって、子どもや赤ちゃんを連れたお母さんや夫婦が多いのだけれど、最近はうちの子も、同じくらいの赤ちゃんを見ると近づいてって、手や顔を触ったりするようになってきたので、こういうイベントがあると、家では見れない行動や仕草が見られたりするのもいいですね。

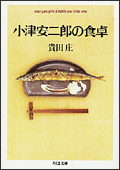 多分、何に対しても「質」より「量」をこなすってのが大切で、吉田健一も言っているように、おいしいものだけ少しずつ食べるのはありえず、おいしいものもまずいものも全部含めてたくさん食べないと、本当においしいものはわからない。そういう意味では、1回の食事の量が多くないわたしは、ほんとうにおいしいものを食べることはないのかもしれないんだろうなぁと思ったりします。いや、小津安二郎が大食漢だったなんて話はここにはほとんど出てこないんですけど‥‥。
多分、何に対しても「質」より「量」をこなすってのが大切で、吉田健一も言っているように、おいしいものだけ少しずつ食べるのはありえず、おいしいものもまずいものも全部含めてたくさん食べないと、本当においしいものはわからない。そういう意味では、1回の食事の量が多くないわたしは、ほんとうにおいしいものを食べることはないのかもしれないんだろうなぁと思ったりします。いや、小津安二郎が大食漢だったなんて話はここにはほとんど出てこないんですけど‥‥。 なんてことを前回書きつつ、結局パリ滞在記に逃げちゃったりしてますが‥‥
なんてことを前回書きつつ、結局パリ滞在記に逃げちゃったりしてますが‥‥ 革命によって故国を捨てたロシア人の娘であるマーシャという芸術家の人生を、彼女の日記や手紙、友人や母親たちのの証言、そして語り手である日本人の「私」から見た姿‥‥といったさまざまな断片を織りまぜることによって再構築した作品。
革命によって故国を捨てたロシア人の娘であるマーシャという芸術家の人生を、彼女の日記や手紙、友人や母親たちのの証言、そして語り手である日本人の「私」から見た姿‥‥といったさまざまな断片を織りまぜることによって再構築した作品。 冬になると花屋の店先に多肉植物が並べられるのは、寒い時期で華やかな花や植木が少なくなってしまうためなのだろうか。
冬になると花屋の店先に多肉植物が並べられるのは、寒い時期で華やかな花や植木が少なくなってしまうためなのだろうか。 志賀直哉の本は、恥ずかしながら中学生くらいのときに「小僧の神様」が収録された短編集しか読んだことがない。10代の頃、日本文学を読んでおけばよかったという気もしないでもないけれど、その頃、読んだとしても分かったかどうかは不明。まぁ分かろうが分からなかろうが、日本語を学ぶという意味でも読んでおくというのが大切なことなのかもしれません。昔の人が意味も分からず漢詩を素読いたみたいにね。ちょっと違うか?
志賀直哉の本は、恥ずかしながら中学生くらいのときに「小僧の神様」が収録された短編集しか読んだことがない。10代の頃、日本文学を読んでおけばよかったという気もしないでもないけれど、その頃、読んだとしても分かったかどうかは不明。まぁ分かろうが分からなかろうが、日本語を学ぶという意味でも読んでおくというのが大切なことなのかもしれません。昔の人が意味も分からず漢詩を素読いたみたいにね。ちょっと違うか?