 「長春五馬路」の前の話。先日リブロに行ったら「木山捷平全詩集」が再刊されていたので、この機会に手に入れておきたいと思う。
「長春五馬路」の前の話。先日リブロに行ったら「木山捷平全詩集」が再刊されていたので、この機会に手に入れておきたいと思う。
先日、会社のPCが新しくなったので、何かいい壁紙がないかと思っていろいろ探しているときに(今まではチチヤスのチー坊の壁紙でした~)、今年スマーフが生誕50年になるということを知りました。
ウィキペディアによると、ペヨが雑誌「ル・ジャーナル・ド・スピルー」で連載していた、漫画「Johan & Pirlouit(ジョアンとピルルイ)」のなかで、1958年10月23日にスマーフは初めて登場したらしい。そのわりにはスマーフ盛り上がってないのが、ちょっと寂しいです。
10年くらい前は、ちょっとした雑貨屋さんでもスマーフのフィギュアが売られてたし、何年か前に、セーラー出版からコミックが再刊されたときも、いろいろな本屋さんの絵本コーナーにスマーフのポスターが貼ってあって、本よりもポスターが欲しいと思ったりしたのにね。という私ももうほとんど、スマーフグッズは買ってません。フィギュアじゃないものが欲しいと思っているのだけれど、フィギュア以外で欲しいものは高いんですよね。その辺も含めて、50周年記念ということで、秋にかけてケアベアみたいに展覧会やったり、新しいグッズが出たりしないかなぁ~と思っているのだが。
今週のボサノヴァコーナー‥‥
[5]「オーリャ・ケン・シェーガ」-タニア・マリア-
う~ん、懐かしい。ただ懐かしいとしか浮かばない。15年くらい前、サバービアが流行っていた頃、ジョイスとかフローラ・プリムなどと一緒によく聴いてましたね~。この辺も自分では持っていなかったりするので、手に入れておきたいです。
[6]「Embalo」-テノーリオ・ジュニオル-
テノーリオ・ジュニオルのピアノを中心に、サックスやトロンボーンといったホーン、ドラム、パーカッション、ヴィオラォン‥‥など、ビッグバンド編成のジャズ・サンバ。どちらかというとジャズ寄りのサウンドなのだけれど、全体的に軽やか感じなので、デューク・エリントンやギル・エヴァンス、ミッシェル・ルグランといったレコードではなくて、プーチョ・アンド・ヒズ・ラテン・ソウル・ブラザーズとかと一緒に聴きたいかも。ファニアにような純粋なラテンともちょっと違うしね。テノーリオ・ジュニオルは、1970年半ばにアルゼンチンに向かったきり消息不明で、アルゼンチンの軍事政府に暗殺されたともいわれているらしい‥‥。

 先日書いたダニエラに置いてあった雑誌によると、双子座のラッキーメニューはそら豆らしい。そら豆の旬が、4~6月頃の初夏までで、店頭に出回る期間が短いのに比べて、枝豆の旬は、春から4、5カ月と長く、いつまでも食膳にあがる。しかも枝豆は、食べられもしない“さや”のまま出てきて、さやと薄皮2枚むかなくてはいけない‥‥というのが、「枝豆は生意気だ」というタイトルの由来。
先日書いたダニエラに置いてあった雑誌によると、双子座のラッキーメニューはそら豆らしい。そら豆の旬が、4~6月頃の初夏までで、店頭に出回る期間が短いのに比べて、枝豆の旬は、春から4、5カ月と長く、いつまでも食膳にあがる。しかも枝豆は、食べられもしない“さや”のまま出てきて、さやと薄皮2枚むかなくてはいけない‥‥というのが、「枝豆は生意気だ」というタイトルの由来。 GWに便乗して一日お休みをとろうと思いつつ結局とらなかったこともあって、19日に有休をとって3連休。人とずらしてお休みをとるとなんだか休んでばかりいるような気になりますね。といっても、下北をぶらついたり、吉祥寺を歩いたり、神保町に行ってみたり、特にどこかに行くということもないです。でも、平日に神保町を歩くというのはいいよ(私だけか?)。月曜はちょっと雨が降ったりしたけれど、久しぶりに週末いい天気が続いてよかった~
GWに便乗して一日お休みをとろうと思いつつ結局とらなかったこともあって、19日に有休をとって3連休。人とずらしてお休みをとるとなんだか休んでばかりいるような気になりますね。といっても、下北をぶらついたり、吉祥寺を歩いたり、神保町に行ってみたり、特にどこかに行くということもないです。でも、平日に神保町を歩くというのはいいよ(私だけか?)。月曜はちょっと雨が降ったりしたけれど、久しぶりに週末いい天気が続いてよかった~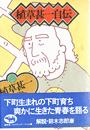 “自伝”というタイトルではあるけれど、もちろん順序立てて書かれたものではなく、少年時代のことや10代、20代のことが書かれたバラバラのエッセイをまとめたもの。なので、普通に本のことが主として書かれているのに、導入として昔の思い出話が書かれているだけものも収録されていたりします。まぁそれはそれなんですけどね。それにしても、植草甚一の文章ってこんなに脱線を繰り返していたのかな。
“自伝”というタイトルではあるけれど、もちろん順序立てて書かれたものではなく、少年時代のことや10代、20代のことが書かれたバラバラのエッセイをまとめたもの。なので、普通に本のことが主として書かれているのに、導入として昔の思い出話が書かれているだけものも収録されていたりします。まぁそれはそれなんですけどね。それにしても、植草甚一の文章ってこんなに脱線を繰り返していたのかな。 今週買ったボサノヴァCD‥‥
今週買ったボサノヴァCD‥‥ テレビの音楽番組を見ていると、“featuring‥‥”という曲がやたらと多くて、なんだかなぁと思う。私のまったくの偏見なのですが、共演と言うには、曲自体にお互いの個性とか持ち味が活かされているようにも思えないし、どうも“featuring”するほうも、される方も、その後ろにいろいろな打算とか計算が隠れているような気がしてしまいます。
テレビの音楽番組を見ていると、“featuring‥‥”という曲がやたらと多くて、なんだかなぁと思う。私のまったくの偏見なのですが、共演と言うには、曲自体にお互いの個性とか持ち味が活かされているようにも思えないし、どうも“featuring”するほうも、される方も、その後ろにいろいろな打算とか計算が隠れているような気がしてしまいます。