 「大東京繁盛記 山の手編」を読んだのは、今年の2月頃だったか?ほんとうは新書の大きさの平凡社ライブラリーを買ってパリに持っていこう、なんて思っていたのだけれど、ネットで調べてみたら「山の手編」の単行本だけ安く売っているのを発見して、ついを買ってしまったのだった。それから10カ月、ようやく両方そろったという感じです。それにしても年末のこの時期になってみると、パリに行ったのなんて、かなり昔のことのような‥‥。
「大東京繁盛記 山の手編」を読んだのは、今年の2月頃だったか?ほんとうは新書の大きさの平凡社ライブラリーを買ってパリに持っていこう、なんて思っていたのだけれど、ネットで調べてみたら「山の手編」の単行本だけ安く売っているのを発見して、ついを買ってしまったのだった。それから10カ月、ようやく両方そろったという感じです。それにしても年末のこの時期になってみると、パリに行ったのなんて、かなり昔のことのような‥‥。
今年の冬も、大正の終わりから昭和の初めに書かれた、東京についての本を読んでみようと思っているのですが、なかなか古本屋さんで見つけることができなくて、まだこの本しか手に入れてません。去年いろいろ調べてピックアップしたリストも、手帳がかわってしまったせいで、あんまりチェックしてないので、忘れてしまっている書名もかなりありますね。とりあえず、休みになったら吉祥寺のリブロに行って、ちくま文庫から出ている幸田文の「ふるさと隅田川」を買ってみようか、と思っているところ。そういえば「作家の娘」というテーマも、最近で言えば津島祐子くらいしか進んでない。
本当はその頃の地図を片手に、文章に出てくる地名を確認しながら読んだらおもしろいのだろうと思う。20代の頃は、よく銀座の本屋さんの前で売っている古地図に群がっている人たちを見て、そんな地図のどこがおもしろいのだろう、と思っていたものだったけれど、だんだんとそういう方面に興味がわいてくる自分がいて、歳を取ったのだなぁ、と感じたりしますね。もっとも時代劇や時代小説には、いまだにまったく興味はないので、江戸時代の地図にはまだ用はないわけですが。
12月は珍しく2本も映画を観ました。「麦の穂をゆらす風」と「イカとクジラ」。ケン・ローチの映画は、たいていは銀座のシネ・ラ・セットで2週間くらいくらいしかかかっていなくて、気がついたら終わっている、ということになりがちなので、ここは絶対に観に行かなくては、と思っていたら、渋谷でもやっていたりして、しかも私が観たときは満席。カンヌのパルムドールを受賞したことをあとで知ったりして、ファンとしてはかなりまぬけ。でも、もともとケン・ローチの「大地と自由」とか歴史物って個人的にあんまり興味がひかれなかったりします。「ケス」は別格としても、「リフ・ラフ」や「レイニング・ストーンズ」「マイ・ネーム・イズ・ジョー」のようにイギリスの労働者階級、普通の人たちを主人公にした映画がやはり好きだな。ところで、「麦の穂をゆらす風」は、1920年代のアイルランドを舞台に、独立戦争から内戦にいたる課程が2人の兄弟をとおして描かれた映画。上映が始まってすぐに、なんとなく終わりはこんな風になるんだろうなぁ、と予想できるのですが、やっぱりその
とおりで、いつもにもまして救いのないエンディングで、席を立つ腰が重くなってしまいました。もう1作上映されていた、アッバス・キアロスタミ、エルマンノ・オルミとのオムニバス映画、「明日へのチケット」は見損ねました。
「イカとクジラ」は、「ザ・ロイヤル・テネンバウムズ」「ライフ・アクアティック」のウェス・アンダーソン監督が製作をつとめた作品。両親の離婚によって混乱する子どもたちを描いているのだけれど、雰囲気的に「サム・サッカー」に似ているような気がしました(「サム・サッカー」の両親は離婚しないけどね)。
あと、父親がポスト・モダン的な小説を書く元売れっ子作家という設定の割には、話の中にカフカ、フィッツジェラルドとかしか作家の名前が出ないのは納得がいかない。少なくともピンチョンとかバーセルミ、自分と同時代の作家を認めたくないのなら、シャーウッド・アンダーソンとかフラナリー・オコナー、ハックスリー‥‥う~ん、あと思い出せないけど、そういうのが出てきてもいいのではないか。字幕で訳してないだけ?

 クリスマスプレゼント。
クリスマスプレゼント。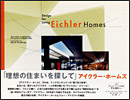 モダンな外観と構造をもつ家族向け住宅を大量生産して、戦後のアメリカを一世風靡したアイクラー・ホームのモデルを100点以上収録した写真集。奥付を見るとこの日本語版が出たのは1999年だから、もう7年も経ってるんですね。この頃はまだ「Casa BRUTUS」とか買ってましたねぇ。いまさら買ってどうするの?という気持ちがないわけではないし、そもそもミッドセンチュリーの家具って、日本の賃貸住宅で暮らしているあいだは、場所をとりすぎるし、まわりとの調和も乱すし、実際には使えないものだと思っていて、そう思ったらなんだか興味が薄れてしまったのだけれど、やっぱりこういう写真を見ているのは楽しい。
モダンな外観と構造をもつ家族向け住宅を大量生産して、戦後のアメリカを一世風靡したアイクラー・ホームのモデルを100点以上収録した写真集。奥付を見るとこの日本語版が出たのは1999年だから、もう7年も経ってるんですね。この頃はまだ「Casa BRUTUS」とか買ってましたねぇ。いまさら買ってどうするの?という気持ちがないわけではないし、そもそもミッドセンチュリーの家具って、日本の賃貸住宅で暮らしているあいだは、場所をとりすぎるし、まわりとの調和も乱すし、実際には使えないものだと思っていて、そう思ったらなんだか興味が薄れてしまったのだけれど、やっぱりこういう写真を見ているのは楽しい。 12月も半ばを過ぎて、今年ももうおしまい、という時期ですね。忘年会やらなんやらで飲みに行く機会が多かったりもするし、年末年始のお休みがひかえていたりするし、12月は短いなぁ、なんてつい思ったりもするけれど、よく考えたら、うちの会社のお休みは29日からなので、23日が土曜ということを考えると、12月のお休みは29日、一日しかなくて普通の月とぜんぜん変わりがない。いや11月よりも働いている日数は長い。う~ん。そういえば、秋の暖かい日に、中央線を八王子から下る古本屋ツアーとか早稲田の古本屋巡りをしようと思っていたのだけれど、秋どころか、今年中はもう無理そう。
12月も半ばを過ぎて、今年ももうおしまい、という時期ですね。忘年会やらなんやらで飲みに行く機会が多かったりもするし、年末年始のお休みがひかえていたりするし、12月は短いなぁ、なんてつい思ったりもするけれど、よく考えたら、うちの会社のお休みは29日からなので、23日が土曜ということを考えると、12月のお休みは29日、一日しかなくて普通の月とぜんぜん変わりがない。いや11月よりも働いている日数は長い。う~ん。そういえば、秋の暖かい日に、中央線を八王子から下る古本屋ツアーとか早稲田の古本屋巡りをしようと思っていたのだけれど、秋どころか、今年中はもう無理そう。 Heavenに遊びに行くのは何年ぶりか、2or3年ぶりくらいか。前回行ったときが思い出せないくらいなのだけれど、レギュラー最後と聴けば行くしかない。昼間ずっと降り続いていた雨も夜になってやんできたし、今日はたくさん人が来てるんだろうなぁ、なんて、年甲斐もなくちょっとわくわくしながら、毛糸の帽子に手袋をして寒さ対策ばっちりのかっこうで井の頭通りを自転車走らせて、久しぶりにDropの扉を開けたらメガネが曇って周りがまったく見えなくなってしまった。暑い‥‥店内に入ったときのことをまったく考えておらず‥‥。
Heavenに遊びに行くのは何年ぶりか、2or3年ぶりくらいか。前回行ったときが思い出せないくらいなのだけれど、レギュラー最後と聴けば行くしかない。昼間ずっと降り続いていた雨も夜になってやんできたし、今日はたくさん人が来てるんだろうなぁ、なんて、年甲斐もなくちょっとわくわくしながら、毛糸の帽子に手袋をして寒さ対策ばっちりのかっこうで井の頭通りを自転車走らせて、久しぶりにDropの扉を開けたらメガネが曇って周りがまったく見えなくなってしまった。暑い‥‥店内に入ったときのことをまったく考えておらず‥‥。 だんだん寒くなってきて、布団から出るのも、外に出るのも億劫になってきて、そんなことを思いつつ、一日を過ごしていると、まだなんにもしていないのにもう外は暗くなり始めて‥‥なんて季節になってしまってます。冬は空気がきれいなので、写真を撮るには絶好の季節と言うけれど、すぐに暗くなってしまうのでなんとなくカメラを持って出歩く気にもなれなくて、北海道に行ったときに取ったフィルムの残りがカメラに入ったまま、1カ月が過ぎてしまってます。実を言うと、北海道で撮った写真も現像が楽しみという感じでもなかったりして、昔だったらシャッターを押したときに「これはよく撮れただろう」という感触があったのものだけれど、そういうのが最近はまったくない。むしろ“なんか失敗したな”という気分ばかりが残ってしまってる感じです。困ったものだなぁ。
だんだん寒くなってきて、布団から出るのも、外に出るのも億劫になってきて、そんなことを思いつつ、一日を過ごしていると、まだなんにもしていないのにもう外は暗くなり始めて‥‥なんて季節になってしまってます。冬は空気がきれいなので、写真を撮るには絶好の季節と言うけれど、すぐに暗くなってしまうのでなんとなくカメラを持って出歩く気にもなれなくて、北海道に行ったときに取ったフィルムの残りがカメラに入ったまま、1カ月が過ぎてしまってます。実を言うと、北海道で撮った写真も現像が楽しみという感じでもなかったりして、昔だったらシャッターを押したときに「これはよく撮れただろう」という感触があったのものだけれど、そういうのが最近はまったくない。むしろ“なんか失敗したな”という気分ばかりが残ってしまってる感じです。困ったものだなぁ。 「あまカラ(抄)」第2巻は学者・評論家篇。私が知っている名前をピックアップすると、池田弥太郎や池島信平、福田恆存、小泉信三、小林秀雄、串田孫一、奥野信太郎、高橋義孝‥‥といったところか。前に読んだ「巻頭随筆」の時も思ったけれど、学者による随筆は名前をぜんぜん知らなくても面白い。まぁ知識があるということもあるし、海外に行く人があまりいなかった時代に、研究などの目的でわりと普通に海外に行っていたりしているということもある、かもしれません。といっても、やはり食べ物のこととなると、ほとんどの人が日本の食べ物のことを書いているんですけどね。
「あまカラ(抄)」第2巻は学者・評論家篇。私が知っている名前をピックアップすると、池田弥太郎や池島信平、福田恆存、小泉信三、小林秀雄、串田孫一、奥野信太郎、高橋義孝‥‥といったところか。前に読んだ「巻頭随筆」の時も思ったけれど、学者による随筆は名前をぜんぜん知らなくても面白い。まぁ知識があるということもあるし、海外に行く人があまりいなかった時代に、研究などの目的でわりと普通に海外に行っていたりしているということもある、かもしれません。といっても、やはり食べ物のこととなると、ほとんどの人が日本の食べ物のことを書いているんですけどね。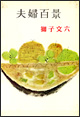 いろいろな夫婦の形をレポートするという内容で、前半は獅子文六自身の夫婦論に始まり知り合いの夫婦について、後半では雑誌の読者から寄せられたちょっと変わった夫婦について、それぞれ「婦人倶楽部」「主婦の友」に連載されたもの。
いろいろな夫婦の形をレポートするという内容で、前半は獅子文六自身の夫婦論に始まり知り合いの夫婦について、後半では雑誌の読者から寄せられたちょっと変わった夫婦について、それぞれ「婦人倶楽部」「主婦の友」に連載されたもの。 個人的には銀座というと、映画を観に行くということが多かったので、映画を観なくなった最近は、年に数回行くか行かないかという感じになってしまってます。この秋山安三郎とか安藤鶴夫、池田弥三郎といった人たちの本を読んでいると、銀座を歩いているだけで楽しかった、といったことが書いてあって、そういう文章を読むのは好きなほうなので、ときどき、東銀座の方まで裏道を歩いてみたらそういう風景がまだ少しは残っているかもしれない、などと思ったりもするけれど、やはりそれは銀座に夜店が出ていたり、資生堂パーラーや千疋屋、風月堂といったお店がハイカラだった時代の話で、少なくとも私には、今の銀座は歩いているだけで楽しいという感じの街ではないですね。かといって、じゃ、歩いているだけで楽しい街ってどこ?と聞かれると困りますけど‥‥。
個人的には銀座というと、映画を観に行くということが多かったので、映画を観なくなった最近は、年に数回行くか行かないかという感じになってしまってます。この秋山安三郎とか安藤鶴夫、池田弥三郎といった人たちの本を読んでいると、銀座を歩いているだけで楽しかった、といったことが書いてあって、そういう文章を読むのは好きなほうなので、ときどき、東銀座の方まで裏道を歩いてみたらそういう風景がまだ少しは残っているかもしれない、などと思ったりもするけれど、やはりそれは銀座に夜店が出ていたり、資生堂パーラーや千疋屋、風月堂といったお店がハイカラだった時代の話で、少なくとも私には、今の銀座は歩いているだけで楽しいという感じの街ではないですね。かといって、じゃ、歩いているだけで楽しい街ってどこ?と聞かれると困りますけど‥‥。 11月から倉庫として駅前のトランクルームを借りたので、毎日、会社から帰ると段ボールに本を詰めて少しずつ運んでいたのですが、週末にラストスパートで4往復してようやく引越完了しました。いままで本を置いていたキッチンの片隅がすっきりして気分がいい。もともとカヌー犬ブックス用の部屋があるわけでもなく、キッチンの隅にカラーボックスを2つ置いてそこに本を詰め込んでいただけだったので、半年くらい前からいろいろ迷っていたのです。一時期は、どうせなら、と引越まで考えたりしたんですよ‥‥。駅前のトランクルームは、古いビルの一画なのでいきなり閉鎖されてしまうのではないかとちょっと不安ですが、まぁとりあえずよかった、という感じ。といっても、そんなに在庫を抱えているわけでもなくて、現在でも850冊くらいだったりするんですけどね。いや実を言うとはじめは100冊くらいだったのです。いくら趣味といえども、いま考えるとかなりひどい。普通1000冊くらいは在庫を作ってからサイトを始めますよね。ここ半年はほとんど在庫が増えていない状態でしたが、これからは少し増やせるようにがんばります。年末だし買取強化キャンペーンでもやろうかしらん。
11月から倉庫として駅前のトランクルームを借りたので、毎日、会社から帰ると段ボールに本を詰めて少しずつ運んでいたのですが、週末にラストスパートで4往復してようやく引越完了しました。いままで本を置いていたキッチンの片隅がすっきりして気分がいい。もともとカヌー犬ブックス用の部屋があるわけでもなく、キッチンの隅にカラーボックスを2つ置いてそこに本を詰め込んでいただけだったので、半年くらい前からいろいろ迷っていたのです。一時期は、どうせなら、と引越まで考えたりしたんですよ‥‥。駅前のトランクルームは、古いビルの一画なのでいきなり閉鎖されてしまうのではないかとちょっと不安ですが、まぁとりあえずよかった、という感じ。といっても、そんなに在庫を抱えているわけでもなくて、現在でも850冊くらいだったりするんですけどね。いや実を言うとはじめは100冊くらいだったのです。いくら趣味といえども、いま考えるとかなりひどい。普通1000冊くらいは在庫を作ってからサイトを始めますよね。ここ半年はほとんど在庫が増えていない状態でしたが、これからは少し増やせるようにがんばります。年末だし買取強化キャンペーンでもやろうかしらん。