 革命によって故国を捨てたロシア人の娘であるマーシャという芸術家の人生を、彼女の日記や手紙、友人や母親たちのの証言、そして語り手である日本人の「私」から見た姿‥‥といったさまざまな断片を織りまぜることによって再構築した作品。
革命によって故国を捨てたロシア人の娘であるマーシャという芸術家の人生を、彼女の日記や手紙、友人や母親たちのの証言、そして語り手である日本人の「私」から見た姿‥‥といったさまざまな断片を織りまぜることによって再構築した作品。
辻邦生の本は、今までパリでの滞在記や、自身をモデルとしたと思われる短篇(かなりフィクションが入っていると思われる)しか読んでいなかったので、完全なフィクションの世界が構築されているこの作品は、よい意味で予想を裏切られた気持ちになってしまいながらも、読み進めるにつれて、その世界に引き込まれてしまいました。ここ数年、私小説を中心に本を読んでいたわたしとしては、ここまでフィクションの世界に引き込まれるのはかなりひさしぶりなので、逆に辻邦生のほかの作品を読むのが怖いくらい。次にどの作品を読むかというのが、かなり重要な気がします、なんて書いたら大げさですね。
昨日は訳あって会社を休んだのだけれど、その“訳”がなくなってしまったのでイケアに行って来ました。今年2回目。というか、前回買った本棚では本が収まりきらず、壁一面本棚、を改め、壁一面半本棚にすることにしたのでした。
平日のイケアは子ども連れでいっぱいで、週末に比べれば人は少ないのに、カート+ベビーカーで通路が埋まってしまう感じ。最近、どこに行っても赤ちゃんや小さな子どもがいる気がして、小さな子どもがいると行ける場所が限定されてくるし、時間や行動パターンも似かよってきちゃうんだろうなぁ、とつくづく思いますね。それはそれで仕方ないし、無理にそこと違うところに行こうとも思わないですけど、それはそれでいいのか、という疑問も少しはあったりして、なかなか難しい‥‥。まぁ選択肢はかなり限られてしまってるので、考えるまでもなかったりするんですけどね。
で、本棚のほうは、明日届く予定なので、3連休は再び組み立て&部屋の片づけで終わりそう、というか、なんかうちのなかが本棚だらけになりそうで怖いです。

 冬になると花屋の店先に多肉植物が並べられるのは、寒い時期で華やかな花や植木が少なくなってしまうためなのだろうか。
冬になると花屋の店先に多肉植物が並べられるのは、寒い時期で華やかな花や植木が少なくなってしまうためなのだろうか。 志賀直哉の本は、恥ずかしながら中学生くらいのときに「小僧の神様」が収録された短編集しか読んだことがない。10代の頃、日本文学を読んでおけばよかったという気もしないでもないけれど、その頃、読んだとしても分かったかどうかは不明。まぁ分かろうが分からなかろうが、日本語を学ぶという意味でも読んでおくというのが大切なことなのかもしれません。昔の人が意味も分からず漢詩を素読いたみたいにね。ちょっと違うか?
志賀直哉の本は、恥ずかしながら中学生くらいのときに「小僧の神様」が収録された短編集しか読んだことがない。10代の頃、日本文学を読んでおけばよかったという気もしないでもないけれど、その頃、読んだとしても分かったかどうかは不明。まぁ分かろうが分からなかろうが、日本語を学ぶという意味でも読んでおくというのが大切なことなのかもしれません。昔の人が意味も分からず漢詩を素読いたみたいにね。ちょっと違うか? 先日は、国立のニチニチ日曜市に行ってきたことを書きましたが、2月はその前に、武蔵小金井でやっている「はけのおいしい朝市」にも行ってたりします。
先日は、国立のニチニチ日曜市に行ってきたことを書きましたが、2月はその前に、武蔵小金井でやっている「はけのおいしい朝市」にも行ってたりします。 小沼丹の作品は、何年か前に出た全集を持っているのですが、本が大きくて持ち歩けないので、老後の楽しみとして取っておいている。でもそれはそれとして、文庫本が出るのはうれしい。
小沼丹の作品は、何年か前に出た全集を持っているのですが、本が大きくて持ち歩けないので、老後の楽しみとして取っておいている。でもそれはそれとして、文庫本が出るのはうれしい。 リビングに大きめのテーブルを買ったので何脚か椅子が欲しいなとずっと思っていて、いま、使っている椅子は、木のスクールチェアで、結婚した時に吉祥寺のジュビリーマーケットで買ったものなので、これと合うものがあるのではと、ジュビリーマーケットなどを見たりしていたのですが、いまいち手頃なものがなかったので、週末、思い切って福生まで行って来ました。一時期は毎年8月の終わりに行われる友好祭に行っていましたが、ここ2年くらい行けなかったので、福生に行くのは久しぶり、かつ友好際の時以外で福生に行くのは初めてなのでちょっとワクワク。
リビングに大きめのテーブルを買ったので何脚か椅子が欲しいなとずっと思っていて、いま、使っている椅子は、木のスクールチェアで、結婚した時に吉祥寺のジュビリーマーケットで買ったものなので、これと合うものがあるのではと、ジュビリーマーケットなどを見たりしていたのですが、いまいち手頃なものがなかったので、週末、思い切って福生まで行って来ました。一時期は毎年8月の終わりに行われる友好祭に行っていましたが、ここ2年くらい行けなかったので、福生に行くのは久しぶり、かつ友好際の時以外で福生に行くのは初めてなのでちょっとワクワク。 この本を読んでいたのは11月ですね。ちょうど引っ越してから少し経ったくらいの頃で、これから読もうと思っていた本はまだ段ボールに入れっぱなし、仕事も割と忙しくて古本屋にも行けず‥‥というわけで、カヌー犬ブックスの本の山から取り出して読んだんですよね。
この本を読んでいたのは11月ですね。ちょうど引っ越してから少し経ったくらいの頃で、これから読もうと思っていた本はまだ段ボールに入れっぱなし、仕事も割と忙しくて古本屋にも行けず‥‥というわけで、カヌー犬ブックスの本の山から取り出して読んだんですよね。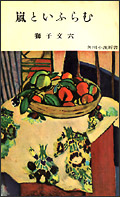 あけましておめでとうございます。今年もカヌー犬ブックスをよろしくお願いいたします。
あけましておめでとうございます。今年もカヌー犬ブックスをよろしくお願いいたします。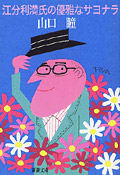 まだ何冊か残っているけど、とりあえず山口瞳の文庫本もひと区切りにしようと思って、最後に読もうと前々から買ってあったこの本を読んでみました。
まだ何冊か残っているけど、とりあえず山口瞳の文庫本もひと区切りにしようと思って、最後に読もうと前々から買ってあったこの本を読んでみました。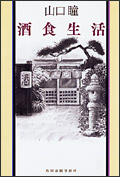 買うときに所収一覧を見たら、「酒飲みの自己弁護」や「江分利満氏大いに怒る」「木槿の花」「迷惑旅行」「行きつけの店」‥‥など、読んだことのある文庫本からの再録が多かったので、買うかどうか迷いつつも、とりあえず読んでみることに。
買うときに所収一覧を見たら、「酒飲みの自己弁護」や「江分利満氏大いに怒る」「木槿の花」「迷惑旅行」「行きつけの店」‥‥など、読んだことのある文庫本からの再録が多かったので、買うかどうか迷いつつも、とりあえず読んでみることに。