 ◆賑やかな週末@レットエムイン
◆賑やかな週末@レットエムイン
鈴木信太郎といえば、個人的には西荻にあるこけし屋や長崎のお菓子クルスがすぐに思い浮かびます。このほかに学芸大前にある洋菓子店のマッターホーンや神田志乃多寿司といったお店でも鈴木信太郎の絵をモチーフにした包装紙などが使われていたり、井伏鮮二や丹羽文雄、尾崎士郎といった作家の本の装丁なども手掛けており、こちらも気になっているところ。
なのですが、この本の著者の鈴木信太郎は、その洋画家の鈴木信太郎とは別の人でフランス文学者。しかもこの二人同い歳ということで、かなり紛らわしい。そのおかげでこのフランス文学者のほうの鈴木信太郎を知ることができたので、それはそれでよかったんですけどね。
墓本的には、生涯、大学教授として東大仏文科を活性化に努めた人なので、翻訳を除くとそれほど多くの著作はないようですが、断片的に描かれるパリ留学時の話ゃ岸田国士、辰野隆といった友人たちの話など、もっと読んでみたい。中でもびっくりしたのは、森茉莉の元夫だった山田珠樹と親友だったということ。山田珠樹については今まで森茉莉の視点からしか描かれているのを読んでなかったので新鮮でした。逆に森茉莉の随筆には、辰野隆が出てきたりするのだけれど、わたしが読み飛ばしただけで、鈴木信太郎も出てきてたのだろうか?出てきたとしたらどんな風に描かれてるのが気になります。(辰野隆もあんまりよく書かれてなかったし、鈴木信太郎もよく書かれていることはないんでしょうけど‥‥)
こうやっていろいろな人の“点”がつながって“線”になっていくのが、交友緑のおもしろさの一つですよね。
TAIYODOがレットエムインで出店しているということで国立へ。
レットエムインのある国立市北区商店会は初めて来たときは、駅から遠いなぁと思いながら、暑い中ベビーカーを押して行った記憶がありますが、それからワイワイ祭など何回か来ているうちにそれほど遠いという気もしなくなりました。ほとんどがTAIYODOが参加していたり教えてもらったりしたイベン卜がらみなんですけどね。
TAIYODOのかんちゃん(サイ卜に名前が出てなかったので愛称で書かせていただきます)は、昔、ミオ犬が吉洋寺のバウスシアターでバイ卜していたときに、一緒にバイトしていた人なのですが、武蔵小金井に引っ越してきてニチニチ日曜市によく行くようになってから、国立の情報をいろいろ教えてもらったり、イベントに誘ってもらったり、イベントを通じて新しい友だちができたりと、かんちゃんがいなかったらかなり味気ない生活になってしまっていたのではないか、と思うくらいなのです。
レットエムインの帰りは籠太でビュッフェランチ。籠太は、会津の郷土料理を中心とした居酒屋なんですが、昼間はビュッフェになっていて、しかもキッズスペースがあったりと子ども連れでも入りやすい。並べられている料理は、煮物が中心なのですが、サラダやポテトグラタンなど子どもでも食べやすいものが多いし、ケーキや和菓子などのデザートなどもいろいろあります。唯ーないのがお酒、ですかね。これでビールが飲めたら最高なんですけどね。って、じゃ夜に行きなよ、と。
ここは20年以上国立に住んでいる友だちに教えてもらいました。この友だちも昔、一緒にイベントをやったり、フリペを作ったりしてた人。そのあともずっとお互いのイベン卜に行ったり一緒に飲みに行ったりしてましたが、引っ越してきて、月に一度レコ―ドを回している福助という飲み屋に遊びに行くようになったり、ニチニチ日曜市に一緒に行ったりと、またよく会うようになりました。
ほんと近所の友だちに感謝です。

TAIYODOのスコーン

 ◆森茉莉と吉田健一が似ている点
◆森茉莉と吉田健一が似ている点
 ◆西荻は遠くになりにけり
◆西荻は遠くになりにけり
 ◆2月によく聴いたCD
◆2月によく聴いたCD ■「Singing Circuit」-Shi-Shonen-
■「Singing Circuit」-Shi-Shonen-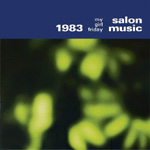 ■「マイ・ガール・フライデー」-サロン・ミュージック-
■「マイ・ガール・フライデー」-サロン・ミュージック-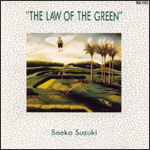 ■「緑の法則」-鈴木さえ子-
■「緑の法則」-鈴木さえ子- ■「SF」-鈴木慶一-
■「SF」-鈴木慶一-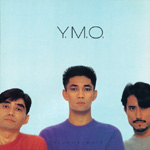 ■「浮気なぼくら」「サーヴィス」-YMO-
■「浮気なぼくら」「サーヴィス」-YMO-