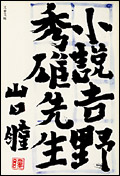 かなり以前に買っていて、いつか読もうと思っていた本。中身を見ていなかったので、タイトルと表紙から勝手に、1冊全部が吉野秀雄について書かれたものだと思い込んでいたのです。さすがに吉野秀雄で1冊は敷居が高い‥‥。
かなり以前に買っていて、いつか読もうと思っていた本。中身を見ていなかったので、タイトルと表紙から勝手に、1冊全部が吉野秀雄について書かれたものだと思い込んでいたのです。さすがに吉野秀雄で1冊は敷居が高い‥‥。
ところが実際ページをめくって目次を見たら、吉野秀雄は、半分くらいしかなくて、川端康成や山本周五郎、高見順、木山捷平、内田百けんと、いろいろな人について書かれていることがわかり、もっと早く読んでおけばよかった、とちょっと後悔。しかも解説は野呂邦暢。
先日(?)山口瞳は、思い入れがある人について書いたとき、ほんとうにいい文章を書くって書いたけれど、ここでもまさに当てはまってます。ただし、後半は文章の量が少なくて、表面的な記述でのみ、踏み込んだところがなく終わっていて、少し物足りないものもありますが‥‥。
さて、シリーズ「今年の夏によく聞いたウエストコーストジャズ」。第一回目は、ホーン・セクションのアレンジが心地よい4枚ということで‥‥
「The West Coast Sound」-Shelly Manne & His Men-
チェット・ベイカーやアート・ペッパーをウエストコースト・ジャスの4番打者、5番打者とするならば、シェリー・マンは、7番打者、守りの要、キャッチャーというところか。しかもドラムなのに編曲までする頭脳派。実際に誰に当てはまるのか普段まったく野球を見ないので分かりませんが‥‥。その4番打者アート・ペッパーをはじめ、バド・シャンク、ボブ・クーパー、ビル・ホルマン、マーティ・ペイチなど、ウエストコースト代表するプレイヤーによる勢いのあるカラっとした演奏が、いかにもウエストコーストという感じがしますね。
「Bud Shank-Shorty Rogers-Bill Perkins」-Bud Shank-
邦題は「昼と夜のバド シャンク」。前半のショーティ・ロジャースとのセッションのジャケット写真が昼のハリウッド・ボウル、ビル・パーキンスとのセッションが夜のハリウッド・ボウルだからという理由でつけられたらしい。演奏的には、ビル・パーキンスとのどちらかというとなめらかというか、やわらかい演奏になっていますが、どちらも昼なんじゃないかな。同時に「夜!しかも熱帯夜!」みたいなオルガンジャズも聴いていたので、それと比べてしまうとねぇ。
「Vol.1: The Quintets」-Lennie Niehaus-
解説にもあるけれど「流線型」という言葉がぴったりのアレンジが心地よいです。上の2枚はまだ個々のプレーヤーのセッションということで、演奏が「個」の集まりという感じなのですが、これは個々のプレーヤーの演奏よりも、アレンジのよさを楽しむという感じですかね。ソロパートでさえも個性よりもアレンジの一部という‥‥。と思ったら、レニー・ニーハウスは、最近では、映画音楽の作曲家として活躍していて、クリント・イーストウッドの映画のほとんどを担当しているらしいです。
「Cool And Sparkling」-Paul Smith-
ポール・スミスがウエストコースト・ジャズなのか、と言われるとかなり微妙、というか違うと思うんですけど、このアルバムは今年かなり聴いたかも。ジャスのイージーリスニング境界線?逆にこのジャケットで、レコード会社がキャピタルという情報から想像したら、ジャズっぽいと感じでしまうのではないか、と思ったりしますが、どうなんでしょう。ラウンジテイストのピアノとゆったりとしたなめらかなホーンセクションがかぶさり合うのだけれど、適度なスイング感あるので甘過ぎになる一歩手前で踏みとどまってます。
 井伏鱒二の本を読むのは、今年初めてですね。特に作品をリストとかにして追っているわけではなくて、たまたま古本屋で見つけたら買う、という感じなので、ちょっと気を抜くとあいだがあいてしまいます。
井伏鱒二の本を読むのは、今年初めてですね。特に作品をリストとかにして追っているわけではなくて、たまたま古本屋で見つけたら買う、という感じなので、ちょっと気を抜くとあいだがあいてしまいます。
 山口瞳が続いてます。リストアップした文庫本で手に入れてないのが、「草競馬流浪記」「酒食生活」「諸君!これが礼儀作法だ」の3冊のみになっていて、ほかに最後に読もうと思ってとっておいた男性自身シリーズ最終巻、「江分利満氏の優雅なサヨナラ」だけになっているので、一気に読んでしまおう思ってるんですが、なぜか「草競馬流浪記」が見つからず。このあいだまでよく見かけていたような気がするんですが‥‥。
山口瞳が続いてます。リストアップした文庫本で手に入れてないのが、「草競馬流浪記」「酒食生活」「諸君!これが礼儀作法だ」の3冊のみになっていて、ほかに最後に読もうと思ってとっておいた男性自身シリーズ最終巻、「江分利満氏の優雅なサヨナラ」だけになっているので、一気に読んでしまおう思ってるんですが、なぜか「草競馬流浪記」が見つからず。このあいだまでよく見かけていたような気がするんですが‥‥。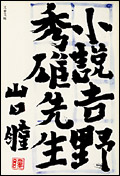 かなり以前に買っていて、いつか読もうと思っていた本。中身を見ていなかったので、タイトルと表紙から勝手に、1冊全部が吉野秀雄について書かれたものだと思い込んでいたのです。さすがに吉野秀雄で1冊は敷居が高い‥‥。
かなり以前に買っていて、いつか読もうと思っていた本。中身を見ていなかったので、タイトルと表紙から勝手に、1冊全部が吉野秀雄について書かれたものだと思い込んでいたのです。さすがに吉野秀雄で1冊は敷居が高い‥‥。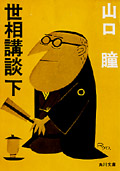 ツイッターによるとこの本を読み終えたのは8月7日らしい。どんだけ放置しているのやら。備忘録にもなってません。
ツイッターによるとこの本を読み終えたのは8月7日らしい。どんだけ放置しているのやら。備忘録にもなってません。