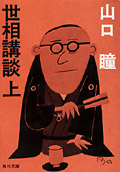 小説の題材として使える話がきけるのではないかと、どこか後ろめたい気持ちを引きずりつつ昔の知り合いや同級生のところに行き、会ってすぐに「小説の題材を探してるんだろう?」と言われてしまう。そんなことが延々と繰り返され、全体的に疲労感、悲壮感に覆われているような作品集。
小説の題材として使える話がきけるのではないかと、どこか後ろめたい気持ちを引きずりつつ昔の知り合いや同級生のところに行き、会ってすぐに「小説の題材を探してるんだろう?」と言われてしまう。そんなことが延々と繰り返され、全体的に疲労感、悲壮感に覆われているような作品集。
これをどう取ったらいいのだろうか?20代までのわたしだったら、そういうことは作品に出すべきではない、とか、わざとらしいポーズがうざいとか、かなり反感を持ったのではないかと思う。かといって、今のわたしが、それに同情したり共感することもなくて、ただ困ってしまうばかりという感じ。そもそも共感を求められているのかも分かりません。でもこの作品が「オール読物」に連載されたのは、昭和40年から昭和44年にかけてなので、山口瞳は1926年生まれということを考えると、連載が始まったときは39歳!ちょうど今のわたしの歳と同じなんですよね。あああ‥‥。山口瞳の才能があれば、そんなに自分を追い詰めなくても作品が書けるのではないかと、凡人のわたしは思ってしまうのですが‥‥。
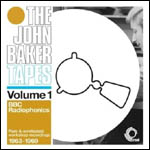 続けて書くこともないので、最近よく聴いている「John Baker Tapes Volume 1」を紹介。英国BBCの電子音楽制作部門である“BBC Radiophonic Workshop”で、1960年代から専属コンポーザーとして活躍したジョン・ベイカーが手がけた、テレビ、ラジオ番組用やCM用に制作したミュージック・コンクレート、電子音楽を収録したCD。身も蓋もない言い方としてしまうと、レイモンド・スコットの「Manhattan Research Inc」のイギリス版ですね。レイモンド・スコットより後なので、実験的な部分がそれほど強くなくて、ちょっとゲーム音楽的な曲もあったりしてかなりポップです。同じように日本の国営放送の電子音楽制作部門だったNHK電子音楽スタジオの作品は、どちらかというと実験音楽的な側面が多いイメージだけれど、こういう作品も残されているのでしょうか?
続けて書くこともないので、最近よく聴いている「John Baker Tapes Volume 1」を紹介。英国BBCの電子音楽制作部門である“BBC Radiophonic Workshop”で、1960年代から専属コンポーザーとして活躍したジョン・ベイカーが手がけた、テレビ、ラジオ番組用やCM用に制作したミュージック・コンクレート、電子音楽を収録したCD。身も蓋もない言い方としてしまうと、レイモンド・スコットの「Manhattan Research Inc」のイギリス版ですね。レイモンド・スコットより後なので、実験的な部分がそれほど強くなくて、ちょっとゲーム音楽的な曲もあったりしてかなりポップです。同じように日本の国営放送の電子音楽制作部門だったNHK電子音楽スタジオの作品は、どちらかというと実験音楽的な側面が多いイメージだけれど、こういう作品も残されているのでしょうか?
ちなみにこのCDが出ているTrunk UKは、こういう電子音楽やモンド、サイケなどの復刻をしているレベールらしいので、ちょっと注目してみようと思ってます。
といいつつも、このところ電子音楽ばかり聴いてきたので、暖かくなってきたことだし、もう少し爽やかで耳に優しい音楽を夏に向けて聴こうと思っている今日この頃だったりします。
今日のおやつは、たねやの「近江ひら餅 よもぎ餅」。ミオ犬の実家に和菓子を送ろうと思って、会社帰りに渋谷の東急のれん街を歩いていたら、自分でも和菓子が食べたくなってしまったのでした。最近なぜか和菓子をよく食べているような気がしますね。特に理由はないけど、なんか和菓子の“よもぎ”って好きなんですよねぇ~。
 40年代から60年代にかけて出版されたアメリカの料理本やレシピ本を紹介した本。もちろんこんなコテコテの料理を自分で作って食べようとは思わないけれど、昔の荒い写真の雰囲気やイラストがかわいいのでときどき開いてはページをめくってみたりしてます。
40年代から60年代にかけて出版されたアメリカの料理本やレシピ本を紹介した本。もちろんこんなコテコテの料理を自分で作って食べようとは思わないけれど、昔の荒い写真の雰囲気やイラストがかわいいのでときどき開いてはページをめくってみたりしてます。
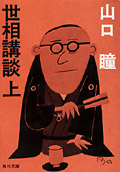 小説の題材として使える話がきけるのではないかと、どこか後ろめたい気持ちを引きずりつつ昔の知り合いや同級生のところに行き、会ってすぐに「小説の題材を探してるんだろう?」と言われてしまう。そんなことが延々と繰り返され、全体的に疲労感、悲壮感に覆われているような作品集。
小説の題材として使える話がきけるのではないかと、どこか後ろめたい気持ちを引きずりつつ昔の知り合いや同級生のところに行き、会ってすぐに「小説の題材を探してるんだろう?」と言われてしまう。そんなことが延々と繰り返され、全体的に疲労感、悲壮感に覆われているような作品集。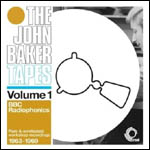 続けて書くこともないので、最近よく聴いている「John Baker Tapes Volume 1」を紹介。英国BBCの電子音楽制作部門である“BBC Radiophonic Workshop”で、1960年代から専属コンポーザーとして活躍したジョン・ベイカーが手がけた、テレビ、ラジオ番組用やCM用に制作したミュージック・コンクレート、電子音楽を収録したCD。身も蓋もない言い方としてしまうと、レイモンド・スコットの「Manhattan Research Inc」のイギリス版ですね。レイモンド・スコットより後なので、実験的な部分がそれほど強くなくて、ちょっとゲーム音楽的な曲もあったりしてかなりポップです。同じように日本の国営放送の電子音楽制作部門だったNHK電子音楽スタジオの作品は、どちらかというと実験音楽的な側面が多いイメージだけれど、こういう作品も残されているのでしょうか?
続けて書くこともないので、最近よく聴いている「John Baker Tapes Volume 1」を紹介。英国BBCの電子音楽制作部門である“BBC Radiophonic Workshop”で、1960年代から専属コンポーザーとして活躍したジョン・ベイカーが手がけた、テレビ、ラジオ番組用やCM用に制作したミュージック・コンクレート、電子音楽を収録したCD。身も蓋もない言い方としてしまうと、レイモンド・スコットの「Manhattan Research Inc」のイギリス版ですね。レイモンド・スコットより後なので、実験的な部分がそれほど強くなくて、ちょっとゲーム音楽的な曲もあったりしてかなりポップです。同じように日本の国営放送の電子音楽制作部門だったNHK電子音楽スタジオの作品は、どちらかというと実験音楽的な側面が多いイメージだけれど、こういう作品も残されているのでしょうか?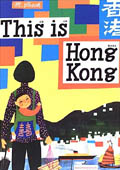 前回書いた「新緑古本大市」で買ったもの。英語版は持っているのだけれど、日本語版だったし、せっかくイベントに行って何も買わない(交換しない)のもなんだな、と思って購入。帯に「100万ドルの夜景~」って書いてありますが、最近、あんまり聞かないフレーズのような‥‥。今でもパッケージツアーのコピーなどに使われているのだろうか?
前回書いた「新緑古本大市」で買ったもの。英語版は持っているのだけれど、日本語版だったし、せっかくイベントに行って何も買わない(交換しない)のもなんだな、と思って購入。帯に「100万ドルの夜景~」って書いてありますが、最近、あんまり聞かないフレーズのような‥‥。今でもパッケージツアーのコピーなどに使われているのだろうか?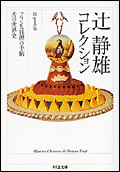 週末はバスに乗って阿佐ヶ谷住宅の一室でやっていた「新緑古本大市」に行って来ました。“古本市”と言っても、読まなくなった本を持っていくと“交換チケット”を換えてくれるので、そのチケットを使ってほかの人が持ってきた本を買う、というシステムなので、どちらかというと、古本“交換会”といったほうが近いかもしれません。本だけでなくオトノハのお弁当や瀬戸口しおりさんのクッキーなども売っていて、どちらかというとわたしは、そちらが目当てだったんですけどね‥‥。
週末はバスに乗って阿佐ヶ谷住宅の一室でやっていた「新緑古本大市」に行って来ました。“古本市”と言っても、読まなくなった本を持っていくと“交換チケット”を換えてくれるので、そのチケットを使ってほかの人が持ってきた本を買う、というシステムなので、どちらかというと、古本“交換会”といったほうが近いかもしれません。本だけでなくオトノハのお弁当や瀬戸口しおりさんのクッキーなども売っていて、どちらかというとわたしは、そちらが目当てだったんですけどね‥‥。 そんなわけで、今日のおやつは古本市で買った瀬戸口しおりさんのクッキー。瀬戸口しおりさんは、前にミオ犬が「私の手料理」という本を紹介していましたが、Kuu Kuuの元スタッフだった人です。
そんなわけで、今日のおやつは古本市で買った瀬戸口しおりさんのクッキー。瀬戸口しおりさんは、前にミオ犬が「私の手料理」という本を紹介していましたが、Kuu Kuuの元スタッフだった人です。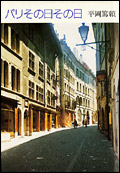 今日のおやつは、シェ・リュイのカヌレ。カヌレなんて食べるの何年ぶりでしょうか。お休み中に孫の顔を見に来たうちの親が買ってきてくれたもの。帰った後に箱を開けてみたらたくさん入っていたので、ここ3日間続けて、おやつにカヌレを食べてるのでした。帰りに妹のところに寄ると言ってたので、その場で開けて分ければよかったです。すまぬ。やっぱりおみやげものはもらったその場で開けるべきですねぇ~
今日のおやつは、シェ・リュイのカヌレ。カヌレなんて食べるの何年ぶりでしょうか。お休み中に孫の顔を見に来たうちの親が買ってきてくれたもの。帰った後に箱を開けてみたらたくさん入っていたので、ここ3日間続けて、おやつにカヌレを食べてるのでした。帰りに妹のところに寄ると言ってたので、その場で開けて分ければよかったです。すまぬ。やっぱりおみやげものはもらったその場で開けるべきですねぇ~ 今日のおやつは‥‥って、シリーズ化しようとしているわけでもないのですが、別にどこに行くというわけでもないので、何か食べた時くらいは書いておこうかなと。
今日のおやつは‥‥って、シリーズ化しようとしているわけでもないのですが、別にどこに行くというわけでもないので、何か食べた時くらいは書いておこうかなと。 上林暁の作品は、基本的には身辺雑記を中心にして、フィクションを交えてまとめたような作風なので、厳密には私小説とは言えないのかもしれないけれど、その分、作品としてカチッとまとまっていて、だらけるところがないので、読んでいても、一つ一つを一気に読んでしまいたくなります。尾崎一雄とか庄野潤三とか、身辺雑記を小説の題材にした作品を読んでいると、なんとなく途中で「もういいかな」と思ってしまう瞬間があるんですよね。単に私の集中力の問題かもしれないけれど‥‥。
上林暁の作品は、基本的には身辺雑記を中心にして、フィクションを交えてまとめたような作風なので、厳密には私小説とは言えないのかもしれないけれど、その分、作品としてカチッとまとまっていて、だらけるところがないので、読んでいても、一つ一つを一気に読んでしまいたくなります。尾崎一雄とか庄野潤三とか、身辺雑記を小説の題材にした作品を読んでいると、なんとなく途中で「もういいかな」と思ってしまう瞬間があるんですよね。単に私の集中力の問題かもしれないけれど‥‥。 「2009 spring / summer」は、ゆったりとしたリズムの中を軽やかにすり抜けるようなエレピや、決して熱く鳴り響かないホーンセクション、そして主張しないコーラス‥‥など、ある意味、まとまりすぎて没個性となりそうなギリギリのラインを狙っている感じがすごい。そして彼らの音楽を「おしゃれ」のひとことで片づけられてもぜんぜん気にしないくらいの潔さがいいと思う。
「2009 spring / summer」は、ゆったりとしたリズムの中を軽やかにすり抜けるようなエレピや、決して熱く鳴り響かないホーンセクション、そして主張しないコーラス‥‥など、ある意味、まとまりすぎて没個性となりそうなギリギリのラインを狙っている感じがすごい。そして彼らの音楽を「おしゃれ」のひとことで片づけられてもぜんぜん気にしないくらいの潔さがいいと思う。