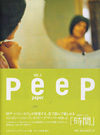 トリトンカフェは神戸にあるカフェで、2年くらい前に一度だけ行ったことがあります。開店と同時に入ったせいもあってお客さんもほとんどいなくて、比較的広い店内にアンティークっぽい木のテーブルと椅子がゆったりと置かれていて、居心地の良いカフェだったという記憶があります。
トリトンカフェは神戸にあるカフェで、2年くらい前に一度だけ行ったことがあります。開店と同時に入ったせいもあってお客さんもほとんどいなくて、比較的広い店内にアンティークっぽい木のテーブルと椅子がゆったりと置かれていて、居心地の良いカフェだったという記憶があります。
このときは京都に行ったついでに一日神戸まで足をのばしてみたのだけれど、カフェアンティークゴヤ(閉店してしまったみたいですね)やFabulous OLD BOOK・・・・などにも駆け足で回りましたね。すぐに名前は思いだせないけれど、また行きたいところがたくさんあります。
この「Peep Paper」はそのトリトンカフェなどの人たちが出している本で、毎回テーマを決めて、それに合った自分たちの好きなものを並べていったという感じの雑誌のようなムックのような(という言い方はあまり好きではないが)本。この号のテーマは「時間」。ちなみにVol.1は「旅」でした。Vol.3も最近2年ぶりに出たようですが、まだ私は本屋で見てません。というか、これが出てから2年も経ってしまってるんだ、という気持ち。Vol.1は発売されてすぐに中目黒のブックオフで見つけて手に入れたのですが、こちらに関してはなかなかそういう出会いもないし、出版元だったギャップ出版が破産申告をしたというニュースを聞いたりしていたのであきらめてたのです。
夏の前までに買おうと思っていたbonobosの「Hover Hover」をやっと手に入れた。夜、コンポのスイッチを入れると、ゆったりしていて心地よいリズムと暖かなメロディが流れ出してすぐにやっぱり夏前に買えば良かった、と思った。予定のない夏の休日にぴったりの音楽。そしてこれはあくまでもbonobos独自のグルーヴであり、bonobosの音楽だ。もうフィッシュマンズにどうのこうのというのはやめよう。
今年の夏の終わり、というか秋の日々のマイ・サウンドトラック・オブ・リヴィング。それにしてもまだ真夏日の日が続いている。いつになったら秋になるのだろうか。

 先日、中央線巡りをしたときにIIとIIIを手に入れたので、これで巻頭随筆も4冊そろったことになる。実際は6まで出ているのだが、5と6は1980年代も後半になってくるので今は読む気はなし。もしかしたら何年かして読みたくなるときがきて、そのときになったら全然手に入らなくなってしまう、なんてことになるかもしれない。でもそのときはそのときということで。先のことは分かりません。
先日、中央線巡りをしたときにIIとIIIを手に入れたので、これで巻頭随筆も4冊そろったことになる。実際は6まで出ているのだが、5と6は1980年代も後半になってくるので今は読む気はなし。もしかしたら何年かして読みたくなるときがきて、そのときになったら全然手に入らなくなってしまう、なんてことになるかもしれない。でもそのときはそのときということで。先のことは分かりません。 「Summer Store」はディモンシュに行くたびに買っていて最初の号から持っているし、夏のイベントにも初めのときから行っていたのだけれど、去年の夏の最後の時には行けなくてこの最終号も手に入れそびれてました。その後も鎌倉に行く機会がなかったので、1年以上ぶりに行ったディモンシュにまだこの本が残っているのを見て嬉しくなって即買いです。
「Summer Store」はディモンシュに行くたびに買っていて最初の号から持っているし、夏のイベントにも初めのときから行っていたのだけれど、去年の夏の最後の時には行けなくてこの最終号も手に入れそびれてました。その後も鎌倉に行く機会がなかったので、1年以上ぶりに行ったディモンシュにまだこの本が残っているのを見て嬉しくなって即買いです。 このギンザ・グラフィック・ギャラリーのシリーズも気がつけばもう10冊くらいになってます。気持ち的にはもう少し大きな判でページ数もあって3000円くらいだといいのにな、と思う。でもこういうデザイン関係の本で3000円くらいの本って以外となくて、たいてい1000~2000円くらいの小さな薄い形で(小冊子を含む)そのデザイナーの主な仕事をさらりとまとめたものか、5000円以上の詳しいもののどちらかな気がします。コスト的に3000円くらいのデザイン本って難しいのだろう。
このギンザ・グラフィック・ギャラリーのシリーズも気がつけばもう10冊くらいになってます。気持ち的にはもう少し大きな判でページ数もあって3000円くらいだといいのにな、と思う。でもこういうデザイン関係の本で3000円くらいの本って以外となくて、たいてい1000~2000円くらいの小さな薄い形で(小冊子を含む)そのデザイナーの主な仕事をさらりとまとめたものか、5000円以上の詳しいもののどちらかな気がします。コスト的に3000円くらいのデザイン本って難しいのだろう。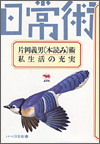 架空のインタビューで、どんなところで本を読むか、最近おすすめの本はなにか・・・・といった質問に片岡義男が答えるという形式で書かれているのだが、質問の内容があまりにも次の話題にうまく持っていくための導線になっているので、読んでいるとちょっと自己完結的な、白々しいような印象を受けてしまいます。前に読んだような気がするのは、この形式のせいなのか、それとも違う本に採録されているのを読んだのだろうか。調べてないのでわかりません。
架空のインタビューで、どんなところで本を読むか、最近おすすめの本はなにか・・・・といった質問に片岡義男が答えるという形式で書かれているのだが、質問の内容があまりにも次の話題にうまく持っていくための導線になっているので、読んでいるとちょっと自己完結的な、白々しいような印象を受けてしまいます。前に読んだような気がするのは、この形式のせいなのか、それとも違う本に採録されているのを読んだのだろうか。調べてないのでわかりません。 「礼儀作法入門」「居酒屋兆治」「血族」「家族」「人殺し」、そのほか競馬、将棋関連・・・・これらは、山口瞳の本で後回しにしようと思っているもので、前者はそのタイトルや映画のイメージが悪いのでちょっとさけているという感じで、後者はタイミングをみて(なんのタイミング?)ちゃんと気合い入れて読もうと思っているんだけれど、なかなか読むことができない状態。
「礼儀作法入門」「居酒屋兆治」「血族」「家族」「人殺し」、そのほか競馬、将棋関連・・・・これらは、山口瞳の本で後回しにしようと思っているもので、前者はそのタイトルや映画のイメージが悪いのでちょっとさけているという感じで、後者はタイミングをみて(なんのタイミング?)ちゃんと気合い入れて読もうと思っているんだけれど、なかなか読むことができない状態。 稲垣達郎は1901年福井県生まれの。大学時代には同人誌に参加したり演劇活動を行っていたが、後に母校の早稲田大学にて教職に就き森鴎外を軸に日本近代文学についての研究を主に行った人。「作家の肖像」「夏目漱石」「森鴎外の歴史小説」などの著作、「森鴎外」「斉藤緑雨集」「近代文学評論大系」などの編著があります。
稲垣達郎は1901年福井県生まれの。大学時代には同人誌に参加したり演劇活動を行っていたが、後に母校の早稲田大学にて教職に就き森鴎外を軸に日本近代文学についての研究を主に行った人。「作家の肖像」「夏目漱石」「森鴎外の歴史小説」などの著作、「森鴎外」「斉藤緑雨集」「近代文学評論大系」などの編著があります。 去年、発売されたときは「絶対に買わないぞ」と思っていた本。特集がいいといって雑誌やムック本を簡単に買っていると、いつのまにかそういう本がたまってしまって置き場に困ってしまうのが目に見えてるから。そうは思いつつも本屋で久しぶりに見かけたので、また立ち読みしていたら、山口瞳と木山捷平の対談が載っているではないですか。
去年、発売されたときは「絶対に買わないぞ」と思っていた本。特集がいいといって雑誌やムック本を簡単に買っていると、いつのまにかそういう本がたまってしまって置き場に困ってしまうのが目に見えてるから。そうは思いつつも本屋で久しぶりに見かけたので、また立ち読みしていたら、山口瞳と木山捷平の対談が載っているではないですか。 庄野潤三の本は好きだけれどどうも読んでいると個人的につらい気分になるので、読まないようにしているのだが、帯に永井龍男の推薦文が書かれていたのを見てつい買ってしまった。
庄野潤三の本は好きだけれどどうも読んでいると個人的につらい気分になるので、読まないようにしているのだが、帯に永井龍男の推薦文が書かれていたのを見てつい買ってしまった。 台風が近づいているせいで今週も週末は雨が降ったり止んだり、という天気。2日続けて近所から出ませんでした。
台風が近づいているせいで今週も週末は雨が降ったり止んだり、という天気。2日続けて近所から出ませんでした。