 まず昨日書き忘れたことから。以前、この日記で山口瞳と永井龍男の2二人に接点はなかったのだろうかということを書いた。2人は同時期に鎌倉に住んでいたようだし、お互いの文章を読んでいると川端康成など同じ人物と交流があったことが書いている。加えて山口瞳は戦後の鎌倉アカデミア出身だし、永井龍男も鎌倉アカデミアには関わっていた、といった理由からそういうことを思ったのだが、その日記を書いた後にそれを見た人からメールが来て、永井龍男の全集に添えられた冊子に山口瞳が寄稿していて、永井龍男と2度会ったことや怖い・厳しいイメージがあったといったことが書いてあるとのこと。
まず昨日書き忘れたことから。以前、この日記で山口瞳と永井龍男の2二人に接点はなかったのだろうかということを書いた。2人は同時期に鎌倉に住んでいたようだし、お互いの文章を読んでいると川端康成など同じ人物と交流があったことが書いている。加えて山口瞳は戦後の鎌倉アカデミア出身だし、永井龍男も鎌倉アカデミアには関わっていた、といった理由からそういうことを思ったのだが、その日記を書いた後にそれを見た人からメールが来て、永井龍男の全集に添えられた冊子に山口瞳が寄稿していて、永井龍男と2度会ったことや怖い・厳しいイメージがあったといったことが書いてあるとのこと。
どちらも仕事上だったようで、個人的なつながりはなかったようだけれど、山口瞳が永井龍男について書いていたというだけで、ちょっとワクワクしたりして、全集に添えられた冊子なんて、単行本などに収録されないだろうし、手に入れることはないだろうとあきらめていました。ところが「新装版 諸君!この人生、大変なんだ」に収録されていたのです。内容はほとんどメールで教えてもらっていたので驚くようなことは書いていないけれど、やっぱりうれしい。つい何度も読み返したりしてます。
さて、「ku:nel」。先週からタワーレコードでダブルポイントキャンペーンをやっているので、せっかくなのでわざわざ渋谷のタワレコまで行って、「ku:nel」とCDを入れるビニールのケースを買って、ついでにいろいろ試聴してみました。ここずっと打ち込みものに興味があるのだけれど、ブレイクビーツとかハウスとか、エレクトロニカとかなんだかぜんぜん分からず。かといって、雑誌など調べる気もないので、ジャケ買いや店員の説明書きを読んで買ってみても、どうも「これ!」というものに出会う確率が低いので、最近はこまめにタワレコとかHMVに行って試聴したり、中古で買うときも試聴できるお店でちゃんと調べてから買うようにしているのです。
そんなわけで2階をうろうろしながらCDを眺めつつ、目に入った「日本人初のニンジャチューンからのリリース」なんて言葉にひかれてRainstick Orchestraを聴いてみる。よく分からないけど、生楽器の響きとエレクトロニクス(コンピュータ)がうまく絡んだ静かで暖かい感じの音楽。「正直言うとこういう音楽っていいんだけど、部屋の掃除しながら聴くわけにもいかないしなんとなくいつ聴いていいのかわからないんだよなぁ」なんて思いながら帯の説明と読んでみたら、「角田縛と田中直道によるユニット」って。前の会社のマックルームにいた角田君じゃないですか!びっくりです。

 この本も山口瞳の中ではちょっと敬遠してました。それなのにちょっと読み始めたら止まらなくなってしまった。いちいちうなずきながら読んでしまうのは、多分、これまで山口瞳の本を読んできて、彼がどんな葛藤を抱えていたのか、どんな風に自分の仕事を行ってきたのか、どんなに自分の周りの人たちを大切にしてつきあってきたのか・・・・など断片的、表面的かもしれないけれど分かってきたからで、これをはじめの頃に読んでいたらこんなに素直に受け入れられなかったのではないかと思う。単に私が歳をとって少しでも「この人生、大変なんだ」と思えるようになってきただけかもしれないけど。確かにこれを20代はじめに読んでも全然実感わかなかっただろうしね。
この本も山口瞳の中ではちょっと敬遠してました。それなのにちょっと読み始めたら止まらなくなってしまった。いちいちうなずきながら読んでしまうのは、多分、これまで山口瞳の本を読んできて、彼がどんな葛藤を抱えていたのか、どんな風に自分の仕事を行ってきたのか、どんなに自分の周りの人たちを大切にしてつきあってきたのか・・・・など断片的、表面的かもしれないけれど分かってきたからで、これをはじめの頃に読んでいたらこんなに素直に受け入れられなかったのではないかと思う。単に私が歳をとって少しでも「この人生、大変なんだ」と思えるようになってきただけかもしれないけど。確かにこれを20代はじめに読んでも全然実感わかなかっただろうしね。 「無心状」については、ちょっと前に単行本で読んだのでここにも書きましたが、ここに収録されている作品とそれほど重なっているわけではない。解説を小沼丹が書いているというだけで私にとってはうれしい。積極的に探しているわけではなかったせいもあり、なかなか手に入れない「清水町先生」を早く読みたくなりました。
「無心状」については、ちょっと前に単行本で読んだのでここにも書きましたが、ここに収録されている作品とそれほど重なっているわけではない。解説を小沼丹が書いているというだけで私にとってはうれしい。積極的に探しているわけではなかったせいもあり、なかなか手に入れない「清水町先生」を早く読みたくなりました。 昭和32年末に上顎腫瘍が発見され癌と診断され、昭和35年には妻てい子が乳癌の手術を受けるという夫婦そろって癌におかされてしまう状況で、庭の自然の移ろいや、前妻との五人の子供達のこと、老いた母のことなどを綴った日記。昭和35年9月から昭和36年7月まで週一回、「化学時評」に連載された。
昭和32年末に上顎腫瘍が発見され癌と診断され、昭和35年には妻てい子が乳癌の手術を受けるという夫婦そろって癌におかされてしまう状況で、庭の自然の移ろいや、前妻との五人の子供達のこと、老いた母のことなどを綴った日記。昭和35年9月から昭和36年7月まで週一回、「化学時評」に連載された。 昭和50年から52年にかけて書かれた下曽我での身辺雑記。
昭和50年から52年にかけて書かれた下曽我での身辺雑記。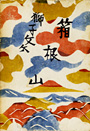 箱根の山を巡って道路や鉄道、バスなどの交通手段、旅館など観光客を目あてにした勢力争いを描いた、朝日新聞に連載され、後に川島雄三監督によって映画化された小説。はじめのシーンから大臣による反目しあう2つの会社の公聴会など、どこか緊張感を与えつつ、でもそういった争いの愚かさ、おかしさが随所に出てます。獅子文六のいかにも新聞小説、いかにも映画の原作(実際は小説があって映画化という順だけれど)といった感じがわりと好きだったりする。
箱根の山を巡って道路や鉄道、バスなどの交通手段、旅館など観光客を目あてにした勢力争いを描いた、朝日新聞に連載され、後に川島雄三監督によって映画化された小説。はじめのシーンから大臣による反目しあう2つの会社の公聴会など、どこか緊張感を与えつつ、でもそういった争いの愚かさ、おかしさが随所に出てます。獅子文六のいかにも新聞小説、いかにも映画の原作(実際は小説があって映画化という順だけれど)といった感じがわりと好きだったりする。 交友録というと、たとえば早稲田や東大仏文といった出身校、あるいは阿佐ヶ谷、鎌倉といった居住地、同人誌仲間・・・・など、ある特定のサークル内での交友が主なものになってきたりするものだけれど、吉田健一についてはそういうサークルがどうも思い浮かばない。友人は多そうだけれど、どうも“どこにも交わらない”といったイメージがあるのは、単なる私の知識不足に過ぎないのだろう。
交友録というと、たとえば早稲田や東大仏文といった出身校、あるいは阿佐ヶ谷、鎌倉といった居住地、同人誌仲間・・・・など、ある特定のサークル内での交友が主なものになってきたりするものだけれど、吉田健一についてはそういうサークルがどうも思い浮かばない。友人は多そうだけれど、どうも“どこにも交わらない”といったイメージがあるのは、単なる私の知識不足に過ぎないのだろう。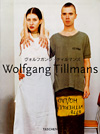 Taschen刊行の「Wolfgang Tillmans(1995)」と「Burg(1998)」の2冊を合本にしたお買い得な写真集。しかも2900円。先週、見に行った展覧会で見つけて、せっかくだからタワーブックスで買おうと思ったいたのだ。お得だけれど、表紙もそれほど厚くないし読んでいるうちにぼろぼろになりそうな気もする。
Taschen刊行の「Wolfgang Tillmans(1995)」と「Burg(1998)」の2冊を合本にしたお買い得な写真集。しかも2900円。先週、見に行った展覧会で見つけて、せっかくだからタワーブックスで買おうと思ったいたのだ。お得だけれど、表紙もそれほど厚くないし読んでいるうちにぼろぼろになりそうな気もする。 東北に向かう電車の窓から一瞬見えた沼の風景にひかれて、あんなところでゆっくりと絵を描けたらいいな、と思ったことから実現した企画で、山口瞳とドスト氏こと関保寿が全国の沼、湖などを巡りつつ絵を描く様子を綴られていく。
東北に向かう電車の窓から一瞬見えた沼の風景にひかれて、あんなところでゆっくりと絵を描けたらいいな、と思ったことから実現した企画で、山口瞳とドスト氏こと関保寿が全国の沼、湖などを巡りつつ絵を描く様子を綴られていく。 里見弴の随筆の言い放つような書き方が気に入っている。でも「極楽とんぼ」も「多情仏心」も「安城家の兄弟」も「善心悪心」も「今年竹」も「道元禅師の話」も読んでない私ですが・・・・。いったい私は里見弴のなにを読んでるのやら。結局なにをやるにも寄り道・回り道ばかりで・・・・
里見弴の随筆の言い放つような書き方が気に入っている。でも「極楽とんぼ」も「多情仏心」も「安城家の兄弟」も「善心悪心」も「今年竹」も「道元禅師の話」も読んでない私ですが・・・・。いったい私は里見弴のなにを読んでるのやら。結局なにをやるにも寄り道・回り道ばかりで・・・・