 気がつけば歩いていると誰も彼もがサンタの格好をしているのでは、と思うくらい、吉祥寺だけでなく富士見ヶ丘駅前の通りをサンタの格好をした女の子が走ってます。セブンイレブンか牛角の店員だと推測されるのだけれど、コンビニでわざわざ店員がサンタの格好をしなくてもいいのでは。そもそも日本でサンタの格好をしていいのはパラダイス山元だけです。
気がつけば歩いていると誰も彼もがサンタの格好をしているのでは、と思うくらい、吉祥寺だけでなく富士見ヶ丘駅前の通りをサンタの格好をした女の子が走ってます。セブンイレブンか牛角の店員だと推測されるのだけれど、コンビニでわざわざ店員がサンタの格好をしなくてもいいのでは。そもそも日本でサンタの格好をしていいのはパラダイス山元だけです。
11月の終わりから仕事が忙しいせいでなかなか古本屋にもレコード屋に行けなかった。しょうがないので会社の近くの本屋さんに行ってみたりしているのだけれど、「本って新品を買うと高いなぁ」と思ってしまう。普通の文庫本で500円以上するのを見ると、500円あれば永井龍男や庄野潤三の単行本が買えるよ、と。そんなことを言ってみても始まらないわけなんですけどね。
この本は、関東大震災の破壊から復興し、モダンボーイ、モダンガールが闊歩する昭和初期の東京の生活と風俗を、官衙、マスコミ、銀行、デパート、刑務所、病院、銀座、浅草、神楽坂、新宿、上野、劇場、映画館、寄席、カフェー、ダンスホール、名所旧跡、年中行事、新名所、縁日、夜店、味覚・・・・など、具体的な項目を挙げつつ記述・記録している。あまり私見を交えていないところがいい。作家や評論家が東京のことを書くとたいてい昔は良かったということに終始してしまい、読み終わった後どうもすっきりした気分になれなくなってします。どうやら人間は得たものよりも失ったものに固執するものらしい、なんてことを思ったりして。

 なんだか仰々しいタイトルではありますが、内容は、結婚6年目の永井龍男が「今日こんな人を見たよ、でも君にはそんな風になって欲しくないね」とか「たまには君も気分を変えてみるのももいいよ」という、妻への手紙、といった趣の短い文章を集めたもの。文体もいつもの永井龍男をちょっと違っていて個人的にはちょっと違和感があるような気もしないでもない。でも考え方を変えれば、「暮しの手帖」の片隅に連載されたもの、と言われても信じてしまうかもしれない、と言えるかも。この文章だったら花森安治のイラストが似合いそうだし・・・・。いや、ただの思いつきですが。
なんだか仰々しいタイトルではありますが、内容は、結婚6年目の永井龍男が「今日こんな人を見たよ、でも君にはそんな風になって欲しくないね」とか「たまには君も気分を変えてみるのももいいよ」という、妻への手紙、といった趣の短い文章を集めたもの。文体もいつもの永井龍男をちょっと違っていて個人的にはちょっと違和感があるような気もしないでもない。でも考え方を変えれば、「暮しの手帖」の片隅に連載されたもの、と言われても信じてしまうかもしれない、と言えるかも。この文章だったら花森安治のイラストが似合いそうだし・・・・。いや、ただの思いつきですが。 いくら釣りに興味がない人にもおもしろく書かれているといっても、この厚さで全部釣りの話というのはちょっと食傷気味になってしまう(文字は大きいが)。ましてや岩波から出ている「川釣り」と同じ話も多く収録されてるし・・・・。個人的には半分くらいにして「釣りの楽しみ&●●●●」みたいに2つのテーマでまとめて欲しい気がしますね。「釣りの楽しみ、将棋の楽しみ」とかね。井伏鱒二の将棋についてや対戦した人についての随筆がまとまっていたらちょっとおもしろそうだと思うのですが、どうでしょうか。
いくら釣りに興味がない人にもおもしろく書かれているといっても、この厚さで全部釣りの話というのはちょっと食傷気味になってしまう(文字は大きいが)。ましてや岩波から出ている「川釣り」と同じ話も多く収録されてるし・・・・。個人的には半分くらいにして「釣りの楽しみ&●●●●」みたいに2つのテーマでまとめて欲しい気がしますね。「釣りの楽しみ、将棋の楽しみ」とかね。井伏鱒二の将棋についてや対戦した人についての随筆がまとまっていたらちょっとおもしろそうだと思うのですが、どうでしょうか。 木村衣有子の「京都カフェ案内」を新幹線の中で眺めながら、京都に着くなり六曜社に行き、まる捨、進々堂、エフィッシュ・・・・などのカフェを回りつつ、京都の町を散歩したり、神戸に出て雑貨屋さんや本屋さんを巡り、南京町を歩いたのは、いつのことか、去年のことか?一昨年のことか?その前にオリーブのカフェグランプリの号を持って、イノダコーヒーやDOJI、オパール、ソワレ・・・・に行ったのは?なんてことを思い出しながら、「今年は引っ越ししたり、転職したりしてどこにもいけなかったな」と年の終わりにこんな本を読みつつ反省してます。
木村衣有子の「京都カフェ案内」を新幹線の中で眺めながら、京都に着くなり六曜社に行き、まる捨、進々堂、エフィッシュ・・・・などのカフェを回りつつ、京都の町を散歩したり、神戸に出て雑貨屋さんや本屋さんを巡り、南京町を歩いたのは、いつのことか、去年のことか?一昨年のことか?その前にオリーブのカフェグランプリの号を持って、イノダコーヒーやDOJI、オパール、ソワレ・・・・に行ったのは?なんてことを思い出しながら、「今年は引っ越ししたり、転職したりしてどこにもいけなかったな」と年の終わりにこんな本を読みつつ反省してます。 「3ガ日の、雪の降るような冷え込む夜には、随分遠くから横須賀線の踏切の警鐘が聞こえてくる。ああ、あそこの踏切だろうと思うと、闇の中に真っ直ぐ線路が見えてくる。どこかへ出かけるつもりになれば、まだどこへだって行けるのだなと思ったりすることもある」
「3ガ日の、雪の降るような冷え込む夜には、随分遠くから横須賀線の踏切の警鐘が聞こえてくる。ああ、あそこの踏切だろうと思うと、闇の中に真っ直ぐ線路が見えてくる。どこかへ出かけるつもりになれば、まだどこへだって行けるのだなと思ったりすることもある」 一言でいうと“戦時下の青春日記”。
一言でいうと“戦時下の青春日記”。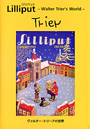 ケストナーの「エミールと探偵たち」などの挿絵でおなじみのヴァルター・トリーア(ついくせでワルター・トリアーと言ってしまう)が、1937年から12年間約100冊、描き続けたイギリスの雑誌「Lilliput Magazine」の表紙を中心に、イラストや古い絵本を紹介した本。厚さはサイズ的には割と小さな本なのは、「Lilliput Magazine」自体もポケット・マガジンということなのでこのくらいのサイズだったのだろうか。個人的には「Lilliput Magazine」以外のイラストももっと掲載して、彼の仕事の全体がわかるような本が欲しいなぁと思う。ちゃんと洋書などを調べれば出ているのかもしれないけど。
ケストナーの「エミールと探偵たち」などの挿絵でおなじみのヴァルター・トリーア(ついくせでワルター・トリアーと言ってしまう)が、1937年から12年間約100冊、描き続けたイギリスの雑誌「Lilliput Magazine」の表紙を中心に、イラストや古い絵本を紹介した本。厚さはサイズ的には割と小さな本なのは、「Lilliput Magazine」自体もポケット・マガジンということなのでこのくらいのサイズだったのだろうか。個人的には「Lilliput Magazine」以外のイラストももっと掲載して、彼の仕事の全体がわかるような本が欲しいなぁと思う。ちゃんと洋書などを調べれば出ているのかもしれないけど。 対談相手は、開高健、永井龍男、丸谷才一、河盛好蔵、尾崎一雄・・・・名前を眺めるだけでこの二人がどんな話をするのだろう、わくわくしてしまう人選は偶然と言うより必然か。でも井伏鱒二が開高健と対談して、一方で木山捷平が山口瞳と対談してる、だからどうということはないけれど、私としてはそこに何かを見つけたくなってしまうわけです。
対談相手は、開高健、永井龍男、丸谷才一、河盛好蔵、尾崎一雄・・・・名前を眺めるだけでこの二人がどんな話をするのだろう、わくわくしてしまう人選は偶然と言うより必然か。でも井伏鱒二が開高健と対談して、一方で木山捷平が山口瞳と対談してる、だからどうということはないけれど、私としてはそこに何かを見つけたくなってしまうわけです。 こんな本を読んだせいで週末は浅草とかのんびり歩いてみたいなぁなんて思っていたら、熱を出して寝込んでしまいました。土曜の夜に雨の中、家に帰る途中、寒気がして歯がカタカタするのでおかしいと思っていたら、39度もあって、そのまま日曜、月曜と寝込むはめに。ちょっと目が覚めても寒気はとれないし、頭はガンガン痛いしで、横になっているとふと眠っているという状態。いつ取ろうか心待ちにしていた代休を無駄にとってしまいました。しかもあとでニュースを見たら日曜はものすごく晴れていて夏日だったとか。
こんな本を読んだせいで週末は浅草とかのんびり歩いてみたいなぁなんて思っていたら、熱を出して寝込んでしまいました。土曜の夜に雨の中、家に帰る途中、寒気がして歯がカタカタするのでおかしいと思っていたら、39度もあって、そのまま日曜、月曜と寝込むはめに。ちょっと目が覚めても寒気はとれないし、頭はガンガン痛いしで、横になっているとふと眠っているという状態。いつ取ろうか心待ちにしていた代休を無駄にとってしまいました。しかもあとでニュースを見たら日曜はものすごく晴れていて夏日だったとか。 この作品の題名を初めて目にしたのは、おそらく中学くらいの国語の授業だったような気がする。でもまさか自分が読むなんてことは想像もしてなかったね。この作品に限らず井伏鱒二の作品は、10代の頃に読む本ではないような気がするな。
この作品の題名を初めて目にしたのは、おそらく中学くらいの国語の授業だったような気がする。でもまさか自分が読むなんてことは想像もしてなかったね。この作品に限らず井伏鱒二の作品は、10代の頃に読む本ではないような気がするな。