 犬を題材にした古今東西の文学作品をめぐるエッセイ集。ロジェ・グルニエは、愛犬のユリシーズが死んだときに、もう犬は飼うまいと決心し、その代わりに犬に関しての本を集め出したのだそう。愛犬家の作家による思い入れたっぷりのから犬を機械とまで定義した厭犬家まで、さまざまな文章が縦横無尽に引用されつつ、グルニエの犬への、特にユリシーズへの思いがつづられてます。私自身は、カヌー犬ブックなんて名前をつけているわりには、それほど犬好きというわけでもなくて、むしろ、小学校くらいまでは犬が嫌いだった、というか怖かった、というほうだったりします。というのも、私が小学校低学年くらいの頃までは、まわりに野犬がいて、しょっちゅう追い回されていたから。学校に行くときにかみつかれて、病院で検査とかされたりしてました。背が低いから顔とかかみつかれちゃうんですよ。
犬を題材にした古今東西の文学作品をめぐるエッセイ集。ロジェ・グルニエは、愛犬のユリシーズが死んだときに、もう犬は飼うまいと決心し、その代わりに犬に関しての本を集め出したのだそう。愛犬家の作家による思い入れたっぷりのから犬を機械とまで定義した厭犬家まで、さまざまな文章が縦横無尽に引用されつつ、グルニエの犬への、特にユリシーズへの思いがつづられてます。私自身は、カヌー犬ブックなんて名前をつけているわりには、それほど犬好きというわけでもなくて、むしろ、小学校くらいまでは犬が嫌いだった、というか怖かった、というほうだったりします。というのも、私が小学校低学年くらいの頃までは、まわりに野犬がいて、しょっちゅう追い回されていたから。学校に行くときにかみつかれて、病院で検査とかされたりしてました。背が低いから顔とかかみつかれちゃうんですよ。
なので、そういった思い入れの部分に関しては、あらあら、ふんふんという感じなんですけど、犬好きの人が読んだら、やはり感じ方が違うのかな。どちらかといえば、こういう散文的なエッセイが好きなこともあり、そういった内容よりも文章の構成や言い回し、引用の仕方‥‥といったことの方が気になるわけで‥‥。まぁそれも内容がおもしろければこそ、ですけど。
月別: 2006年8月
「ニコラスのペット」-インゲル&ラッセ・サンドベルイ-
 銀座で友達と待ち合わせしていたので、自転車で荻窪まで出て、阿波踊りとも知らず好書会でも行こうと思って高円寺に行ったら、駅前からすごい人でした。
銀座で友達と待ち合わせしていたので、自転車で荻窪まで出て、阿波踊りとも知らず好書会でも行こうと思って高円寺に行ったら、駅前からすごい人でした。
まだ始まっていない時間だったのだけれど、もう道の両端はビニールシートとか敷いてあって場所取りしてあったり、すでに飲み始めている人がいたり、とうぜん通り沿いのお店は、店の前にいろいろ出してたり‥‥いまにも祭りが始まる寸前という感じの雰囲気。阿波踊りって、場所とって見るものということを初めて知りました。よく考えれば、七夕祭りみたいに飾り付けとかあるわけではないし、行列が動いてくるわけだから、こちらが歩く必要はないですね。
そんな中、店の前でフリマみたいなのをやっているところがあり、洋服とかレコードとかおもちゃとかの中に「ニコラスのペット」と「ボタンくんとスナップくん」を発見。講談社から出ていた世界の絵本シリーズのスウェーデン編とフィンランド編で、おしゃれな雑貨屋とかに行くと洋書は置いてあったりするけれど、絵本はやはり日本語版の方がいいかも。もちろん洋書には洋書のよさがあるけれど、日本語だったら普通に読めるし‥‥といっても、絵本とそんなに繰り返して読むわけでもないか。
さて、銀座では、前の会社で同じ部署だった人と3人で飲んだ。一人はしょっちゅう会っているのけれど、もう一人のほうは会うのは一年ぶりくらい。会社に入ってきたときは新卒で、それから3年くらいしか経ってないのに、「最近の新人は~」なんて言い出すのがおかしい。いや、そういうことは言っちゃいかんよ、(威張ってはいかんよ)、と常盤新平風に思ったりもするけれど、女の子が多そうな職場だし、別の意味で大変なのかも知らん。
で、いろいろ話してるうちにiPodの話とか聴いてる音楽の話とかになって、今度は「最近わたし、スウェデッシュ・ポップに凝っていて、ジャニスとかに通ってるんですぉ」って‥‥。2006年のいま、スウェデッシュ・ポップとか、ジャニスとか聴くとは思いませんでした。
でも先週、エッジエンドに行ったときに、「次はスウェデッシュポップ特集なんですよ」と、ACID HOUSE KINGSのジャケ写が使われたevery planets sonのフライヤーをもらったし、実は流行ってるんですか?スウェデッシュ・ポップ?ま・さ・か・ねぇ。
というか、なんだか「スウェデッシュ・ポップ」という言葉を声に出すだけで。恥ずかしい気持ちになってしまうんですけど‥‥。わたしだけか?
そんなわたしですが、うちに帰ってCDラック探したら思っていたより売り払ってなくて、30枚くらいありました。「恥ずかしい気持ち」なんて言う資格なしですね。
「おやじの女」-安藤鶴夫-
 安藤鶴夫の本は、「昔・東京の町の売り声」や「あんつる君の便箋」、「年年歳歳」、「雪まろげ」、「ごぶ・ゆるね」‥‥など、タイトルを見ているだけで読みたくなってしまうものが多い。この本のタイトルとなった「おやじの女」は、安藤鶴夫がものごころついたときから死ぬときまで、父親に女の人がいなかったことはなくて、ときには堂々と家につれて泊めてみたり、母親とその女の人がお酒を飲んだりしていたことを書いた短い文章なのだが、なんてこともないさらりした文章に時代を感じたりもします。タイトルとしても、義太夫だった父親をとおして明治の芸人たちの生き方を、遠く昔に眺めているような感じがするような気がしていいな、と思う。ところで、原作:安藤鶴夫となっている松竹新喜劇の「おやじの女」は、この随筆が元になっているのだろうか。ほかに「おやじの女」という作品があるのだろうか。ちょっと気になります。
安藤鶴夫の本は、「昔・東京の町の売り声」や「あんつる君の便箋」、「年年歳歳」、「雪まろげ」、「ごぶ・ゆるね」‥‥など、タイトルを見ているだけで読みたくなってしまうものが多い。この本のタイトルとなった「おやじの女」は、安藤鶴夫がものごころついたときから死ぬときまで、父親に女の人がいなかったことはなくて、ときには堂々と家につれて泊めてみたり、母親とその女の人がお酒を飲んだりしていたことを書いた短い文章なのだが、なんてこともないさらりした文章に時代を感じたりもします。タイトルとしても、義太夫だった父親をとおして明治の芸人たちの生き方を、遠く昔に眺めているような感じがするような気がしていいな、と思う。ところで、原作:安藤鶴夫となっている松竹新喜劇の「おやじの女」は、この随筆が元になっているのだろうか。ほかに「おやじの女」という作品があるのだろうか。ちょっと気になります。
で、結局のところ、外に女の人を作るのも、本人にそれだけの器があるか、ということにつきるのか、単に時代や考え方が変わっただけなのか、どっちなのだろう。もちろん私にはそんな器はないけれど、器のない人間が無理をすると、どこかで破綻してしまうわけで、その破綻がどんな結果になるかは、そのときの運次第ということなのだろう。なんて、なんのことかといえば、ウディ・アレンの新作「マッチ・ポイント」の話だったりする。
元プロテニス・プレイヤーの主人公クリスが、ロンドンの上流階級であるトムと知り合ったことがきっかけとなり、その妹と結婚することになるのだが、クリスはトムの婚約者であるノラにひかれてしまう‥‥というこれ以上ないストレートなメロドラマ。これを新境地とみるかどうかで、この映画の見方が変わるのだろうけれど、個人的には、なんでこの映画をウディ・アレンが撮る必要が?という印象は否めないかな。もちろん上流階級の妻とアメリカ人女性を手玉に取るような器の主人公もどうかと思うけれど、ウディ・アレンの映画としては、そういう器がまったくない主人公が、なんだかんだといいながら都合よく立ち回って、結果的に手玉に取ってしまっているような、いないような‥‥という展開を期待してしまうのは、私のウディ・アレンに対する偏見か。
「オリンピックスマーフ」-ペヨ-
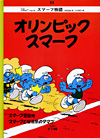 部屋のスペースなどの問題もあって、基本的にスマーフとフレッドくん以外のキャラクターグッズは買わないようにしているのだけれど、最近はどちらもあまり見かけないような気がします。スマーフのフィギュアも、前はおもちゃ屋や雑貨屋にも普通に置いてあったのに、ちょっとマニアックなお店にしか置いていなくて、そういうお店ではたいてい高い値段がつけられているので、買う機会もほとんどない。
部屋のスペースなどの問題もあって、基本的にスマーフとフレッドくん以外のキャラクターグッズは買わないようにしているのだけれど、最近はどちらもあまり見かけないような気がします。スマーフのフィギュアも、前はおもちゃ屋や雑貨屋にも普通に置いてあったのに、ちょっとマニアックなお店にしか置いていなくて、そういうお店ではたいてい高い値段がつけられているので、買う機会もほとんどない。
3、4年前くらいに復刊されたこの絵本のシリーズも、結局、復刊されたものは一冊も買っていないしね。今でも絵本コーナーとかに置いてあるのかな。分かりません。本よりも売り場に貼ってあったポスターが欲しかったなぁ。もうとっくに捨てられてるだろうけれど‥‥。
お盆休み中は、電車も街中も少しだけ空いていて、いいですね。先日、ライズXで、ビースティ・ボーイズの「撮られっぱなし天国」を観たのですが、観客は10人くらいしかいなくて、単に平日の昼間はいつもこうなのか、お盆休みだからなのか、そもそもビースティの人気がないだけなのか、ちょっと考えてしまった。
ライブが始まってから終わるまで、録画を止めないというルールで、観客50人にビデオ・カメラを渡して、それぞれのカメラで撮影されたものを編集したというビースティらしいライブ映画なのけれど、実際は、DJブースのアップをはじめ、バックステージやステージ上などの映像がほとんどで、観客が撮った映像はときおり使われる程度でした。そういう意味では、アイデアはよかったが、素人の観客席からの映像を集めただけじゃちょっと無理があったかという印象。そんなところもビースティらしいといえばビースティらしい。ライブ自体はマジソン・スクエア・ガーデンでの地元凱旋ライブだけあって、いろいろな演出とかもあったりしておもしろかったけどね。
ただ映像がかなり揺れるので、ちょっと眠くなると、目の焦点が合わなくなって、つい寝てしまった。あぁ結局、1/3くらいは寝てたか。
「陽気なクラウン・オフィス・ロウ」-庄野潤三-
 チャールズ・ラムをめぐる10日間のイギリス滞在記。実際にラムゆかりの場所に行ったときの印象をはじめとして、その場所についてのラムの文章の引用や庄野潤三のラムに関する思い出だけなく、福原麟太郎、吉田健一、小沼丹、河盛好蔵といった作家たちによるイギリス滞在記からの引用などが多くあり、いろいろな面から楽しめます。イギリスに行ったのが1980年にもかかわらず、雑誌「文學界」に連載されたのが1982年から1983年にかけて、ということからも、単なる滞在記ではなく、帰国後にかなり関連する資料を調べたり、内容を練ったりしたことがわかります。と言っても、やはり「エリア随筆」を先に読んでおいたほうが面白いと思いますが。いや、逆にこれを先に読んでおいてから、「エリア随筆」を読むという順番のほうがいいかもしれない。そんなことはどうでもいい?
チャールズ・ラムをめぐる10日間のイギリス滞在記。実際にラムゆかりの場所に行ったときの印象をはじめとして、その場所についてのラムの文章の引用や庄野潤三のラムに関する思い出だけなく、福原麟太郎、吉田健一、小沼丹、河盛好蔵といった作家たちによるイギリス滞在記からの引用などが多くあり、いろいろな面から楽しめます。イギリスに行ったのが1980年にもかかわらず、雑誌「文學界」に連載されたのが1982年から1983年にかけて、ということからも、単なる滞在記ではなく、帰国後にかなり関連する資料を調べたり、内容を練ったりしたことがわかります。と言っても、やはり「エリア随筆」を先に読んでおいたほうが面白いと思いますが。いや、逆にこれを先に読んでおいてから、「エリア随筆」を読むという順番のほうがいいかもしれない。そんなことはどうでもいい?
昨日、今日は会社の夏休みだったのだけれど、なんでこんなに眠いのか?というほど眠ってばかりです。朝、9時にかけた目覚ましで起きれずに、10時半頃起き出して、朝ごはん食べたあと、洗濯機をまわしながら、ちょっとテレビのスイッチを入れてソファーに座ったら、そのまま眠ってしまい、起きたら、12時過ぎ。で、洗濯物干して、出かける準備しなくちゃなぁ、なんて思いつつ、ついうたたね。起きると3時。夕方ちょっと出かけて、ご飯を食べたりして、帰ってきてソファーにすわったとたん、眠気が!そんな感じなのに、夜眠れないってこともなく、1時過ぎくらいになるとあくびが出てきて、普通に眠れてしまう。つかれてるのか?夏ばてなのか?その割には普通に食欲あるんですけど‥‥。
そんな一日ですが、やっと眠気が覚めて、外も涼しくなった夕方から、国分寺のトネリコに行ってきました。4人がけのテーブルが3つと2人がけのテーブルが1つ、あとカウンター席というお店で、近所に住んでいると思われる人が、あいさつしながら次々と入ってきて気がつけば満席。そのあともお店の前で中をのぞいて、座る席がないのがわかると、お店の人に声をかけて去っていく人がいたりして、とてもいい雰囲気。料理をする人と接客する人の2人しかいないこともあって忙しそうでした。
そんな中、窓際の2人席でわたしたちは、kuukuuにもあった南風荘ビール(ビール+グレープフルーツ)を飲みながら、カツオのたたきとかトルコ風肉だんごなどの、ちょっと懐かしい風味のご飯を食べて満腹に。うちの場合二人とも少食なんで、こういうときは、何人かで行って少しずつ食べたい。場所が遠いので頻繁に行くことはできないけれど、国分寺の街もゆっくり歩いたりしたいしまた行きたいです。
「男の風俗・男の酒」-丸谷才一VS.山口瞳-
 一時期、山口瞳と永井龍男の本ばかり読んでばかりいたような気がするのだけれど、最近はなかなか手に入らなくてほとんど読んでいない。山口瞳に関しては、まだ普通に手に入る本(文庫)で、読んでいないものがあるので、今年の命日あたりにまた何冊か続けて読んでみようと思ってる。
一時期、山口瞳と永井龍男の本ばかり読んでばかりいたような気がするのだけれど、最近はなかなか手に入らなくてほとんど読んでいない。山口瞳に関しては、まだ普通に手に入る本(文庫)で、読んでいないものがあるので、今年の命日あたりにまた何冊か続けて読んでみようと思ってる。
さて、山口瞳の対談と言うと、高橋義孝や木山捷平、あるいは常盤新平との対談くらいしか思いつかなかったりする。前に河出から出ていたムックに何人かの対談が収録されていたのだが、あまり内容も覚えていない。偏見に満ちた持論を強引に展開するところを山口瞳の真骨頂とするならば(それも偏見か)、対談という形式は似合わないような‥‥、というのも偏見ですかね。前述した人たちも、師弟の“師”と“弟”で、内容的には対談というよりもインタビューに近かったような気がします(前者では山口瞳が、後者では常盤新平がインタビュアー)。もっとも本人もこの本のまえがきで「気持ちよく終わる対談というものはあまりないものだ」みたいなことをいってたりするし‥‥。
丸谷才一は、その辺のことがよく分かっていて、ときに山口瞳の意見に同調して、「そこがあなたの持ち味なんですよ」みたいなことを言って持ち上げつつ、持論を引き出してみたり、逆に暴走しそうになると、さっと「僕は山形(出身)なんでそうでもないけどね」みたいなことを言い出して、反対するでもなく(反対するとよけい暴走することが分かっている)、その意見を収束させてみたり、ものすごく冷静に場をコントロールしていると思う。たしかに山口瞳にとっては言いたいことも言えるし、言ってしまって自己嫌悪におちいる直前でうまく話をそらせてくれるし、気持ちよく終わる対談だっただろう。もっとも読者としては、物足りないような気もしないでもないけれど。
先日、高山なおみの本を立ち読みしていたら、kuukuuのスタッフだった人が国立で開いたニチニチというお店が出てきて、久しぶりに国立に行きたくなってしまった。ちょっと検索してみたら、小さなお店みたいだけれど、ときどきライブをやったりもしているらしい。ついでに国分寺にもkuukuuの元スタッフが開いたトネリコというお店があるらしく、いつかまたkuukuuの人たちが集まって、吉祥寺でいい感じのお店を開いてくれないかなぁ、とずっと思っていた私としては寂しい気分半分と、そうやってひとりひとりが、kuukuuでの経験を活かしつつ自分らしいお店を開いていく感じがなんとなくいいなぁとも思う。それが吉祥寺ではなく、国立や国分寺というところもなんとなく“らしい”気がします。
そういえば前回、国立に行ったのは、さくらの花が咲いている頃で、通りには出店が並んでいてものすごい人混みのなかを歩きながら、中央線の高架にともないあの駅舎がなくなってしまうのか、なんてことを思っていたけれど、あれからどうなったのだろうか?
