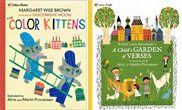 絵がかわいかったのと比較的値段が安かったので、下のサセックの本と一緒に注文してみた。実際に届いてみると思っていたよりも大きなしっかりとしたハードカバーの本だったのでうれしい。(写真では同じにしてしまっているけれど「A Child’s Garden of Verses」の大きいです。)
絵がかわいかったのと比較的値段が安かったので、下のサセックの本と一緒に注文してみた。実際に届いてみると思っていたよりも大きなしっかりとしたハードカバーの本だったのでうれしい。(写真では同じにしてしまっているけれど「A Child’s Garden of Verses」の大きいです。)
それぞれGolden Books Family Storytime、Golden Books Classicsというシリーズの一冊らしいのだけれど、これはLittle Golden Booksの復刻版なのかな。ちょっと分かりません。
作者のプロヴェンセン夫妻は、夫のマーチンがディズニーの「ファンタジア」「ダンボ」などの制作にかかわっているときに知り合い、1947年に、「The Fine Side of Folk Songs」というフォークソング集の挿絵を初めて二人で手がけたのをきっかけに、以後50冊以上の本を刊行しているアメリカを代表する絵本作家。日本では、「スティーヴンソンのおかしなふねのたび」(翻訳:平野敬一)「シェイカー通りの人びと」(翻訳:江國香織)「パパの大飛行」(翻訳:脇 明子)といった本が翻訳されているようです。「A Child’s Garden of Verses」は「いろいろこねこ」という題名みたいです。
なんてことを書いていますが、実は何にも知らずに表紙だけ見ていいなと思うものを適当に買ったら同じ作者だったのでちょっとびっくりしました。絵の感じも同じというわけでもないし・・・・。

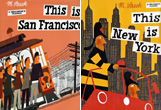 ミロスラフ・サセックの子どものための旅行絵本シリーズより、最近復刊されたニューヨークとサン・フランシスコの本。
ミロスラフ・サセックの子どものための旅行絵本シリーズより、最近復刊されたニューヨークとサン・フランシスコの本。 新宿の南口にあるスタンダードカフェでお茶して東口のほうに歩いていたら、ヴィクトリアの裏側に古本屋を発見。「畸人堂 趣味の古本屋(だったかな)」と書かれた看板に不安を覚えつつも行ってみると、かなり普通の古本屋。映画や音楽、アート関係の本もなにげにたくさんあって得した気分でとりあえず鎌倉特集の「太陽」を買う。
新宿の南口にあるスタンダードカフェでお茶して東口のほうに歩いていたら、ヴィクトリアの裏側に古本屋を発見。「畸人堂 趣味の古本屋(だったかな)」と書かれた看板に不安を覚えつつも行ってみると、かなり普通の古本屋。映画や音楽、アート関係の本もなにげにたくさんあって得した気分でとりあえず鎌倉特集の「太陽」を買う。 訳あって最近送別会多し。昨日も会社の人の送別会で、解散後もちょっと飲んで帰ろうと思ったら電車の乗りつぎを考えると井の頭線の最終に間に合いそうもない。しょうがないので荻窪に住む同僚と中央線で西荻まで出て歩いて帰ることにする。しかも西荻の駅で降りるとパラパラと雨が、時間はすでに1時過ぎ。
訳あって最近送別会多し。昨日も会社の人の送別会で、解散後もちょっと飲んで帰ろうと思ったら電車の乗りつぎを考えると井の頭線の最終に間に合いそうもない。しょうがないので荻窪に住む同僚と中央線で西荻まで出て歩いて帰ることにする。しかも西荻の駅で降りるとパラパラと雨が、時間はすでに1時過ぎ。 週末に吉祥寺のブックオフにて購入。「ルー・ドーフスマン」は前にも書いた世界のグラフィックデザインシリーズの中の一冊。この間買ったばかりのヘンリク・トマシェフスキはなかったけれどソール・バスやアイヴァン・チャマイエフなど7、8冊が半額で売られていました。しかも結構きれいな状態で・・・・
週末に吉祥寺のブックオフにて購入。「ルー・ドーフスマン」は前にも書いた世界のグラフィックデザインシリーズの中の一冊。この間買ったばかりのヘンリク・トマシェフスキはなかったけれどソール・バスやアイヴァン・チャマイエフなど7、8冊が半額で売られていました。しかも結構きれいな状態で・・・・ 下の本を検索しているときにネットで見つけた絵本が届いた。
下の本を検索しているときにネットで見つけた絵本が届いた。 相変わらず吉田健一の本ばかり読んでいます。というより高校生の時からいままでアメリカ文学ばかり読んでいた身としては、アメリカ文学に興味を失った今何を読んでいいのかよくわからないだけなんですけどね。ほんとは小沼丹とかも読みたいんだけれど、講談社から出ている文庫以外の本がネットで調べても高いので手に入れることができないし状態。
相変わらず吉田健一の本ばかり読んでいます。というより高校生の時からいままでアメリカ文学ばかり読んでいた身としては、アメリカ文学に興味を失った今何を読んでいいのかよくわからないだけなんですけどね。ほんとは小沼丹とかも読みたいんだけれど、講談社から出ている文庫以外の本がネットで調べても高いので手に入れることができないし状態。 うちの会社はデスクでものを食べてはいけないため、昼休みには誰もいなくなってしまいます。そこで順番に昼休みをずらしてとることになっていて、今日は私の番。1時からご飯を食べに外に出るとどこも空いていていい感じ。最近は4月にできたばかりの東京ランダムウォークという本屋でちょっと洋書とかチェックしてその前にあるサブウェイで本をめくりながらサンドウィッチを食べてます。
うちの会社はデスクでものを食べてはいけないため、昼休みには誰もいなくなってしまいます。そこで順番に昼休みをずらしてとることになっていて、今日は私の番。1時からご飯を食べに外に出るとどこも空いていていい感じ。最近は4月にできたばかりの東京ランダムウォークという本屋でちょっと洋書とかチェックしてその前にあるサブウェイで本をめくりながらサンドウィッチを食べてます。 金曜日は寄り道デイ、ということでパルコやユニオン、レコファン、ブックファーストなど渋谷をうろうろ。
金曜日は寄り道デイ、ということでパルコやユニオン、レコファン、ブックファーストなど渋谷をうろうろ。 須賀敦子のエッセイはアントニオ・タブツキの本に夢中になっていた頃からずっと読んでみたかったのだけど、書評などで「凛とした詩情溢れる文章が紡ぎ出す」とか「作者が熟成させた言葉の優雅な果実を、いまは心ゆくまで享受したい」なんていう文章を見てしまうと、どうも気恥ずかしいような気がしてなかなか手が出せないままになってしまってました。
須賀敦子のエッセイはアントニオ・タブツキの本に夢中になっていた頃からずっと読んでみたかったのだけど、書評などで「凛とした詩情溢れる文章が紡ぎ出す」とか「作者が熟成させた言葉の優雅な果実を、いまは心ゆくまで享受したい」なんていう文章を見てしまうと、どうも気恥ずかしいような気がしてなかなか手が出せないままになってしまってました。