Fritz Siebel-
「江分利満氏の優雅な生活」
 山口瞳の本を読み始めたときにいつかは読んでおかなくちゃ、と思って買ってはみたけれど、どうも読む気がしなくて本棚に置きっぱなしにした本。
山口瞳の本を読み始めたときにいつかは読んでおかなくちゃ、と思って買ってはみたけれど、どうも読む気がしなくて本棚に置きっぱなしにした本。
でも最初の方に読まなくて良かったです。山口瞳の本をいくつか読んでみて、山口瞳の経歴を大まかでもわかった後に読んだので、実はかなり深い作品じゃないかと思いました。江分利満(エヴリマン)と言いつつかなり個人的な要素が含まれているのではないでしょうか。その個人的な要素と風俗的な要素をうまく組み合わせている点にこの本のおもしろさがあります。
さて、ちょっと前にトリスウィスキーにアンクルトリスのグラスがついているのを見て以来迷っていたのですが、今日西友で見たらグラスのついているものがあと3つになっていたので、「これは買うしかない」とトリスウィスキーを買ってしまいました。グラスが冷えるとアンクルトリスの顔が赤くなります。
わたしは家ではほとんどお酒を飲まないのだけれど、とりあえずこの1本がなくなるまで頻繁に飲んでしまいそうです。(今も飲みながらこれ書いてます)
「すてきな 三にんぐみ」-トミー・アンゲラー-
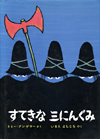 9月に入ってからの真夏日すでに9日だそうです。あきらかに8月よりも夏、ですね。
9月に入ってからの真夏日すでに9日だそうです。あきらかに8月よりも夏、ですね。
「夏の気分をもう一度!」というわけではないけれど、今日は夏休みにできなかった冷蔵庫の上にのせるための棚を一日かけて作ってました。
夕方、あらかたできあがったのでご飯(焼きそば)の材料を買いにいくついでに、久我山の南口にある古本屋さんをちょっとのぞいてみたらこの「すてきな 三にんぐみ」を発見。ずっと欲しかったんだよ。980円の定価なので素直に買えばいいのだけれどそういう機会もなく、それじゃ特に欲しいわけじゃないんじゃないの?という意見もあるとは思うけれど、そういうわけでもないのよ。よくわかりませんが・・・・。
この本屋は(名前は忘れました)結構きれいなだし、本も「おぉぉ」というほどじゃないにしても割とそろっているのだけれど、ちょっと駅から遠いので会社帰りとかに気軽に寄るということができないのが残念。会社の帰り道に毎日のように寄れる古本屋さんがあるといいのにな。
そういえば「本業失格」のなかで誰かが「午前2時に開いてる古本屋が近くにあるといいよね」なんてことを言っていたけれど、わたしもそう思います。西荻から帰るとたくさんあるんだろうけど、まぁそうなるとそれはそれでいろいろ問題が・・・・?
「本業失格」-松浦弥太郎-
 神保町に行きたーい!2カ月くらいからそう思っていたのだけれど、この本を読んでまた強く思うようになってしまいました。毎週じゃなくていいから1カ月に一度くらいは行きたいです。
神保町に行きたーい!2カ月くらいからそう思っていたのだけれど、この本を読んでまた強く思うようになってしまいました。毎週じゃなくていいから1カ月に一度くらいは行きたいです。
で、僕の勝手なイメージとしては、どうも週末はお店が閉まっているような気がするのと気分的に平日の昼間にうろうろとしたい。
結構人でにぎわっているんだけど、実は学生とさぼっていると思われる会社員、そして普段何しているのかよく分からないような人ばっかり、なんて中で「あっちに喫茶店あったな」なんて思って歩いているうちに知らない古本屋が目に入ったりして、お昼ご飯を食べるすきもないくらい次々と本屋に入って、本がいっぱい詰まったリュックサックとトートバッグはずっしりと肩に食い込むし、レコードなんかも買ってしまって結構じゃまで、とりあえず喫茶店で休んでバッグの中の本を整理しているうちにあたりは暗くなってくるし、休んだはずなのに帰りの電車は通勤ラッシュにぶつかってしまっていつもより辛かったり・・・・。
以前は割と残業や休日出勤があったりして代休も取れたものなのですが、最近はそういうのが全然ありません。かといって定時にあがってその後に神保町に行くってわけにもいかないし・・・・。こうなったら有給使うか・・・・。
でも私は基本的に「読んだら買う」という感じなので、読んでない本が何十冊もたまってしまうというくらい本を買い込むことはありません。だから週に何回か西荻か吉祥寺の古本屋に行って、気が向いたら高円寺とか荻窪とかを歩いて、という感じで満足なんですよ。
「東京の横町」-永井龍男-
 正直言って永井龍男について知っていることはほとんどありません。この間、小津安二郎展を鎌倉文学館に見に行ったときにちょっと展示を見たくらい。奥付を見て鎌倉文学館の初代館長だったということもはじめて知りました。
正直言って永井龍男について知っていることはほとんどありません。この間、小津安二郎展を鎌倉文学館に見に行ったときにちょっと展示を見たくらい。奥付を見て鎌倉文学館の初代館長だったということもはじめて知りました。
この本は1980年代に日経新聞に連載した「私の履歴書」を中心にまとめたもの。幼少期から前後文藝春秋を退社して作家としてやっていくまでの経歴が書かれています。
ここでは文藝春秋の社長である菊池寛はもちろんのこと、さすがにいろいろな人が登場してきます。なかでも川端康成や小林秀雄、里見惇など鎌倉に住む人々が出てくるとなんだかわくわくしてきます。先日読んだ山口瞳は隣に川端康成が住んでいたという話を書いていたし、井伏鱒二の本には小林秀雄が出てきたり、小沼丹の随筆には井伏鱒二が出てきて・・・・そうやっていろいろな本を読みながら戦前から戦後にかけての作家たちの交友関係が自分の頭の中でできあがって、そして動いていく感じがとても楽しい。
これ一冊読んでどうこういう筋合いではないので次回はちゃんとした小説を読んでみたいです。
「僕が書いたあの島」-片岡義男-
 PickwickWebのどこかに、いつか書いたような気がするけれど、私にとって片岡義男のイメージは角川映画の原作であり本屋でずらりと赤い背表紙で、中学、高校の頃は、本棚に赤い表紙が並んでいるような人とは絶対に友達になりたくないと思ったものです。
PickwickWebのどこかに、いつか書いたような気がするけれど、私にとって片岡義男のイメージは角川映画の原作であり本屋でずらりと赤い背表紙で、中学、高校の頃は、本棚に赤い表紙が並んでいるような人とは絶対に友達になりたくないと思ったものです。
それがちょっと変わったのはちくま文庫から出ていた「エルヴィスから始まった」という初期のエッセイを読んでからで、それから気が向くと彼のエッセイを読むようになりました。さすがに「コミックを文章化した」という小説読みませんけどね。
片岡義男のエッセイのおもしろさというのは簡単にいうと、[1]豊富な知識を背景に持っている、[2]そこから自分なりの結論をきちんと出している、[3]その結論にたどり着くまでの道筋が論理的である、[4]題材によってさまざまな表現形式を用いている、ということでしょうか。適当ですが。
サーフィンとハワイについて書かれたこの本について、そのどちらにも興味のない私としてはそれほど読んでみたいとは思っていなかったのですが、やはり読んでみるとおもしろくて、一気に読み終えてしまったという感じです。
「太陽 特集:金子光晴 アジア漂流」(1997年4月号)
 あっ、というまに今日から9月。「September Song」じゃないけれど、9月になったと思うとすぐにクリスマスになってしまう、のかな。
あっ、というまに今日から9月。「September Song」じゃないけれど、9月になったと思うとすぐにクリスマスになってしまう、のかな。
先週の終わりくらいからいろいろやることがあって3時、4時くらいまでパソコンの前に座ってたのですが、歳をとったせいかやっぱりだるい。会社に泊まって仕事して明け方明るくなってくるころにそのままいすを並べて寝たり、終電まで働いて朝まで飲んでそのまま会社に行く、なんてもうできないなぁとしみじみ思ってしまいます。というか、できればそういう生活はしたくないです。
といいつつも先週金曜日から渋谷の東急でやっている古本市に会社帰りに寄ってみたりして。金子光晴については私は全然知らないし、たぶんこれからも詩なんて読むことはないだろうけれど、本屋でたまたま「どくろ杯」「ねむれ巴里」という本を見つけて以来、この2冊は私の「いつかちかいうちに読む本のリスト」に加わっています。でもこの雑誌を古本市で見つけて「次に読みたい本のリスト」に加わることになりました。
「旦那の意見」-山口瞳-
 それほど多くの本を読んでいるわけではないけれど、今まで読んだ山口瞳の本の中で一番読みごたえがあった。それは本人があとがきにも書いているように川端康成と田中角栄に関する文章が“芯”となっているから。
それほど多くの本を読んでいるわけではないけれど、今まで読んだ山口瞳の本の中で一番読みごたえがあった。それは本人があとがきにも書いているように川端康成と田中角栄に関する文章が“芯”となっているから。
はじめの方に収録されている随筆は「男性自身」などの作品とかわりはないけれど、本を読み進めていくうちに気がつくとどんどんシリアスな方向に話が進んでいきます。しかもその移行があまりにもスムーズなことと、シリアスな話を書いているときにも山口瞳特有のユーモアは失われていないので読者は本を読み終わった後に「いつのまにかそんなところにきてしまった」ということに気がつくのです。
山口瞳に関しては軽いものだけでいいかなと思っていたけれど、シリアスな作品といわれている「血族」も読みたくなりました。そしてこういう作品があるからこそ「男性自身」のような文章をまた違った気持ちで読むことができるのだと思います。
「たろうのともだち」-堀内誠一-、「喫茶店百科大図鑑」-沼田元氣-
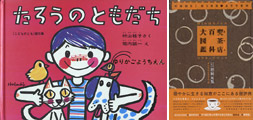 昨日は福生の横田基地友好祭に行ったので今日は家でのんびり掃除や洗濯をして夕方から吉祥寺へ。いまだにアーケードのないサンロードになじめません。まずはKuu Kuuで遅い昼食(or早い夕食)をとった後、古本屋やレコード屋、カルディなど、8時くらいまで歩き回りました。夏の散歩は夕方~夜に限りますね。
昨日は福生の横田基地友好祭に行ったので今日は家でのんびり掃除や洗濯をして夕方から吉祥寺へ。いまだにアーケードのないサンロードになじめません。まずはKuu Kuuで遅い昼食(or早い夕食)をとった後、古本屋やレコード屋、カルディなど、8時くらいまで歩き回りました。夏の散歩は夕方~夜に限りますね。
さて、「たろうのともだち」は中央線の高架下にあるりぶろりべろで購入。ここはなにが特徴というわけではないけれど、たまに行くと「おっ」と思う本が見つかる本屋さん。なにげに絵本とか雑誌とかもたくさんあるし・・・・。
話かわってヌマゲンは喫茶店(カフェ)の本を出し過ぎたと思うのだけどどうでしょうか。いろいろな書くことがあったんだろうなぁともこういう切り口で一冊本を作ったら、なんて考えてるうちに何冊にもなってしまったのはよく分かります。でもいっぱい書くことがある中であえて一冊しか出さない、というのが粋なのではないか、なんて勝手に思うのは、単に私が「買おうかな」と迷っているうちにどんどん出てしまって追いかけられなくなってしまったせいです。すみません。
こちらは家でコーヒーを飲んだり、散歩するときに持っていったりしつつのんびり読むことにします。
「愛ってなに?」-山口瞳-
 「愛ってなに?」なんて言われても出てくるのは定年間近の会社の部長や成功したデザイナー、ジャーナリストたちの浮気話(主に昔話)ばっかり、ということで読み終わる頃にはちょっと飽きてきてしまいました。
「愛ってなに?」なんて言われても出てくるのは定年間近の会社の部長や成功したデザイナー、ジャーナリストたちの浮気話(主に昔話)ばっかり、ということで読み終わる頃にはちょっと飽きてきてしまいました。
今週も曇り空ばっかりでなんだか気が重い気分のまま過ごしているんですけど、暑かったら暑いで「暑すぎてだるい」なんて言い出しそうなのでこれはこれでいいのかもしれません。雨さえ降らなければね。
そういえば夏休みの一日目にタワーレコードに行って、今年の夏のBGMを探してみたんですけど、どうも気持ちが盛り上がるようなCDがなくて、しょうがないのでノーナリーヴスの新しいアルバムを試聴してみたらいきなり「人生で最高の夏!」みたいな歌詞が飛び出してきて一気に気持ちがさめてしまいました。これまでも「夏だからはじけよう」みたいな夏は過ごしてこなかったけれど、30歳過ぎるとほんとにそんな気分から遠くなってしまって、もう「人生で最高の夏!」なんて思えるような夏を過ごすこともないんだろうなぁ、なんて思ってしまいます。別につまらない毎日を過ごしているわけではないけれど、かといって「今が最高!」なんて口が裂けても言えないわけですよ。
で、そうなると当然私の人生のうちで最高の夏はいつだったのだろうか、という疑問も湧いてくるわけなんですけど、いつだったんでしょうねぇ・・・・。
