 気がつけば前回書いてから一週間経ってしまってました。はやいねぇ。
気がつけば前回書いてから一週間経ってしまってました。はやいねぇ。
常盤新平の本は高校生の頃よく読んでいました。多分、海外文学の本を選ぶ基準として初めて意識した翻訳家かもしれません。でも翻訳家として有名な割には作品としてはアーウィン・ショーと「大雪のニューヨークを歩くには」くらいしか思い浮かばないんですけどね。それよりも20年代のアメリカや「ニューヨーカー」についてなどのエッセイのほうが記憶に残ってます。
「東京の小さな喫茶店」は、彼がむかし通った喫茶店の思い出をつづったもの。私は行ったことのない喫茶店ばかり、そして今ではなくなってしまったお店もたくさん出てくるだけれど有名なお店なのでしょうか。よく分かりません。でも基本的に彼がその店にかよっていた頃の喫茶店での(あるいは自身に起きた)出来事や喫茶店の店長の話(喫茶店をはじめたきっかけとか、どんなふうに、どんな気持ちで喫茶店を営んでいたとかなど)が中心となっているので、そのお店自体を知らなくても楽しめます。
私は彼のように自由業ではないので気が向いたらとか気分転換にちょっとコーヒーを飲みに行く、なんてことはできないけれど、朝、会社に行く前の30分だったり、お昼休みだったり、会社を出て家に帰るまでのあいだだったり、一日のうちで一回でいいからそういう自分の気持ちをリセットできるような時間があればいいと思います。今のところそれは家に帰ってご飯を食べた後、ゆっくりとコーヒーを淹れる時間になるのかな。自分でゆっくりお湯を落としていくときが好きなんで、ただコーヒーを飲むというよりその前に淹れるというのが私にとっては大切だったりします。

 昔は一つの雑誌を好きになると内容も見ずに発売日になると本屋に行って、もしそれがあまりおもしろくなかったとしても「次に期待」という感じで雑誌を買っていました。でもいつのまにか毎月絶対買うという雑誌もなくなってしまってなんだか寂しいような、「いや欲しい雑誌がないのが悪いのよ」となかば開き直りのような態度をとってます。
昔は一つの雑誌を好きになると内容も見ずに発売日になると本屋に行って、もしそれがあまりおもしろくなかったとしても「次に期待」という感じで雑誌を買っていました。でもいつのまにか毎月絶対買うという雑誌もなくなってしまってなんだか寂しいような、「いや欲しい雑誌がないのが悪いのよ」となかば開き直りのような態度をとってます。 「コラージュ日記」が発売されているせいもあって、最近また植草甚一の本を読み返してみようかなぁ、なんて思っているのだけれど、10代や20代の頃に聴いて置くべき音楽や読んでおくべき本、観ておくべき映画・・・・というものがやっぱりあって、植草甚一の本は私にとってそれにあたっていて、30代半ばにして植草甚一の本を読みふけるというのは健全でない気がしてしまう。あの知識の多さや生き方はどう考えても若い頃に憧れるものだと思う。それを30過ぎまで引きずってしまうのはどうなんだろう。かといってノスタルジックな気分で読むのも納得がいかないし・・・・なんてことを考えて迷ってるところ。
「コラージュ日記」が発売されているせいもあって、最近また植草甚一の本を読み返してみようかなぁ、なんて思っているのだけれど、10代や20代の頃に聴いて置くべき音楽や読んでおくべき本、観ておくべき映画・・・・というものがやっぱりあって、植草甚一の本は私にとってそれにあたっていて、30代半ばにして植草甚一の本を読みふけるというのは健全でない気がしてしまう。あの知識の多さや生き方はどう考えても若い頃に憧れるものだと思う。それを30過ぎまで引きずってしまうのはどうなんだろう。かといってノスタルジックな気分で読むのも納得がいかないし・・・・なんてことを考えて迷ってるところ。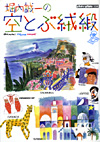 このところ暇さえあれば古本屋に寄っているという感じなので(昔からか?)、ネットで本を注文することもなかったのだけれど、欲しい本があったのでいくつか注文してみました。やっぱり欲しい本が決まっているときはネットは便利ですね。
このところ暇さえあれば古本屋に寄っているという感じなので(昔からか?)、ネットで本を注文することもなかったのだけれど、欲しい本があったのでいくつか注文してみました。やっぱり欲しい本が決まっているときはネットは便利ですね。 カフェブームというものがいつから始まったのか、そしてもう終わってるのか、続いてるのか、よく分かりませんが、2000年に発行されたこの本を読んでいると「ブームの前から」という言葉が何回も出てきて、特に感慨もないけれど「ブームだったんだなぁ」と思ってしまいます。そういえばこの本を前後していくつもカフェの本が出たものだけれど、最近はあまり話題にならないような気がしますね。単にチェックしてないだけかな。
カフェブームというものがいつから始まったのか、そしてもう終わってるのか、続いてるのか、よく分かりませんが、2000年に発行されたこの本を読んでいると「ブームの前から」という言葉が何回も出てきて、特に感慨もないけれど「ブームだったんだなぁ」と思ってしまいます。そういえばこの本を前後していくつもカフェの本が出たものだけれど、最近はあまり話題にならないような気がしますね。単にチェックしてないだけかな。 前の会社で仲の良かった人が会社を辞めることになったので、金曜日の夜に送別会に行って来ました。30人弱の小さな会社なのですが、送別会に出席した人数は27人。その内半数近くがすでに辞めてしまった人という状態。来れない人からは電話があったりして「変わんないなぁ」なんて思いながら久しぶりに酒を飲みつつ、「●●(会社名ね)はこれからこういう方向で進んでいくべき」とか「どういう風に仕事をするべき」とか「Webのデザインはどうあるべきか」なんてことをもう辞めてしまった人たちどうしで話したりして、よく考えるとなんだか変な光景でした。
前の会社で仲の良かった人が会社を辞めることになったので、金曜日の夜に送別会に行って来ました。30人弱の小さな会社なのですが、送別会に出席した人数は27人。その内半数近くがすでに辞めてしまった人という状態。来れない人からは電話があったりして「変わんないなぁ」なんて思いながら久しぶりに酒を飲みつつ、「●●(会社名ね)はこれからこういう方向で進んでいくべき」とか「どういう風に仕事をするべき」とか「Webのデザインはどうあるべきか」なんてことをもう辞めてしまった人たちどうしで話したりして、よく考えるとなんだか変な光景でした。 山口瞳の本は、電車の中はもちろんちょっとした時間ができるたびにちょこちょこ読んでいって、まだ何冊もあるしね、なんて思いつつすぐに読んでしまいます。といっているうちに文庫本を読み尽くしてしまうのかな。
山口瞳の本は、電車の中はもちろんちょっとした時間ができるたびにちょこちょこ読んでいって、まだ何冊もあるしね、なんて思いつつすぐに読んでしまいます。といっているうちに文庫本を読み尽くしてしまうのかな。 私は別に懐古的ではないと思うけれど、年末が近づく頃になると日本的な文章が読みたくなってしまい、20代の頃でも普段はアメリカやラテンアメリカの作家の本ばかり読んでいるのに、12月になると池波正太郎の本ばかり読んでいました。この「私の浅草」もその頃から読みたかった本で、でも「暮らしの手帖」+「昔の浅草」+「沢村貞子」というストレートな組み合わせが恥ずかしくて買うことができませんでした。
私は別に懐古的ではないと思うけれど、年末が近づく頃になると日本的な文章が読みたくなってしまい、20代の頃でも普段はアメリカやラテンアメリカの作家の本ばかり読んでいるのに、12月になると池波正太郎の本ばかり読んでいました。この「私の浅草」もその頃から読みたかった本で、でも「暮らしの手帖」+「昔の浅草」+「沢村貞子」というストレートな組み合わせが恥ずかしくて買うことができませんでした。 休日に遊びに行くちょっと前だとか寝る寸前の時間とかに少しずつ読んでいた「最低で最高の本屋」が読み終わってしまった。基本的に読みやすい文章だし、それほど厚い本でもないので一気に読んだらすぐに読めてしまうのだろうけれど、なんだかすぐに読んでしまうのがもったいないという気分になってしまうのはなんでなのでしょうか?
休日に遊びに行くちょっと前だとか寝る寸前の時間とかに少しずつ読んでいた「最低で最高の本屋」が読み終わってしまった。基本的に読みやすい文章だし、それほど厚い本でもないので一気に読んだらすぐに読めてしまうのだろうけれど、なんだかすぐに読んでしまうのがもったいないという気分になってしまうのはなんでなのでしょうか? 庄野潤三が奥さんと神戸を訪ね、市内を歩いたり、食事をしたり、さまざまなところを見物したりするという内容で、これといったストーリーはなく作者が私の「神戸物語」というように、同行する芦屋に住む妻の叔父夫妻と、作者の大阪外語学校時代の同級生で新聞社を停年退職したばかりの生粋の神戸っ子・太地一郎、作者の米国留学が縁でその息子たちと知り合った香港出身の貿易商の郭さん夫妻に証言を織り込んだ神戸案内と言えます。なのでそれぞれにとっての神戸であり、全体的なテーマなどがあるわけではありません。
庄野潤三が奥さんと神戸を訪ね、市内を歩いたり、食事をしたり、さまざまなところを見物したりするという内容で、これといったストーリーはなく作者が私の「神戸物語」というように、同行する芦屋に住む妻の叔父夫妻と、作者の大阪外語学校時代の同級生で新聞社を停年退職したばかりの生粋の神戸っ子・太地一郎、作者の米国留学が縁でその息子たちと知り合った香港出身の貿易商の郭さん夫妻に証言を織り込んだ神戸案内と言えます。なのでそれぞれにとっての神戸であり、全体的なテーマなどがあるわけではありません。