 小沼丹の本は以前ランカウイ島に行ったときに、「小さな手袋」や「懐中時計」など講談社文芸文庫から出ているものを集めて持っていって、空港や飛行機の中、ホテルの部屋やプールサイドで読み続けたのだけれど、小沼丹の本は手に入りにくいだけにいっぺんに読んでしまうのはもったいなかったな、という気もするし、あれは贅沢な時間だったという気もする。
小沼丹の本は以前ランカウイ島に行ったときに、「小さな手袋」や「懐中時計」など講談社文芸文庫から出ているものを集めて持っていって、空港や飛行機の中、ホテルの部屋やプールサイドで読み続けたのだけれど、小沼丹の本は手に入りにくいだけにいっぺんに読んでしまうのはもったいなかったな、という気もするし、あれは贅沢な時間だったという気もする。
で、最近になって新刊として出ていることを知ったこの作品はなんと推理小説。といってもそれほど深刻でないところがこの人らしい。推理よりも登場人物の性格や行動に重点が置かれています。
話は変わって、うちの会社は禁煙なので3階のテラスでたばこをすっていて、私はたいてい午前中は10時半くらい、午後は3時くらいと5時前くらいに、たばこをすいに外にでます。ついこの間までは5時になると外は真っ暗だったものですが、最近は明るくなってきましたね。まぁ寒いことは寒い。コートを着ていくわけにもいかないので、ほんとたばこ一本分くらいしか外にはいられない感じです。
小学生の頃、夏至は6月なのに暑いのは8月で、冬至は12月なのに寒いのは2月なのはなぜなんだろうと思ったことなどを思い出しながらたばこを吸ってます。今考えると「日照時間が長い」=「暑い」とならないことは明らかなんですけどね。そうじゃないとフォンランドの夏は猛暑になってしまうわけで・・・・。

 週末はなんかだらだら過ごしてしまったなぁ、という感じなのだけれど、相変わらず歩き回ったのでなんとなく筋肉痛気味で今週もスタート。
週末はなんかだらだら過ごしてしまったなぁ、という感じなのだけれど、相変わらず歩き回ったのでなんとなく筋肉痛気味で今週もスタート。 金曜日は会社が終わってから大森で新年会。8時待ち合わせ。残業はしない予定なので6時過ぎに会社を出れば大森近辺で1時間くらいのんびりできるかな、駅前に古本屋とかないかな、お茶する時間はないだろうけどいい感じの喫茶店とかあるかな、事前にネットでいろいろ調べなくちゃね、などと思いつつ週の真ん中を過ごしてきたのだが、こういう日に限ってめずらしく6時から来客、打ち合わせ。結局、遅刻。
金曜日は会社が終わってから大森で新年会。8時待ち合わせ。残業はしない予定なので6時過ぎに会社を出れば大森近辺で1時間くらいのんびりできるかな、駅前に古本屋とかないかな、お茶する時間はないだろうけどいい感じの喫茶店とかあるかな、事前にネットでいろいろ調べなくちゃね、などと思いつつ週の真ん中を過ごしてきたのだが、こういう日に限ってめずらしく6時から来客、打ち合わせ。結局、遅刻。 「どこ吹く風」というのは、ここに出てくる女の人たちをさしているのではないか、という高橋呉郎の解説での言葉が本を読み進めるうちに胸に重くのしかかってくるような短編集。
「どこ吹く風」というのは、ここに出てくる女の人たちをさしているのではないか、という高橋呉郎の解説での言葉が本を読み進めるうちに胸に重くのしかかってくるような短編集。 「ku:nel」は、号を追うごとに「都会を離れて田舎でのんびり暮らそう」みたいな雑誌になっていくような気がします。確かに東京で自分のペースで暮らしてる人ってそんなにいないのだろう。ここに出てくる人もたいていがフリーで、しかも雑誌の性格上女の人がほとんどだ。
「ku:nel」は、号を追うごとに「都会を離れて田舎でのんびり暮らそう」みたいな雑誌になっていくような気がします。確かに東京で自分のペースで暮らしてる人ってそんなにいないのだろう。ここに出てくる人もたいていがフリーで、しかも雑誌の性格上女の人がほとんどだ。 表題の「ネクタイの幅」は、普段スーツを着る機会のない永井龍男が、たまに背広を着て出かけると「そのネクタイいいですね」とほめられる。でもそのネクタイはもう20年も前から使っているもの。それをあまりにもそれをほめられるので、ちょっと恥ずかしい気分になってしまう。
表題の「ネクタイの幅」は、普段スーツを着る機会のない永井龍男が、たまに背広を着て出かけると「そのネクタイいいですね」とほめられる。でもそのネクタイはもう20年も前から使っているもの。それをあまりにもそれをほめられるので、ちょっと恥ずかしい気分になってしまう。 先週はちょこちょこと本を買ったので、ここの更新ができるなと思っていた割には、金、土と飲みに行ってしまったこともありなかなか更新できず。
先週はちょこちょこと本を買ったので、ここの更新ができるなと思っていた割には、金、土と飲みに行ってしまったこともありなかなか更新できず。 吉田健一の小説は全部絵空ごとである、なんて言いつつ、でも吉田健一の小説のおもしろさはただそういうストーリーを追うところ以外にあり、また小説というのは結局のところどれも絵空ごとに過ぎないという吉田健一のメッセージもこめられているんだ、といったことはきっとどこかで誰かがもっと説得力のある文章で書いているだろうから、私が書いてもしょうがないわけなのだけれど、それとは関係ないことかもしれないが、とりあえずある本を読んでいるとその本を読んでいるその合間はなぜかその作者の文体で考えてしまうということで、ついこんな長い文章を書いてしまうわけです。
吉田健一の小説は全部絵空ごとである、なんて言いつつ、でも吉田健一の小説のおもしろさはただそういうストーリーを追うところ以外にあり、また小説というのは結局のところどれも絵空ごとに過ぎないという吉田健一のメッセージもこめられているんだ、といったことはきっとどこかで誰かがもっと説得力のある文章で書いているだろうから、私が書いてもしょうがないわけなのだけれど、それとは関係ないことかもしれないが、とりあえずある本を読んでいるとその本を読んでいるその合間はなぜかその作者の文体で考えてしまうということで、ついこんな長い文章を書いてしまうわけです。 獅子文六の小説はどれもテレビのホームドラマの小説版といった感じなのだが、これが昭和12年に書かれたもの打と思うと許せてしまいます。続けて読もうとは思いませんが・・・・。
獅子文六の小説はどれもテレビのホームドラマの小説版といった感じなのだが、これが昭和12年に書かれたもの打と思うと許せてしまいます。続けて読もうとは思いませんが・・・・。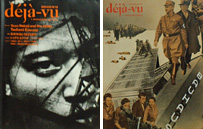 今日からミオ犬が長崎に帰省中。というわけではないけど、昼は中央線沿いを歩き回り夜は会社の友達と「バー部(イクラじゃないよ)」で浅草のフラミンゴバーへ。
今日からミオ犬が長崎に帰省中。というわけではないけど、昼は中央線沿いを歩き回り夜は会社の友達と「バー部(イクラじゃないよ)」で浅草のフラミンゴバーへ。