 一冊買うとついまた買ってしまうという悪い癖が・・・・。でも5冊揃えようとしない、あるいは揃わないのも悪い癖とも言えるかな・・・・。ちなみに某古本屋さんでは5冊セットで12500円で売ってました。
一冊買うとついまた買ってしまうという悪い癖が・・・・。でも5冊揃えようとしない、あるいは揃わないのも悪い癖とも言えるかな・・・・。ちなみに某古本屋さんでは5冊セットで12500円で売ってました。
昨日、今日と吉祥寺、月窓寺の盆踊り。ここ数年行っていなかったなぁと思っていたのですが、3年ぶりということ。なんだやってなかったのね。でも3年ぶりで集まりが悪かったのか知りませんが、あまり縁日とかも出ていなくてちょっと寂しい。
前はタイカレーのお店やミスタードーナッツとかその他いろいろサンロードのお店が屋台を出していたのに、今年は焼きそばも売ってなくて、中央で音楽の一足先に踊り方を教えるおじさんのマイクの声だけが盛り上げそうとしているような感じ。日曜だからかな、昨日だったら盛り上がってたのかな?よく分かりませんが来年に期待!ということで。
そういえば通りがかりにちらっとテントの中をのぞいたら盆踊りのレコード(シングル盤)をテクニクスのプレーヤーでかけてました。しかもその横にはCDJが2台置いてあった。どういうことなんだろう?曲の間が空かないように頭出しとかしてるのだろうか?もしくは曲と曲のあいだにスクラッチが入ったりして!?
話は戻って、昼間は暑い中、中目黒・代官山散策。朝起きたときちょっと曇ってたような気がしたので、思いきっていってみたのだが、単なる気のせいだったらしく、歩いているとものすごく暑い。ひとりで代官山に行ったときはたいていeau cafeかオーガニックカフェに行く。ほかのところはどうもきれいすぎて一人だと落ち着かないし、そもそも入り口からして一人で入る雰囲気ではないような気がしてしまう。たばこがすえればオクラがベストなんだが・・・・。
それでも周りと見渡せば女の子しかいない店内で、一人、本を読みながらクロックムッシュを食べアイスコーヒーを飲んでいる35歳男はいかがなものか?お店にとってもちょっと遠慮して欲しい、ドトールとか行って欲しい、などと思われているのだろうか?
ところでeau cafeは、8月31日まで江ノ島の海岸でbeach house eau cafeという海の家をやっているとのこと。夕方からライブやDJイベントもあるらしいので、ちょっと行ってみたい気もする。でも「これ!」というイベントが見あたらないんだよなぁ。

 堀江敏幸の「郊外へ」を知り合いに借りて読んだときの気持ちは忘れられない。現実と虚構とそして史実をの垣根を軽やかに飛び越えて行き来し、そしてそれらが絡み合い緻密に組み立てられた構成の前に、僕はその世界にただ夢中になり、ただため息をつくしかないという感じでした。
堀江敏幸の「郊外へ」を知り合いに借りて読んだときの気持ちは忘れられない。現実と虚構とそして史実をの垣根を軽やかに飛び越えて行き来し、そしてそれらが絡み合い緻密に組み立てられた構成の前に、僕はその世界にただ夢中になり、ただため息をつくしかないという感じでした。 ツイデニ、コンナホンモ、カッテミマシタヨ。
ツイデニ、コンナホンモ、カッテミマシタヨ。 で、予告どおり山口瞳。といってもこの本についてのコメントはなし。一つ引用するとすれば・・・・
で、予告どおり山口瞳。といってもこの本についてのコメントはなし。一つ引用するとすれば・・・・ 2冊続けて山口瞳。実は今読んでるのも山口瞳の本。なぜかといえば、ストックしてある本が山口瞳しかなくなってしまったから。
2冊続けて山口瞳。実は今読んでるのも山口瞳の本。なぜかといえば、ストックしてある本が山口瞳しかなくなってしまったから。 2カ月なんてすぐに経ってしまう。前の号が出たのが引越しする直前だったのでこの部屋に来てからもう2カ月になるわけで。時間が過ぎていくのは早いことは早いんだけれども、久我山4丁目に住んでいたときのことなんてかなり前のことのように感じられてしまう。ましてや三鷹台に住んでいた頃なんてね・・・・。
2カ月なんてすぐに経ってしまう。前の号が出たのが引越しする直前だったのでこの部屋に来てからもう2カ月になるわけで。時間が過ぎていくのは早いことは早いんだけれども、久我山4丁目に住んでいたときのことなんてかなり前のことのように感じられてしまう。ましてや三鷹台に住んでいた頃なんてね・・・・。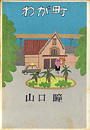 「たとえば一軒の床屋があって、日曜日にそこへやってくる高校生からおじいさんにいたるまでのひとが、順番を待ちながら、のんびりと一回分だけ読んでくれるというような小説を書きたいと思ってこれを書いた」・・・・というようなことが帯に書いてあって、それいゆに置いてある「西荻カメラ」を思い出したりした。
「たとえば一軒の床屋があって、日曜日にそこへやってくる高校生からおじいさんにいたるまでのひとが、順番を待ちながら、のんびりと一回分だけ読んでくれるというような小説を書きたいと思ってこれを書いた」・・・・というようなことが帯に書いてあって、それいゆに置いてある「西荻カメラ」を思い出したりした。 永井龍男は新聞の隅に見つけたなにげない小さな事件の記事をスクラップにして置いて、その事件を何年もかけて少しずつ頭の中でふくらませて一つの短編小説を作るという。
永井龍男は新聞の隅に見つけたなにげない小さな事件の記事をスクラップにして置いて、その事件を何年もかけて少しずつ頭の中でふくらませて一つの短編小説を作るという。 今年はお休みやお金、その他もろもろの理由から旅行なんて行けそうにないくて、しかも次の旅行先がパリという確立は割と低いと思うんですが、本屋で見つけてつい買ってしまいました。今から割と欲しかったんですよ。
今年はお休みやお金、その他もろもろの理由から旅行なんて行けそうにないくて、しかも次の旅行先がパリという確立は割と低いと思うんですが、本屋で見つけてつい買ってしまいました。今から割と欲しかったんですよ。 自分の生涯について振り返り語った本。「話し言葉で読みやすいなぁ」と思っていたら本当に里見弴がしゃべった言葉を速記して文字に起こした後、自身によって赤を入れるという方法で書かれたということ。よく考えれば、里見弴は1888年に生まれて1983年に亡くなっているのでこの本が出た1972年ではすでに80歳を越えてるんですよね。子供の頃、お盆などで田舎に帰ったときに縁側でお菓子かなんか食べながらおじいさんの昔話を聞いているって感じです。なんて言ったら失礼か!
自分の生涯について振り返り語った本。「話し言葉で読みやすいなぁ」と思っていたら本当に里見弴がしゃべった言葉を速記して文字に起こした後、自身によって赤を入れるという方法で書かれたということ。よく考えれば、里見弴は1888年に生まれて1983年に亡くなっているのでこの本が出た1972年ではすでに80歳を越えてるんですよね。子供の頃、お盆などで田舎に帰ったときに縁側でお菓子かなんか食べながらおじいさんの昔話を聞いているって感じです。なんて言ったら失礼か!