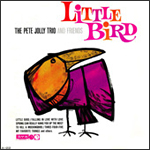◆2010年のちょっとしたまとめ
◆2010年のちょっとしたまとめ
死後にまとめられた随筆集。だからというわけではないと思うけれど、随筆集としてはかなり分量もあり、内容も能についてのものから交友録、釣りの話、身辺雑記までと幅広く収録されているので、一気に読むのではなくてもう少しゆっくりと、何冊かの本と並行して読むくらいのスピードで読めばよかった。複数の本を並行して読むという習慣があまりないので読み終えるまでぜんぜん気がつかなかったです。
ところでこの本で、今年の雑記は59冊目。あと残っているのは小西康陽の「僕は散歩と雑学が好きだった」と「電子音楽InThe(Lost)World」だけなので年内に全部書けないけれど、とりあえず61冊。去年読んだ本で今年に持ち越した本が10冊くらいあったので、読んだ本としては実質51冊くらい。去年は56冊くらい読んでいて、今年は70~80冊くらいは読みたいなと年始に書いてますが、70~80冊どころか減ってるという結果に‥‥。
ただ後半、写真集とか買うようになりましたが、雑誌とかもまったく買ってないし、取り上げている本がほぼ小説ばかりと考えると、だいたい週に1冊読むか読まないかというペースなので、このくらいの分量がちょうどいいのかも、なんて思ったりもします。
来年もこのペースを保つとして小説を50冊、に加えて写真集やデザインの本などを15冊くらい、そのほか10冊くらいで合計70~80冊くらいに着地できるといいなと思いますね。どうなるのかわかりませんが。
それから今年の読書のテーマは“女性作家もしくは随筆家”としていたのですが、こちらもあまり達成できた感じではないです。一番読んだ森茉莉でさえ6冊、あと野上弥生子、萩原葉子が2冊、そのほかには室生朝子、佐多稲子、広津桃子、矢田津世子、増田れい子といったところになってます。年の初めにリストアップした読みたい作家の数に比べて消化数が少なかったのは、単に手に入らなかったから。そもそもリストアップした作家や作品が少なかったのに加えて、読んでもいないのに途中で自分の中での評価が変わってしまったりした作品もありましたしね。
これに限らず本やCDなどでなにかテーマを決めて買おうとするときは、一応、いろいろ調べてみて手帳にリストアップしておくのだけれど、たいていの場合、リストが多すぎて1/3くらいしか手に入れることができてません。
例えば正直なところモーグのCDを60枚近くリストアップしたって絶対全部手に入れることはできないし、そもそもそんなにモーグばかり聴くのか?と思うのだけれど、手に入れられる数が結果的に少なくてもピックアップだけはしておかないと、古本屋や中古レコード屋で探すときに記憶の網に残ってなくて、結局、少ないリストのそのまた半分くらいしか見つけられなかったりするものなんだな、とかなにを言いたいのかよくわからないどうでもいいことを考えたりしている年末、そうやって手に入れた本やCDの片付けがまったく進んでないうちに年が明けそうなんですけど‥‥。

 ◆12月にあいそうなピアノのCD
◆12月にあいそうなピアノのCD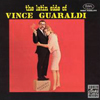 ■「ラテン・サイド・オブ・ガラルディ」(ヴィンス・ガラルディ)
■「ラテン・サイド・オブ・ガラルディ」(ヴィンス・ガラルディ)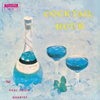 ■「カクテル・アワー」(ポール・スミス)
■「カクテル・アワー」(ポール・スミス)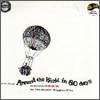 ■「80日間世界一周旅行」(ジェラルド・ウィギンス)
■「80日間世界一周旅行」(ジェラルド・ウィギンス)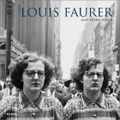 ◆ルイス・フォアの写真集とロンドンで撮った写真
◆ルイス・フォアの写真集とロンドンで撮った写真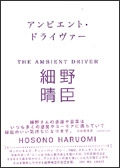 ◆12月はピアノのレコードを聴く。その1:「リトルバード」(ピート・ジョリー)
◆12月はピアノのレコードを聴く。その1:「リトルバード」(ピート・ジョリー)