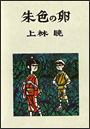 途中で会社を抜け出して、青山ブックセンターでやっていた堀内隆志のトークショーに行ってきました。店内の片隅で行われたのだけれど、思っていたよりも人が来ていて、しかもほとんどが女の子という中で、スーツ姿の男性が混じっていたりしてました。話の内容としては、最近出た「珈琲と雑貨と音楽と―鎌倉のカフェから“好き”をかたちに」に関連して、お店を始めたきっかけや開店したばかりのころのことなどが中心で、堀内さんって意外と話がうまいのだなぁなんて思ったりして‥‥。25、6歳の頃は、誰でもあいつより自分の方が知ってる、と思うときで、そのときだからこそカフェを始められた、という言葉が印象的でした。
途中で会社を抜け出して、青山ブックセンターでやっていた堀内隆志のトークショーに行ってきました。店内の片隅で行われたのだけれど、思っていたよりも人が来ていて、しかもほとんどが女の子という中で、スーツ姿の男性が混じっていたりしてました。話の内容としては、最近出た「珈琲と雑貨と音楽と―鎌倉のカフェから“好き”をかたちに」に関連して、お店を始めたきっかけや開店したばかりのころのことなどが中心で、堀内さんって意外と話がうまいのだなぁなんて思ったりして‥‥。25、6歳の頃は、誰でもあいつより自分の方が知ってる、と思うときで、そのときだからこそカフェを始められた、という言葉が印象的でした。
質問コーナーの途中で会社に戻ったのですが、カヌー犬ブックスもだらだらと3年間続けてしまってるなぁ、と反省。これからでも少しずついろいろやっていこう、なんてことを歩きながら考えてしまいました。そろそろまた鎌倉にも遊びに行きたいです。
月別: 2006年10月
「家族」-山口瞳-
 このところリリー・アレン「オーライ・スティル」ばかり聴いてます。MTVかなにかで初めて「スマイル」を聴いたときから、イギリスらしい、レゲエというには軽快なリズム感がいいなとは思っていたんだけど、結局アルバムを買ってしまった‥‥。お休みの日にこういう音楽を聴きながら朝食を食べて、そのあと映画を観に渋谷に行って、ついでに原宿まで歩いたり、洋服を見たり、カフェでお茶したり、小さなギャラリーでやっている展覧会を見たりしていると、なんだかイマドキの若者みたいだな、なんて思ってしまうのだけれど、実際の若い人がどんな休日を過ごしているかなんて知るよしもないです。でも西荻のそれいゆとかで遅い朝食を食べて、そのまま西荻、荻窪の古本屋をのぞいたりしつつ、高円寺の古書会館に行ったりしているよりは若者らしいんじゃないかな。だからどうしたということでもないけれど‥‥。
このところリリー・アレン「オーライ・スティル」ばかり聴いてます。MTVかなにかで初めて「スマイル」を聴いたときから、イギリスらしい、レゲエというには軽快なリズム感がいいなとは思っていたんだけど、結局アルバムを買ってしまった‥‥。お休みの日にこういう音楽を聴きながら朝食を食べて、そのあと映画を観に渋谷に行って、ついでに原宿まで歩いたり、洋服を見たり、カフェでお茶したり、小さなギャラリーでやっている展覧会を見たりしていると、なんだかイマドキの若者みたいだな、なんて思ってしまうのだけれど、実際の若い人がどんな休日を過ごしているかなんて知るよしもないです。でも西荻のそれいゆとかで遅い朝食を食べて、そのまま西荻、荻窪の古本屋をのぞいたりしつつ、高円寺の古書会館に行ったりしているよりは若者らしいんじゃないかな。だからどうしたということでもないけれど‥‥。
さて、前売りを買って、公開したらすぐにでも見に行こうと思っていたのに、なかなか行くことができなかったマイク・ミルズの「サムサッカー」を見てきました。親指を吸うクセが直らない17歳の少年を主人公にした物語で、「大切なのは、答えのない人生を生き抜く力。」という30代半ばのわたしにはちょっと青いテーマの作品なのだけれど、主人公の少年だけでなく、両親や先生、主人公が治療を受けている歯科医の先生など大人たちの心理もきちんと描かれているところが良かったです。舞台となる郊外の風景のいかにもサーバービアという感じもいいしね。イントロで映させれる風景の感じがなんだかホンマタカシっぽい。と思っていたら、マイク・ミルズとホンマタカシは友達なんですね。後で知りました。実をいうとマイク・ミルズについて断片的にしか知らないんですよ。
ついでに原宿まで歩いて、ドゥファミリィ美術館でやっている「WORKSHOP MU」の展覧会を見る。ドゥファミリィ美術館なんて行ったことがなかったのですが、思っていたよりも広くて、でも土曜日なのにお客さんは自分たち以外誰もいないという‥‥不思議な空間でした。「WORKSHOP MU」は、1970年代に小坂忠、細野晴臣、大滝詠一、はっぴいえんど、YMO、サディスティックミカバンドなどのレコードジャケットのデザインを手がけたデザイナー集団。そのうちの一人が現在、ドゥファミリィの役員をしていることから、ここで展覧会が開かれたらしい。なので、音楽関係のレコードジャケットやポスターだけでなく、その後の作品としてドゥファミリィの販促なども置いてありました。
個人的には、ナイアガラレーベル一連のオールディーズっぽいジャケットのイメージが強かったので、今回、細野晴臣とかYMOのジャケットも手がけていることを知ったり、特に大滝詠一のトレードマークとなっている(と思われる)丸い円の中で男女がキスしているイラストが、WORKSHOP MUによるもので、しかも大滝詠一だけではなく、サディスティックミカバンドのジャケットでも使われていたことにちょっとした衝撃を受けました。本も出ているので、近いうちに手に入れようと思ってます。
「ずばり東京」-開高健-
 アンソロジーなどに収録されていたものは別として、開高健の本を読むのは実は初めてだったりする。深夜タクシーや屋台のオデン屋、うたごえ喫茶、下水処理場‥‥など、1960年代前半、東京オリンピック前後の東京のあちらこちらに行き、そこにいる人の話を聞くという昭和38年10月~39年11月にかけて「週刊朝日」に連載されたルポタージュ。
アンソロジーなどに収録されていたものは別として、開高健の本を読むのは実は初めてだったりする。深夜タクシーや屋台のオデン屋、うたごえ喫茶、下水処理場‥‥など、1960年代前半、東京オリンピック前後の東京のあちらこちらに行き、そこにいる人の話を聞くという昭和38年10月~39年11月にかけて「週刊朝日」に連載されたルポタージュ。
あとがきで本人が書いているように、各章をさまざまな文体でかき分けていたりするので、どことなく習作っぽい雰囲気もあるけれど、それぞれの完成度は高いし、それによってより対象に迫っている感じで出ている面もあるので、前後の作品を読んでいないわたしには、この本が開高健の中でどういう位置にあるのかの判断は難しい。ただこの連載が終わった後に、連載終了の褒美として、朝日新聞の臨時海外特派員としてベトナム戦にいくことになったらしいので、ある意味、転機の作品と言えるのかもしれない、言えないのかもしれない。
そして確かに1960年代前半に、その当時の東京を取材したものではあるけれど、取材されている人々の話を読んでいると、実は2006年の今、同じような場所を同じように取材しても、大きな変化はないのではないか、と思ったりもする。確かに表面的な街の様子や人々の暮らしは変わっただろうけれど、実はそれは見かけだけなのかもしれない。いや適当。
そんなわけで、週末は、ラピュタ阿佐ケ谷でやっている倍賞千恵子特集の「下町の太陽」を見る予定だったのだが、10時半からの上映時間に間に合うように起きれず、断念。下町の工場を舞台に、下町長屋での生活を脱し、ホワイトカラーの団地生活を夢みる若者を描いた1963年、山田洋次監督作、ということで、山田洋次監督や倍賞千恵子にはそれほどひかれないけれど、この本と同じ1960年代初めの東京を描いた作品として比べてみるのもおもしろいのではないかと思ったのだ。映画だったらストーリーだけでなく当時の町並みも映像で見ることができるしね。21日までなのでチャンスはあと一回しかないのだが、はたして見れるかどうか‥‥。
「Krakel Spektakel Koper En Klubba」-レンナート・ヘルシング/スティッグ・リンドバーグ-
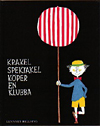 普段はそれほど気にしているわけではないけれど、先日、オイリ・タンニネンなどの絵本を買ったせいで、最近、古本屋さんに行くと必ず絵本コーナーをチェックするようになってしまいました。でも、うちでは絵本用のコーナーとなっている棚の1列が、もうすでに埋まってしまっていて、2月にパリに行ったときに買った本などはクローゼットのなかに無造作に置かれているという状態なので、実際に買うまではなかなかいたらないんですけどね。気持ち的には、今ある本を少し整理しつつ2段くらいは確保したい、けど、なかなかそうもいかないもので‥‥。そんなことを考えているうちに、ものの適正な量ってどこくらいなのだろう?なんてことを考えたりしてしまう。本は?レコードは?CDは?スノードームは?ファイヤーキングのマグは?スマーフ、フレッドくんグッズは?‥‥。ひとつひとつ考えていくとものすごく広い部屋に住まなくちゃいけないことになってしまうんだろうなぁ。現実的に絵本も含めて年末までにいろいろ部屋の中を整理したい、と思っている今日この頃です。
普段はそれほど気にしているわけではないけれど、先日、オイリ・タンニネンなどの絵本を買ったせいで、最近、古本屋さんに行くと必ず絵本コーナーをチェックするようになってしまいました。でも、うちでは絵本用のコーナーとなっている棚の1列が、もうすでに埋まってしまっていて、2月にパリに行ったときに買った本などはクローゼットのなかに無造作に置かれているという状態なので、実際に買うまではなかなかいたらないんですけどね。気持ち的には、今ある本を少し整理しつつ2段くらいは確保したい、けど、なかなかそうもいかないもので‥‥。そんなことを考えているうちに、ものの適正な量ってどこくらいなのだろう?なんてことを考えたりしてしまう。本は?レコードは?CDは?スノードームは?ファイヤーキングのマグは?スマーフ、フレッドくんグッズは?‥‥。ひとつひとつ考えていくとものすごく広い部屋に住まなくちゃいけないことになってしまうんだろうなぁ。現実的に絵本も含めて年末までにいろいろ部屋の中を整理したい、と思っている今日この頃です。
こんなところに書くのもなんですが、連休の最終日に熱を出して寝込んでしまったために、本の出荷が遅れてしまいました。申し訳ありませんでした。自分では昔に比べて健康になったと思っているのけれど、熱を出して寝込むのが今年3回目ということを考えると、あまり健康でもないのかもしれない。でも3回とも一晩寝た後の次の日には、普通に会社に行ったり、遊びに行ったりしているので、回復力は意外とあり。というか、寝込んでいるときはものすごい汗をかいたりして大変なのだけれど、あまりにも簡単に直ってしまうので、なんだか気が抜けてしまう。そもそもこれは風邪なのか?いや風邪なんだろうなぁ‥‥と。
「父の乳」-獅子文六-
 「娘と私」と対をなす作品。“父親と息子”をテーマに、10歳の時に亡くなった父親のおもかげを追いかけながら、自分の少年時代を描いた前半と、60歳になって初めて男の子の父親となり、「自分はこの子が10歳になるまで生きられるだろうか」と思いつつ、男の子が生まれたうれしさを描いた後半とで構成されている。そのあいだの出来事は「娘と私」という関係。
「娘と私」と対をなす作品。“父親と息子”をテーマに、10歳の時に亡くなった父親のおもかげを追いかけながら、自分の少年時代を描いた前半と、60歳になって初めて男の子の父親となり、「自分はこの子が10歳になるまで生きられるだろうか」と思いつつ、男の子が生まれたうれしさを描いた後半とで構成されている。そのあいだの出来事は「娘と私」という関係。
大正時代から昭和の初めにかけての横浜の様子を随所に入れ込んだ前半は、おもしろいのだけれど、遅く生まれた長男ということで、かわいくてしょうがないという気持ちが、あふれんばかりに出てしまっていたり、慶応の幼稚舎に子どもを入れるために奮闘したり、学校帰りに誘拐されないかと心配してみたり‥‥と、意図的なのかもしれないけれど、親バカぶりばかりが目立ってしまう後半には、ちょっと閉口してしまった。個人的には、後半部分は蛇足のような気もしないでもない。でも獅子文六としては後半の出来事が前半部分を思い起こす呼び水となっただけに、息子について書かずにいられなかった、というところなのかな。
「血族」-山口瞳-
 雑記を書かなくちゃなぁ、と思いつつ、なんだか9月はそんな余裕もなくて、いつのまにか10月に入ってしまいました。この本を読んだものもかなり前のこと。
雑記を書かなくちゃなぁ、と思いつつ、なんだか9月はそんな余裕もなくて、いつのまにか10月に入ってしまいました。この本を読んだものもかなり前のこと。
8月30日は山口瞳の命日だったので、その近辺に山口瞳の本を読もうと思っていたら、8月の中頃からCSで「血族」が放送されていて、ドラマなんてめったに見ないのに、めずらしく毎回見てしまい、ついには本のほうも読んでしまいました。
母方の親戚をたどっていって最終的には実家が女郎屋だったことを知るという、エッセイなどで何度もふられている内容なので、だいたいの事実関係や話の流れはわかるのですが、一つの作品の中で、ここまで執拗に追求する様子を読んでいると、気持ち的にはちょっとひいてしまう部分もあったりするけれど、ほっと肩の荷の降りるようなラストが用意されていて、今まで後回しにしていたのを後悔するくらいよかったです。わたしは年代順に本を読んでいるわけではないので分かりませんが、この「血族」の前後でエッセイの書き方が変わってしまっても不思議ではないと思う。
ドラマの方は、もとは1980年にHNKで放送された番組で、主演は小林桂樹。小林桂樹といえば、岡本喜八監督によって映画化された「江分利満氏の優雅な生活」でも、江分利満(≠山口瞳)を演じているだけに、どうしても山口瞳と同一視していまいます。もちろん小説とはすこし違うし、鬼気迫る様子がコメディっぽく見えてしまうところもある。特に会話の部分、本では独白との部分と会話がそのまま続いているので、気持ちの流れに違和感がないのだけれど、ドラマではナレーションが押さえられている分、普通に会話をしているときに急に小林桂樹が怒り出したりする場面が出てきてしまうので、単におかしな怒りっぽい人みたいな印象を受けてしまう。でもストーリーの流れとしては押さえるところは押さえてあって、ドラマ化としては及第点という感じかな。それよりもこんなドラマをNHKで放送していいのか、という気持ちになったりもするけど。
ミーハーなわたしとしては、つい横須賀に行ってみたいような、どうでもいいような‥‥。いや、テレビで見た柏木田の寂れた風景がなんとなくよかったんですよね。でも26年前の風景なのでかなり変わっているんだろうなぁ。
そういえば「居酒屋兆冶」のモデルになった国立のお店も9月で閉店しちゃったみたいですね。
