 6月に入ってから天気がまったく読めない‥‥。見るたびに天気予報も変わるので、当日の朝にならないと、はっきりわからない。というのはすでに“予報”ではないんじゃないかと思うがどうなんだろう?おまけに先日、関東の梅雨入りは間違っていました、というニュースまで出ていて、なんとなく梅雨が明けてからが夏というイメージがあったりするので、それじゃ、先週までの晴れは春?初夏?なんて思ってしまったり、昨日今日の雨は春雨?なんて思ってしまったり‥‥。
6月に入ってから天気がまったく読めない‥‥。見るたびに天気予報も変わるので、当日の朝にならないと、はっきりわからない。というのはすでに“予報”ではないんじゃないかと思うがどうなんだろう?おまけに先日、関東の梅雨入りは間違っていました、というニュースまで出ていて、なんとなく梅雨が明けてからが夏というイメージがあったりするので、それじゃ、先週までの晴れは春?初夏?なんて思ってしまったり、昨日今日の雨は春雨?なんて思ってしまったり‥‥。
そんなわけで、週末飲みに行ったときは、「明日は上野水上音楽堂でやるLOVERS FESTIVALに行くから雨が降らないといいなぁ。屋根はあるけど、一応野外だし‥‥」なんて言っていたのに、朝起きてみたら晴天で、それはそれでうれしいのだけれど、ここまで晴れなくても、という気分になった。出演者は、高橋健太郎、ChesterCopperpot、高橋徹也、朝日美穂、Chocolat & Akitoの5組。こう言ってはなんだけど、どこか懐かしいメンツ。ちゃんと今でも聴いてるのってChocolat & Akitoくらいか、というか、ショコラはあんまり聴いてないから、片寄明人くらいか。でもChocolat & Akitoの「Tropical」は良かったな。片寄明人のポップスを作る音楽家としてのいい面が出ていて、ロッテンハッツの「SMILE」、とりわけ「ノー・リグレッツ」を複雑な気持ちで聴いていた人間としては、感慨深いものがあります。それから片寄明人を音楽家として考えたことがこれまであまりなかったかも、ということにも気づかされたり、片寄明人がショコラにその「ノー・リグレッツ」を提供して、その後結婚したとき、山下達郎が、自分のアルバムと竹内まりや(あるいは、吉田美奈子、大貫妙子)のアルバムで、自分の音楽性を使い分けているように、グレイト3とショコラで使い分けていくのかな、と勝手な憶測をしていたな、なんてことも思い出したりしました。実際はぜんぜん違ったけれどね。もともと、一つの感情だけでなく対局にある感情や相反する感情、両方を一つの曲に入れたい、みたいなことを言っていたので、そんな風に簡単に切り分けられるものでもないのだろうと思うけれど、それより前に、そうやって職人のように使い分けられるほど器用な人でもないような気がします。これもわたしの勝手な憶測ですけどね‥‥。
ライブのほうは、ショコラのキーボードと片寄明人のギターのほかに、リトル・クリーチャーズの栗原務がドラムを担当。最小限のメンバーで片寄明人もギターを弾きまくるというタイプではないし、もちろんショコラもキーボードがうまいというわけではないのに、安定したいいライブに思えるのは、アレンジのセンスのせいなのか、栗原務のドラムがうまいせいなのか。それよりも片寄明人と栗原務に囲まれるとショコラの顔が小さいことが強調されすぎで、そればかり気になってしまいました。
カテゴリー: 未分類
「This Is Edinburgh」-Miroslav Sasek-
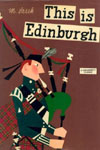 昨日は月に一度のイン・ザ・パシフィック。いつになく(失礼)人がたくさんいて盛り上がり、Heavenのスズキさんの誕生日当日ということで、最後にみんなでケーキを食べたりして、11時半くらいまでエッジエンドにいて、いつものように井の頭組でまとまって帰る。最近、下北周辺の人たちがタクシーで帰るので、井の頭組も少ない。ちょっと酔っていたので、本の発送作業などはやめにして(すみません)、慌ててお風呂に入って1時過ぎに寝た。
昨日は月に一度のイン・ザ・パシフィック。いつになく(失礼)人がたくさんいて盛り上がり、Heavenのスズキさんの誕生日当日ということで、最後にみんなでケーキを食べたりして、11時半くらいまでエッジエンドにいて、いつものように井の頭組でまとまって帰る。最近、下北周辺の人たちがタクシーで帰るので、井の頭組も少ない。ちょっと酔っていたので、本の発送作業などはやめにして(すみません)、慌ててお風呂に入って1時過ぎに寝た。
さて、今日はお弁当日ではなかったので(昨日帰ったのが遅かったせい?)、会社の人4人で、近くのレストランにパスタを食べに行く。飲み放題のドリンクを持ってきた後、パスタが出てくるまでいつものように他愛もない雑談していると‥‥。
「昨日は3時過ぎまで飲んでてタクシーで帰ったから今日はちょー眠い‥‥久々にやっちゃたよー」と机にあごを乗せそうなAさん。
「いやぁ昨日さぁ、麻雀やって4時くらいに家に帰ったら、部屋に入った床の上に奥さんが寝ててさ、布団はひいてあるんだけど、頭ぐらいしかたどり着いてないんだよ。どうやら酒を飲んで帰ってきてそのまま寝ちゃったらしいんだよね。で、起こしたあと、『酒癖が悪いんだからあんまり飲まないように』って一時間くらい説教しちゃったから、2、3時間しか寝てない‥‥」と、そもそも自分も4時帰りで、酔っぱらって帰ってバイクにひかれたことのあるBさん。
「それを言うなら昨日、旦那と飲みに行って帰ってきて、向こうがお風呂に入っている間についそのまま布団に入っちゃって、3時頃ふと起きたら、旦那は普通に隣で寝てて、自分は服着たままで、びっくりしちゃったよ。起こしてくれないんだよ。というか、起こしてくれたのに起きなかったのかもしれないから確かめられないけど‥‥」とCさん。
そんな話を聞きながら、11時半まで飲んでそのまままっすぐ帰って1時に寝るって、もしかしてかなり健全な生活なのでは‥‥と思うわたしでした。
「This Is Hong Kong」-Miroslav Sasek-
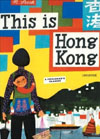 アマゾンのセールで安くなっているのを見つけてすぐに購入。ここでは取り上げていないけれど、最近、アマゾンでいろいろ買ってます。サセックの旅行絵本もいつの間にかたくさん復刊されていて、きちんと追い切れてないですね。今、何冊復刊されているのかなー。一時期の盛り上がりはなくなってきたと思うので、今でもきちんと買っている人はそんなにいないような気もしないでもないけど。復刊前は、洋書の古本屋さんや雑貨屋さんで、オリジナルの本がかなりの値段がつけられていたものですが、今でもそれなりの値段がつけられているのだろうか?わたしはオリジナルにこだわるほうではないし、このシリーズに関して言えば復刻版でも割ときちんとしているんじゃないかなと思ってるので、これはこれで満足です。まぁオリジナルを持っているわけではないので、細かい違いなどはわかりませんが‥‥。どちらにしろオリジナルにこだわる人と、復刻版で満足してしまう人のあいだには、どちらがいいかということではなく、その“もの”に対する関わりというか、姿勢に大きな違いがあるなーとは思います。
アマゾンのセールで安くなっているのを見つけてすぐに購入。ここでは取り上げていないけれど、最近、アマゾンでいろいろ買ってます。サセックの旅行絵本もいつの間にかたくさん復刊されていて、きちんと追い切れてないですね。今、何冊復刊されているのかなー。一時期の盛り上がりはなくなってきたと思うので、今でもきちんと買っている人はそんなにいないような気もしないでもないけど。復刊前は、洋書の古本屋さんや雑貨屋さんで、オリジナルの本がかなりの値段がつけられていたものですが、今でもそれなりの値段がつけられているのだろうか?わたしはオリジナルにこだわるほうではないし、このシリーズに関して言えば復刻版でも割ときちんとしているんじゃないかなと思ってるので、これはこれで満足です。まぁオリジナルを持っているわけではないので、細かい違いなどはわかりませんが‥‥。どちらにしろオリジナルにこだわる人と、復刻版で満足してしまう人のあいだには、どちらがいいかということではなく、その“もの”に対する関わりというか、姿勢に大きな違いがあるなーとは思います。
先日、「英国野郎」というイベントに行ったとき、終わってから友だちと飲みに行って、3時過ぎくらいまで音楽などの話をしたりしました。みんなだいたい同年代で、わたしのほかは、定期的にDJをやったりしている人たちだったのですが、全然レコード/CDにこだわっていなくて、DJのときは基本的に全部CDでかけてるという人や、オリジナルのUK盤でかけるということに意義があるという人、買うのはアナログ盤が主だけれどこすったりするので、全部CD-Rに焼いてから使っているという人などさまざまで、話を聞いていておもしろかった。
音楽や本は、最終的には曲が聴ければいいとか、内容が読めればいい、という側面があるだけに、人それぞれ考え方が大きく違ってしまうような気がします。今ならiTunesで音のデータだけダウンロードすればいいいう人も多いだろうと思うしね。
話は変わって‥‥。
週末、約2年ぶりに携帯を買い換えました。窓口で古い携帯から新しい携帯にデータを移すとき、「通常30分から1時間くらいかかるので、そのあいだ買い物などに出かけてきてもいいですよ」、と言われたのですが、実際に古い携帯に入っているデータを調べたところ、全然入ってなかったようで、5分くらいで終わってしまいました。そういわれてみると、携帯で写真を撮るということをほとんどしていないので、アドレスデータのほかに、データフォルダに入っているものといえば、2、3の待ち受け用の画像とYahoo!地図情報から落とした地図画像くらいなのだった。わざわざそんなものまで移動させる必要もなかったのですが、まぁ5分なら‥‥と。
携帯で写真を撮らないのは、カメラを持ち歩いているときは、あたりまえだけれど、それで撮るし、持ち歩いていないときも携帯で撮ってもなーと思ってしまうから。フィルムで撮ったり、デジカメで撮ったり、携帯で撮ったり、ポラロイドで撮ったり、できあがったメディアがバラバラになってしまうのが、なんとなく嫌なのだ。フィルムとポラくらいにしておかないと整理できないのですよ。
そういう意味で、音楽はできればCDのみでそろえたいし(でもレコードで持っていてCD化されてないものも結構あるんでしょうがない‥‥)、本も山口瞳は文庫でしか買わないとか、吉田健一は単行本でそろえたいとか、Dr.Seussのシリーズの新しい本は、表面がコーティングされていてつるつるした感じがいやなので、昔の本で買いたいとか思ったり、オリジナルかどうかなんかよりもそういうことが気になってしまう。う~ん、結局そういう結論なのかなぁ~?
「飲み・食い・書く」-獅子文六-
 もう金曜日かぁ‥‥今週はあっという間に過ぎてしまいました。5月に休日出勤した分の代休を月曜日にとって、日月と伊豆の温泉に行って、帰ってきてから4周年記念のプレゼントやページを作ったりして、13日は誕生日だったので、仕事中に会社の人が買ってきてくれたケーキを食べたりして、夜は久しぶりに渋谷のカンティプールでネパール料理をお腹いっぱい食べて、次の日も仕事中にケーキなんて食べたりしながら、夜は会社の人に誕生会を開いてもらって、帰ってきてからは、ちょっと酔っぱらったままプレゼントページをアップしたり、メルマガの準備をしたり‥‥。とうとう梅雨に入っちゃったな、なんて思っていたら今日は晴天で、週末はどうなんだろう?
もう金曜日かぁ‥‥今週はあっという間に過ぎてしまいました。5月に休日出勤した分の代休を月曜日にとって、日月と伊豆の温泉に行って、帰ってきてから4周年記念のプレゼントやページを作ったりして、13日は誕生日だったので、仕事中に会社の人が買ってきてくれたケーキを食べたりして、夜は久しぶりに渋谷のカンティプールでネパール料理をお腹いっぱい食べて、次の日も仕事中にケーキなんて食べたりしながら、夜は会社の人に誕生会を開いてもらって、帰ってきてからは、ちょっと酔っぱらったままプレゼントページをアップしたり、メルマガの準備をしたり‥‥。とうとう梅雨に入っちゃったな、なんて思っていたら今日は晴天で、週末はどうなんだろう?
4周年記念のプレゼントキャンペーンは、ほんとはオープンした10日から始めたかったのですが、なかなかプレゼントの内容が決まらず、ちょっと過ぎてしまいました。そもそもプレゼントなんてどうなのよ、という気持ちもあって去年はやらなくて、今年もいいかな、と思っていたのだけれど、5月の終わりにスキャナを修理に出したら、(当たり前だけれど)調子が良くなったので、たまには写真集でも作ってみようかなという気分になりました。で、写真集にパリの写真を入れることにしたので、パリに関係のあるものとしてモールスキンの手帳を、と。やはり(いいものかどうかは別として)オリジナルのものでないと気分的にやる意味がないような気がしますね。来年は5周年なので、トートバックとかちゃんとオリジナルグッズを作ってみたい。
それにしてももう4年も経っちゃったかぁという気持ちはあります。それにしては進歩があまりないけど‥‥。それでも続いてきたのは、ページを見てくれる人や喜んでくれる人がいるからで、注文時のコメントを読んで元気づけられたり、反省したり‥‥きちんと返事を書けてませんが、かなり励みになっています。皆さまありがとうございます。5年目もよろしくお願いします。
「老イテマスマス耄碌」-吉行淳之介、山口瞳-
 庄野潤三の「星に願いを」のときに「人間の晩年なんてこんな静かな心境じゃないでしょう」なんて書いてしまったけれど、歳をとって病気の話ばかり書かれるのもちょっとなぁ~と思う。この本は、ある意味軽い感じの対談集なので良いけれど、「男性自身」の最後の方は病気の話ばかりになってそうな気が‥‥(まだ「江分利満氏の優雅なサヨナラ 」は未読)。
庄野潤三の「星に願いを」のときに「人間の晩年なんてこんな静かな心境じゃないでしょう」なんて書いてしまったけれど、歳をとって病気の話ばかり書かれるのもちょっとなぁ~と思う。この本は、ある意味軽い感じの対談集なので良いけれど、「男性自身」の最後の方は病気の話ばかりになってそうな気が‥‥(まだ「江分利満氏の優雅なサヨナラ 」は未読)。
そういえば「おしまいのページで」だったか何人かの作家が順番にエッセイを書いている本で、一人が病気の話をし出すと、次に書く人がそれに対して自分の病気の話を書き出して、また別の人がそれに続く‥‥というすごいことになってたのを思い出しました。
ゴールデンウィーク前くらいに、中古レコード屋でスパイラル・ステアケースの「More Today Than Yesterday」の紙ジャケを見つけたので、なんとなく買ってiPodに入れて通勤の時に聴いてみたら、ちょうどお休み前だったし天気がよかったこともあって、すっかりはまってしまい、これから夏くらいまではソフトロックを聴いて過ごそうかな、なんて思いつつ、ユア・ソング・イズ・グッドの新譜を試聴しながら最近オルガンジャズとか聴いてないなぁとか、ディモンシュのフリペを読んでボサノバのCDがどんどん再発されてるみたいだしこれを機に集めちゃおうかなとか、スペシャでよく流れてるJUSTICEの「D.A.N.C.E.」を聴きながら、やっぱり今までにあまり聴いたことのないジャンルの音楽を聴きたいし今年はフレンチエレクトロか!‥‥なんて、相変わらず優柔不断な誕生日前30代後半男なのだった。
「東京っ子」-秋山安三郎-
 先日、会社で回覧されてきたPC関連の新聞(?)を読んでいたら、最近が読めない人が多くなってきている、というテーマのコラムが掲載されていました。そのコラムでは、漢字が読めなくなったその原因として、字を書かずにキーボードで打つようになったからということをあげる人が多いと、よく言われる理由をあげておいて、その後、昔の開発者たちが、いかにPCに2バイトの漢字をキーボードで打ち、画面で表示させるために努力したかということが、文章の4/5くらいに渡って書かれ、最後の最後に、「でも、漢字が読めなくなったのは、パソコンのせいではなく、テレビのせいだと思う。~」と、いきなりそれまでのことがなかったかのような理由を出してきてひっくり返してしまうという、業界に気を使った結論で笑ってしまいました。
先日、会社で回覧されてきたPC関連の新聞(?)を読んでいたら、最近が読めない人が多くなってきている、というテーマのコラムが掲載されていました。そのコラムでは、漢字が読めなくなったその原因として、字を書かずにキーボードで打つようになったからということをあげる人が多いと、よく言われる理由をあげておいて、その後、昔の開発者たちが、いかにPCに2バイトの漢字をキーボードで打ち、画面で表示させるために努力したかということが、文章の4/5くらいに渡って書かれ、最後の最後に、「でも、漢字が読めなくなったのは、パソコンのせいではなく、テレビのせいだと思う。~」と、いきなりそれまでのことがなかったかのような理由を出してきてひっくり返してしまうという、業界に気を使った結論で笑ってしまいました。
「東京っ子」は、前半で昔の東京の風習や風俗、暮らしについて、後半は戦時中に書かれた芝居についての文章が収録されてます。当時の演劇の様子はもちろん、出てくる役者の名前などがまったくわからないので、後半は、かなりちんぷんかんぷんで、実を言うと途中で読むのをあきらめてしまった。でも前半もわからない言葉が出てきたりしてあんまり理解できていないような気がするな。旧仮名遣いで書かれているわけではないのだけれど、読めない漢字もかなり出てくるし‥‥。いや、内容はおもしろいんだけどね。
でも「僕ら、私ら」は関西弁で、東京ッ子は「僕たち、私たち」というとか、東京ッ子は「かける」なんて言わない、「走る」と言う。なんて言われてしまうと、別に困らないけれど、なんだか困ってしまいます。ほかに「霧雨」は、関西では「きりさめ」、東京では「きりざめ」と濁る、「ド真ん中」など関西は「ド」をつけたがる、松茸は東京は「松だけ」と濁る‥‥といった言葉が例に挙げられてます。正しい言葉なんてないということはわかっているけれど、正しい日本語で話したり、書いたりするのには、その成り立ちや変遷までもわかっていないといけないのだな、と思ったりもします。う~ん、難しいなぁ~。
さて、わたしも含めて漢字を読めなくなったのは、パソコンのせいでも、テレビのせいでもなく、漢字を使わなくても普通に暮らしていけるからだ。特に不自由がなければ、無理して覚える必要もないし、覚えたとしても忘れやすいものだと思うのだけれど、どうなのだろう?適当。
「星に願いを」-庄野潤三-
 ミオ犬が図書館で借りてきた本。わたし的には晩年に近づいた夫婦の日常を描いた「貝がらと海の音」以降のシリーズは、あまり食指がのびないのだけれど、ちょうど小沼丹全集が出た頃を重なっていて、小沼丹についていろいろ書かれているということだったで読んでみることにしました。
ミオ犬が図書館で借りてきた本。わたし的には晩年に近づいた夫婦の日常を描いた「貝がらと海の音」以降のシリーズは、あまり食指がのびないのだけれど、ちょうど小沼丹全集が出た頃を重なっていて、小沼丹についていろいろ書かれているということだったで読んでみることにしました。
ここに書かれていることがすべてではないとしても、これほど作家として、ひとりの人として幸せな人生を送っている人も珍しいのではないだろうか。恵まれた環境で育ち、見かけ上は大きな苦労もないように見えるけれど(20代はじめの戦争に行く前の頃を描いた「前途」でさえ切実な暗さはないし)、実際は見えないところでものすごく努力をしていたり、意志の強い人なのだろう。朝日放送時代の庄野潤三は厳しい上司だったということを、誰かが書いているのをどこかで読んだこと記憶もある。
夫婦の日常が、まるでただ日記を書き写したかのようにさらり(だらり?)と描かれている感じのこの本でも、実は取り上げる出来事の取捨選択や、全体の流れ、ものすごく平易な言葉の一つ一つにも周到な計算されているように思う。あまりにも隙がない(あるいは隙間だらけ?)ので、読んでいて、これは実はフィクションなのではないか、という気さえしてしまうのはわたしだけではないはず。現実ではすでに奥さんも亡くなっていて、実は庄野潤三自身も病院に入院しながら病室でこれを書いているのでは、なんて、ひどいことまで思ったりしてしまうのは、単にわたしの性格がひねくれているだけですけど‥‥。いや、描かれている日常が平和で平坦過ぎてるので、人間の晩年なんてこんな静かな心境じゃないでしょう、と思ってしまうのですよ。庄野潤三がそういう作家ではないことは、わかっているのだけれど、その辺の葛藤とかがバックにまったく感じられないのもどうもどうかと。
さて、Rock yaというところで友だちがイベントやっていたので、夕方から高円寺に行って古本屋とかレコード屋とかをちょっとまわって、9時前くらいからで飲んだ。「英国野郎」というタイトルのイベントで、トニー・マッコウレイ系のハーモニーポップから、フーなどのビートバンド、ジャムやスミスなどのパンク、ニューウェイブ、そしてヴュー(リトル・マン・テイトはかからず)まで、幅広くイギリスの音楽がかかる。
高円寺という場所柄か、単に昔からの遊び友だちがそのまま歳を取っているだけなのかわからないけれど、同じくらいの歳の人たちがたくさん集まってDJの回す音楽を聴きながら、酒を飲みながらしゃゃべったり騒いだりしているのを見ていると、いろいろなことをやり続けていれば、歳をとってもそれなりに楽しんで暮らしていけるのだろうとも思う。
「サラサーテの盤」-内田百けん-
 吉祥寺にあったkuukuuのスタッフだった人が、国立でニチニチというお店をやっているということを、去年の夏くらいに書いたのだけれど、残念ながらまだ行く機会がないままになってます。お店の開店が5時半なので、夕方国立まで出かけていって、そこでご飯を食べて、ある程度お酒を飲んで帰ってこなくては、と思うとなかなか難しい。
吉祥寺にあったkuukuuのスタッフだった人が、国立でニチニチというお店をやっているということを、去年の夏くらいに書いたのだけれど、残念ながらまだ行く機会がないままになってます。お店の開店が5時半なので、夕方国立まで出かけていって、そこでご飯を食べて、ある程度お酒を飲んで帰ってこなくては、と思うとなかなか難しい。
そんなわけで、お店の存在を知ってから一年近くが立ってしまいましたが、先日、ミオ犬が西荻の雑貨屋さんで、第三日曜日にニチニチで日曜市をやっているということを聞いてきたので、タイミングもいいし、パンやマフィン、ジャム、陶器、古本‥‥など、チラシに書いてあったお店(?)も期待できそうだし、と、ひさしぶりに国立まで行って来ました。
「早めに行かないといろいろ売り切れちゃうよ」と言われていたので、朝ご飯を食べないで起きたらすぐに出かけて、イートインコーナーでパンでも食べようと計画でいたものの、珍しく土曜日に会社に行ったりしたため、当然、早く起きられるはずもなく、ニチニチに着いたのはお昼過ぎ。シフォンケーキやマフィンは残っていたけれど、カレーパンなどは売り切れで、先着80名に配られていた2周年記念のエコバックもすでになくなってました。そもそもお店の中は人でいっぱいで、イートインコーナーでゆっくりパンを食べるなんて感じではなかったです‥‥。日曜市では、とりあえずマフィンとシフォンケーキを買って、しばらくのあいだお皿や雑貨を見たり、西荻の雑貨屋さん(なんて名前の店か忘れてしまいました)と話をしていたりしてから、国立といえば、ということでロージナ茶房でお茶をする。
その後、大学通りを散歩したり、古本屋やレコード屋をのぞいたりして、3時過ぎには吉祥寺に移動してしまったので、けっきょく今回もニチニチでご飯を食べることはできず、でした。ニチニチでご飯を食べるのはいつになることやら。
「めぐらし屋」-堀江敏幸-
 普段、古本屋ばかり回って、もう亡くなってしまった作家の本ばかり読んでいるので、同時代に生きている作家の新作を心待ちにする、という楽しみがないがちょっと寂しい。改めてそんなことを思うと、実は大きな楽しみを逃しているような気になったりするけれど、きっかけがないのと、今の読書傾向を追いかけるだけでいっぱいなので、まぁしょうがないです。堀江敏幸は、そんな楽しみを味わせてくれる数少ない作家。いや、ひとりだけかも知れません。
普段、古本屋ばかり回って、もう亡くなってしまった作家の本ばかり読んでいるので、同時代に生きている作家の新作を心待ちにする、という楽しみがないがちょっと寂しい。改めてそんなことを思うと、実は大きな楽しみを逃しているような気になったりするけれど、きっかけがないのと、今の読書傾向を追いかけるだけでいっぱいなので、まぁしょうがないです。堀江敏幸は、そんな楽しみを味わせてくれる数少ない作家。いや、ひとりだけかも知れません。
大学卒業後、知り合いの会社に長く勤める蕗子さんは、低血圧でいつも体調が悪く、感覚的にもちょっとまわりの人たちとズレている独身女性。ある日、蕗子さんは、長いあいだ離れて暮らしていた父の遺品を整理するために、父親が暮らしていたアパートまで出かける。近くにひょうたん池のあるそのアパートでみつけた「めぐらし屋」と書かれた大学ノート、そしてそのノートに貼られていた蕗子さんが幼い頃に描いた黄色い傘の絵にひかれ、謎のようなそのノートと、蕗子さんがアパートにいるときにたまたまかかってきた要領の得ない電話、近くに住む父親の知人といった点をたどって、知らなかった父親の過去に想いをめぐらせていく‥‥。
ストーリーとしてはものすごくあっさりとして、帯に書かれている「わからないことは わからないままにしておくのが いちばんいい」という言葉のように、物語の終わりになにかが大きく変わったり、誰もが納得するような答えが用意されているわけではない。そんな淡泊な物語も含めて、文章全体から漂う感触やディテールへのこだわりなど、堀江敏幸のいつもの作品とあまり変わっていない。強いていえば、新聞の日曜版に連載されたせいか、ディテールへのこだわりよりも全体の感触に重みが置かれているように思う。わたしとしては、その辺にちょっと物足りなさを感じてしまったかな。
「七つの街道」-井伏鱒二-
 諸般の事情により、ゴールデンウィーク明けからちょっと営業をお休みしていましたが、昨日より通常どおり営業を再開させていただいております。お休みのあいだいろいろな人にご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。
諸般の事情により、ゴールデンウィーク明けからちょっと営業をお休みしていましたが、昨日より通常どおり営業を再開させていただいております。お休みのあいだいろいろな人にご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。
週末は、鎌倉に行って来ました。暖かくなってちょっと出かけるにはいい季候になだけに、駅を出たところからすでにものすごい人混みで、イワタのホットケーキなんて、なんと50分待ち!(実際はもう少し早く出てきたけど)という状態。昼過ぎに家を出たせいで、鎌倉に着いたのが3時過ぎだったので、イワタで中庭を眺めたり、雑誌を拾い読みしたりして、ホットケーキ食べて外に出てみると、なんとなくもう夕方気分。小町通りを歩く人たちも駅に向かう人のほうが多い。
鎌倉に行ったのは、20日まで神奈川県立近代美術館でやっている「佐伯祐三と佐野繁次郎展」を見るためだったのですが、(ここまで書いて分かる人には分かると思いますが‥‥)4時半前、閉館ぎりぎりに美術館に着いて、チケットまで買ってから、「佐伯祐三と佐野繁次郎展」がやっているのは葉山館だということに気づくという大失態。払い戻しができたのはよかったけれど、時間的にも距離的にも、葉山館に移動することもできず、わざわざ来たのになんだかなぁ、という感じでした。葉山館は、2003年の秋に開館していたらしいです。前回、近代美術館で見た展覧会は、「チャペック兄弟とチェコ・アヴァンギャルド展」だったので2002年秋、開館する1年前だから知らないのも無理ないけど、それからも度々鎌倉に行っているのに全然知らなかった~迂闊でした~
