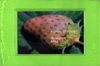 気がつけば週の真ん中。
気がつけば週の真ん中。
先日、世田谷文学館でやっていた植草甚一の展覧会に、終了間際駆け込みで行って来ました。会場はそれほど大きなところではありませんが、植草甚一の幅広い仕事(趣味?)をコンパクトにポイントを抑えて展示してあって、思っていたよりもいい展覧会でした。もっともそんな風に思えるのは、個人的に、植草甚一を追っかけていたころから、かなり時間が経ってしまっているからなんだと思います。もし夢中になっている頃だったら、物足りない部分やもっと自分を知らない部分を求めてしまっただろうしね。
まぁ、植草甚一の展覧会を、世田谷文学館でやる、ということに大きな意味があるような、ないような‥‥。
で、改めて植草甚一が選んだものを見てみたら、どの分野に関しても選ぶ基準がはっきりしていることと、かなり真っ当なセレクトをしていることにに気がつきました。特に音楽に関しては、過去のさまざまなジャンルのお墓を掘りおこし尽くしたピチカート・ファイヴ→サバービア→モンド・ミュージックを通り抜けたあとだけに、植草甚一のこだわりがより目立つました。
あとは手紙やノートなどの私物を見られたことがよかったです。私物や私信であっても、どれも丁寧にきちんと書かれていたり、作られていたりして、昼間は神保町などを歩き回り、夜は映画を観て、帰ってきてこんなものをコツコツと作っていたとすると、この人は一体いつ寝てたんだろうという疑問が頭を離れません。あー、お酒飲まないから?いや知らないけど、あまりお酒のこと書いないような気がするし‥‥。

 庄野潤三が1957年秋から翌58年夏まで、米国オハイオ州ガンビアのケニオンカレッジに留学していたときのことを、後年、そのときの日記を見ながらつづったエッセイ集。
庄野潤三が1957年秋から翌58年夏まで、米国オハイオ州ガンビアのケニオンカレッジに留学していたときのことを、後年、そのときの日記を見ながらつづったエッセイ集。 11月に入ってからいろいろあって雑記を書いているような状況ではなくて、気がつけば半月ぶりになってしまいました。本も全然読んでないしね。そんな感じではあるのですが、今日でこの雑記も500回目です。初めてから4年半くらいなので、一年で約100ちょっと、3日に1回くらいですか。まぁ多いのか、少ないのかわからん。
11月に入ってからいろいろあって雑記を書いているような状況ではなくて、気がつけば半月ぶりになってしまいました。本も全然読んでないしね。そんな感じではあるのですが、今日でこの雑記も500回目です。初めてから4年半くらいなので、一年で約100ちょっと、3日に1回くらいですか。まぁ多いのか、少ないのかわからん。 前に読んだ「屋上がえり」のようにテーマがきちんと決まっていないので、ときどきこれは実はフィクションなのではないかと思うときがあるのだが、実際はどうなのだろう。よくわからない。でも気分的には、実は半分くらいフィクションだったらなぁ、とも思う。
前に読んだ「屋上がえり」のようにテーマがきちんと決まっていないので、ときどきこれは実はフィクションなのではないかと思うときがあるのだが、実際はどうなのだろう。よくわからない。でも気分的には、実は半分くらいフィクションだったらなぁ、とも思う。