 この本の解説は、堀江敏幸。ある作家の本を読み始めたばかりの時に、好きな作家がその本の解説を書いていたりするとなんとなくうれしい。でも、たまたま買ったCDをあけてみたら、小西康陽が解説を書いていた、というのはちょっとがっかりしてしまう、のはなんでかな。
この本の解説は、堀江敏幸。ある作家の本を読み始めたばかりの時に、好きな作家がその本の解説を書いていたりするとなんとなくうれしい。でも、たまたま買ったCDをあけてみたら、小西康陽が解説を書いていた、というのはちょっとがっかりしてしまう、のはなんでかな。
ようやく「ハリー細野 クラウン・イヤーズ 1974-1977」を買った。「トロピカル・ダンディ」も「泰安洋行」もアナログではもっているのだけれど、気軽に聴けるCDでそろえたいと思っていたところだったし、それよりも中華街でのライヴが全部収録されているというのがうれしい。映像も全部入ってたらなぁ、と思うけれど、それは残っていないのだろう。今年は新春放談をきちんと聞いたことや、このボックスの発売の影響か、年が明けたくらいから、ティン・パン・アレイ周辺のCDばかり買っていてます。気分にまかせてついバラバラとCDを買ってしまうので、改めて聴こうとすると意外とCDを持っていなかったりします。鈴木茂の「バンドワゴン」でさえ、高校の時レンタルレコード屋で借りだけで、買ってなかったりするし‥‥。というわけで、iPodの中は、小坂忠や鈴木茂、吉田美奈子、松任谷正隆、久保田真琴、大貫妙子、ブレッド&バター、西岡恭蔵、南佳孝‥‥といったアーティストの曲ばかりになってます。
聴き始めた頃は、2月の終わりくらいまでこの路線を聴いていこうと思っていたのだけれど、いつになくはまってしまっていて、このまま夏前くらいまで聞き続けようと思ってます。でもティン・パン・アレイ周辺といいつつも、吉田美奈子とか大貫妙子のファーストとか聴いていると、やはり山下達郎のアレンジのセンスの良さを改めて気づかされます。
ところで、ちょっと自慢なのですが、うちには細野晴臣、鈴木茂、林立夫、ジョン山崎、吉田美奈子、小坂忠のサインが入ったティン・パン・アレイの色紙があります。詳しくは知らないのですが、友だちのおじさんが北海道に住んでいて、若いときにそういうバンドを何組か呼んで、今で言うフェスみたいなもの開いたことがあって、そのときにもらったもの、らしい。でも、そのおじさん自身はティン・パン・アレイのことをほとんど知らなかったらしいのだけれど‥‥。吉田美奈子のサインの「子」の横棒の先にハートマークが入っているのがちょっと微笑ましい。
で、このボックスのブックレットには、1974年10月から1977年9月までの細野晴臣の活動記録が詳細に記載されていたので、この色紙が、いつ行われたどんなイベントのときに書かれたものなのか調べてみたのですが、どうも記載がない。細野晴臣のサインの前に「泰安洋行」と書かれているので1976年。北海道の野外イベントなのでその夏ではないかと予測はしていたのですが、ないんですよねぇ~。1976年は「パラダイスツアー」で札幌に行ってるだけだし、1977年の夏は「札幌ロック祭」に参加しているのですが、ティン・パン・アレイではなく、夕焼け楽団+細野晴臣と書かれているし、謎は深まるばかり‥‥。
ちなみに、この年譜を書いているのは長門芳郎。10代から20代の初めの頃は、この人の書いたレコードの解説に出てくるグループやアーティストをメモって、中古レコード屋にいくたびにチェックしたものです。その辺は、今、好きな作家の随筆の中に出てくる作家の本を手帳にメモって、古本屋でチェックしているのと変わらない。なにが変わったと言えば、わたしが音楽を聴くということに、昔ほど情熱がなくなったということだけか?

 3月に参加するモノクロ写真の引き伸ばしのワークショップの前に、一応手順などを予習しておこうと思って購入。1カ月くらい前から本屋さんに行くたびにチェックはしていたのですが、あまり置いてないものですね。カメラコーナーは、基本的にデジカメの操作の仕方とか、撮影の仕方についての本しか置いてないような気がします。あと、今流行りのおもちゃというか雑貨ぽいカメラの本、もしくはライカやハッセルなどのヴィンテージものの本といったところか。
3月に参加するモノクロ写真の引き伸ばしのワークショップの前に、一応手順などを予習しておこうと思って購入。1カ月くらい前から本屋さんに行くたびにチェックはしていたのですが、あまり置いてないものですね。カメラコーナーは、基本的にデジカメの操作の仕方とか、撮影の仕方についての本しか置いてないような気がします。あと、今流行りのおもちゃというか雑貨ぽいカメラの本、もしくはライカやハッセルなどのヴィンテージものの本といったところか。 内田百けんは、読んだらおもしろいんだろうなぁ、と思いつつ、黒沢明の映画のせいでなんとなく敬遠してきた作家なのだけれど、高橋義孝と山口瞳の対談を読んでいたら、やはり読んでみるべき、という気持ちが強くなった。希望としては、ここは旺文社文庫でそろえたい、ところなのだが、どうみても簡単にそろいそうもないので、ちくま文庫の内田百けん集成で我慢することに。全24巻、1カ月に2冊ずつくらい読んでいけば、年末くらいに全部読めればという計画です。今年の目標の1つですね(ほかにどんな目標が?と言われると。「‥‥」ですが)。
内田百けんは、読んだらおもしろいんだろうなぁ、と思いつつ、黒沢明の映画のせいでなんとなく敬遠してきた作家なのだけれど、高橋義孝と山口瞳の対談を読んでいたら、やはり読んでみるべき、という気持ちが強くなった。希望としては、ここは旺文社文庫でそろえたい、ところなのだが、どうみても簡単にそろいそうもないので、ちくま文庫の内田百けん集成で我慢することに。全24巻、1カ月に2冊ずつくらい読んでいけば、年末くらいに全部読めればという計画です。今年の目標の1つですね(ほかにどんな目標が?と言われると。「‥‥」ですが)。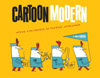 こちらもアマゾンで注文した本。著者は、「ANIMATION WORLD MAGAZINE」や「ANIMATION JOURNAL」「ASIFA MAGAZINE」といった雑誌に関わり、1996年に創刊されたアニメーションについての専門誌(1998年以降はWeb)「ANIMATION BLAST」を主宰している人物らしい。現在はこの本に連動した1950年代カートゥーン専門の「
こちらもアマゾンで注文した本。著者は、「ANIMATION WORLD MAGAZINE」や「ANIMATION JOURNAL」「ASIFA MAGAZINE」といった雑誌に関わり、1996年に創刊されたアニメーションについての専門誌(1998年以降はWeb)「ANIMATION BLAST」を主宰している人物らしい。現在はこの本に連動した1950年代カートゥーン専門の「 年始めに青山ブックセンターの洋書バーゲンに行ってなに買わず、帰ってきてアマゾンに注文した本がようやく届きました。ペンギンブックスが誕生した1935年から2005年までの本の表紙と、それらに対しての考察を掲載したもの。著者は、有名なタイポグラファーで、美術大学でも教鞭とっているらしい。といっても内容については読んでないのでわかりませんけどね。
年始めに青山ブックセンターの洋書バーゲンに行ってなに買わず、帰ってきてアマゾンに注文した本がようやく届きました。ペンギンブックスが誕生した1935年から2005年までの本の表紙と、それらに対しての考察を掲載したもの。著者は、有名なタイポグラファーで、美術大学でも教鞭とっているらしい。といっても内容については読んでないのでわかりませんけどね。