 一応、カヌー犬ブックスは、海外文学と料理に関する古本をあつかっている古本屋、なんですけれど、ここに海外文学の本が取り上げられることはほとんどないし、料理についてに書くこともほとんどなかったりします。たまには「週末のパーティで用意した●●●の作り方」なんてレシピをここに書いてみるのもいいかもしれない、なんて言ってみたりして。いやいや週末のパーティってなんなんですか?
一応、カヌー犬ブックスは、海外文学と料理に関する古本をあつかっている古本屋、なんですけれど、ここに海外文学の本が取り上げられることはほとんどないし、料理についてに書くこともほとんどなかったりします。たまには「週末のパーティで用意した●●●の作り方」なんてレシピをここに書いてみるのもいいかもしれない、なんて言ってみたりして。いやいや週末のパーティってなんなんですか?
そんなことはさておき、カート・ヴォネガットが亡くなったそうだ。84歳。今となっては、最後に読んだヴォネガットの本がなんだったのか思い出せないくらいずっと読んでなくて、よく読んでいた時期といえば高校生から大学の初めまでのあいだ、1980年年代半ばから1990年の初めくらい。Wikipediaによると「1980年代、日本でも認知がすすみヴォネガットブームとも言える状況が到来」とか「ヴォネガットから影響を受けたとされる村上春樹(とりわけ『風の歌を聴け』)や高橋源一郎、橋本治等の若手作家たちの台頭もこの時期」とある。そういうブームに影響を受けていたのだろうなぁ、と今になって思えば、そんな時代だったような気さえしてしまったりして。実際、ヴォネガット自身が歳を取って、作品をあまり発表しなくなったこともあるかもしれないけれど、1990年代の後半になるとほとんど翻訳本も刊行されていないみたいです。ついでにヴォネガットの作品で翻訳されている本は以下のとおり。
■「プレイヤー・ピアノ」
■「タイタンの妖女」
■「母なる夜」
■「猫のゆりかご」
■「ローズウォーターさん、あなたに神のお恵みを」
■「スローターハウス5」
■「さよならハッピー・バースディ」
■「チャンピオンたちの朝食」
■「スラップスティック」
■「ジェイルバード」
■「デッドアイ・ディック」
■「ガラパゴスの箱舟」
■「青ひげ」
■「ホーカス・ポーカス」
■「タイムクエイク -時震」
■「ヴォネガット、大いに語る」
■「パームサンデー -自伝的コラージュ」
■「死よりも悪い運命 -1980年代の自伝的コラージュ」
■「モンキー・ハウスへようこそ」
■「バゴンボの嗅ぎタバコ入れ」
全部で20冊?。もっと出ているような気もするけれど気のせいかな。この中で読んでいない本は、1990年代後半に出た「タイムクエイク -時震」と「死よりも悪い運命 -1980年代の自伝的コラージュ」、「バゴンボの嗅ぎタバコ入れ」くらいかな。意外と読んでますね。内容は忘れてしまったり、他の作品とごっちゃになっているけど。
個人的な経験からすると、10代の頃にこういう本を読んでしまうと、日本の作家の作品が平面的・直線的すぎて、物足りなくなってしまうんじゃないかと思う。最終的に収拾がつかなくても物語は複雑であるほど、おもしろいし、本に感動なんて求めるのは、愚の骨頂。本とは泣くためにあるわけじゃないし、“共感”なんてなに言ってんの?という感じになってしまう。そして最終的にはメタフィクションとラテンアメリカ文学にたどり着くのだけれど、わたしの場合、そこで振り切って日本の私小説に走ってしまうあたりが、どうも両極端なわけで‥‥。

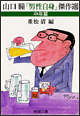 せっかくなので‥‥、という始まりもどうかと思うけれど、金曜日の夕方だし、もう気分は週末、というわけで、5時から30分だけ会社を中抜けして、ミッドタウンの地下で行われていたエマーソン北村のライブを見に行って、それからまたちょっと仕事して、7時50分に仕事を切り上げて、8時から土岐麻子を見るなんてことをしてみました。親ガメの背中に乗っかって、気がついたらこんなところまでつれてこられてしまったのだから、このくらいの恩恵がなくちゃね、と。
せっかくなので‥‥、という始まりもどうかと思うけれど、金曜日の夕方だし、もう気分は週末、というわけで、5時から30分だけ会社を中抜けして、ミッドタウンの地下で行われていたエマーソン北村のライブを見に行って、それからまたちょっと仕事して、7時50分に仕事を切り上げて、8時から土岐麻子を見るなんてことをしてみました。親ガメの背中に乗っかって、気がついたらこんなところまでつれてこられてしまったのだから、このくらいの恩恵がなくちゃね、と。 春の天気は変わりやすい。
春の天気は変わりやすい。