 うちにある2つのカフェオレボウルは、ほとんどカフェオレを飲むときに使われることはなくて、おもにはスープやごはん、あるいはちょっとしたお総菜などをよそうのに使われているのだけれど、そういった用途としても機会が、出会いがあれば、いい感じのボウルがあるといいな、なんて思っていたところ、先日、吉祥寺のギャラリー・フェブでこの本の出版記念イベント「フランスのボウルと小さな物産展」が開かれていたので、それほど期待もせずに行って、模様や形に工夫を凝らしたいくつものカフェオレボウルが、棚や階段に並べられているのを見ていたら、なんだか新しいボウルが欲しい気分になってしまい、とりあえず本を購入。実際は、どこにでも置いてあるものでもないので、ゆっくり探せばいいなぁ、と思ってます。
うちにある2つのカフェオレボウルは、ほとんどカフェオレを飲むときに使われることはなくて、おもにはスープやごはん、あるいはちょっとしたお総菜などをよそうのに使われているのだけれど、そういった用途としても機会が、出会いがあれば、いい感じのボウルがあるといいな、なんて思っていたところ、先日、吉祥寺のギャラリー・フェブでこの本の出版記念イベント「フランスのボウルと小さな物産展」が開かれていたので、それほど期待もせずに行って、模様や形に工夫を凝らしたいくつものカフェオレボウルが、棚や階段に並べられているのを見ていたら、なんだか新しいボウルが欲しい気分になってしまい、とりあえず本を購入。実際は、どこにでも置いてあるものでもないので、ゆっくり探せばいいなぁ、と思ってます。
ところで、カフェオレボウルといえば、その存在を知って間もない頃、あるフランス映画を観ていたら(タイトルは忘れました)、朝、男の人がベッドで寝ている女性に「コーヒー飲む?」と聞いて棚から取り出したのが、カップではなくボウルで、「ホントにフランスで使われてるんだぁ」、なんて思っていたら、そのあと、無造作にボウルの中にインスタントコーヒーの粉を入れ、そのまま水道のお湯をボウルに入れて、女の人に差し出した・・・・というシーンが忘れられませんね。少なくともお湯くらい沸かして欲しいし、ミルクも入れて欲しかった。フランスの自宅におけるコーヒーの扱いなんてそんなものなのかな。日本人はなんでも凝りすぎるからね。
そんな日本人の性癖を半分皮肉りつつコーヒーの入れ方とお茶の作法を関連させていたのは、獅子文六の「コーヒーと恋愛(可否道)」でした。ついでに獅子文六は、この本を書くためにコーヒーを飲み過ぎて胃を悪くしたとか。皮肉っているのか、まじめに説いているのか、分からない話。
コーヒーついでにもうひとつ、今年になってからまったく映画を観ていないのは、会社が終わるとレイトショーにも行けない時間になってしまっているのと、休日は古本屋巡りばかりしているせい、そして大きいテレビとDVDプレーヤーを買ったので、TSUTAYAでDVDを借りたりしているせいで、かといって、予告も見てないし、チラシももらってきてないので、今なにが上映されているかぜんぜんわからないのだけれど、とりあえず、目に付いたジャームッシュ監督の「コーヒー&シガレット」を見るべく、前売り券を購入。
コーヒーとタバコにまつわる短編映画として1986年に作られたものの単独長編化らしい。11本のショート・ストーリーを連ねた掌編集なので、長編化ではないのかな。よくわからん。前売りを買うとロゴの入ったライターがついてくるのが個人的にはうれしい。黒はもうなくなっていたので、白が二つになってしまったけれどね。でも公開は4月2日から、まだまだ先ですね。
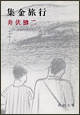 荻窪にあるあるアパートの主人が死んで、小学生の男の子がひとり取り残された。主人と親しかった主人公は。部屋代を踏み倒して逃げた人たちから勘定を取り立てるため、昔の恋人に慰謝料を請求する年増美人と一緒に、岩国、下関、福岡、尾道、福山と集金旅行に出る・・・・という話。
荻窪にあるあるアパートの主人が死んで、小学生の男の子がひとり取り残された。主人と親しかった主人公は。部屋代を踏み倒して逃げた人たちから勘定を取り立てるため、昔の恋人に慰謝料を請求する年増美人と一緒に、岩国、下関、福岡、尾道、福山と集金旅行に出る・・・・という話。
 雑誌「あまカラ」のせいで、なんとなく小島政二郎というと食べ物に詳しい、食通というイメージがあるけれど、久米正雄に「小島なんか、鼻ッつまりじゃないか。鼻ッつまりに、物のうまいまずいが分かってたまるものか」なんて言われていたとは。とはいうものの、日本のあちらこちら出かけていっておいしいものを求めるさまを読んでいると、ほんとうにたべることがすきなのだなぁ、と思う。もちろん“好き”なだけではないのだろうけれど・・・・。今の世の中なんて小島政二郎に言わせれば、まずい食材に過度に人工的な手を加えたどうしようもないものばかり、ということになるのだろうか。いや、食べ物だけでなく、空気までまずいと言われそう。
雑誌「あまカラ」のせいで、なんとなく小島政二郎というと食べ物に詳しい、食通というイメージがあるけれど、久米正雄に「小島なんか、鼻ッつまりじゃないか。鼻ッつまりに、物のうまいまずいが分かってたまるものか」なんて言われていたとは。とはいうものの、日本のあちらこちら出かけていっておいしいものを求めるさまを読んでいると、ほんとうにたべることがすきなのだなぁ、と思う。もちろん“好き”なだけではないのだろうけれど・・・・。今の世の中なんて小島政二郎に言わせれば、まずい食材に過度に人工的な手を加えたどうしようもないものばかり、ということになるのだろうか。いや、食べ物だけでなく、空気までまずいと言われそう。 3月になっても寒い日が続いていて、なかなか春らしい暖かい日は来ない。しかも今日の夜から明日にかけては雪が降るらしい。まだ外は薄日が差しているという感じだけれど、どうなのだろう。
3月になっても寒い日が続いていて、なかなか春らしい暖かい日は来ない。しかも今日の夜から明日にかけては雪が降るらしい。まだ外は薄日が差しているという感じだけれど、どうなのだろう。 うちにある2つのカフェオレボウルは、ほとんどカフェオレを飲むときに使われることはなくて、おもにはスープやごはん、あるいはちょっとしたお総菜などをよそうのに使われているのだけれど、そういった用途としても機会が、出会いがあれば、いい感じのボウルがあるといいな、なんて思っていたところ、先日、吉祥寺のギャラリー・フェブでこの本の出版記念イベント「フランスのボウルと小さな物産展」が開かれていたので、それほど期待もせずに行って、模様や形に工夫を凝らしたいくつものカフェオレボウルが、棚や階段に並べられているのを見ていたら、なんだか新しいボウルが欲しい気分になってしまい、とりあえず本を購入。実際は、どこにでも置いてあるものでもないので、ゆっくり探せばいいなぁ、と思ってます。
うちにある2つのカフェオレボウルは、ほとんどカフェオレを飲むときに使われることはなくて、おもにはスープやごはん、あるいはちょっとしたお総菜などをよそうのに使われているのだけれど、そういった用途としても機会が、出会いがあれば、いい感じのボウルがあるといいな、なんて思っていたところ、先日、吉祥寺のギャラリー・フェブでこの本の出版記念イベント「フランスのボウルと小さな物産展」が開かれていたので、それほど期待もせずに行って、模様や形に工夫を凝らしたいくつものカフェオレボウルが、棚や階段に並べられているのを見ていたら、なんだか新しいボウルが欲しい気分になってしまい、とりあえず本を購入。実際は、どこにでも置いてあるものでもないので、ゆっくり探せばいいなぁ、と思ってます。