 今、山口瞳が流行っているらしい。本屋にも山口瞳特集のムック本が平積みにされていたし、そういえば6月に北尾堂ブックカフェに行った時も北尾さんがそんな話をしていたような気がする。まぁアンクルトリス→柳原良平ときて次に山口瞳がくるのはわかります。私がそうなので‥‥。そういう意味で私は流行りに左右されやすいのだ。
今、山口瞳が流行っているらしい。本屋にも山口瞳特集のムック本が平積みにされていたし、そういえば6月に北尾堂ブックカフェに行った時も北尾さんがそんな話をしていたような気がする。まぁアンクルトリス→柳原良平ときて次に山口瞳がくるのはわかります。私がそうなので‥‥。そういう意味で私は流行りに左右されやすいのだ。
でも実は新潮社からかなり出ている彼の著作のほとんどが絶版になっていて手に入れようとするとなかなか手に入らない。別に「礼儀作法入門」だとか「 温泉へ行こう」とか初めに読みたくないしね。そんなわけで最近古本屋で山口瞳の文庫本を見つけては買っている。どれも100円とか200円といったところなのでいつのまにか読んでいない本が5、6册くらいたまっているという状態。
さて今日も夕方から外出。阿佐ヶ谷へ。JRを降りると何故か人だかりで不思議に思っているとどうやら今日から七夕祭りということがわかる。とりあえずちょっと時間もあるので喫茶店でコーヒーを飲みながら本を読むことにする。2日外出が続いたせいで一気にこの本も読み終わってしまった。
1980年代中ごろの東京を19景。その頃は土地もどんどん値が上がり、そこいらじゅうにビルを建てて都市整備なんて言ってたりしていた真っ盛りだったと思うが、今でも同じ感覚なのが恐ろしい。「汚い路地を整理して、新しい快適な街を作る」と当時再開発を行っていた人の言葉が出てくるのだけれど、森ビルの社長が同じ言葉を六本木ヒルズができた時に言っているのを聞いた。

 仕事で荻窪に行ったついでに立ち寄ったブックオフで250円で購入。レオ・レオニの本は「あおくん と きいろちゃん」をはじめ前から欲しかったのでちょっとよれてるけどまぁしょうがない、と。
仕事で荻窪に行ったついでに立ち寄ったブックオフで250円で購入。レオ・レオニの本は「あおくん と きいろちゃん」をはじめ前から欲しかったのでちょっとよれてるけどまぁしょうがない、と。 井伏鱒二といえば「黒い雨」か「山椒魚」くらいしか知識がなくて、おまけに前者は読んだこともないし後者を読んだのは中学生の頃であんまり記憶がなかったりする。そんな作家の本をいまさら読んでみようと思ったのは、大好きな小沼丹の師匠ということと荻窪に住んでいたということを知ったから。ほんとは初めに「珍品堂主人」を読みたいと思っていたのだけれど、先週の土曜日に古本屋周りをしたときにたまたまこの本を見つけてしまったのです。
井伏鱒二といえば「黒い雨」か「山椒魚」くらいしか知識がなくて、おまけに前者は読んだこともないし後者を読んだのは中学生の頃であんまり記憶がなかったりする。そんな作家の本をいまさら読んでみようと思ったのは、大好きな小沼丹の師匠ということと荻窪に住んでいたということを知ったから。ほんとは初めに「珍品堂主人」を読みたいと思っていたのだけれど、先週の土曜日に古本屋周りをしたときにたまたまこの本を見つけてしまったのです。 旅行に行って帰ってきてすぐの頃は、旅の疲れがたまってしまったり、急に日常に戻ったせいで慌ただしかったりして「当分、旅行なんて行かないだろうな」と思ってしまいますが、1カ月くらい経って次第に落ち着いてくると急に旅行先のことを思い出しだしてなんだかそわそわしてしまったりして、そんなときに山口瞳の「酔いどれ紀行」やこんな本を読んだりするともう夏休みも近いし国内でもいいからどこかに行きたい、なんて気分になってしまいます。
旅行に行って帰ってきてすぐの頃は、旅の疲れがたまってしまったり、急に日常に戻ったせいで慌ただしかったりして「当分、旅行なんて行かないだろうな」と思ってしまいますが、1カ月くらい経って次第に落ち着いてくると急に旅行先のことを思い出しだしてなんだかそわそわしてしまったりして、そんなときに山口瞳の「酔いどれ紀行」やこんな本を読んだりするともう夏休みも近いし国内でもいいからどこかに行きたい、なんて気分になってしまいます。 続いて山口瞳の紀行もの。新潮社なのに表紙が柳原良平じゃない、しかも変な絵は誰?、なんて思っていたら山口瞳本人の絵でした。すっすみません。
続いて山口瞳の紀行もの。新潮社なのに表紙が柳原良平じゃない、しかも変な絵は誰?、なんて思っていたら山口瞳本人の絵でした。すっすみません。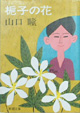 山口瞳の本は柳原良平が表紙を書いていることが多くて、それにひかれて前々から一冊は読んでみようと思っていました。でもこの本を含めて「酔いどれ紀行」や「新東京百景」「私本歳時記」など読んでみたいなぁと思うものが軒並み絶版になってしまって本屋に置いてないし、意外と古本屋さんにもない気が‥‥。
山口瞳の本は柳原良平が表紙を書いていることが多くて、それにひかれて前々から一冊は読んでみようと思っていました。でもこの本を含めて「酔いどれ紀行」や「新東京百景」「私本歳時記」など読んでみたいなぁと思うものが軒並み絶版になってしまって本屋に置いてないし、意外と古本屋さんにもない気が‥‥。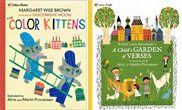 絵がかわいかったのと比較的値段が安かったので、下のサセックの本と一緒に注文してみた。実際に届いてみると思っていたよりも大きなしっかりとしたハードカバーの本だったのでうれしい。(写真では同じにしてしまっているけれど「A Child’s Garden of Verses」の大きいです。)
絵がかわいかったのと比較的値段が安かったので、下のサセックの本と一緒に注文してみた。実際に届いてみると思っていたよりも大きなしっかりとしたハードカバーの本だったのでうれしい。(写真では同じにしてしまっているけれど「A Child’s Garden of Verses」の大きいです。)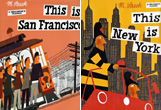 ミロスラフ・サセックの子どものための旅行絵本シリーズより、最近復刊されたニューヨークとサン・フランシスコの本。
ミロスラフ・サセックの子どものための旅行絵本シリーズより、最近復刊されたニューヨークとサン・フランシスコの本。 新宿の南口にあるスタンダードカフェでお茶して東口のほうに歩いていたら、ヴィクトリアの裏側に古本屋を発見。「畸人堂 趣味の古本屋(だったかな)」と書かれた看板に不安を覚えつつも行ってみると、かなり普通の古本屋。映画や音楽、アート関係の本もなにげにたくさんあって得した気分でとりあえず鎌倉特集の「太陽」を買う。
新宿の南口にあるスタンダードカフェでお茶して東口のほうに歩いていたら、ヴィクトリアの裏側に古本屋を発見。「畸人堂 趣味の古本屋(だったかな)」と書かれた看板に不安を覚えつつも行ってみると、かなり普通の古本屋。映画や音楽、アート関係の本もなにげにたくさんあって得した気分でとりあえず鎌倉特集の「太陽」を買う。 訳あって最近送別会多し。昨日も会社の人の送別会で、解散後もちょっと飲んで帰ろうと思ったら電車の乗りつぎを考えると井の頭線の最終に間に合いそうもない。しょうがないので荻窪に住む同僚と中央線で西荻まで出て歩いて帰ることにする。しかも西荻の駅で降りるとパラパラと雨が、時間はすでに1時過ぎ。
訳あって最近送別会多し。昨日も会社の人の送別会で、解散後もちょっと飲んで帰ろうと思ったら電車の乗りつぎを考えると井の頭線の最終に間に合いそうもない。しょうがないので荻窪に住む同僚と中央線で西荻まで出て歩いて帰ることにする。しかも西荻の駅で降りるとパラパラと雨が、時間はすでに1時過ぎ。