 正直言って永井龍男について知っていることはほとんどありません。この間、小津安二郎展を鎌倉文学館に見に行ったときにちょっと展示を見たくらい。奥付を見て鎌倉文学館の初代館長だったということもはじめて知りました。
正直言って永井龍男について知っていることはほとんどありません。この間、小津安二郎展を鎌倉文学館に見に行ったときにちょっと展示を見たくらい。奥付を見て鎌倉文学館の初代館長だったということもはじめて知りました。
この本は1980年代に日経新聞に連載した「私の履歴書」を中心にまとめたもの。幼少期から前後文藝春秋を退社して作家としてやっていくまでの経歴が書かれています。
ここでは文藝春秋の社長である菊池寛はもちろんのこと、さすがにいろいろな人が登場してきます。なかでも川端康成や小林秀雄、里見惇など鎌倉に住む人々が出てくるとなんだかわくわくしてきます。先日読んだ山口瞳は隣に川端康成が住んでいたという話を書いていたし、井伏鱒二の本には小林秀雄が出てきたり、小沼丹の随筆には井伏鱒二が出てきて・・・・そうやっていろいろな本を読みながら戦前から戦後にかけての作家たちの交友関係が自分の頭の中でできあがって、そして動いていく感じがとても楽しい。
これ一冊読んでどうこういう筋合いではないので次回はちゃんとした小説を読んでみたいです。

 PickwickWebのどこかに、いつか書いたような気がするけれど、私にとって片岡義男のイメージは角川映画の原作であり本屋でずらりと赤い背表紙で、中学、高校の頃は、本棚に赤い表紙が並んでいるような人とは絶対に友達になりたくないと思ったものです。
PickwickWebのどこかに、いつか書いたような気がするけれど、私にとって片岡義男のイメージは角川映画の原作であり本屋でずらりと赤い背表紙で、中学、高校の頃は、本棚に赤い表紙が並んでいるような人とは絶対に友達になりたくないと思ったものです。 あっ、というまに今日から9月。「September Song」じゃないけれど、9月になったと思うとすぐにクリスマスになってしまう、のかな。
あっ、というまに今日から9月。「September Song」じゃないけれど、9月になったと思うとすぐにクリスマスになってしまう、のかな。 それほど多くの本を読んでいるわけではないけれど、今まで読んだ山口瞳の本の中で一番読みごたえがあった。それは本人があとがきにも書いているように川端康成と田中角栄に関する文章が“芯”となっているから。
それほど多くの本を読んでいるわけではないけれど、今まで読んだ山口瞳の本の中で一番読みごたえがあった。それは本人があとがきにも書いているように川端康成と田中角栄に関する文章が“芯”となっているから。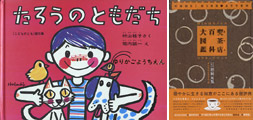 昨日は福生の横田基地友好祭に行ったので今日は家でのんびり掃除や洗濯をして夕方から吉祥寺へ。いまだにアーケードのないサンロードになじめません。まずはKuu Kuuで遅い昼食(or早い夕食)をとった後、古本屋やレコード屋、カルディなど、8時くらいまで歩き回りました。夏の散歩は夕方~夜に限りますね。
昨日は福生の横田基地友好祭に行ったので今日は家でのんびり掃除や洗濯をして夕方から吉祥寺へ。いまだにアーケードのないサンロードになじめません。まずはKuu Kuuで遅い昼食(or早い夕食)をとった後、古本屋やレコード屋、カルディなど、8時くらいまで歩き回りました。夏の散歩は夕方~夜に限りますね。 「愛ってなに?」なんて言われても出てくるのは定年間近の会社の部長や成功したデザイナー、ジャーナリストたちの浮気話(主に昔話)ばっかり、ということで読み終わる頃にはちょっと飽きてきてしまいました。
「愛ってなに?」なんて言われても出てくるのは定年間近の会社の部長や成功したデザイナー、ジャーナリストたちの浮気話(主に昔話)ばっかり、ということで読み終わる頃にはちょっと飽きてきてしまいました。 コーヒーフィルターが切れたので会社帰りに下北沢のモルディブというコーヒー専門店に寄った。ここは前から気にはなっていたんだけれど、敷居が高いような気がしてなかなか入ることができなかったお店。
コーヒーフィルターが切れたので会社帰りに下北沢のモルディブというコーヒー専門店に寄った。ここは前から気にはなっていたんだけれど、敷居が高いような気がしてなかなか入ることができなかったお店。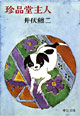 夏休みだというのに雨の日続きでこんな時期に長袖シャツを着るなんてなどと思いつつ夕方くらいからちょっと近くを歩いて回る日々。予定していた食器棚作りもできないしかなりフラストレーションたまってます。
夏休みだというのに雨の日続きでこんな時期に長袖シャツを着るなんてなどと思いつつ夕方くらいからちょっと近くを歩いて回る日々。予定していた食器棚作りもできないしかなりフラストレーションたまってます。 今日から夏休み。土日合わせて5日という短いものですが、まぁのんびりさせていただきます。ちなみに今日は荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺を散策し、夜は新宿で映画を見ました。いろいろ買い込んで重くなったリュックをしょって歩き回りました。
今日から夏休み。土日合わせて5日という短いものですが、まぁのんびりさせていただきます。ちなみに今日は荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺を散策し、夜は新宿で映画を見ました。いろいろ買い込んで重くなったリュックをしょって歩き回りました。 続けて山口瞳。「週刊新潮」で昭和38年から連載していたコラム「男性自身」をまとめた本。内容はここに書くほどではないけれど、電車の中で、喫茶店で、ちょっとした待ち時間に、寝る前にちょっと・・・・などいろいろなときにいろいろなところで気軽に読めて楽しい。
続けて山口瞳。「週刊新潮」で昭和38年から連載していたコラム「男性自身」をまとめた本。内容はここに書くほどではないけれど、電車の中で、喫茶店で、ちょっとした待ち時間に、寝る前にちょっと・・・・などいろいろなときにいろいろなところで気軽に読めて楽しい。