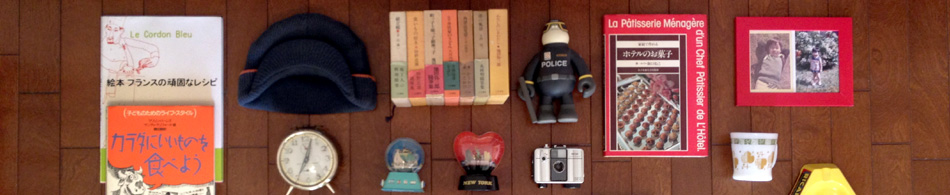食べものの解説・紹介 (全35件)
「しょうゆ風土記」
 | ||
| 著者: | 河野友美 | |
| 出版社: | 朝日新聞社 | |
| サイズ: | 単行本(ハードカバー) | |
| 発行年: | 1974年初版 | |
| 価格: | 700円 | |
| 状態: | A | |
| ▼ 本の紹介 ▼ | ||
|
「しょうゆが、今や世界的調味料になるつつあるとき、もう一度、日本人がつくりあげた、この不思議な調味料を“味覚風土”という角度から見直してみたい。それが私の出会いである(著者の言葉から)」(帯より)
【目次より】 「しょうゆの香り」「しょうゆの原型」「すまし汁」「しょうゆどころ」「歴史の残る町」「しょうゆの映画」「バニラとしょうゆ」「スキヤキ東西の違い」・・・・など |
||
「料理人たちの饗宴―西洋料理のルーツをさぐる」
 | ||
| 著者: | 桜沢琢海 | |
| 出版社: | 河出書房新社 | |
| サイズ: | 単行本(ハードカバー) | |
| 発行年: | 2002年初版 | |
| 価格: | 800円 | |
| 状態: | A | |
| ▼ 本の紹介 ▼ | ||
|
「ルネッサンス期の画家、カルパッチョがなぜ20世紀になって料理の名になったのか?知識の数だけ料理は美味しい。日本でも多くの人に親しまれている西洋料理、菓子のルーツをさぐる、30の『美味しい逸話』」(紹介文より)
【目次より】 「王様のガレットにまつわる東方の三王」「聖ヤコブの帆立貝」「恋の成就をもたらしたアントニオのパネトーネ」「カテリーナ・デ・メディチとノストラダムスの甘い話」「アイスクリームを広めたプロコープ」「ポーランド王レクチンスキーは稀代のお菓子研究家」「マヨネーズを考案したのは元帥にして大使」「ポーツマスにならなかったサンドイッチ」「レストランの創始者、ブーランジェ」「カリフラワーを愛したデュ・バリー伯爵夫人」‥‥など |
||
「しょうゆの本」
 | ||
| 著者: | 田村平治、平野正章編 | |
| 出版社: | 柴田書店 | |
| サイズ: | 単行本(ハードカバー) | |
| 発行年: | 1971年初版 | |
| 価格: | 1000円 | |
| 状態: | B/函背ヤケ | |
| ▼ 本の紹介 ▼ | ||
|
昔、政治文化の中心地であった関西地方で製造が始められ、江戸時代に下総の野田や銚子で造られ、全国的な規模に広まった長い歴史を秘めた醤油を知識と料理の両面から解説。醤油の歴史・製造法・醤油風土記から、刺身・汁もの・焼きもの・煮ものといった料理法の解説、そして醤油にまつわる各界名士の思い出までを収録
→このほかに「平野正章」の本があるか調べてみる |
||
「すしの本」
 | ||
| 著者: | 篠田統 | |
| 出版社: | 柴田書店 | |
| サイズ: | 単行本(ハードカバー) | |
| 発行年: | 1966年5版 | |
| 価格: | 800円 | |
| 状態: | B/記名あり、その他はきれいです | |
| ▼ 本の紹介 ▼ | ||
|
米と魚を漬けこんで自然発酵させる馴れずしから今日の粋な握りずしまでのすしの歴史2000年を、調理学的・歴史地理学的に論じる。軽妙な語り口、横道にそれる楽しい蘊蓄。和漢の膨大な文献を渉猟し、17000通余のアンケートと80冊を越える聞取帳をもとに著わされた、自然科学・人文科学を横断する碩学の決定的な名著
|
||
「西洋料理事典」
 | ||
| 著者: | 田中徳三郎 | |
| 出版社: | 柴田書店 | |
| サイズ: | 単行本(ハードカバー) | |
| 発行年: | 1975年29刷 | |
| 価格: | 800円 | |
| 状態: | A | |
| ▼ 本の紹介 ▼ | ||
|
西洋料理を勉強されている人が、料理の原書を能率的に判読に必要で、かつ使用頻度の高いと思われる料理用語とその解説、料理名と調理法を集録した事典
|
||